
奈良県総務部知事公室広報・広聴課 様
20年度下期「なら県民電子会議室」の報告書
〜県政について県民同士での意見交換〜
2009年度4月4日
NPO法人電子自治体アドバイザークラブ
理事長 奥家孝彦
【目 次】
I. はじめに
II. 提言
III.電子会議室の報告
III-1 (テーマ1) :奈良の魅力の発信と観光客の誘致
〜奈良の歴史文化を発信し、奈良ファンをつくるために〜
コーディネーター:金田充史
III-2 (テーマ2) :受診者の立場から医療資源を考える
〜限られた医療資源を守るために何をなすべきか〜
コーディネーター:馬詰真一郎/吉岡敏子
III-3(テーマ3):地域ぐるみで学校を支援しよう
〜学校支援地域本部の取組を生かして〜
コーディネーター:三宅基之
III-4(テーマ4):平城遷都1300年祭を成功させよう
〜平城遷都1300年祭を機に「もてなし」を考える〜
コーディネーター:金田充史

IV.広報活動、登録・投稿・アクセス集計
V. まとめ
【添付資料】
1.20年度下期運営委員会委員
2.20年度下期「なら県民電子会議室」
ポスター
I.はじめに
1.目的
この電子会議室は、インターネットを活用して県民同士が県政について幅広く議論できる場を提供することにより、県民の県政に関する理解と関心を高めることを目的とする。
2.電子会議室に期待するもの
〜電子会議室の、さらなる活性化を目指して〜
自治体のポータルサイト内のリンク集に「電子会議・電子掲示板のページ」を開設する自治体は多い。しかし、発言もほとんどなく「閑古鳥が鳴いている」という例も少なくない。そんな中で、なら県民電子会議室は3年を経過しようとしている。この時期に総括してみることは有意義であり、そして、今後どのような方向を目指していくべきかを考えてみる。
なら県民電子会議室は、平成18年度上期に、システムの構築や、運用ルールなどを検討し、同年11月に奈良県の事業として本格的な稼働を開始した。以来、アクセス数、発言数は毎年順調に推移しているものの、途中、事前登録の簡素化やテーマ数の増加など、活性化策を講じてきたが、参加者が少なく固定化したり、伸びとしては横ばいの傾向にある。平成21年3月31日時点で、トップページ・アクセス数は累計10万820件、会議室の総発言数は3287件となっている。
この会議室での議論を、県政に反映していただくために、この電子会議室で出てきた意見を運営委員会がまとめ、奈良県に提出する仕組みになっている。もちろん、意見のすべてが反映されるわけではないが、奈良県側も出された提案についてはきちんと回答をすることになっている。 提案と回答はインターネットでも公開されている。
(1)電子会議室を活発にするためには、
(1) まず、県民の意見を県政へフィードバックする仕組みがきちんと出来上がっていることが重要である。自治体が「インターネットを通じて届けられる様々な県民の様々な意見に対し、『聞きっぱなし』ではなく、庁内にて責任を持って吟味し、責任ある回答を県民に返すという覚悟」が必要である。単なる交流の場なら、「Yahooなど民間ポータルが開設している圧倒的な登録者数を有する掲示板に勝るものはない」のである。つまり、魅力的なコミュニティを作れるとすれば、自治体が持つ情報を積極的に発信することが望まれる。
(2) さらに、「運営委員会」「コーディネーター」「事務局」という組織が、電子会議室を円滑に回すためにうまく機能することである。
ア。運営委員会は、会議室のテーマ策定や意見を集約して県への提案書をまとめるのが主な役割である。運営委員はテーマの決定に参加し、参加者自らが主催する会議室なので、行政は情報を提供する立場となる。行政と県民の間に運営委員会が入って“緩衝剤”の役割を果たすことで、対立姿勢に陥ることなく『お互いの役割を考えながら自分たちでできることは自分たちでやろう』というパートナーシップ関係が生まれてくる。
イ。「運営委員会」とならんで重要な役割を果たすのが「コーディネーター」である。「コーディネーター」はテーマごとの電子会議室を管理し、論点整理や誹謗中傷など発言の削除などを行う。発言削除権限も持っている。参考までに、過去に誹謗中傷などで実際に権限を行使して削除に至った例はない。とはいえ、電子会議室でのトラブルは起こりうる可能性がある。
ウ。電子会議室を実際に取り仕切っていく「事務局」は、電子会議室全体を円滑に運営するためには、欠かせない役割を担っている。
これら3者が、うまくかみ合うことによって、正常な電子会議室が運営できる。
(3) テーマの担当課が直接参加
自治体の電子会議室を盛り上げるためには、これまでの経験で、行政情報の提供が議論を活性化することが分った。21年4月から、テーマの担当課がそれぞれの情報を発信するように県に要請し、副コーディネーターの対応で可能になった。その方が原則的には対応が迅速になるからである。
「既に広報紙などで公開されている情報については、会議室に回答するのに決済は不要」であり、「具体的な施策についての考え方などの情報で、自分の課だけで回答できる場合は課長決裁」は必要になるが、こうした取り組みによって、自主的に各課で情報を提供していただけるものと期待をしている。情報提供や返信は担当する各課がそれぞれ直接するという方向を望みたい。投稿者の側から見ると、今以上にもっと行政の声を直接聞きたがっているのも事実である。
(4) 県民の参加促進について
ア。紙媒体(ポスター、チラシ、地域情報誌など)、電子媒体(HPリンク、メールマガジン、放送など)による広報活動が大切である。しかし、せっかく普及活動をしても、興味を持って参加してみた県民にとって得るものがなければリピーターにはなってくれない。まずは行政による情報提供の質・量、レスポンスのスピードをさらに向上させることが、最も重要と言えるだろう。
イ。地域活動をしているグループも電子会議室に参加してもらいたいと考えている。県内各地で地域活動をしているグループがたくさんあるが、こうした人たちの情報交流の場を電子会議室で持てるような仕組みを検討していきたい。 ネット上でも地域コミュニティを作っていこうというのがまず一つである。
ウ。電子会議室を盛り上げるためには、これまでの経験で、市民の参加しやすい雰囲気作りが不可欠である。最近では投稿者がこの会議室を通じて交流するケースもでてきた。
(2)地域社会に根ざした電子会議室を目指して
協働型地域社会を形成するには、“コミュニケーションの場”が必要である。多くの人がリアルタイムに関わることができるのは、ネットが最適である。文化や経験の異なる人が、自由に対話することにより気付くこともあり、多様性を認め合うことができる。多様な主体が、地域課題について協働するには、多様性を支える不断の努力が成功の鍵と言える。
電子化と縁遠かった人間同士の付き合い方も変わりつつある。それは、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で代表される電子掲示板の普及である。連絡、情報交換の有効な手段との側面が強まっている。SNS利用が幅広い年代に拡大するにつれ、ネット上での最大の情報伝達手段が電子メールからSNSにシフトしそうである。
連絡や人脈作り、情報の在り方はウエブ上にあり、パソコンや携帯端末はウエブにアクセスする窓に過ぎない。これは、今世界で急速に広がっているクラウド(雲=ネット)コンピューティングと呼ばれる、インターネット中心の情報処理形態の典型例である。クラウドコンピューティングは、現実として急速に世界に浸透しつつある。職場や家庭におけるITの意味合いは本質的に変わろうとしている。そして、社会の営みの様々な形式・規則・法律等の物理的制約を変化させ、こういう状況に耐えていくために、行政及び地域は新しい試みを求められている。この“コミュニケーションの場”を、如何に有効活用するかが問われている。
II.提言
各電子会議室でまとめた「提案」の項目を提言として項目のみ下記する。詳しくは、後記する各電子会議室の報告をご参照いただきたい。
1.T−1:奈良の魅力の発信と観光客の誘致
〜奈良の歴史文化を発信し、奈良ファンをつくるために〜
(1)時代の風物史などを含めた歴史館なるものを展示するスペースを作ろう。
(2)見に行って・参加して楽しかったお祭りをもっと創造したり、発信したりしよう。
(3)奈良が出てくる映画・ドラマ・アニメ等々をもっと活用しよう。
(4)産業施設を集約して、自然と歴史の奈良の魅力を復活しよう。
・道州制の議論をもっと活発化する
・奈良の価値意識共有のための啓蒙活動強化
・本来の奈良の魅力度を高める
・木の香りが漂う町
(5)奈良県に来て頂いた御客様に自慢できる場所を持とう
(6)「大阪」「京都」「神戸」「奈良」の「四都」を形成できるように露出を広げよう。
(7)発信力を強化しよう。
(8)奈良の景観と建設とのパラドックスを解消し、ベストな建造物で奈良らしさを演出しよう。
奈良の景観を悪化させるような高層近代ホテルの建設は問題有り
平城旧跡を横断する近鉄奈良線の架線と支柱デザインを考える
(9)外国人労働者の支援しよう。
(10)「ホームステイ」を充実させよう。
(11)魅力の有る景観保全は、全体の眺望の重要性だと云うのを、行政府も県民も自覚しよう
(12)寺院の伽藍こそが奈良の都市としての独自性で有る事も自覚しよう。
(13)「奈良は大いなる田舎です」とは何を意味するか。
(14)奈良は宿泊施設が全国一少ない事を自覚して居るか
(15)現状イベントのブラッシュアップにより、奈良の魅力をアップさせよう。
(16)奈良近鉄ビル(奈良駅)改装案を再考せよ
(17)平城京の各条坊大路の位置をわかりやすく表示しよう
(18)IT技術で観光事業を活性化しよう。
(19)MBSラジオウォークに参加して。
(20)県プール跡の活用はどうなる!?
(21)道路行政はきちんと分析して見直しているのかを検証しよう。
2.T−2 :受診者の立場から医療資源を考える
〜限られた医療資源を守るために何をなすべきか〜
(1)医療資源の何が不足しているのか
(2)赤字公立病院経営の健全化は必要か。
(3)(医療崩壊は医療行政の問題
(4)医師不足ではなく、医師は増加している。
(5)周産期医療の崩壊の原因は産科診療所の激減。
(6)産科医を巡る諸問題について
(7)医療事故報道に対する批判。
(8)医師不足の原因は新臨床研修制度とする見方。
(9)医師不足問題を克服した兵庫県立柏原病院を見習いたい。
3.T−3 :地域ぐるみで学校を支援しよう
〜学校支援地域本部の取組を生かして〜
(1)学校支援地域本部設置の取り組み情報を積極的に公開する。
(2)学校支援地域本部事業の運営に関する情報を共有できる仕組みが必要。
(3)地域の教育的な活動をプログラム化する。
4.T−4 :平城遷都1300年祭を成功させよう
〜平城遷都1300年祭を機に「もてなし」を考える〜
 (1)トイレの改善
(1)トイレの改善
(2)交通渋滞改善策の推進
(3)1300年祭への県民意識高揚策
(4)挨拶運動の推進
(5)奈良公園の整備の推進
(6)マイベストスポットの発掘による奈良の
魅力の深耕
(7)美化活動推進
(8)平城遷都3キャラの活用
(9)その他
●まほろば検定試験には「もてなしの心」に関する出題を入れるべき
●1300年祭のPR兼ね東京での正倉院展等の積極開催
●まほろば検定受験者に対する特典・諸行事に関する案内の定期発送
●「鹿男あおによし」の撮影モニュメントの設置(平城宮蹟等主要撮影場所に)
III.電子会議室の報告
Ⅲ−1(T−1):奈良の魅力の発信と観光客の誘致
〜奈良の歴史文化を発信し、奈良ファンをつくるために〜
コーディネーター:金田充史
1.はじめに
奈良の歴史文化を発信しようとすれば、まず我々奈良県民が奈良の歴史文化が「どの様なモノが有って」「どういう意味を持っていて」「何の為・誰の為に行われているか」が分からないと発信する事が出来ません。そこで、この会議室では「奈良の歴史文化」を「奈良の魅力」と解釈し、御近所でこんな事が行われている、から、大々的な宗教行事までを研究し、発信していくデーターベースを造っていきたい、と考えております。例えば、近所の神社の秋祭りを調査していくうち、そのルーツは素晴らしい行事だった、何て事があるかも知れません。また、二月堂修二会の際に、練行衆が行っている行も異国情緒の香りがしますし、また、一つ一つの行に意味があります。奈良を知らしめるには、まず奈良県民が、奈良の魅力の再発見をしていき、これがひいては奈良ファンを増やしていくベースになろうかと考えますので、皆様のお知恵を貸してください。と、冒頭で説明をして、趣旨を明確にして、議論をしていく様に心がけた。ただ、このテーマは、漠然としていて、普段、我々が意識していないが故に、再度考え直さないと判りにくかったテーマで有った事は否めない。それ故に、魅力のとらえ方が人それぞれで多種多様な内容が見受けられる会議室となった様に思われる。
2.提案
(1)時代の風物史などを含めた歴史館なるものを展示するスペースを作ろう。
(2)見に行って・参加して楽しかったお祭りをもっと創造したり、発信したりしよう。
(3)奈良が出てくる映画・ドラマ・アニメ等々をもっと活用しよう。
(4)産業施設を集約して、自然と歴史の奈良の魅力を復活しよう。
・道州制の議論をもっと活発化する
・奈良の価値意識共有のための啓蒙活動強化
・本来の奈良の魅力度を高める
・木の香りが漂う町
(5)奈良県に来て頂いた御客様に自慢できる場所を持とう
(6)「大阪」「京都」「神戸」「奈良」の「四都」を形成できるように露出を広げよう。
(7)発信力を強化しよう。
(8)奈良の景観と建設とのパラドックスを解消し、ベストな建造物で奈良らしさを演出しよう。
奈良の景観を悪化させるような高層近代ホテルの建設は問題有り
平城旧跡を横断する近鉄奈良線の架線と支柱デザインを考える
(9)外国人労働者の支援しよう。
(10)「ホームステイ」を充実させよう。
(11)魅力の有る景観保全は、全体の眺望の重要性だと云うのを、行政府も県民も自覚しよう
(12)寺院の伽藍こそが奈良の都市としての独自性で有る事も自覚しよう。
(13)「奈良は大いなる田舎です」とは何を意味するか。
(14)奈良は宿泊施設が全国一少ない事を自覚して居るか
(15)現状イベントのブラッシアップにより、奈良の魅力をアップさせよう。
(16)奈良近鉄ビル(奈良駅)改装案を再考せよ
(17)平城京の各条坊大路の位置をわかりやすく表示しよう
(18)IT技術で観光事業を活性化しよう。
(19)MBSラジオウォークに参加して。
(20)県プール跡の活用はどうなる!?
(21)道路行政はきちんと分析して見直しているのかを検証しよう。
3.発言の概略
(1)時代の風物史などを含めた歴史館なるものを展示するスペースを作ろう。
「江戸時代」の「幕末」の「奈良」はどの様な環境だったのかは、奈良時代の雰囲気の分かるものが、時代考証が難しいのと、天皇家に触るからか、テレビなどのドラマのストーリーに成り得ていない事も一つで有ると感じる。
伊勢街道は、現在のルートで言えば、大阪の心斎橋を出て中央大通りを通り、枚岡神社横から暗峠・室ノ木峠を越えて、赤膚山、砂茶屋、尼ヶ辻を通ってJR奈良駅へ出て三条通り経由で猿沢池まで来る。この後は、旧上街道を通って奈良町を抜け、京終・帯解・櫟本・天理、桜井と続いていく。ここから、宇陀を通り、御杖村の山中から松阪へ抜けていき、宇治山田から伊勢へ入る。大阪・奈良・三重との3府県合同のプロモーションや、奈良単独ででも北部と南部をつなぐ観光ルートにも成りうる可能性も秘めている。現代の伊勢街道を復活させよう。我々は普段何気なく見過ごして居るが、こんな事が地域の魅力ではないか。
街道は、周辺との関わりが育まれて、馴染み、愛着が湧いて来る。その人々の思いを知り、感じ、共有するものが無いと何の意味も為さない。郷土史研究家とか大学での講座など、街道にまつわる研究をしている人たちがいるはずで、その人たちの知識を一般に広める努力をサポートする仕掛けが必要なのではないか。現代が歴史上最も幸せな時とは思えない。その楽しさ、豊かさを思い起こす、発掘する、広めることが大切だと考える。それで、「公開講座を積極的に開く。」「奈良をテーマとした芸術を公募し分野別に表彰する。」「古地図の活用」などの対策が望まれる
(2)見に行って・参加して楽しかったお祭りをもっと創造したり、発信したりしよう。
「見に行って楽しかったお祭り」「参加して楽しかったお祭り」「ずっとずっと昔から、おじいちゃんの子供の頃から行われているお祭り」等々に参加されたり、見に行ったり、と云う事が有ろうかと感じるが、具体的に挙げれば何が有るだろうか。
やはり「なら燈花会」を立ち上げた時。夏の奈良を何とかせにゃ!と云う考えの基で、浮雲園地で試験点灯までをこぎ着けた事は、昨日の様に記憶している。こんな経験は一生涯のうちで何度も無いが、この経験が基で、いろいろな小さな催事を経験出来る様になった。
ならまちセンターでの「篝火コンサート」。街角でのプチコンサートという感じの近親感が良い。年に何回かやっているので、宿泊客に案内してもよさそうだ。
県庁屋上での「夕暮れコンサート」。景色抜群の処、カラスか鳩か、鳥が舞う、その高さを共有出来て、正に天空で聴く音楽の味わいが良い。
榛原の体育館で開催されていた農業品評会。地元で採取したきのこや、鹿肉の入ったきのこ汁を販売していた事だ。県民自体が参加してみたいという祭りを奈良で開催すべきだ。
(3)奈良が出てくる映画・ドラマ・アニメ等々をもっと活用しよう。
発信力が無い、的な議論も有ったかと感じるが、発信するツールの一つとして映像が有るが、奈良県下でロケハンされた映画・ドラマ・奈良県が舞台のアニメなどはどんなモノがあるか検証する必要が有る。得てしてドラマロケ地などは、監督自身が魅力に感じているから、ロケ地選定される訳で、我々の気の付いていない事も有ろうかと感じる。
古いところでは「春の坂道」。柳生街道が大混雑したそうだ。東映映画では、ちょっと古いが「連合艦隊」。猿沢池や東大寺が出て来る。中井貴一が若い。また、唐招提寺で「空海」のロケ。加藤剛、が最澄役で出演していた。
山岡荘八著、柳生石舟斎。これは山岡荘八の目で石舟斎を現代に生き返させた。その他、雑誌の力、写真の力も見逃せない。絵画もその仲間だ。
関西在住作家5人が競作したうちの一編の「ひかりもの」というお題で、螺鈿(奈良漆器)とか、万華鏡(水門町の喫茶しろあむ)、大仏蛍、燈花会、さまざま織り交ぜてストーリーが展開する。
(4)産業施設を集約して、自然と歴史の奈良の魅力を復活しよう。
・道州制の議論をもっと活発化する
道州制への移行が議論されているが、県という単位でなく、関西庁・近畿統括庁という括りの中で広域に合致した機能を促進させるしかないのでは無いか。それで工業団地など、奈良県という枠組みにとらわれると県の税収と言う観点から重要だが、阪神港湾地区と比べると相対優位性が全くない。奈良は国或いは広域行政区の直轄観光行政重点地区としての位置づけ、或いは道州制の中での観光特区としての位置づけを狙っていくべきではないかと思料する。人口減少が進む今後の日本の構造変化の下、現在の奈良県や奈良市という行政単位ではこの素晴らしすぎる国富、偉大な観光資源を保全しながら盛り上げていくのは発想としてムリがある。
しかし、斯様な事が本当に可能な事なのか?言い方を変えれば、国家によって経営される観光資源、と感じるが、奈良市長・奈良県知事は共に中央官僚、彼等の得意分野かも知れないが、現状は斯様な感じはしない。しかし、世界遺産が3カ所も有る現状は、世界に誇る資産でも有り、出来ればこんなに素晴らしい事は無い。これを実現させる為には、県民・市町村民として何をすれば良いかを考える必要が有る。
・奈良の価値意識共有のための啓蒙活動強化
奈良女子大や奈良教育大などりっぱな国立大があるにもかかわらず、どうも他大学とのカリキュラム上の差別化が不十分だと感じる。奈良としてソフト力(古都都市計画論、仏教建築、奈良仏教論など)を高めていく上で折角二つも国立大学があって実力次第では全国或いは海外からでも留学生が来る可能性だってあるのだから真剣に奈良のソフト力を高めるような学府として機能してもらいたい。私立大学では、奈良大学や帝塚山大学は、特徴のある取組をしているように思う。奈良大学は、地理学では有名だし、帝塚山大学は、eラーニングで全国的な取組で有名。奈良県も、世界から若い学生を増やす政策を取り入れるには、世界に通用する学府が重要だ。
県立大学は、全国に先駆けて「観光学部」を創設したが、まだまだ現場観光業のとコラボレーションは出来ていないし、学問の域を出ていない。奈良の大学で、こんな学部で、こんな学問を実地も含めて出来る、と云うのは、どの様なモノが有るだろうか。
奈良の学府で育成し、それが日本全体はもちろん奈良に貢献するような学問としては、景観法運用の実践者プロ育成としての「まちづくり」。この中でどう町屋を維持し、まちづくりの中でどうコミュニティを維持していくべきか、について是非、専門家を育成し、建築のプロというベースで人材を育成していくべきかと考える「まちづくり建築学科」。
持続的サイクルを林業、街並み、農業の総合的観点から確立し、CO2排出をコントロールできる地域づくりを目指す「環境学科」。
持続的に森林の維持を手掛け、まちづくりを木で担っていけるためには人材が必要だ。
ホテルマン育成でなく、奈良がハードに頼らずソフトで勝負できるような観光・宿泊事業者で牽引されるような人材育成の場として、歴史・地理・食事他文化全般での有識を持った上でサービス提供できる独自の「観光学科」。
東大寺や興福寺、薬師寺などとのコラボで、仏教のみならず世界の宗教を学んだ上で奈良仏教の位置づけ、方向性を極められる「宗教学科」。
奈良県立大学では、地域創造学部の中に観光学科があり、そこでは、歴史・地理・社会・文化等の知識を育み、観光まちづくりや観光産業に従事する人材を育てている事に対して、もっと誇りをもって、しっかりとアピールしてもらいたい。しかし、研究材料にこれほど興味深いものは無いのにも拘わらず、卒業生が県内でなく県外に流失しているとも思われ、これがさみしい限りだ。しかし、奈良県のファンになって、県内で就職したいと考えている卒業生は少なくないと思うので、奈良の産業界、地域が一体となって、大学をもりあげ、その大学がしっかりと産業界や地域や行政を支えていくという仕組みを作り出す必要があると切に願う。
・本来の奈良の魅力度を高める
奈良の魅力は自然と歴史だと思うが、その中にその魅力を壊す工場や商業施設が混在する。典型的な事例が平城京跡前の積水工場だ。奈良県に散らばって自然と歴史を破壊している工業・商業施設を工業団地に集約する。有利な条件で場所や支援を準備する。そのようにして、奈良に来る観光客には本当の自然や歴史を堪能してもらえるようにする。
奈良県内は、産業誘致のノウハウが薄かった為、負け続け、唯一の成功例が西名阪横の郡山市工業団地だが、ここも工場の更新時期となり、移転計画も持ち上っている。ただ、工業用水の確保や土地面積の現状を考えると、大阪・名古屋方向の物流拠点としての機能を求めるしか現状は難しい。また、新大宮周辺の雑居ビル、道路沿いの中高層ビル・広告もかなり古都の雰囲気とはかけ離れており、行政・規制が何もしなかった結果だ。景観法の積極活用と都市計画の抜本見直しが必要だ。工場団地の件は、場所の確保さえ出来れば良い。少し大胆だが、もう今の都道府県制度の元では奈良の歴史風土・観光機能を維持・促進するのはムリがある。今までも行政がそれなりに取組んできたことだが、相対的な地盤沈下は否めない。逆に、大手商業ゾーンを積極的に誕生させると、地元の零細商業者は閉業を余儀なくされていると云う見方も有る。奈良市内では、お年寄りの買い物に不自由な地域が出てきている。県北部には、大規模開発できる土地は残されて居ない。また、ここはどこを掘っても埋没文化財が現れ、文化庁や教育委員会の規制が加わり、予定通りのスケジュールで完成しない。南和地区も景観保護の観点からすると、大規模開発は難しい。観光客誘致と、地元住民の生活保護という観点は対立しないが、地元住民にとっての利便性を考えた上で、活力ある地元商店、活力ある地元産業というあり方を考えたほうがよい。
・木の香りが漂う町
寺社は、伊勢神宮の遷宮事業に見られるように、背後の山林も育成している。春日原林の周辺などは明らかに香りが漂っており、独特だ。奈良の町全体が品のある香りでカバーされたらどんなに素晴らしいことか。一方で、クルマでのアクセスについては一定の制限が必要と考える。国立博物館前の登大路から大仏前、春日大社前など、完全にクルマを閉め出しても良いのでは無いか。奈良公園の松林の劣化や古代建造物へのダメージも懸念されるところであり、社会的責任として、自動車メーカーへの訴追も将来は展望に入れても良いかもしれない。
奈良県は、県土の77%が森林で、春日山原始林」・「紀伊山地の霊場と参詣道」共に世界遺産と、三拍子も四拍子も揃っている。中にはヒノキの香り成分を抽出したり、チップを枕に埋め込むなどのアイデア商品を販売されているところもある。1300年祭でも、宮跡会場内では県産材を使うそうだが、どんどん使って木を伐り出し、また新たに植林して、うまく循環させてほしい。県は、民営駐車場の経営者に気を使うあまり、車の締め出しには消極的だが、大ナタを振るうべき時期が来ていると考える。大仏前交差点の東南角の原生林を伐採して大駐車場を、と云う計画を、奈良商工会議所で見た事が有るがとんでもない話だ。また、文化財保護の観点から、奈良旧市街地の寺社近くへのバスの流入も控えていく時期にさしかかっているかも知れない。
(5)奈良県に来て頂いた御客様に自慢できる場所を持とう
・奈良県内の自慢出来る所はどこですか
奈良県民が、他府県からの御客様が有った時、どこを見せたいか。色々な場所があろうかと思うが、これこそ奈良県の魅力ではないか?御客様には、近所でも、車ででも満足して頂けると信じる所にご案内をする筈だ。葛城の路から臨む天香具山・耳成山・畝傍山の一望。葛城王朝に選んだ理由が判りそうな開けた清涼感がたまらない。日本の出発点を感じさせてくれて、まずここを見てもらい、そのあと各地を見てほしい。
ヨーロッパから来た、神道仏教とか日本の歴史に明るくない方たちでも喜ばれるのは、鹿とふれあえる公園と、東大寺大仏。奈良在住の人には素麺作りがうけた。関東地方に住む50歳以上の人達には明日香の石像群、柳生、室生。絵を描く人達には墨作り体験、筆作り見学が喜ばれた。九州からの若い人達は鍵型をした古墳を見てみたいというので崇神天皇陵。神社巡りが好きな人には三輪神社、というところと考える。日本人には、奈良は廃都なので、想像して風景を見てほしいと申している。しかし、亀型の水盤があるところも囲みこんで有料にしていたが、整備せず、囲い込まないようにはできないのか。
奈良の場合、他に類を見ないのが、どこにでもある畑や古びた商店街のある所に国の宝がちらばっている所に特徴が有ると考える。一個の重要文化財をとても大事にあがめている所ばかりだ。京都観光より安く観光できるというメリットを作ったら面白い。お寺の宝物も庭も京都のそれと比べたら寂しい所が多いので、高い拝観料を取られると一気に奈良の印象は悪くなってしまう。
・早朝の駅前周辺の問題点
京都は、朝からおいしいコーヒーが飲める老舗の喫茶店や、かわいいカフェが多くあって便利だが奈良のカフェは、朝はやってないし、靴脱いで・・・というお家系が多いので、ちょっと面倒。奈良での気の利いた喫茶店は、有るには有るが、交通の便がよいとは限らない。しかし、知らしめる努力が足りないのではないか。
外国語での情報発信といえばNara explorerがあるが、こちらに「早朝から営業している喫茶店の情報提供はありますか?」との照会を掛けてみてはいかが。JR・近鉄付近と、商店街内には、7時から朝食の準備をしている店も有り、これらの情報も有機的につなぐ必要も有る。また、奈良発の夜行バスについても同様で、チケット購入時に、近辺のホテル風呂や銭湯案内も添えたら、たいへん重宝される。フィットネスクラブに入ってもらって、そのシャワールームを提供する、という運用も考えても良いかもしれない。奈良発夜行便の場合は、近辺に銭湯の紹介で充分と考える。ネット予約で、乗車票を手元で印刷する際、一緒に広告や案内チケットも含めて印刷してもらうようにすれば手軽だと考える。この様な事に対して行政は、利用者、消費者、市民、県民の意見として判断し、対処することを期待したい。
(6)「大阪」「京都」「神戸」「奈良」の「四都」を形成できるように露出を広げよう。
「奈良」は「三都物語」に入らないし、「新幹線」からはかなり遠い。「大阪」「京都」「神戸」「奈良」の「四都」を形成できるように露出を広げる事を考える。京奈和道を完成させよう。奈良県の縦走は観光客誘致にも住民の生活道路にも重要な背骨になる。
今の外人旅行者は、団体よりも西欧は個人が主流だ。もっと個人にターゲットを絞り、関西エリアとして受入の仲間入りをすべきだ。京奈和道は、物流観点から意味が無い。阪和道で十分対応可だ。24号や天理線の混雑は目に余るが、これは高規格道路でも対応可だし、京都・奈良・和歌山を一本でつなぐ事とは直接関係無いと考える。京奈和は、平城旧跡地下や恋の窪の高架の問題も孕んでおり、過去の大規模道路の幻想の感も否めない。また、通過車輌増大による排気ガスの問題も出てきて、盆地故にガスの逃げ場が無い。
(7)発信力の強化しよう。
催しの案内は、チラシやポスターで行っているのだろうが、一般には、なかなか知りえない。安くもっと広く伝わるような系統的な広報手段がないものか。
広報手段としては、催事にせよ何にせよ現状は、チラシ・ポスター戦が主だが、電子媒体も使っている。しかし、一番大変なのは、チラシを何処で撒き、ポスターを何処へ貼るか、また貼るにはどうするかだ。チラシを自分で置きに行ったり、ポスターを張り廻ったりしないといけない。電子媒体も星の数ほど有り、どうしてアクセスを増やすかも大変だ。この事は、発信者側の思いを広く多くの人に伝えるには、無作為で発信しては届かないと云う事が分かる。実はこの問題が、今一番ホットなWeb問題なのだと思う。良質な情報(HP)への案内をしてくれるポータルサイトを有志団体が運営する様になるかも知れない。Web時代のコンシェルジェのような役目をしてくれるわけで、こんな仕組みが出来ると、奈良の文化力を発信して、お客を招く力になると思う。
(8)奈良の景観と建設とのパラドックスを解消し、ベストな建造物で奈良らしさを演出しよう。
奈良県の客室数は全国最下位、宿泊施設数は全国最下位から2番目、斯様な数字の為に、奈良市がJR奈良駅西側再開発・シルクロードタウン21計画と云うモノを打ち出して、ここへ旧三井ガーデンホテルを誘致した。また百貨店やホールなども装備して平成10年に完成予定が、現在も未だ手つかずだ。ホテルも結構だが、ここで斯様な建造物が当然の事として増えて来ると、眺望景観は無惨な状態になるし、またそれだけでなく、今でも新大宮周辺は地方都市の容貌そのままだ。ただ県の申すように、客室数・施設数だけで見ると、最下位クラスは事実で有る。斯様な条件で、どうしたら奈良に宿泊施設が満足に出来て、また無理矢理誘致と云う手段に打って出なくても自然と建ってくる環境になりうるだろうか。今、県営プール跡地は、高度規制25m・容積率60%・建坪率40%、奈良市の誘致しようとしたマリオットコートヤードは、高度規制40m・容積率600%・建坪率80%です。この規制の是非も含めて、如何お考えか。
・奈良の景観を悪化させるような高層近代ホテルの建設は問題有り
観光客増加のためという名目で、奈良の景観を悪化させるような高層近代ホテルの建設には反対だ。観光としても、価値のある奈良の根源的な古都としての存在意義は、歴史・自然景観を残し、持続的サイクルが伝統と共に維持されていることが素晴らしい、ということで、自然や景観を破壊する行為は、本来の奈良の良さを大事にしたい旅人、或いは奈良を良いところと思って、いつかは訪れたいとする人々の心さえも痛める。奈良に宿泊する方は京都と異なり、物欲先行でなく、精神性或いは歴史、仏さまなどきちんとしたテーマがあって来られる方が多いように見受けられる。そのような方々にとっては、奈良公園周辺に昔からある宿屋こそが好ましく、近代高層ホテルなど建ててしまえば、奈良自体が幻滅の悲哀になってしまう。奈良市が誘致しようとしているマリオットコートヤードなど論外だ。ホテル日航は既に建ってしまって、薬師寺、西ノ京、あるいは平城宮跡地からの奈良東方の景観が著しく悪化している。むしろ、奈良町周辺の町屋や旧市街でのホームスティなどで宿泊部屋数を伸ばすべきだ。そのためには既存の宿泊事業者さん有志で、組合形式で新しい運営組織を立ち上げ、奈良での宿泊サービスのスタンダードを決め、サービスできる人材を育成するのが望ましい。「ホテル」を誘致建てるのでなく既存の店舗宿泊施設の再開発して魅力ある地域にするという再構築に資源を投入するほうが良いと考える。奈良を訪問する観光客を何人か案内したが、全てに共通しているのは「和への回帰」志向だ。奈良においても、畳のある宿泊施設、或いは旅館、或いはクラシックホテルの奈良ホテルなどが支持され、こういった所が、奈良の独自性に有り得ると思う。かつての旧日吉館が、どれだけ奈良の印象を良くしたことか。ソフト力が大事だ。今は薬師寺からの写真でポスターに使うのは全て合成偽装になってしまっている。奈良のファンを増やすということはリピーターを確保することでありそのためには大量消費的なハード志向の高層近代ホテルは不適格だ。各地から奈良に来られる方達と一緒に、奈良を観光して回っていた時に気付いた事は、数は少ないのかもしれないが、魅力的な宿泊施設がなかなか見つけられない、というのが問題だ。少し遠くへ目をやれば昔の人が見たであろう景色が見られるようにしておかなければ、それが奈良の観光資源化と思う。魅力的な宿泊施設とは、ここだけにしかないものがある宿泊施設だ。江戸三に一度泊まりたいと切望した。魅力的といえば奈良ホテルを挙げられると思う。
・平城旧跡を横断する近鉄奈良線の架線と支柱デザインを考える
平城宮跡を横切る電車だが、地下はダメとなっている。しかし、何が景観を崩しているかと言うと、架線とその支柱だ。つまり、架線を外せば景観はずっと良くなる。平城宮跡を走る近鉄線の架線をセンターポール式にして、さらに太い電線類を地面に下ろした場合、この程度なら景観としてなんとか許容でき、比較的低コストでできるのではないか。近鉄の線路を見たら、黒い電線と薄い青色の電線とが架かっていた。薄青色の電線は、さほど目ざわりでは無い。実際に一部の電線の色が最近変わったのか、明るさやカメラ位置の関係で全部の電線が黒っぽく見えていたのかはわからないが、電線の色によって目ざわり具合が、かなり変わる可能性もある。奈良大学で、「平城宮跡の国営公園化と奈良のまちづくり」というシンポジウムが開催され、最近は「線路はそのままでいいじゃないか」とか「電車の窓からの景色がすばらしい」という意見も有った様だ。
(9)外国人労働者の支援しよう。
ブラジルや東南アジアから多くの外国労働者の、数万人は住んでいるとのことで、大半のひとは、自国へ送金している為、日本での生活は決して余裕のある生活ではない。言葉の問題が大きいようだが、真面目に勉強している人もいる。奈良のよさを知ってもらうために、雇い主と連携して、こういう人を支援するNPO活動があっても良い。
(10)「ホームステイ」を充実させよう。
「ホームステイ」というのはいかが。通常、外国人を受け入れるものだが、他県のものを受け入れるという発想だ。各家のキャパにもよるが、部屋数が多く、空いている家であれば2・3組は宿泊可能だし、むしろ泊まる側も他人の家に泊まるとき1組で泊まる方が気を遣うかもしれない。ホストファミリーが170箇所で1ホテル分は生み出せる。実際に奈良の高齢化も進んでおり、空き部屋が存在する家が相当あると思われる。大きさだけが良さでは無い。外国観光客海外は、安く気楽に泊まれる処を探している。確かに奈良町辺りを散策していると、小さな旅館に出入りしているのを見かける。外国の人だけではなく日本人でも旅館のあり様によっては受け入れられる。奈良に訪れ、奈良の人に接してもらい、家族ぐるみの生活を観光で体験してもらう。これこそ人の絆ができて、それでこそ、奈良ファンを生み、リピーターを作っていくのではないか。
(11)魅力の有る景観保全は、全体の眺望の重要性だと云うのを、行政府も県民も自覚しよう
素晴らしい・美しい、残していきたいと感じられた風景について語って頂きたい。
あの川に舞う蛍が見たい・あの山にいっぱいススキが生えるのが見たい・若草山の山焼きのとき、山全体が燃えるといいな・街道から眺める山がきれいなのだけど、あの建物、電柱が邪魔だな・街を安心して散策できて、疲れたら気楽に休める場所がほしいな、そんな身近なことから、動き始めることが大事だ。その火付け役、支援、広報を県、市町村が率先して行う風土を作ることだ。道路沿いの電線の見苦しいことこの上無い。残していきたいと感じられる奈良の風景とは、個々の古建築の風景もさることながら全体の眺望だ。日本の都市空間は京都をはじめどこも近代化の流れでコンクリジャングル化、都市景観規制概念の欠如で、かなり危機的状況だが、まだ救われている。素晴らしい眺望点としては、あの県庁、近鉄奈良がなければもっと最高だが、二月堂或いは若草山、高円山からの奈良市街眺望はわが国の都市景観としては最高峰に挙げられる。これらの地点からでは、「30度で見下ろす俯瞰」が景観上のポイントだ。見下ろす眺望で、遮蔽物がほとんどなく、東大寺伽藍、興福寺伽藍と奈良公園の歴史・自然空間を堪能できる贅沢な風景美だ。また市内からなら猿沢池以南からの興福寺伽藍を見上げるシーンも絵になる秀逸さだ。平城宮跡地からの奈良外京の見上げる景色は、巨大な大仏殿と若草山がやはり他の都市空間にはない素晴らしさになっている。浮かんでくる風景には、ビルなどの人工的構造物は存在し得ないのは、風景の中に有ってはいけない物なのだろう。大規模ホテルは不要との理論が相当有り、行政は方針転換をしてほしいモノだ。若草山・高円だけではなく、これに類した規模の山々では全て使えそうだ。全て使えると云う事は眺望景観が如何に大切かを教えている気もする。海外では、「世界遺産の建物で暮らせるんだから」とむしろ「誇り」にしていて、暮らしにくいとは云え、理由には納得のいくローカルルールが存在する。奈良も、もう一歩踏み出しても良い。鹿に鹿煎餅以外のものを与えたら罰金や営業停止、大台ケ原への生き物連れ込み禁止(介助犬除外)、など。
(12)寺院の伽藍こそが奈良の都市としての独自性で有る事も自覚しよう。
寺院も、東大寺や興福寺、蔵王堂などの巨大な寺院から、奈良町の町中の、こじんまりとしたモノまで様々だ。また大小に拘わらず、すでに風景内にとけ込み、奈良の風景と一体化している所が全て、と言っても過言ではない。ここで、素晴らしいと感じられた寺院と、それにとけ込んでいる風景について語って頂きたい。
奈良の寺院は格別であり、巨大であり、迫力があり、オリジナリティを尊重している。興福寺の五重塔など何度となく焼失しているが、その都度再建し、今でも、奈良時代創建時のスタイルに則り、聳え立ち、奈良のランドマークになっている。寺院の伽藍こそが奈良の都市としての独自性であり、アイデンティティだ。この伽藍と自然の風景が融合してこその奈良であり、寺社の姿はその創建時になるべく回帰することが求められる。そこには奈良仏教としての教えがあり、ハード(伽藍・仏像)と仏教の教え(ソフト)が一体である。高層建造物が建ち並ぶまでは、市内のどこからも、絵になるような景色で眺めることができた。絵になる風景としての心象になりえるのが奈良の寺社の特別さだ。
寺院は、伽藍、建物だけではなく、ソフト面が大事とする中で、仏教開花の奈良の地でさえ仏教離れの現状にあることが由々しき課題だ。本質は釈尊の知恵であり、マネーゲームに狂う世相にあって、今こそこの知恵を活かす奈良からの元気な発信が望まれる。その現状の問題を考えれば、奈良のよさ、景観復興の意味が自ずと見えてくる。単なる見世物で終わるのではなく、また訪れたい、そう思うもの、それは、その訪れる場所がいつも新鮮に感じる、生きている、脈動していると感じることが出来る、寺、神社、地域住民がともに溶け込んだ環境を造ることだ。
(13)「奈良は大いなる田舎です」とは何を意味するか。
一人旅の女性と小さなレストランで出会った。「奈良のどんなところが良いのですか?」質問した処、「奈良の人は親切です」と答えが返ってきた。「奈良ってどんな所ですか?」質問した処、「奈良は大いなる田舎です」と答えてくれた人がいた。「素朴な奥床しさが残っている」のが奈良だと云われる。滋賀直哉は奈良に住んでいたことは有名だが、武者小路実篤も奈良に住んでいた時期がある。新潟出身の会津八一も奈良を愛したひとりだ。その他多くの文人が奈良に魅力を感じていたし、他府県の方々も、奈良の良さに惹かれて移り住んで来られている。大きな都市の中に原生林があるのは奈良だけではないか。「奈良は大いなる田舎」とは、なかなか意味のある表現だ。奈良を表わす端的な表現かもしれない。”大いなる田舎”、”素朴な奥床しさ”等、この表現の中にある特徴を分り易くして、流行語になるくらい、使用してみては如何か。
奈良の良いところを思い返してみて、一番印象的だったのが、やはり地元の方々の姿だ。興福寺には、南円堂で手を合わせては去っていく地元の方をたくさん見た。他にも、52段の階段や猿沢池で話し込む若者たち、平城宮跡の原っぱでキャッチボールをする少年たち、私が勝手にイメージしていた「世界遺産」とは違った日常的な凄みがあったように思う。1000年以上前に、祈りをこめて寺や仏像を造った人がいて、その後も、時代ごとにそれを受け継ぐ人がいて、今に至っていて。その凄さを全身で感じた。「大いなる田舎」という言葉が、ほんとうにぴったりとそれを表しているように思える。しかし、一方では、奈良については心情として「美しきかな奈良」は、全ての奈良に係わり合いのある人々にはそういうフィーリングであって欲しいと願ってやまないが、果たして、奈良に「田舎」という表現が相応しいかどうかという点が気になる。奈良をして田舎と呼ぶのでなく「古都」として表現されるべきかと思う。と云う意見も存在する。
(14)奈良は宿泊施設が全国一少ない事を自覚して居るか
TVで奈良は宿泊施設が全国一少ないと伝えられていた。何かの間違いではと思ったが、事実で、47位だった。奈良には沢山のお寺や神社があるが、泊めていただける所が少ないように思う。この投稿をご覧になったお寺のご住職、神主さん、宿坊として観光客を泊めて頂けたら、また、神社・仏閣にご縁のある方、それぞれに働きかけて頂いたら、宿泊施設の増加にならないか。お寺や神社の行事等を真近に見て、観光客は勉強になるし、心を養うこともできる。又、お寺や神社のPRにもなり、多少の収入になろうかとも思う。
寺院の施設で宿泊するのは難しいのなら、その周辺民家で、ビジターを泊めるという事も出来そうだ。そんな事を通じ、交流が豊かになって来る。一人で始めるのは大変だから、これを支え、提案する民間機関の芽生えに期待したいと思う。
宿泊施設が少ないのは、需要が無いからだ。神社・仏閣の宿坊を利用するというのは企画としては目玉の一つにはなるが、それで奈良の観光が変わるわけでは無い。夜20時に閉めてしまうような観光街に誰が泊まるだろうか。食事処も、京都には地産地消のほかにも、隣接地から供給を受けて名物にしているが、奈良は地元に拘り過ぎて、何ら名物らしいものを発信していない。如何に観光客にお金を落としてもらい、泊まりたい町にするかが先決だ。行政と産業界は車の両輪のような役割があり、奈良県の現状をみると、これがよく見えない。車の両輪をつなぐ心棒のような役割をするコーディネーターのような人がいないように思う。次に言えることは、県民に「知らせる場」を作っても、魂が入っていないから、単に作ったという実績だけに終わって成果が出ていないことが多い。これらの問題を解決しないとなかなか発展しないように思う。
(15)現状イベントのブラッシュアップにより、奈良の魅力をアップさせよう。
2010年には平城宮蹟に大極殿が復元される。朱雀門が復元されて久しいが、雑草が生え、わびしい。発掘遺構を見ただけでは建物の空間が想像しがたい。そこで建物と周辺を復元する。しかしその建物をいかに利用したかは想像できない。そこで営まれた人々の活動を復元する。観光客はその素晴らしさを理解し、文化の奥深さを感じる。世界遺産は建物とそこで営まれた活動を含めていたはずであったと記憶している。観光客は、文化の奥深さに嵌まり宿泊するようになるだろう。世界的な観光客争奪戦の中、奈良は負けられない。平城旧跡は、遺跡研究者、ボランティアガイドの皆さんが頑張っている。これが何よりうれしいことで、木簡の読み解きは埋もれた歴史の楽譜を読み解くかのようで、楽章がつながり壮大な物語として展開している。これを文字(楽譜)として図書館に収めても、奏でる術を知らない人々にはちっとも面白くない。楽譜を読める人に奏でてほしい。それが文化を広め、楽しむということだと思う。平城京で誰が、何のために、どのようなことを行っていたのか、今日の社会との関連はどのようなことなのか、当時の食事は、一般の人たちの食べ物、貴族の食べ物、遊び、衣装はなど、それを復元し、観光客に提供する場を設けることを、関係者は考えていることと思う。
(16)奈良近鉄ビル(奈良駅)改装案を再考せよ
奈良近鉄ビル(奈良駅)が遷都1300年祭への対応で全面改装となり、ガラスを使った二重壁とし、透明感のある現代風に改造するとのこと。夜間は二重壁の間に照明を設置してライトアップする(奈良新聞報道)。1300年祭への対応という意味では良いかもしれないがこの近鉄の外観改装には違和感を覚える。
この建造物は、奈良の品位、街並みバランスを壊している。とても奈良の景観に似合うとは思えない。本来、駅ビルと云うのは、飲食店街や名産店街、専門店などが入居して、ランドマークとなる建物で有る訳だが、こんなにも人が上に上がらないビルは珍しい。いっその事取り壊して低層階の奈良の景観に相応しいランドマークビルにしてしまうのも、一つの手段なのかも知れない。昔は、近鉄奈良駅は地上で、木造駅舎で有った。この時代のデザインを踏襲して、現代風に建ててみるのも手かも知れない。また、あの狭い観光案内でとても奈良の観光のために、機能発揮しているとも思えない。近鉄奈良駅で観光客を迎えるという機能は不十分だ。奈良市は、人通りが多い近鉄ビルの方で近鉄と連携して奈良らしい外観でより機能アップした施設を造るよう努力すべきだ。
(17)平城京の各条坊大路の位置をわかりやすく表示しよう
奈良市民は、自分の住んでいるところが平城京の何条何坊にあるのか認識している人は少ないのではないか。そこで、平城京の各条坊大路の位置をわかりやすく表示したらどうか思う。
「奈良時代MAP 平城京編」(新創社著作/光村推古書院発行)と云う地図帳が有るが、この地図帳は、現代地図をトレーシングペーパーの様な紙に印刷し、その下の昔の地図を透かして見る事が出来るが、昔の方がこんな所を歩いていた、的なロマンを感じる様な街で有りたい訳だが、看板は当然の事乍ら、築地塀などを部分的に復元させるとか、古代の道路の様式を再現するとか、目で見て判る様にすれば、もっと親しみがわくのでは無いか。他府県には無い訳だから、これこそ住んでみたい街の要素の一つかと感じる。標識や案内板も、市民や観光客の声が高くなれば、いずれ実現するのではないか。気長に声をあげていくことが必要だと思う。
(18)IT技術で観光事業を活性化しよう。
奈良の魅力の発信と観光客誘致というテーマにおいて、IT技術で観光事業を活性化する提案があまりないように思う。IT技術で観光客を動かしていくことをe-観光と勝手に命名してみる。たとえば観光客は近距離(10m)でのデータ通信ができる携帯電話、4000万台の普及があるワンセグ放送受信機を持っているとすると、近鉄駅に到着すると奈良のイベントがすべて見ることができる。そのイベントの会場に行ける交通機関、到達距離・時間が付加され、興味を引くイベントに観光客は動く。また観光地では情報をe街路灯から上記の端末に提供される。街灯にカメラを取り付けて防犯も兼ねる。これらのシステムが構築できるインフラを整備し1300年記念事業として実証実験を行うことは将来の観光事業を活性化させるのではないだろうか。これらの観光情報を関西空港、東京駅のディスプレイに表示できれば奈良の観光客の増加を産まないだろうか。
(19)MBSラジオウォークに参加して。
2月11日のMBSラジオウォークに参加した。当日の飛鳥は好天に恵まれ、約2万人の参加があった。この大イベントに、奈良県観光課や橿原市観光課の顔が見えなかったのは、大変残念だ。行政のメンバーが見えなかったとのことだが、2万人の中に混じってはわからないし、ちょっと目立つことをやって、注目しているよとのアピールが望まれるところなのか。この辺りのところが、行政人の下手なところなのか。住民は顧客なのだとの認識が薄いのだと思うので、やはり市長が率先して意識改革を進めないとこれからの時代は行政も大変になる。また2万人も集まるその魅力は一体何なのか。
日本の古都としての潜在需要か。パブリシティ戦略は、テレビやラジオ、新聞、雑誌等のマス媒体を利用して、広告ではなく、イベント情報を発信してもらうことで、消費者に訴えるプロモーション戦略のことで、奈良県は下手だ。大阪府の橋下知事や宮崎県の東国原知事を先頭に、京都府の山田知事や滋賀県の嘉田由紀子知事などは、うまくパブリシティを利用している。県地域振興部がその所轄部署になると考えるが、奈良の観光情報をツーリストに売り込みをすると同様、このようなイベントを参考にして積極的に仕掛けをし、売り込みするチャンスがあると理解した。
(20)県プール跡の活用はどうなる!?
2月25日の新聞報道によると、奈良県は、県プール跡のホテル誘致事業について、隣接する奈良警察署を移転して、跡地を一体的に開発する方針が報じられている。商業施設等を誘致し、ホテルとの相乗効果を狙うとのこと。詳細不明だが、なかなか思い切った発想だ。平城宮跡にも近いことだし、地域の活性化になるのではと、期待している。
こちらは、県が誘致しようとしている場所で、今回の藤原市長の立候補断念まで追い込んだ計画は、JR奈良駅西側だ。ただ、これに失敗してしまったが故、県の事業にも暗雲が立ちこめだしたのも否めない事実なので、まだまだ誘致しようと水面下で工作されている様だ。
また、税金は、「公益性」が必要だ。結婚、死亡、交通事故その他諸々、住民、あるいは市役所、警察署の職員にとっても隣接していることは大変利便性が高い。その利便性を無くしてまで、ホテルを誘致するというのが理解に苦しむ。各種アンケートや県民アンケートを見ても、行政に対して望むことは、「医療介護」「教育」「治安、安全」が上位にあり、観光客の誘致、ましてはホテルの誘致を行政に求めているとは思えない。
(21)道路行政はきちんと分析して見直しているのかを検証しよう。
(1)JR奈良駅の高架工事に伴う阪奈道路油坂の交差点の渋滞は見通しの悪さと情報分析の浅さが顕れている。
(2)ジャスコ西大寺東側から秋篠川に沿って奈良競輪に行く途中の踏切が双方向でいつも渋滞。そのバイパスの延長線でT路交差点の東側に南北歩道が無い。そこを押熊側(北へ)曲がりしばらく行ったところに、東西に渡る地下道があるが、閉鎖されたまま。
これで道路行政が出来ているのか、これらは全て10年以上放置しているがどうしたものか?何故工夫しないのか。観光誘致の奈良はこれで良いのか。
行政側から言わせると「邪魔なので移転、移動させてください」で障害を除くことができない難しさがあるのだろうが、本来、10年先とかではなく、次世代をも考えて整備をしないと、もたもたしている間に既成事実ができてしまって整備が後手になるという構図とも思う。このようなところが何時も気になる部分で、行政は組織の都合でなく、住民志向で継続性を維持した計画フォローをする責務を認識していると思うので、疑問になる点を行政窓口に問い合わせすると、「それなりの」回答が得られる。行政側はワンストップサービスを目指し、奈良市では「ご意見箱」奈良県では「奈良県知事公室広報広聴課」が担当されている。住民がどしどし利用することでもっと充実した対応がなされると思う。
奈良県内の主要道路の国道24号線、25号線は、慢性的な渋滞問題を抱えている道路事情だが、その対策として、西名阪自動車道、香芝→天理間の無料にして貰いたい。西名阪が無料になれば、25号線の渋滞も緩和され、地域住民の利便性の向上や、物流、観光の誘致にも役立つことだ。
国道24号線などの主要国道だが、渋滞していない時間帯もある。渋滞する時の規模が半端でない、という「質」もちょっと意識しておかないと、終日渋滞という誤解を与えかねないと思う。香芝IC付近の道路整備が中途半端な現状で無料化しても、王寺や香芝周辺の混雑が増えるだけで、結果として国道25号線の混雑緩和には結びつかないと考える。本当に渋滞緩和のメリットを考えるのであれば、松原JCTまで全線を無料化にしないと本領発揮にはならない感じがする。
4、おわりに
「奈良の魅力の発信と、観光客の誘致」と云うテーマで会議をスタートさせたが、あまりにも大きなテーマで有るが故に、当初に如何なる投げかけを行うかで、相当考えた。これを間違うと、「魅力」の意味が各人各様にも取れるが故に、半年間の間の議論が上滑りしてしまう可能性が有ったからである。しかし当初の杞憂とは裏腹、興味を持たれた方も多数有り、また、観光と云う分野だけでは無く、街作りや生活していく上での必要な事の議論にまで及んでいった。この上で、奈良は楽しい所だ、と云う様にお考えの方も多数居られた事が非常に喜ばしい事だと感じる反面、まだまだ受け身の商業体制と感じて居られる方も居られた事も事実であった。また、平城遷都1300年実施の為か、平城旧跡に奈良県民の皆様の関心が集まっている事も意外な要素でも有る、と感じた。横切っている近鉄奈良線の支柱や電線の見え具合、大極殿再興の際の儀礼式的な催事、二条大路、三条大路の表示など、少し前なら本来なら、見向きもされなかった所で有る。元来の事を考えれば、奈良の魅力と云うのは、東大寺や興福寺、吉野山などが出てくるのが想定されたが、東大寺や興福寺は、寺院の魅力や風景の魅力、眺望景観などの議論の中で出てきたが、吉野山の桜や洞川温泉、十津川などが、全くと云って良い位、議論にならなかった。これはコーディネーターとしての議論のやり方がまずかったのか、本当に議論頂いている皆様方の頭の中に、南部方面の魅力が魅力として映らなかったのかは、今となっては推し量るすべは無い。しかし、南部方面には、北部とは全く違った魅力が有るのは事実で有り、意見として出ていなかった、と云う事は、まだまだ宣伝が不足している、とでも云うほかは無いかもしれない。また、大規模ホテル建設についても、必要と感じて居られる方々は非常に少なく、それ以前に、奈良としての、他府県とは異なった性格の宿泊施設を望んで居られる事に、行政側は何らかの方針転換が必要とも考える。奈良としてのホテルの重要性よりも、風土・眺望を破壊しないと云う事が余程大切か、と云う事を県民の皆様方一人一人が考えて居られる事を、行政は自覚しないといけない、と感じる。それには、むしろ宿坊や民宿を増やし、もっと地元の人々とふれあえる様な施設の建築を促進していく、と云う政策を取る事が大切だ、と云う事が民意で有る。それに伴い、景観と眺望を守っていく事が、真の意味で大切で、既存のビルの管理者などは、宿泊施設も含めて、自身の建造物の現状が、本当に原風景を破壊していないかを再度検証する必要にも迫られている。これは、現状の建築基準や風致基準の策定が、まだまだ不十分で有る事の裏返しでも有り、対策の急がれる事で有る。また、交通手段が多様化された結果、夜行便の多発により、早朝・夜の入浴なども考えに入れていく必要が有り、行政としても働きかけてほしい。これには現状法令の壁も有り、事業者同士と行政がテーブルに着く事が大切で有る。
反省点としては、コーディネーター自身も、万全の状態で全てが把握出来ている訳では無く、せっかくの投稿者からの意見を巧くコーディネート出来なかった点が気になった。調査や関係者への意見聴取も行ったが、行政機関・民間関係機関等々の全てを把握する事は不可能な為ご容赦頂きたいと考えている。
Ⅲ−2(T−2):受診者の立場から医療資源を考える
〜限られた医療資源を守るために何をなすべきか〜
コーディネーター 馬詰 真一郎
吉岡 敏子
1. はじめに
このようなテーマで会議を始めることになりました。限られた医療資源というような、一般には知られてないような表現に、皆さんが参加してくださるのかどうか、心配でした。それで最初に、お気軽に何か医療に対するお気持ちをお書きください、と付け加えました。こんな心配は無用なようでした。参加者は少なかったけれど、提案の内容は実に充実しているのに驚きました。例えば、何気なく使っている「周産期」というのは、妊娠22週から生後満7日、未満までの期間で、合併症妊娠や分娩時の新生児仮死など、母体・胎児や新生児の生命に関わる事態が発生する可能性がある、時期だ、というような専門的な表現が出てきます。このように、いろいろな提言は、一般の受診者という水準より高度な、専門的な意見が多かったような気がします。
2. 提案
(1)医療資源の何が不足しているのか。
最初に「限られた医療資源」というのは、漠然と「医療資源」が「限られている=不足している」とは感じていると思っていても、何がどれだけ不足し、それによってここでこういうことができないということが見えていない。だから協力しなければと思っても、何を協力したらいいのかわからないということもあるのでは?と言う声に対して、県の地域医療連携課から「県政諸問題に関する評価書」を掲載してくださいました。
(2)赤字公立病院経営の健全化は必要か。
県からご提供くださった資料は非常に参考になりましたが、そのなかで、平成18年県内公立病院の経営指標が、10病院全てが赤字経営であることが注目されました。奈良の公立病院全てが赤字という原因を解決しなければ、必要な医師も採用できないことになる。病院経営の健全化が緊急な課題だ、との提言とか、赤字解消が医療崩壊の解決策ではない、公共事業だから止むを得ない、と打ち消しもありました。
しかし、公立病院のすべてが赤字といっても、国保中央病院が一番成績のよいのは、県内で唯一の緩和ケア病床があることが理由ではないか、との提言もありました。
(3)(医療崩壊は医療行政の問題。
病院の財政難問題が採り上げられました。最初に大阪府の松原市立病院が、財政難で閉鎖されることが話題になりました。病院の経営破たんの原因は、正直に点数報告していれば、経営が成り立つのかどうか、とか、1台何億円もする機器を購入しなければ診断が追いつかない、医療行政の問題だ、ということになりました。
医療行政問題が、奈良県のがん診療連携拠点病院の話に発展しました。奈良医大病院の他に『地域がん診療連携拠点病院』は、県立奈良病院・国保中央病院・天理よろづ相談所病院・近畿大学医学部奈良病院の5病院で、いずれも奈良県北部に位置し、奈良県南部はゼロと言う状態で、『奈良県南部の住民に、がん患者はいない』と言う事になると言うのです。そして、その根源は、県廰が奈良市にあることで、やはり、奈良県庁は橿原市ぐらいに移転するのが良い。県庁移転が絶対条件だ、と言う意見も出てきました。
(4)医師不足ではなく、医師は増加している。
医療崩壊の問題は、必然的に医師不足問題に発展してきました。日本の人口は、右肩下がりの減少カーブを描いているのに、医師総数は、医学生の増員もあって毎年3,000人〜3,500人の増加傾向にある。医師総数が増加傾向にあるのに、何故『医師不足』が発生するのか。1994年は、医者1人当りの人口は569人、2008年は、医者1人当りの人口は473人。数字的には医者がだぶついているのに、何故『医師不足』か?この『原因』を考えよう、から始まりました。
(5)周産期医療の崩壊の原因は産科診療所の激減。
日本は、世界トップの質の高い周産期医療を国民に提供してきています。しかし現在、周産期医療の崩壊が叫ばれています。その原因は(1)地域の分娩を担う医師の不足、産科診療所の減少。(2)助産師不足。(3)二次・三次病院の機能不全。(4)産婦人科勤務医の劣悪な労働環境。(5)多い訴訟。これらが崩壊の要因となっています。全ての領域の医療崩壊が始まっていますが、周産期医療が最も深刻です。
(6)産科医を巡る諸問題について
1)奈良県の産科医数がこんなに減少。
ここで、奈良県の産科医数が問題になります。2004年の厚生労働省のデーターによると、単位人口当たりの医師数で奈良県は26位、人口=1,431,000人・医師数=2,815人・10万人当りの医師数=196人となっています。
一方、産科医数では、奈良県は42位で、極端に少なくなっています。産科医数=104人・10万人当りの医師数=7人となっています。奈良県の産科医事情が、何故これほど悪いのでしょうか?行政として早急に且つ真剣に調査する必要があると思います。
2)産科医になりたがらない理由。
また、医学生が、産婦人科医師になりたがらない理由は、(1)若い女性の患者さんが男性医師を嫌うこと、(2)医療事故が発生すると母体と乳児の二人から訴訟されること、(3)損害賠償の金額については、余命年数の長い母体と乳児が対象のため莫大な賠償金になること、(4)産婦人科・小児科・麻酔科は24時間待ったなしで、仕事が過酷であること、(5)産婦人科医師は、女性医師が増えているが、結婚すると休職する医師が多いこと、(6)男性産科医は、高齢者の先生が多く、新旧交代がうまく行っていないこと等です。この様に、医学生がリスクを避ける傾向にあるため、日本の医療体制に大きな歪を生じています。
3)助産師の活用案に対する問題点。
産科医不足を助産師で賄う的な方法についても、つぎのような見解があります。正常分娩かどうかはあくまでも結果であることを、必ず念頭に置いて考えるべきではないか。経過が正常であっても、分娩が「正常」かどうかは、娩出するまでわからない。助産院での違法な医療行為の問題や、搬送の遅れによる母子の健康状態の悪化といった問題も見受けられる。縫合などの医療行為を要するケースはいわゆる正常分娩でも非常に多い。助産師さんの力を借りて分娩できる場をつなぐにしても、いかに安全を確保した体制が組めるか、お産を扱う産科医との緊密な連携確保などが非常に重要になる。"院内助産所開設"という記事をよく目にするようになったが、その定義は?と疑問である。病院での出産であってもお産の間医師が付きっきりということはなく、基本的にお産の主導は助産師さん。だからそれ以上に助産師さん主導のお産となると、もはや医療行為も関与すると思う。
4)産科医師確保の方策。
産科医師を確保する方策についての考察もありました。短期的には(1)全国から産科医を募集する。(2)労働に見合った給料が必要です。分娩料(30万円〜40万円)が安いこと。日産婦医会の試算では適正な料金が60万円〜70万円と言うことです。(3)現在、産科を開業している診療所が継続できるような支援、すなわち適正な分娩費用の設置と助産師確保対策が必要です。(4)医療に伴い発生する障害に対する補償制度の創設。特に、脳性麻痺の無過失補償制度です。(5)国民の理解が必要です。分娩はリスクがあり、どんなに医療が進んでも死亡をゼロにはできないということを認識する必要があります。
5)産科医確保策の他府県例を見る。
産科医師の確保策については他府県の例があります。産科医不足に対応するため、多くの自治体が、産婦人科を目指す研修医や医学生を対象にした貸付金制度などを導入している。だが、医師の育成には時間がかかる。妊婦の受け入れ拒否が相次ぐ非常事態の中、緊急の課題は、現在お産の現場で働いている医師をいかにつなぎとめるかだ栃木県は今年度から、切迫早産や帝王切開など、ハイリスクの妊婦の出産を受け入れた病院に、出産1件あたり1万円を県費で補助する事業を始めた。 医師の負担軽減策としては、静岡県が今年度、産婦人科医師の事務を補助する「医療クラーク」を病院が雇用した場合、人件費の半額を補助する制度を始めた。開業医との連携を模索する動きもある。
仙台市では、検診は近所の診療所、出産は病院で行う「仙台セミオープンシステム」を導入。
共通診療ノートを発行、診療所と病院で情報を共有した上で、時間外や緊急時の対応は病院が行う。女性医師の復職支援策では、神奈川県、山口県、大阪府などが今年度から、出産、育児などで第一線を離れた人に、公費で2〜6か月程度の技能研修を行う制度を始めた。等々いろいろとあります。
(7)医療事故報道に対する批判。
東京の周産期母子医療センターでの医療事故報道から、医療事故の問題が採り上げられました。出産死亡率は高いのか、低いのか。2005年の統計では総出産数106万人のうち、17%に当たる約18万4千人が帝王切開で出産している。妊婦の6人に1人が帝王切開で出産していることになる。出産数自体は減少しているのに、帝王切開による出産は過去20年間で約2倍に増えている。この中で、出産中の死亡事故は全国で約50件、「出産安全神話」の観点から言うと多いかも知れないが、出産事故死亡率から言うと、0.0047%になる。このように、大変低い死亡率にも拘わらず、新聞やテレビの報道は、騒ぎ立てれば勝ちみたいなところがある。新聞販売数のアップやテレビ視聴率アップのためには、医療バッシングの方が都合が良いようです。しかし、最近の報道機関は真実を伝える良心が少し欠けていると、と冷静な意見だと思います。
(8)医師不足の原因は新臨床研修制度とする見方。
医療事故、医療訴訟の問題から、勤務医の過重労働の問題となり、医師の地域偏在の規制はできないか、の問題に展開して行きました。医師の数は不足しているのではなくて、必要な地域に必要な数の医師がいないだけだ、というのです。新臨床研修制度(2年間)。導入後は原則自由に研修先を選べるようになり、都市部の一般病院を選ぶケースが増えた。このような意見に同調して、医師の自由開業、自由標榜制度が医師不足の原因だから、一日も早くドイツ、英国のような、システムにすべき、との意見も出てきました。これに対して医学部生に国民の要請に応えよと強制するのであれば、その他の学部生も同様でないと理屈に合わない。学費・教材費・住居費すべて無料にするくらいのインセンティブがあって、初めて要請しうる気がする。在学中に給与が支払われる防衛大学校であっても任官拒否は認められている。自治医科大学の学生はどのような配置になっているか、との反論もありました。
(9)医師不足問題を克服した兵庫県立柏原病院を見習いたい。
勤務医不足問題等いろいろな問題で、柏原病院の問題が採り上げられてきました。これをたくさんな提言の最後に記載いたします。近年、勤務医不足で医師の負担が激増している。特に激務で知られる小児科の状況は深刻で、中には、小児科医が確保できず、小児科を閉鎖する病院も相次いでいる。兵庫県立柏原病院もそのような病院の一つである。。柏原病院でも、人事異動と後任医師の不足から小児科閉鎖の危機となった。また、小児科が閉鎖となれば、生まれてきた子供の治療が不可能となるため、産科も休止になるのが一般的である。これに危機感を抱いた地域住民7人が結成したのが『県立柏原病院の小児科を守る会』である。小児科の適切な利用方法を周知するなどの活動で、小児科医の負担を減少させることで小児科の閉鎖を食い止めるのを目標としている。特に、軽症でも安易に救急外来を利用するというコンビニ受診の減少に重点を置いた活動を行っている。奈良県でもこの様な運動を出来ないのでしょうか?というのでした。
3.発言の概略
(1)○テーマにある「限られた医療資源」というのは、今日の医師や看護師の不足、分娩の中止や小児2次輪番の減少等からわかる気がします。確かに患者や地域の医療要求に十分に応えられる「資源」がないとは思います。しかし、患者や地域側から、どの資源がどれだけ不足をし、そのため何ができなくなっているのか見えません。何がどれだけ不足し、それによってここでこういうことができないということが見えていない。だから協力しなければと思っても、何を協力したらいいのかわからないということもあるのでは?そのようなことがわかっていない、理解されていない。
(2)○データの提供で非常に参考になります。この中で、平成18年県内公立病院の経営指標が、10病院全てが赤字経営です。奈良の公立病院全てが赤字という原因を解決しなければ、必要な医師も採用できない。病院経営の健全化が緊急な課題だと思いますが。
○公立病院の経営健全化について述べておられますが、赤字解消が医療崩壊の解決策になるのでしょうか?公立病院は公共事業ですから、必要な赤字も止むを得ないのでは?
○これは国保中央病院が経営が上手なのもあるのでしょうが、県内で唯一の緩和ケア病床があることが理由ではないか、と思います。
(3)○病院の経営破綻に関しては、難しい問題があると思います。正直に点数報告をしていれば、経営が成り立つのかどうかという、国民健康保険制度の問題と、それ以上に、医療機器の問題があると思います。一台何億もする機器を、購入しなければ診断が追いつかない昨今、その機器メーカーの暴利に、経営が破綻しているのではないでしょうか。
○平成20年4月1日現在で、厚生労働省の『がん診療連携拠点病院指定』は下記の如くです。『都道府県がん診療連携拠点病院』に関して言えば、奈良県は奈良県立医科大学附属病院が兼務しています。奈良県の『地域がん診療連携拠点病院』は、県立奈良病院・国保中央病院・天理よろづ相談所病院・近畿大学医学部奈良病院の4病院で、これら4病院はいずれも奈良県北部に位置し、奈良県南部はゼロと言う状態です。『奈良県南部の住民に、がん患者はいない』と言う事なのでしょうか。根源は、県廰が奈良市にあること、県廰は奈良県の地図と実情が見えていないことです。やはり、奈良県庁は橿原市ぐらいに移転するのが良いでしょう。
(4)○日本の人口は、2004年をピークに右肩下が りの減少カーブを描いています。一方、医師総数は、医学生の増員もあって毎年3,000人〜3,500人の増加傾向にあります。即ち、日本の人口が減少傾向で医師総数が増加傾向にあるのに、何故『医師不足』が発生するのでしょうか。1994年は、医者1人当りの人口は569人でした。2008年は、医者1人当りの人口は473人です。この様に、数字的には医者がダブ付いている筈なのに、何故『医師不足』なのですか?この不思議な現象の『原因』を真剣に考えてみませんか。本当の『原因』が分かれば、『医師不足』の対策は自ずから見えてくるものです。
(5)○分娩医療機関、特に産科診療所の激減の原因は、下記の如くです。(1)産科医、NICU 医・助産師の不足と偏在による分娩医療機関の減少。(2)新医師臨床研修制度の開始により、大学関連病院から大学へと産婦人科医が呼び戻された。(3)周産期医療のシステムの不備。(4)国の医療費削減により、労働環境が悪化し、産科医が減少。(5)「団塊の世代」の産婦人科医が定年を迎え大量に退職。(6)医療事故に対する業務上過失致死傷罪違反嫌疑等による刑事司法の産科医療現場への介入で、分娩の撤退。(7)妊婦の分娩機関に対する要望、特にホテル並みの快適性と豪華な食事を求めて、対応できない産科診療所は撤退。(8)後継者不足と医師の高齢化から撤退する医療機関が増えた。
(6)○2004年の厚生労働省のデータによると、単位人口当たりの医師数で奈良県は26位でその数値は、人口=1,431,000人・医師数=2,815人・10万人当りの医師数=196人となっています。一方、産科医数は、奈良県は42位で、極端に産科医が少なくなっています。産科医数=104人・10万人当りの医師数=7人となっています。奈良県の産科医事情が、何故これほど悪いのでしょうか? 行政として早急に且つ真剣に調査する必要があると思います。行政は徳島県と鳥取県のベンチワーキングを至急実施してください。奈良県民の安全を守るために宜しくお願いします。
○また、医学生が、産婦人科医師になりたがらない理由は、(1)若い女性の患者さんが男性医師を嫌うこと、(2)医療事故が発生すると母体と乳児の二人から訴訟されること、(3)損害賠償の金額については、余命年数の長い母体と乳児が対象のため莫大な賠償金になること、(4)産婦人科・小児科・麻酔科は仕事が過酷であること、(5)産婦人科医師は、女性医師が増えているが、結婚すると休職する医師が多いこと、(6)男性産科医は、高齢者の先生が多く、新旧交代がうまく行っていないこと等です。
○産科医師確保策と医師偏在を無くすための施策に付いて、短期的には、(1)全国から産科医を募集する。(2)労働に見合った給料が必要です。分娩料(30万円〜40万円)が安いこと。日産婦医会の試算では適 正な料金が60万円〜70万円と言うことです。(3)現在、産科を開業している診療所が継続できるような支援、すなわち適正な分娩費用の設置と助産師確保対策が必要です。(4)医療に伴い発生する障害に対する補償制度の創設。特に、脳性麻痺の無過失補償制度です。(5)国民の理解が必要です。分娩はリスクがあり、どんなに医療が進んでも死亡をゼロにはできないということ。
○産科医不足に対応するため、多くの自治体が、産婦人科を目指す研修医や医学生を対象にした貸付金制度などを導入している。だが、緊急の課題は、現在、お産の現場で働いている医師をいかにつなぎとめるかだ。栃木県は今年度から、切迫早産や帝王切開など、ハイリスクの妊婦の出産を受け入れた病院に、出産1件あたり1万円を県費で補助する事業を始めた。医師の負担軽減策としては、静岡県が今年度、産婦人科医師の事務を補助する「医療クラーク」を病院が雇用した場合、人件費の半額を補助する制度を始めた。。開業医との連携を模索する動きもある。仙台市では、検診は近所の診療所、出産は病院で行う「仙台セミオープンシステム」を導入。共通診療ノートを発行、診療所と病院で情報を共有した上で、時間外や緊急時の対応は病院が行う。女性医師の復職支援策では、神奈川県、山口県、大阪府などが今年度から、出産、育児などで第一線を離れた人に、公費で2〜6か月程度の技能研修を行う制度を始めた。
(7)○医療事故について述べておられますが、情報や新聞のニュースを読むときに重要なのは、数字に関して言うと、量と率の関係を念頭に入れて理解する必要があります。例えば、出産に関して言うと、、2005年の統計では、総出産数106万人のうち17%にあたる約18万4千人が帝王切開で出産しました。妊婦さんの6人に1人が帝王切開により出産していることになります。また、出産数自体は減少しているにもかかわらず、帝王切開による出産は過去20年間で約2倍に増えています。この中で、出産時の死亡事故は、全国で約50件です。量的には、『出産安全神話』の観点から言うと50件は多いかもしれません。しかし、出産死亡事故率から言うと、0.0047%になります。
(8)○『医師不足』の原因の1つに、新臨床研修制度があります。2004年度に始まった新臨床研修制度(2年間)。導入後は原則自由に研修先を選べるようになり、都市部の一般病院を選ぶケースが増えた。人手不足となった大学病院が各地の病院に派遣していた医師を引き揚げ、地方の病院の医師不足を加速させたとされる。
○国公立大学の学生は、誰もが大なり小なり税金の恩恵にあずかっているので、医学部生に国民の要請に応えよと強制するのであれば、その他の学部生も同様でないと理屈に合わない気がします。医学部を国公立単科大学化して学費・教材費・住居費すべて無料にするくらいのインセンティブがあって、初めて要請しうる気がします。在学中に給与が支払われる防衛大学校であっても任官拒否は認められていますよね。設立の理念「医療に恵まれないへき地等における医療の確保及び向上と地域住民の福祉の増進を図るため」と謳っている自治医科大学の学生さんたちはどのような配置がなされているのでしょうか。
(9)○近年、勤務医不足で医師の負担が激増している。特に激務で知られる小児科の状況は深刻で、全国の医師から小児科は忌避され、医師の数が減少している。中には小児科医が確保できず、小児科医を閉鎖する病院も相次いでいる。兵庫県立柏原病院もそのような病院の一つである。柏原病院のある丹波も、柏原赤十字病院が産科を休止するなど、医療崩壊は深刻な状況である。柏原病院でも、人事異動と後任医師の不足から小児科閉鎖の危機となった。また、小児科が閉鎖となれば、生まれてきた子供の治療が不可能となるため、産科も休止になるのが一般的である(東京都の日野市立病院の例など)。これに危機感を抱いた地域住民7人が結成したのが『県立柏原病院の小児科を守る会』である。小児科の適切な利用方法を周知するなどの活動で、小児科医の負担を減少させることで小児科の閉鎖を食い止めるのを目標としている。特に、軽症でも安易に救急外来を利用するというコンビニ受診の減少に重点を置いた活動を行っている。
○兵庫県立柏原病院の『柏原病院の小児科を守る会』は、(1)コンビニ受診を控えよう・(2)かかりつけ医を持とう・(3)お医者さんに感謝の気持ちを伝えようの、3つのスローガンを掲げて地域医療活性化の運動をしておられます。具体的には、ホームページやブログを作られて、医師の負担軽減への呼びかけ、(1)コンビニ受診を控えよう運動をしておられます。(3)お医者さんに感謝の気持ちを伝えように関しては、県民の感謝のメッセージを募る 「ありがとうポスト」の設置などに取り組んでおられます。(2)かかりつけ医を持とうに関する具体的な運動は、病院とかかりつけ医のコミュニケーションがうまく機能するように、柏原病院内に地域医療連携室を設けて、FAXや電話で意思伝達できるシステムを構築しておられます。
4.おわりに
極めて少ない投稿しかなかったのに、こんなに長い報告になってしまいまして、申し訳ないと思います。けれど、内容は多岐に亘り、奈良県の、というよりわが国全体の医療が抱える問題を詳しく書いておられますので、矢張りご紹介せずにはおられませんでした。私たちがこのテーマで半年間話し合った結論は、医療崩壊の問題、県に産科医師がいないのを如何するのか。医師の絶対数は昔より増えているのに、全国的に産科医師や小児科医師は足りない。それは現在のわが国の医療制度が、直面している大きな問題である。では現在の制度を良くするために如何すればよいのか。それには大きな力が必要である。しかしその力は何処からも来ない。私たち皆が、一人でも多く、この現実を正確に知ることが大切である。そのためにメディアも興味本位でない正確な報道を繰り返して欲しい。
最後に、私たちは、今回のテーマで一番胸を打たれた、つぎのような意見、というよりも問いかけをご報告したいと思います。少しでも早く、県民の皆様の一人にでもこんな心配、悩みをしていただかなくても良いように、努力したいと思います。
「できればもう1人産みたいので、奈良の小児医療や産科の状況に関心あるのですが…。いざというときに、慌てて周囲を見渡してもどこにも受け入れ先がない…となっては怖いのですが…。」
Ⅲ−3(T−3):地域ぐるみで学校を支援しよう
〜学校支援地域本部の取組を生かして〜
コーディネーター:三宅基之
1.はじめに
この会議室では三度目の教育をテーマとしてもので「地域ぐるみで学校を支援しよう」を話題に扱った。これまでの議論の流れから生まれてきた学校支援地域本部事業の実践を取り上げ、具体的な教育施策の中で、実践的な広がりに重点をおいて議論を取り扱うこととした。学校設置者である市町村自治体担当者から、活動情報を共有する仕組を検討したいという要望もあり、地域本部事業を設置推進していくための課題解決のための情報ネットワークとして県民電子会議室を活用する方策を探るというねらいもあった。これらの実践に基づいた要望と、議論をオープンにするという本来の電子会議室の主旨との整合は困難であった。詳細については、文科省委託事業奈良市地域本部評価検証委員会の報告書を別途参考にしていただきたい。しかしながら、情報技術を活用した課題解決のための人的ネットワークの構築の必要性は高まっており、実践とうまくかみ合った活用方法を今後検討していくことは、今後とも意義があると思われる。
会議室での議論の大分類は下記の5つを設定した。
(1)地域本部ってなに?−(「地域本部」の目的?あなたの主張は?)
(2)地域本部あるある大辞典−(現在取り組みや昔の思い出話など)
(3)こんな「地域本部」がいい?−(どんな「地域本部」が地域で子どもを育てやすいか)
(4)特集−学校へいこう!−(最近学校へ立ち寄った方の学校の様子の紹介)
(5)フリー「しゃべり場ホットトーク」−(子育てや学校に関するどんなことでも気軽に)
特に電子会議室は、自由に書き込める要素が必要だという利用者からの提案に基づいて、スタート1ヶ月目から(5)のフリーな項目を追加設定した。
実践を中心にした議論は、活動のフィールドを持つ情報と持たない情報に分かれてしまい、議論することが難しいことがわかる。議論の前提として、どのような情報を共有していることが大切かということが理解できた。当然のことだが、話し合いには言葉の共有、予備知識や興味関心、スキルなどの前提が必要であり、電子会議室も同様であることがわかる。情報ネットワークで物理的な障壁が取り除かれる分だけ、内容やスキルなどのソフト面を共有している必要があると思われる。そのソフトが共有されることで内容の濃い有意義な意見交換がされることもわかった。
| 5つの分類項目の書き込み数 | 書き込み件数 |
| (1)地域本部ってなに? | 34 |
| (2)地域本部あるある大辞典 | 32 |
| (3)こんな「地域本部」がいい? | 0 |
| (4)特集−学校へいこう!− | 11 |
| (5)フリー「しゃべり場ホットトーク」 | 83 |
2.提案
特に議論の中から提案されているものは見当たらないが、この電子会議室を活用した情報のやりとり自体が提案にあたると思われるため、一部を整理してみたい。
(1)学校支援地域本部設置の取り組み情報を積極的に公開する。
県内各地域で実践されている学校支援地域本部の活動情報を一覧できるようになると、活動目標や参考にできるところが増えると思われる。特に平成20年度は初期の段階であるため、今後新たな情報を常時供給していくことが行政に求められる。
(2)学校支援地域本部事業の運営に関する情報を共有できる仕組みが必要。
学校ボランティアや特にコーディネーターの役割を担う人たちは、共通の悩みや試行錯誤を繰り返しながら実践に努めている。自身の取り組みの悩みや不安を共有することで、連帯感や今後のネットワークの伸長につながる。
(3)地域の教育的な活動をプログラム化する。
自主防災や防犯活動と、スクールガードのボランティア活動が単体のもので終わるのではなく、学校を拠点にして行われることで、子どもを地域で育てる体験プログラムにできるという提案。そのためにも地域の学びの場をつなぐ団体が必要になる。
3.発言の概略<経過と論点>
2008年10月〜2009年3月の論点
「地域ぐるみで学校を支援しよう」というテーマで議論された内容については、概ね下記のようなカテゴリーに分けられる。
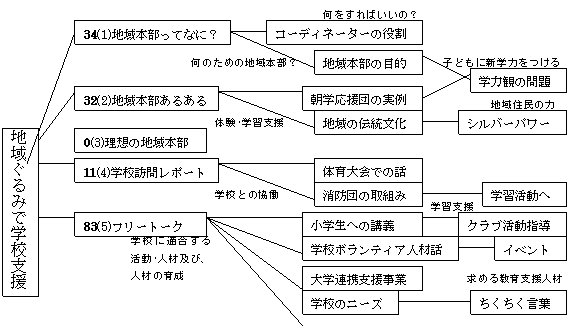
(1)地域本部ってなに?
学校支援地域本部とは、なぜ必要なのか、なにが目的なのか、なにをするのか、コーディネーターの役割はなんなのか、実際の疑問が多く出されたのは実態とも合っている。
【36】
私はうちのまちの子ども達がいいオトナに育って欲しいんです。自己中心になりがちな今の社会に、そうじゃないんだ。友のために町のために一肌脱ぐんだって、そういう人に育って欲しいんです。勉強が出来る子育てたって世の中平和にならないと思うのです。
(大いに誤解を招くところですが、知恵のある子を育てることが大切だと言う意味です)
【105】
子どもに関わるっていうのは、子どもにとっても大人にとっても学びがありますよね。いろんな世代の大人がつながって、その中で子どもが育っていく場がつくれるってのがいいですよね。
いろんな世代間で学びあうというのでしょうか。場の安心感を生んでいる気がします。
世代間でいいつながりをつくる工夫が必要なんでしょうけど。
(2)地域本部あるある大辞典
実際の活動を紹介してもらい、それをもとにして色々な「あるある」を考える。そこから課題や新たなテーマ、疑問をみつける。
【38】
校区ごと複数の地域コーディネーターがおられるわけですね。1つの市町村でたくさんのコーディネーターが生まれるわけで、お互いに議論する場として、電子会議室を利用することは大いに意義のあることではないでしょうか。奈良県全域、或いは、関心のある特定の自治体(教育委員会)に、この電子会議室を利用するような働きかけはできないものだろうか。
【67】
「地域コーディネーター会議室」というものを設けておおいに意見交換すれば、学校支援のアイデアが出てくると思います。私は、機会があったら、子供達に「ものづくりの原点」について話をしてみたいと思っています。
【84】
歴代のPTA、育友会の会長さんなどが音頭とりをしてくれています。まさにおやじの会ですね。
田舎なので親同士が同窓生だったり芋づる式で友達が友達を呼んでみたいなこともあるようです。 地域のつながりという点では理想的かも知れないですね。
(3)こんな地域本部がいい?
地域本部で学校をサポートできる具体的な分野や方法はなにかを考え合う。
【 】
話題提供がありませんでした。
(4)学校へ行こう!
最近学校へいくとどんな様子だったか、昔の学校と今の学校は違うのか、近くの学校へでかけてみて、話題提供していただき話し合います。
【12】
運動会の運営は、5年生、6年生が前面に出て行っていました。先生は、サポートしている、といった感じでした。例えば、100m競争であれば、スターター(ピストルと撃つ人)やゴールで対応する人は、全て生徒がやっています。それぞれ担当の先生は、ついていますが助言したり、サポート役でした。これも、教育の一貫だと思いました。
【92】
職場体験学習の準備として、生徒はマナー講習を受けます。
電話をかけたり、挨拶をしたりすることが多くなるので、この機会にマナーを勉強しようということで、私達のような礼法を学んだものがマナー講習ということで指導に入っております。
各クラス1校時ずつ総合学習の時間を取っていると思います。(時間が取れないときは学活の時間を当てているときもありましたが・・・)
(5)フリートーク
地域の教育的な活動、家庭の教育的な活動、学校の教育活動、いま社会や大人の世界で必要なことを自由に考え合う。
【71】
これから始まる学校支援地域本部に関わる人に関しては、何らかの形で「この人は必要な知識や経験やスキルがある人です。」と資格というか認証されるものがあるとわかりやすいですよね。
【34】
平成20年の(奈良市消防団活性化認定事業経費負担に応募の結果、認められ7台のICボイスレコーダー等、録音再生に必要な機材を入手できました。最新鋭の機材が揃いましたので今後の録音編集はテープレコーダーを必要とせずパソコンで作業を短時間で済ませる事が出来ます。
【115】
地域本部の役割は、斜めの関係を取り込んで地域の教育力を再構築することになるはずですが、うまくこの考え方を柱にすえていくことが出来れば芯のずれないものになっていくでしょうね
【161】
「ものづくり教育」に参加した科学クラブの子どもたちが、書いた感想文を見ることが出来ました。感想文を読んで、驚くほどよく観察していることが分りました。子どもたちの率直な気持ちが伝わってくるようで嬉しいものです。
6.おわりに
平成19年から「教育」テーマとして、特に公立学校の教育に話題を絞り込んだ学校教育改革の中でも地域住民の学校教育活動への参加を話題にした。この間に教育基本法、教育三法の改正が行われ、指導要領の改訂に向けた指針も中教審から出されたが、そのどこにも地域総がかりで教育に取り組むことの重要性が盛り込まれている。奈良県固有の課題としては、学力学習力状況調査の結果による、教科学力に比べた規範意識、社会性の乖離、体力調査の全国最下位結果という現実も報道された。そんな中で、平成20年度から学校支援地域本部設置事業が進められている奈良県では、その成果を高めるためにも全県的なサポート体制の整備が求められている。「学校」特に義務教育諸学校の持つ役割について藤田英典の言葉をあらためて引用しておわりにしたい。
「つまり、学校は地域の人々にとって共同性の基盤として存在しているということである。さまざまな活動を共にし、思いや利害をぶつけ合い、共通の経験を蓄積し、共通の思い出と愛着を育む基盤、共生的生活圏の核として存在している。」「教育改革」-共生時代の学校づくり-(岩波新書)p4
Ⅲ−4(T−4) :平城遷都1300年祭を成功させよう
〜平城遷都1300年祭を機に「もてなし」を考える〜
コーディネーター:中西久夫
1.はじめに
この会議室では目前に迫った「平城遷都1300年祭を成功させよう」という掛け声の許、これを機に奈良の「もてなし」を考えようということで、県民一人ひとりが「もてなしの心を持って行動することが豊かな人間関係作りや活力ある地域づくりの源となる。住民はもちろん訪れる人にとっても、美しさ、温かさ、楽しさが感じられる魅力のあるまちづくりにつながる。もちろん息の長い取り組みが必要であるが、奈良にとって2010年に迫った平城遷都1300年祭は絶好の機会であり、奈良の現状はどうか、どんな改善点があるか、具体的な改善提案、あるいはほのぼのとするような良い事例紹介、・・等々なんでも結構、気軽に参画・討議しましょう。というスタンスで会議を運営しました。もてなしの心については奈良・もてなしの心推進県民会議による推進行動プログラムの許、体系的かつ組織的推進が図られており、そのコンセプト・基本方針・展開プログラム等は他県の模範とするところではありますが、会議室においては、あえて推進県民会議の内容熟知を前提とせずして、一般庶民感覚でのフリー討議を重視することとした。
過去のテーマの中で討議された内容と重複するものもあるが、平城遷都1300年祭が間近に迫ってきている現時点かつ、もてなしを考えるという切口に基づくものです。
2.提案
投稿内容は関係者が都度原文を読み行政にいかせる、お客様の声は宝の山という感覚で活用いただくのが本来でその姿勢が何より必要であると思います。個々のお客様の生の声をコーディネータが取捨選択・脚色すべきものでも有りませんが、具体的提案に至ったケースは少ないものの貴重な改善のヒントになると思われるものも多々有り、できる限り生の声を尊重しながら、改善ポイントとして提案する次第です。
(1)トイレの改善
トイレはその国の印象を大きく左右します。先進国で観光地である奈良は一流レベルにあるかと言う点については、「トイレのマークが小さくて遠くから見えない、洋式トイレの割合が少ないのでは、駅のトイレに紙が置いてないところがある」という意見があり改善を要します。台湾では公衆トイレが大変きれいであり、そのレベルに付き公的機関による定期的監査・格付けシステムがあるようです。きれいなトイレに優秀トイレマークなるものが張ってある。ドイツでは公衆有人トイレがあり、トイレはきれいに維持されており、お礼にチップを置いていくお客さんが多い。トイレは文化のバロメーター。公衆トイレ格付け制度を設け、奈良は日本で一番きれいで快適なトイレの県にする取り組みを提案します。
又、公共交通機関である駅トイレに紙が置いてない件については、実態調査と必要に応じ指導を望みます。
(2)交通渋滞改善策の推進
“奈良は交通渋滞がひどい2度と来たくない、1300年祭に来て欲しくない。開かずの踏み切、連日の交通渋滞にほとほとあきれ返っている。”1300年祭以前の問題で「もてなし」以前の実態にあり県民の関心が非常に強いものがあります。11月には交通渋滞緩和の社会実験が行われましたが、この実験が単発的なものに終わることなく、県民を巻き込み改善推進を待ったなしで継続的にやって欲しい。又、1300年祭には「車はでこないで欲しい、電車がお勧めといった」キャンペーンを公に張ることを提案します。何もしないでは「もてなしの奈良」ではないといった危機感を持った意見が多かった。
(3)1300年祭への県民意識高揚策
1300年祭のイベントの具体性はゼロ、1年前に具体的な内容が示せないと観光業者が計画に進めない、役所が勝手にやっていて市民は何も知らんようではうまく行くわけない、県民のものになっていない、といった意見が多くあった。1300年祭は「せんとくん」の活躍並びに奈良の持てる歴史的資産並びにこれからの頑張りで格好がついてくると思われるが、県民の参画意識アップは最低必要なことといえます。
●イベントの成功判定目標の中に県民参画意識何%以上といった目標を設けること。
●第3者からなる1300年祭伝道師なるものを任命し、自治会レベル等での対話による県民参画
意識高揚活動を推進することの2点を提案します。
(4)挨拶運動の推進
県の「もてなしの心の推進行動プログラム」にも「挨拶・声かけ県民運動」の推進が重要な位置づけで述べられています。この県民運動は大賛成、挨拶は最大のもてなしと思う。子供の教育上も基本中の基本、すべては挨拶に始まり挨拶に終わるといっても過言でない、といった意見が多かった。
いい例としては、奈良もてなしの心推進県民会議 通信6号に掲載の十津川小原中学校の小さな親切実行賞、ある地元の町内会の掲示板に「おはよう、おかえり、こんにちは、声かけ、気をかけ、笑顔かけ」というポスターがあって気づかされた。といったものが紹介あった。
平城遷都1300年祭を機に「挨拶・声かけ県民運動」が定着するよう旗振り・啓蒙活動をいっそう推進いただきたい。
(5)奈良公園の整備の推進
吉城園と副知事公舎の再開発、知事公舎の園外移転検討、奈良駅前の行基広場周辺並びに東大寺門前町の石畳化等々については、大歓迎。知事にエールを送りたいといった意見が多かった。再開発に際しては「奈良のもてなし拠点作り」も考慮いただくことを提案します。
奈良もてなしの心推進については一般にPRが出来ていない。殆ど誰も聞いたことがないというのが実態であり拠点作りも必要。
尚、整備計画の発表は新聞記事で見たものの県のホームページにも掲載されていなかった。奈良の広報のやり方はもっと工夫すべき、「知事の思いもどんどん発信すべき、発信なくして進展なし」との意見があった。開かれた県政を目指しホームページも含めた積極的広報への改善望みます。
奈良公園周辺の猿沢池土産屋商店街(3条通りにあり、たいがいシャッターの降りている20軒ほどの土産屋街、興福寺の石垣が隠れている場所のよう。)についても何とかならないかといった意見があった。終戦時からの時代の変遷で現状に至っているようであるが、「薬師寺の伽藍復元の夢を興福寺に」といった意見もあり、いずれにせよ「ノーモアシャッター街」という観点で問題意識をもつ必要がある。
(6)マイベストスポットの発掘による奈良の魅力の深耕
奈良には魅力的スポットが一杯ある。体験型旅行といったものがますます進化する時代を迎えると思うが、奈良の地元住人お勧めマイベスットスッポトなるものをネットで紹介、奈良の魅力の深耕を図るシステムの構築を提案します。平城宮跡大極殿基壇からみるご来光、県庁舎屋上からの眺め、朱雀門東東側池からの夕日に映える朱雀門、2月堂舞台から見る夜景等々 感動的スポットが一杯あり、その発掘をはかり観光に結び付けていくことで他県と差別化をはかることが必要。
(7)美化活動推進
1300年祭に向け県内違法広告物を「年内に半減」、官民の連絡会議発足の発表がありました。1300年祭を機に大いにやって欲しい。又、地域での清掃美化活動も盛り上がりを期待します。
平城宮跡等はゴミを捨てる人がいてもきれいに片付けるクリーンパトロールが勝っておりボランティアグループの活動に頭が下がります。行政の啓蒙活動は引き続き活発にお願いします。
但し、阪奈道路等の主要道路の両脇は盲点になっており大変汚い。道路わきの清掃活動は危険なこともありボランティアの手が入ってないことによります。家の玄関口に当たるところであり改善を提案します。(美化維持の為には清掃会社へのまる投げだけでは解決できないと思います。地域ボランティアの意見も聞き、知恵も力も借りることも必要かと考える。)
(8)平城遷都3キャラの活用
いきさつはともあれ「せんとくん」の知名度は全国的です。奈良県外では「せんとくん」は知っているが平安遷都1300年祭はしらない、聴いたこともない・・といった実態にあります。
「まんとくん」「なーむくん」を含めた3キャラの知名度も上がっており、その経済効果は大変大きいものがあります。「せんとくん」単独でなく3キャラの活用を図るべきとの意見があります。「せんとくん」はもとより3キャラの最大活用方針宣言を提案します。
過去のいきさつにこだわるようでは折角のチャンスが逃げて行きます。1300年祭の景気づけにはこれが一番。各キャラが個別にやっていては積極的な企画が出来ないのでは。
(9)その他
●まほろば検定試験には「もてなしの心」に関する出題を入れるべき
●1300年祭のPR兼ね東京での正倉院展等の積極開催
●まほろば検定受験者に対する特典・諸行事に関する案内の定期発送
●「鹿男あおによし」の撮影モニュメントの設置(平城宮蹟等主要撮影場所に)
3.発言の概略
紙面の関係で紹介は極一部に限られていますが、大変参考になる生々しい声も多いことよりスレッドNBRをつけております。必要に応じ参照頂ければ幸いです。
(1)トイレの改善
79・トイレのマークが小さくて遠くからは見えなくて、そばまで行かないと分らない
80・日本のトイレは最近はきれいで金がかかっていますが。トイレの洋式化率調査が必要
84・路線・駅によって対応がバラバラなので、この辺を指摘した方が良いのではと思います。
81・全く同感ですね。トイレに紙があるのは常識の範囲で、経営努力して欲しいです。
(2)交通渋滞改善策の推進
33・平城宮跡周辺に住む人に1300年事業の話をしたら、「これ以上来ていらんわ!」というきつい答えが返ってきました。
34・1300年祭以前の問題ですね。こんなことでは「もてなし」といったものでない、駐車場は朱雀門の近くに出来ても道路が混むようでは。もてなしどころでなくなりますね。奈良は交通渋滞がひどく二度ときたくないという話は私もよく聞きます。どう対応するのか真剣に考える必要ありますね。来年3月には近鉄も阪神とつながります。また環境破壊、鹿の交通事故による犠牲等を考えても電車がお勧めですね。道路の整備は進めても住民の交通渋滞解消だけで、イベント時にはもてなす方、またもてなしを受ける方にとっても、車はNOをはっきりすべきでは。甲子園球場は車でこないで欲しいという宣伝が行き届いていますが、奈良公園、平城宮蹟も同様の宣伝を前向きにしてはと思います。如何でしょうか。
44・マイカー以外へのシフトを強力に推進する必要があります
70・11月8日9日は交通渋滞緩和の社会実験行われましたが、奈良公園周辺の一方通行、パーク&ライド、電気バスの導入等に対する利用者のアンケート結果、渋滞緩和効果等の検証結果は如何だったでしょうか。今回の実験についてはTV/新聞等でも報道ましたが、結果はどこでいつ発表されるのでしょうか。1300年祭に向けての渋滞緩和策を探るという試みであり、タイムリーな結果公表は継続的に改善を図るためにも県民の協力、理解を深めるためにも必要と思います。次の実験はいつやるといった発表も一緒にやられては、いかがでしょうか。今回の試みが単発的なものに終わることなく、この機に一気に継続的に進むことを期待します
72・電気バスは、とても快適な 乗り物でした。
73・駐車場から自転車で回れるのも大変魅力あり行って見たい。ということでした。
47・今回の奈良の実験はツェルマットの日本版のようになればと期待するものです。
42・「奈良は電車で来てください」と連呼することの方が重要だし、メッセージ性がある
(3) 1300年祭への県民意識高揚
107・現状、イベントの具体性はゼロと言っていいと思います。いつ具体化するのか
106・「1年前には具体的な内容が示せないと観光業者は計画に落とせない。」
28 ・関係者の頑張り程には、市民、県民レベルに浸透していない
29 ・具体的な内容を一般県民にもっと知らしめる努力が必要でしょう。
98 ・県民のものになってない。主催者側の顔が見えない。
112・コーディネータのような人を採用して、各自治会を訪問して、きめ細かく活動する
115・おっしゃるように、第三者が適任ですね。”遷都祭伝道師”として、100人くらい採用して、2人ペアーで各自治会を訪問して、啓蒙活動をする。県が企画していることを説明し、各自治会で何が出来るかを一緒に議論して、一緒に参加意識をもってもらうことが大事。もてなしの心を育むよい機会になるでしょう
122・対話なくして何も始まらず、何も変わらずでは困るのは市民ですからね。
123・県民の参画意識・賛同意識何%以上といった目標を掲げる必要あるのでは、現状はどの程度かといったことはサンプリングで調査すれば数字で直ぐに出てきます。目標に対し悪ければ目標達成の為の活動が行動としてでてくることになります。そういう目標がないと協会は企画する人、県民は無関心で傍観といった雰囲気に陥っても、問題が認識されない状態で放置される。成果判定目標のなかに初めからそういう目標を入れておくべきでは。
(4)挨拶運動の推進
124・奈良・もてなしの心推進県民会議 通信第6号にこんないい例が掲載されていますので紹介します。『地域でのもてなしの取り組み紹介・・十津川立小原中学校の取り組み・・・小原中学校では、登下校の時に出会った方や来校された方に対して、ハキハキと大きな声であいさつする取り組みを行っています。同校は温泉地に立地していることもあり、観光客が多数訪れます。生徒にあいさつされた観光客から、「うれしかった」「心が温かくなった」などと学校へ感謝の電話があるそうです。このことから、平成19年度7月「小さな親切」実行章が受賞されました。
31・挨拶は人間関係を円滑にする上の基本であり、また、もてなしのスタートにもなると思いますが、日頃気になっていることがあります。
先日 和歌山の日高川に鮎釣り行きました。遠方なら早朝現地に到着し橋の上から川の状況を確認していると、小学校に登校する子供たちの一団がやってきました。ここで驚いたのは、こちらから声をかける前に大きな声で「おはようございます。」と元気な挨拶が飛んできたことです。その一声は何よりのもてなしで、その日は一日温かい気持ちになり釣りを楽しむとともに、日高川とその地域またそこに住む人達が心温まるものとなりました。
私は奈良の都市部に住んでおり、毎日朝は散歩をしますが、すれ違う人達はお互い挨拶しないのがいつしかあたり前の慣習になっています。
(5)奈良公園の整備の推進
132・県は28日観光地・奈良公園の本格整備に21年度以降着手すると発表した。
135・ところで知事の定例会見の詳細内容は県のホームページにでも掲載されてこない
140・時代の変遷で名産店になっていったのです。
142・これはウソか真かは知りませんが、興福寺の石垣が有るそうです。
147・これは政策の問題で、立ち退かせれば解決する事では無い
143・「奈良もてなしの心」推進については一般にPRが出来てないと思います。
土産物店や飲食店が立ち並ぶ奈良公園の東大寺門前町で県が年内にアスファルト園路を石畳に改修する計画を進めている。
『北側が南大門や大仏殿などを結ぶ石畳参道につながっており、参道との一体感を演出するのが狙い。1300年祭の22年1月までの完成を目指す。土産物店や飲食店9軒が立ち並ぶアスファルト園路。観光地奈良の顔とも言える門前町の魅力を向上させたい考え。土地の地代値上げを提示しあわせて園路を石畳に改修する検討を始めた。21年度予算化を検討、順調に進めば今年夏ごろ着工。』という内容が掲載されていました。私はこれに関連し下記提案したいと思います。
名称:「奈良もてなしの心の空間」とする。「もてなしの心なら」のシンボルマークを石畳につける。奈良もてなし宣言の立て札も掲示。もてなしの心のシールをここで配布。
「奈良もてなしの心」推進については一般にPRが出来てないと思います。殆ど誰も聞いたことが無い。奈良の観光の顔といえるこの場所で名乗り出て活動の県民推進の起点とする。
少し唐突に感じられるかもしれませんが、でも絶好のPRのチャンスじゃないでしょうか。皆さん如何でしょうか。
145・「もてなし」って、役所が押しつけるモノかどうか、もう一度考えないといけない
(6)マイベストスポット発掘による奈良の魅力の深耕
149・第二次大極殿に立ちご来光を眺めていると朝もやに包まれた興福寺の五重塔の・・
150・私のベストスポットを紹介します。それは、県庁舎の屋上からみる奈良公園です。
151・私のマイベストスポットを後一つ紹介します。お水取りの二月堂の舞台から見る奈良の夕暮れ夜景です。3月12日はお水取りで大松明が上がりこのときは毎年TVでの新聞にも出ますがあまりにも有名で人が一杯で身動き取れません。私のお勧めは3月1日から11日と13日の19時からの松明です。大松明より小さいですが見事な篭松明が毎晩上がります。余り知られてなく最高の穴場なのです。松明の前後には二月堂の舞台にも上がれ夕暮れも夜景も楽しめます。外人さんも一度案内したことありますが本当に感激されていました。これは自信のマイベストスポットです。
153・平城宮跡の朱雀門の側に池がありますが、そこから、眺める朱雀門・・
(7)美化運動推進
167・違法広告物「年内に半減」方針確認。官民の連絡会議、1300年祭に向け。奈良も1300年祭で来られる多くの人々に好印象を持って帰っていただけるよう、大いに県民のこの種活動の盛り上がりに期待したいですね。
173・本日早朝平城宮蹟に散歩に行きました。3連休の最終日ながら雨でしっとりとした平城宮跡を満喫しました。ここでの体験を披露します。朱雀門の西側にごみが一杯散らかっていました。よくみてみると昨夜誰かが酒盛りをやったようで、一升瓶、酒パック、ビール缶等でカラスが散らかしたようです。これでは折角の平城宮跡が台無しです。小生が片付けるにも量が多く散歩をしながら気になっていました。でも私は平城宮跡にはいろんな清掃ボランティアさんが活動されているのを何度も目撃しておりましたが、散歩の途中でゴミ袋を手に勤務前の清掃をやっておられる管理事務所?の方に会いました。「実はごみが散らばっていますのでよろしく」とお願いしました。
昨夜宴会やったんだろうな、散らかしてかえるなんて ええんかい(いいんかい)といった駄洒落が帰ってきました。散らかすけしからんグループがいても、直ぐにきれいにしてくれるこういったグループがあることのありがたさを感じました。清掃はもてなしの基本。1時間ほど散歩して戻ってきましたがきれいに片付けられていました。そこにはもう観光客がこられていました。もし清掃されてなければ奈良に幻滅を感じられたことでしょう。大切なもてなしの心ではないでしょうか。
(8)平城遷都キャラの活用
9 ・前期の電子会議室で議論されていましたが、せんとくん、まんとくん、なーむくんを有効活用できるような取組についての提案です。本日、ある人からクレームを聞きました。
「東京では、このキャラクターを大々的に宣伝しており、購入するつもりで奈良にきたが、なかなか手に入らない。やっと見つけたお店でも、3種類そろっているところは無い。せんとくんは、県が選定したもので、県の管理しているお店でしか売っていない。他のお店では扱えない。従って、3種類手にいれるのに別々のお店で探すしかない。この時間の浪費は、観光客にとっては絶えられないものである。」というものです。3種類のキャラクターを同じお店で扱ってこそ、選択できるし、3種類そろえたいという人にも喜ばれる。別々のお店でしか手に入らないようでは、「もてなしの心」とは言えません。観光客に喜んでもらえるように、希望するお店は3種類とも扱えるようにすべきだと思います。県の考え方を聞きたいものです
48・3人のキャラクターが、共演共存するのが一番よいと思います。平城遷都祭の話題性を高める手段として、大いに活用したらよいと思います。
146・遷都君は行政の立場、まんと君は県民の立場、なーむ君は仏教界の立場、ある意味、奈良の全員が揃って登場したことになりますね。私はこれを奈良遷都「3兄弟」と思っています。
何とも不思議なのは、その生い立ちで、それ故のにらみ合いがあったりして、でもその時期は過ぎて、思えばやはりそこは同じ土壌に生まれた「3兄弟」。キャラクターグッズも3つ揃って価値が出てきます。これをプロモートする人がいないだけの話でしょいうから、そこは一肌、観光連盟さんが踏んばるべき時でしょう。頼みます。荒井さん、鶴の一声どうですか。
4.おわりに
全般的にはいい討議が出来たと思います。僭越ながら小生の鈍い感度で抜粋、要約し提案に絞り込み報告書にまとめたわけですが、皆さんの生の声を充分反映できてない点も多々あろうかと思います予めお断り・お詫びしておきます。
「もてなし」については幸い21年度上期のテーマにも挙がっており、引き続きの討議をお願いする次第です。又、最後に行政の方におかれましては忙しい中ではあろうかと思いますが、この電子会議室は毎日覗くという習慣を持って頂ければ幸です。
IV.広報活動、登録・投稿・アクセス集計
1. 電子会議の広報活動(実施した広報媒体)
| (1)新聞発表 (奈良新聞) | 1件 | 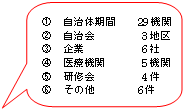 |
(2)ホームページリンク(団体、機関) | 13件 |
| (3)メールマガジン(団体、機関) | 5件 |
|
| (4)機関紙/地域情報誌 | 2誌 |
|
| (5)会報 | 3000部 |
|
| (6)放送 | 2件 |
|
| (7)ポスター(公共施設、企業、交通機関) | 144枚 |
|
| (8)チラシ (公共施設、企業、交通機関) | 6553枚 |
2.電子会議室 アクセス・投稿状況
(1) 電子会議室アクセス数(2006/11/1〜2009/3/31)
| TP | HP | 18下 T-1 |
18下 T-2 |
19上 T-1 |
19上 T-2 |
19上 T-3 |
19下 T-1 |
19下 T-2 |
19下 T-3 |
|
| 18年度 | 11078 | 7108 | 4419 | 2685 | ||||||
| 19年度上 累計 |
22702 33780 |
23286 30394 |
913 5332 |
495 3184 |
6667 |
5176 |
9979 |
|||
| 19年度下 累計 |
22356 56136 |
25672 56066 |
760 6092 |
477 3661 |
623 7290 |
650 5660 |
2168 11774 |
7486 |
8117 |
5332 |
| TP | HP/計 | 20上 T-1 | 20上 T-2 | 20上 T-3 | 20上 T-4 | 20下 T-1 | 20下 T-2 | 20下 T-3 | 20下 T-4 | |
| 20年上 累計 |
21545 77681 |
29948 86014 |
4328 |
6758 |
5650 |
6183 |
||||
| 08/10 | 5452 | 6935 | 158 | 152 | 155 | 213 | 1476 | 1396 | 978 | 1335 |
| 08/11 | 4009 | 5676 | 81 | 82 | 113 | 144 | 1292 | 1073 | 855 | 1343 |
| 08/12 | 3421 | 4553 | 67 | 75 | 83 | 97 | 1140 | 884 | 552 | 967 |
| 09/01 | 3468 | 4489 | 58 | 68 | 83 | 104 | 1100 | 769 | 600 | 1013 |
| 09/02 | 2812 | 4272 | 70 | 71 | 71 | 77 | 1090 | 588 | 468 | 1047 |
| 09/03 | 2977 | 4094 | 78 | 91 | 103 | 99 | 951 | 456 | 436 | 897 |
| 20下期 累計 |
22139 99820 |
30019 116033 |
512 |
539 |
608 |
734 |
7049 |
5270 |
3889 |
6602 |
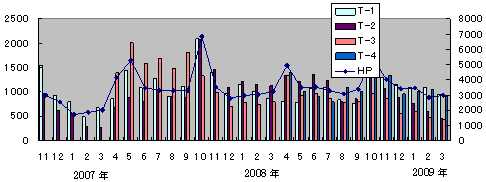
| 18下 | 19上 | 19下 | 20上 | 08/10 | 08/11 | 08/12 | 09/1 | 09/2 | 09/3 | 累計 | |
| 登録数 | 60 | 65 | 35 | 32 | 17 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 233 |
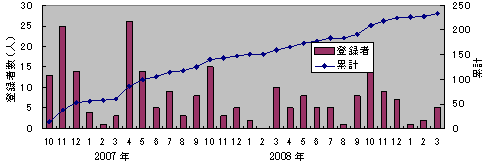
| 年月 | 18下 /T1 |
18下 /T2 |
19上 /T1 |
19上 /T2 |
19上 /T3 |
19下 /T1 |
19下 /T2 |
19下 /T3 |
合計 |
| 18年計 | 124 | 61 | 185 | ||||||
| 19年上計 | 124 | 360 | 398 | 882/1067 | |||||
| 19年下期 | 174 | 212 | 297 | 683/1750 |
| 20上 T-1 |
20上 T-2 |
20上 T-3 |
20上 T-4 |
20下 T-1 |
20下 T-2 |
20下 T-3 |
20下 T-4 |
合計 | |
| 20年上期 | 141 | 184 | 233 | 190 | 748/2498 | ||||
| 08/10 | 93 | 37 | 52 | 37 | 219 | ||||
| 08/11 | 62 | 29 | 65 | 49 | 205 | ||||
| 08/12 | 43 | 22 | 8 | 19 | 92 | ||||
| 09/01 | 40 | 19 | 21 | 29 | 109 | ||||
| 09/02 | 32 | 16 | 9 | 27 | 84 | ||||
| 09/03 | 34 | 16 | 12 | 18 | 80 | ||||
| 20年下期 | 264 | 123 | 167 | 179 | 733/3231 |
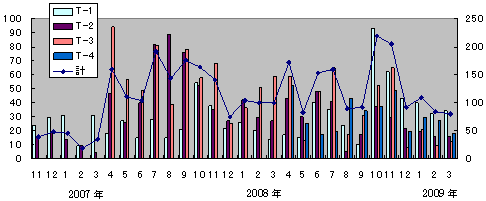
V.まとめ
1.全般
電子会議では6ヶ月間という短期間で、大変意義ある論議が出来たことを投稿者の皆さんに感謝申し上げたい。広範囲で、家庭から地域でのあらゆる分野に言及でき、熱心に色んな角度から議論が行われ、奈良県の実状をある程度的確に捉まえた議論、及び提案ができたのではないかと思う。投稿件数は、今期は748件になり、累計で2498件に達した。この中で、テーマ1では、21件、テーマ2では9件、テーマ3では3件、テーマ4では9件、合計42件の提案としてまとめることができた。また、トップ頁のアクセス数が22,139件になり、累計で99,820件、投稿数は、733件、累計で3231件であった。多くの方々が閲覧していただいている。今後の検討課題として、広く県民に広げるための広報のあり方と、県政や民間において地域の活性化の為に取組むに値する項目を実行することであると思う。
情報化社会において、多くの問題が山積する中で、多様な意見をフランクに投げかけ議論し提案できる場として、電子会議室は広く県民にメッセージを伝達し、議論して県民の意見を集約する有効な手段である。より多くの県民への理解と関心を高め、少しでも多くの会議室参加者の呼びかけを引き続き継続し、今後も幅広く議論できる「なら県民電子会議室」にしていきたい。
2.課題
(1) 投稿者が固定化してきている。登録者、投稿者をもっと増やし、特に、女性層や若い層の参加を増やし、より多様な議論を展開することである。平成18年11月から21年3月までの、登録者数は233名に対して、投稿者と回数の関係は下記のとおり。
| 投稿回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 50回以上 | 投稿者総数 | |
| 投稿者数 | 35名 | 14名 | 18名 | 8名 | 4名 | 15名 | 136名 | |
| 割合 | 25.7% | 10.3% | 13.2% | 5.9% | 2.9% | 11% |
(2) 既存の団体や組織による情報の共有化や協調体制作りとか地域住民による魅力ある街づくりと行政の協働体制といったテーマについての議論がなされなかったのは心残りに思う。
(3) この会議室は県の事業でありながら、一般には県の考え方が分らないという不満がある。県の方針なり考え方を明示して議論することがあってもよい。実際に県のトップの方々が関心を持っておられるのかどうか全く感じられなかった。
(4) 品質管理のPDCAサイクルを回すことが基本と考えるので、報告書をあげて終わりではなく、その結果まで考察し、議論に参画した人達に報告する義務がある。
(5) 口コミによる勧誘
・投稿している人を通じて知り合いの人に働きかけてもらう。
・インセンチブ(ポイント制)・・・・・紹介した人数によりポイントを与える。
一定のポイントになると、インセンチブ(例、イベントの招待券など)を与える。
(6) 会議室での発言をもっと増やすために、会議室の進行役のなり手がなかなかいないのが実情である。「会議室」の進行役を務めてくれるような人材の育成が今後の課題である。
3.県への要望
(1)県職員および関係者の参加について
(1) 各テーマについては相当な専門メンバーによる推進県民会議のようなものが存在し委員会で論議されているが、はじめにそういった委員会との連携体制を構築しておくべきでは。(連携がなく、電子会議室に関心を持ってないのではとも思える。)
(2) 関係部署の業務に関係する投稿があった場合、既に実施中の事業について、投稿者がそれを知らない場合、或いは間違って議論されている場合、担当課から、自主的に内容の紹介をして欲しい。議論の中で壁が必ず出てくる。投稿者は結局最先端の情報なり実情を把握している訳ではないので、議論が壁の前で止まってしまうことになるが、電子会議の中で、行政側の見解として発言を加えてもらうとか、報告結果に基き行政としての対応結果を電子会議室の中で報告してもらう、議論のフィードバックがなされるようにしてもらうと会議室での議論が空論で終わることなく、さらに有効に機能する場になると考える。
(3) 知事自らのメッセージを顔写真と共に会議室のトップページに載せて頂く事は出来ないものか。その事によって、県のトップが県民の声を積極的に聞く姿勢がある事が直接伝わり、投稿者の裾野を大きく広げる事にもつながる。
(2)広報活動について
「なら県民電子会議室」は、まだまだ、県民に知られていない。チラシ、ポスター、メールマガジン、サイトなどを利用して、広報に努めているが、認知度は低い。テーマに関係する部門からの広報支援をお願いしたい。
(3)県の政策への反映
投稿者からは、提案に対する県の取り組みについて、強い関心を持っている。その期待があるからこそ、投稿を続けている。電子会議室を継続させるには、提案に対する県の前向きな取り組み姿勢が必要である。
4.補足
■ 運営委員会の開催日:2ヶ月ごとに開催
■ コーディネーター会議:運営委員会のない隔月に開催
最後に、この電子会議室を盛り上げていただいた運営委員会の皆様や、広報活動にご協力いただいた企業、団体、個人の方々に心から感謝申し上げます。
【添付資料】
1.20年度下期運営委員会委員
2.20年度下期「なら県民電子会議室」ポスター

