
19年度上期「なら県民電子会議室」報告書の概要
〜県政について県民同士での意見交換〜
2007年度10月6日
NPO法人電子自治体アドバイザークラブ
理事長 奥家孝彦
I.はじめに
(1)目的
この会議室は、インターネットを活用して県民同士が県政について幅広く議論できる場を 提供することにより、県民の県政に関する理解と関心を高めることを目的とする。
(2)電子会議室に期待するもの
ここ数年で、インターネットの利便性によって、相当部分が効率的にできるようになった。自治体においてもインターネット活用が大いに進んでいる。今では、行政サービスの電子化が進み、ホームページを通じた情報公開も進んだ。自治体のWebサイトでさまざまな行政情報を確認できるのは当たり前となり、公共施設のネット予約など、便利なサービスも広がりつつある。
一方、一人の人間が入手できる情報量が爆発的に増え、専門分野が細分化して問題が複雑化している。その結果、全体像を把握しにくくなっている。環境や高齢化など、現代の日本が抱える問題は複雑化する一方である。 インターネットを利用したサービスの種類や質も、自治体によって大きく異なっている。教育現場の情報インフラの整備や庁内のセキュリティ対策なども、自治体によって驚くほど差がある。日経パソコンの調査によると、約60%の自治体が、部署ごとのメールアドレスをWebサイトに掲載して、各部署が住民からのメールでの問合せに対応できる体制を整えているが、残りの40%はそういう体制になく、意識改革が必要であると結んでいる。
電子会議室の特長は、「対話」、「気付き」、「多様性」である。人と人がネット上で対話することで気付くこともある。文化や経験の異なる人が、自由に対話することにより「多様性」を認めあうことができる。地域SNSやブログコミュニティなどの拡大により、社会環境が変化してきている。インターネットを利用して生活の隅々まで広がる新しいサービス、価値の創造が始まっている。電子会議室は、情報化社会で、県民の意見を集約する有効な手段になってきている。このためには、電子会議室へのアクセス・登録・投稿を増やす施策が必要である。多様性を支える不断の革新が成功の鍵と言える。
電子会議室は、インターネットのホームページ上に設置した電子掲示板などを使って、参加者が自由に意見を述べ、議論に参加できるため、参加者同士あるいは参加者と県職員が地域の課題について一緒に考えていく新たな県民参画の場として期待されている。
19年度上期は、3つのテーマについて、6ヶ月に亘って、議論を進めてきた。各電子会議室で、議論された内容からまとめた報告を下記する。奈良をよくしたい、自分の住んでいる地域を良くしたい、と思った人たちが集まって議論した内容であり、県政に生かしていただければ幸いである。
II.提言
各電子会議室でまとめた「提案」の項目を提言として項目のみ下記する。詳しくは、後記する各電子会議室の報告をご参照いただきたい。
(1)テーマ1:自分たちでできるまちづくり
(1)県内のまちづくり情報などの発信の充実(まちづくり情報センター)
(2)まちづくりに関する相談が可能な総合的窓口の設置(まちづくり相談窓口)
(3)身近なまちづくりを支援する専門的知識を有するボランティア、コーディネーターなどの養成、派遣制度(まちづくりお手伝い隊)
(4)観光客を楽しませる、お客さんをもてなす伝統的お祭り、イベントの復興支援等(もてなしまちづくり支援)
(5)防災をキーワードにしたまちづくり活動支援(防災まちづくり)
(2)テーマ2:みんなで教育について語ろう
(1)学校支援地域本部を積極的に設置する。
(2)PTAや学校に向けた学校支援地域本部の設置研修会を行う。
(3)ネットワーク型授業(よのなか科の授業)をカリキュラムに導入する。
(4)地域のリソースを学校教育に注入するための検討会「産業教育研究会」を設置する。
(5)学校経営に関する管理職向け研修会(人事交流も含めて)を積極的に行う。
(3)奈良県の観光戦略について考えよう
(1)地場産の農畜産物を購入しやすい仕組み作り
(2)この会議室で出てきた各意見についての県の評価
(3)海外論調の把握、外国語ページの充実
(4)道路標識や案内板が不親切、充実した地図やパンフレットも必要
(5)奈良観光のモデルコースの設定
(6)観光3団体の連携が必要
(7)知事公舎の迎賓館化
(8)奈良「ランドオペレーター」構想
(9)バーチャル・リアリティによる平城宮跡の復原(幻視)
(10)県庁の移転と跡地のホテルへの転用
(11)正倉院展宝物のレプリカ(模造品)展
(12)奈良美観都市宣言
(13)投稿方法の改善
(14)奈良観光振興への提言
(15)B&B(Bed and Breakfast 宿泊と朝食のみの施設)による誘客
III.電子会議室の報告
III−1。テーマ1
自分たちでできるまちづくり
〜地域住民主体による魅力あるまちづくりの提案〜
コーディネーター:藤野正文
1.はじめに
県内各地で住民が主体となったまちづくりが進められているが、さらなる魅力あるまちづくりの提案を多くの人に様々な意見や提案を述べいただき、その成果を今後の施策に反映して頂こうとの主旨でスタートした。会議室参加者は23名、会議室での発言数は124件であった。
2.提案
(1)県内のまちづくり情報などの発信の充実(まちづくり情報センター)
NPOなどと協働による県内一円を網羅した地元でしか解らない、地域コミュニティによる生きた伝統的お祭りやイベント、先進的な地域のまちづくり活動、まちづくり組織、まちづくり人など地域の生の情報をリアルタイムで発信。各地のまちづくり活動交流機会の充実。また、行政のまちづくり情報を総合的に紹介、情報提供、発信する機能の充実。
(2)まちづくりに関する相談が可能な総合的窓口の設置(まちづくり相談窓口)
多様な県民によるまちづくり・地域づくり活動に対して総合的に情報支援したり、助言・相談、案内する総合的窓口の設置。
(3)身近なまちづくりを支援する専門的知識を有するボランティア、コーディネーターなどの養成、派遣制度(まちづくりお手伝い隊)
身近なまちづくり活動に対してボランティアへの研修機会の豊富化するとともに、専門的な相談に応じたり、お手伝いをしたり、橋渡しとなるボランティア(リタイア世代の活用を含む。)を募り、派遣などをおこなう制度の拡充、創設。
(4)観光客を楽しませる、お客さんをもてなす伝統的お祭り、イベントの復興支援等(もてなしまちづくり支援)
観光客、お客様とふれあう、楽しんでもらえる、地域コミュニティ等による伝統的お祭りやイベントの復興支援とその情報を地域ごとまとめたマップなどの作成の支援
(5)防災をキーワードにしたまちづくり活動支援(防災まちづくり)
地域コミュニティの活性化につながる、災害時の非常用燈火器の作成や燈火イベントなどや地域の「防災をキーワードにした地域レベルのまちづくり活動」の支援
3.発言の概略
このテーマについては、当初から特に分類を設けなかったことから、コーディネータの判断により、分類整理をおこった。また、内容が長くなり読み辛いが、投稿者の思いを出来る限り生の声として伝えたく、発言に近いかたちでとりまとめた。
(1)まちづくり意識の醸成
・『まちづくり』は、問題点を話し合うことが第一で、『コミュニケーションを通じて、住民のコミュニティーを形成すること』。身近な問題点は沢山あり、住民の話し合いが始まれば、行動を通じて環境を意識的に変化させることは可能である。あきらめては『まちづくり』は始まらない。
・これからのまちづくりは考え方、価値観の変更が必要。まず自分のまちをゆっくりと歩いて自分の目線で町を知る。自分でできる事から初めて、そのうち気の合った仲間を見つけて楽しくまちづくりに役立つ事をする。使わなくなった学校や施設ももっとオープンにして、用事がなくても人がたくさん集まりやすい場所にする。町のホームページももっと住民に役にたつ、面白い事を考える。これから卒業する団塊の世代は半分仕事をして、1/4は地域に役立ち、1/4は自分の趣味に活きるという素晴らしく人間らしい生活を送りたい。
(2)身近な活動によるまちづくり
・住んでいる街の環境を住民自らの手で良くすることで、地域によりよい関心を持つようになり、それが犯罪の抑止や住環境の改善を促し、より安心して暮らせるまちづくりにつながっていく。住宅地近隣の河川を浄化するため、様々な取り組み(炭素繊維を川底に敷き、好気性の細菌の増殖を促す。ヘドロに砂を混ぜて固める。台所の配水管に雑菌が増殖するのを抑える液体を町内会で作り、各家庭の台所の排水溝に蒔く等)が出来ないだろうか。
・先ず、自分達の住んでいる町でのボランティアに参加して、家々から出る排水溝の掃除や家庭のゴミを如何にして減らすか、町内親睦を兼ねた活動をするべき。
・同じ地域内に住んでいても、知り合いの人は少なく、声をかけることも少ないのが現状である。犬の散歩の時、会う人には、声をかけるように心がけている。お互いに声をかけて、親睦を深めることがまちをよくする第一歩。
・近くに森があり、毎日、犬の散歩をしている。同じ時間帯に、ゴミ袋を片手に犬の散歩をする近所の人がいる。ジュースのカンやタバコの吸殻などゴミを拾いながら散歩している。30分くらい散歩すると、袋にいっぱいになるという。学びたい行為、心がけ1つでこんなに違う。マナーアップ・キャンペーンでも、草の根的に大きな動きにしたい。まず、足元からやれることを・・・。
・今年の年初より村の役員に選ばれて、四苦八苦しているが、既に会社勤めも卒業し、いずれは役に立ちたいとは思っていた。既に新たに皆さんとで子供を守る安全パトロール隊や、自主防災組織の結成等々に取り組んできた。そこで何をするにも先ず感じるのは、ここで生まれ育った私にとって、先輩の方々の徹底したボランティア精神のご苦労があっての村の歴史であると、思い知らされる。何はともあれ、先人の方々への恩返しと捉えて、先ずは足元から、自分でやれることからやって行こうと思っている。
・ボランティア精神とは、外部から強要されるのではなく、自主的に行動し、少なくとも営利を主たる目的としない精神であろうと思う。自分のやれることからやっていくこと、その同じ動機の持ち主が集まって、ボランティア団体の活動となっていく。
・「ほのぼのひかり」の作り方を教わったので、我が地元防災会で報告と実演したら、「いっぱいならべたら、綺麗やで〜」ということで、我が町の公園に自治会の世帯数204個を列べた!!防災をキーワードにして子ども、親、ご近所さん連れ添って、ちょっとした世代間交流があった。とっても綺麗で!ゆらゆらと揺れる炎で心が癒され、炎の「怖さ」と「ありがたさ」を大人達は再認識し、子どもたちは、学んだと思う。また、団体や企業などに参加してもらえるような取り組みを考えていく。多くの人に、参加してもらえれば、コミュニティーの活性化へと繋がる。
・奈良町のある町では、火災が続けて発生したことをきっかけに、おもてに消火用のバケツをおいてある。もし火災が発生したら、実際、バケツ一杯で消せることはないが、住民の心がけのシンボルかもしれない。住民の共通認識の図りやすい、防災をきっかけにしたまちづくり、コミュニティづくりが広がらないだろうか?
・平城宮跡の解説ボランティアの募集を知り応募した。現在でも失敗や恥の連続だが、見学者の方々から「ありがとうございました」、「話を聞いてよかった」と言われるのが明日への励みにもなる。時には見学者の方から便りを頂くこともある。来訪者は小学生から大学生、あらゆる世代の家族ずれ、老若男女、身障者の方、時には外国の方、いろんなグループや団体、たくさんの方々と接することが出来る。このボランティアを通して奈良をより理解してもらい、奈良ファンがひとりでも増えて、奈良の活性化に役立てばと、心ひそかに、リタイヤ組みの社会貢献?と思う。
・家の近くに、ユーモラスな光景で笑いをよんでいるお店がある。(1)真夏に翻る鯉のぼり、(2)真夏にサンタークローズが屋根にのぼる。いづれも、季節はずれの風景であるが、めざわりというより、事件の多い世間を忘れてユーモアーのある風景として、受け取られている。これらの、季節はずれの風景が、現在を忘れさせてくれる清涼剤ともなるのかも知れない。心に一瞬のゆとりを与えてくれる。簡単にできるユーモアのあるまちづくりも如何。
・「自分たちでできるまちづくり」って、行政ではできない事を住民自身が考えながら、地域に付加価値を付けていくこと。先日、高取町の古い町並みが残る土佐を散策して、多分住民自ら楽しみながら、訪問者をもてなしている、すてきな「花のある風景」を家々の前で見つけた。
(3)観光客を楽しませる、お客様をもてなすまちづくり
・意識改革が必要だが、ただ、自分の御客様に対して、「もう来るな!」と云う人間なら兎も角、普通は自分への御客様は大歓迎のはず、奈良県民が、奈良へ来られた全ての方が「御客様」という意識を持って頂ける政策。では、具体的に何?は、自分の頭では一寸思いつかない。
・観光業の方は、自分の主張を押し付けず、お客様のニーズをしっかり見極めれば大丈夫と思う。観光に関連しない一般市民の方は、観光業の方と一緒に、来客を楽しめるか?あるいは、自分たちの生活を乱し、環境を悪化する邪魔者と考えるか?大規模のイベントを中途半端に実施し、交通渋滞、ごみの山を生むと、私でも後者の考えになる。こうならないために、県あるいは市民レベルで実施できる施策が必要と思う。
・お祭りは、基本的にやっている人々が楽しくなくては出来ない物。私はこれが基本中の基本で有る、と考えている。やっている人間が楽しくないと、気分が乗らないので、来客にも此の気分が移ってしまい、結局双方が楽しくなくなって、潰れてしまう。双方楽しい例として、「岸和田だんじり祭り」が挙げられる。やっている人、見学者、双方楽しんでいる。これがお祭りの基本で有る、と思う。イベントは一寸違う。イベントは、商売なので、やっている者は給料を貰ってやっている。無論、此処でもボランティアが活躍して居るが、主体的な事業自体は公共工事で、楽しいとか云う事とは別の問題で、職業として見るべき。地域振興は商売ではない。イベントでは無く、「お祭り」として考えるものではないだろうか。
・奈良のよさを育てるために、観光客に優しく、楽しんでもらえるよう伝統的イベントの復活を
・伝統的なイベントは局地的に行われているし、新たに生み出された物も有る。此は一人では出来ない。ベースは、地域コミュニティーが此の地区に存在しているか否かにかかっている。
・「観光客を楽しませるまちづくり」は、お客様が楽しくなければ、いくら自分たちが楽しんでも意味がない。一方、「自分たちが楽しむまちづくり」は、自分たちが楽しく生活できればいいと思う。目的によって、考え方は変わると思う。
・高知市内の商店街の「ひろめ市場」のような所が奈良にもあったらいい。だれかれかまわず、空いた席に座り、バザーのように並ぶお店で好きなものを買ってきて飲んで食う。見知らぬ隣の人ともすぐ友達のように打ち解ける雰囲気。子供づれの家族、勤め帰りのサラリーマン、たぶん我々のような旅行者。ここには飲食店、魚屋、肉屋、駄菓子屋など56店舗が集まっている。事業目的は「市民及び観光客への食文化の発信、また地場産業や土佐文化の発信」である。
・この市場は商店街活性化の一つとして98年に始まった。今では、高知市の食事処にも成っている。当然、観光名所にも成っているが、やはり普段から此処で食事やお買い物をする定住者が居る、と云う事が大きいと感じる。
・私が奈良にもあったらいいな、と思うのは、小人数の友人や初めての人を観光案内した時、食事の場所選び。もうひとつは「ひろめ市場」のような場所が奈良にあれば、外国人観光客との交流の場にもなると思う。奈良での宿泊客を増やそうと新しいホテル建設の計画も耳にするが、最近の関西での外国人観光客は「新今宮」泊まりも多いと聞いたが、お客さんのニーズに合ったものを用意した方が良いと思う。
・県民が住みやすく、観光客には「また奈良に来たい」と思ってもらえる町づくりのための提案をしていきたい。観光客にも「此処で住みたい」と言って頂きたい。定住人口増加策の一つ。
・本当に外国人に見て貰って恥ずかしくないかは此処で住んでいる人々の意識だけの問題かとも感じる。ホスピタリティーって云うのは、決して凄い木造建築が有ったり、世界遺産だから、と云う物では無いはずで、来て良かった、と感じて貰えるのは、どんな人とそこで出会ったか、だと思う。奈良が真の三つ星かどうかは、これから試される。
(4)歴史的資源を活かしたまちづくり
・私見として、奈良県は歴史を保存することに力点を置き過ぎている。歴史的資源を有効に利用する知恵が欠けていると思う。人が変化し、社会が変化し、強いては万物が変化しているのに、何故、奈良県民は変化を嫌うのだろうか。変化に自信が持てないからである。変化で損をするかもしれないと言う、疑心暗鬼な気持ちがあるのではないか。
・私は生まれも育ちも奈良県民、私も周りも別に変化を嫌っている訳ではない。その証拠に住居地の周りにもマンションが林立し、住民も移動している。商店街も様変わりした。三条通りなどは良い例だと思う。変える所、変えてはいけない所、この2つが有る、と云う事をわきまえて、住み続ける地域で有る、と思っている。
・先日、近鉄田原本駅前に用事があって車で出かけたが、迷路のような町でした。昭和の初期にタイムスリップしたような街並み。アンティークな街並みで良いのかも知れないが、街を訪れる者に取っては大変迷惑な街である。奈良県はこの様な街並みが多いのではないだろうか。行政改革も必要だが、住民の意識改革と街並み改革が最優先ではないだろうか。
・町並み保存と改革、奈良の宿命。奈良商工会議所編集「奈良大和路の歴史と文化」に、橿原の今井町や宇陀の松山地区に継ぐ歴史的景観を残す町並みとして「田原本の寺内町」が記してあった。田原本の人たちも日常の不便を感じながらも、町並み保存には誇りを持っていると思う。
・町並みの保存も大切だが、時代への適応性や時代の先取りも大切。街並み保存とカッコ良く言っているが、本当のところは所有権の移転や土地区画整理が出来ないのが本音ではないか。この様な町が奈良県には多すぎる。『最大多数の最大幸福』が民主主義の根本原理。
・『新しいまちづくりに取り組んでください』と町の方々に申し上げたい。
・京都から橿原まで近鉄で移動する際、田原本町駅を車窓から観察してみた。どこか似てるかなと思ったのは都電荒川線や江ノ島電鉄。駅構内に入ったあたりで、「町の中に囲まれている」という旅行者の気持ちに対する温かさを感じた。駅構内から見える各家屋に、花木を置いたり、家屋に錆が浮いていれば補修して、ちょっとだけ小綺麗にするだけでも印象が良くなりそうである。
(5)ボランティアのまちづくり参加
・リタイア組の社会貢献について、ボランティアの需要を把握し、自発的にボランティアをしていただく人を募る仕組みに。金銭的な見返りは期待せず、創造性、開拓性、先駆性といった自己実現が大事。職員の補助と考えると失敗すると言われてる。「ボランティア受け入れの前にすべきこと」を決めておかないと、「誰でも良い=あてにされてない」が見透かされる。本当のボランティアは「自分の気持ちや行動を積極的に押し出す」「自分の活動を自分の判断で決められる」といえば、ここで議論されている皆さんも良く判るはず。
・ボランティア組織やNPOのもっと積極的な働きかけが必要。例えば体験ボランティア、NPOリタイア対象インターンシップとか・・?リタイア組もリタイアする前から準備運動を・・・
(6)まちづくりの情報
・私は西部の新興住宅地に住んでいるが、こういう活動に協力しようと思っても、情報不足でなかなか踏み切れない。どこかで情報を一元管理しているか教えて欲しい。団塊の世代が退職する今、興味を持っている人は多いと思う。
・地域単位での、楽しみマップの作成。地域ごとばらばらにせずに、県の方針のもと作成情報を県ホームページで発信。いまでも、多くの情報が発信されているが、情報が作られきれい過ぎると思う。地元しか分からない、生の生きた情報を手作りで作成して提供するのはいかが。
・行政ではなく、此こそNPOの職務ではないだろうか。県下一円を網羅したシステムが必要。
・情報を提供するのは市民レベルで行うとしても、情報の管理・更新などには費用がかかる。このインフラの作成と整備などの運用はNPOでも、費用は行政が負担しないと継続運用は難しい。
(7)景観まちづくり
・奈良という郷土に誇りをもち、その景観、環境を気持ち良いものとし続けるためにも住宅の外観意匠はなるべく和風で周囲にマッチしたものを心がけていくべき。屋根の形態、外壁の色、形状、或いは塀のある宅の場合は塀の形態、屋根の形態など、どのように意匠面で工夫すれば奈良らしい景観・環境か、できれば地域住民、自治会レベルでガイドラインを設ける。景観のある街づくりを推進していくことで地元の一体感、地元への愛着心が深まり、町としての活力や観光都市としての独自性、強さを維持するだけでなく防犯面でも威力を発揮していく。
(8)その他
・関西の自治体は、『県民の、県民による、県民のための自治体』になっていないように思う。中央政府の出先機関であったり上意で物を言う事なかれ主義の役人行政になっていないだろうか。即ち旧式『他治行政』が罷り通っていないだろうか。本来の『市民政府行政』になっていない。
・以前は地域に青年団・婦人会などの社会教育団体があり、自主的な活動を通じてまちづくりを行っていた。最近は行政が「地域福祉推進協議会」とか老人を対象に「ふれあいサロン」などの企画を立案し、地域の自治会や民生委員会などに管理運営を丸投げするため、自治会役員や民生委員に加重な負担がかかり、任期満了時に後任のなり手が無く困っている。地域住民のニーズに基づかない施策を、行政の人気取りのための施策として増やさないでほしい。
・行政は、ボランティアや熱意を当然視して、此にたかって「当たり前」面をしている事が多々ある。例えば「なら燈花会」を企画会社へ丸投げすれば、経費はゼロが後に二つ位付く。私は、全てに於いて、この「たかり体質」が元凶の気がする。
・一条に住んでいたのですが、時折、塩素系の異臭が漂い頭痛がすることがあった。左京のごみ処理工場、黒髪の運動場を不燃物ごみの一時置き場に関係しているかも。更に、大和北道路の地下案では、換気塔を両端に寄せる案が示されており、北側は高さ8mの換気塔が左京の清掃工場付近に設置される予定だが、ここから排出される排煙は、佐保台住宅地から一条、近鉄奈良駅、奈良公園一帯等を直撃する。秋になれば、水田の野火焼きの煙や匂いが大気の逆転層のため拡散せず、一面に漂う奈良の特殊な地勢ということも考えて欲しい。
・西九条佐保線の道路計画がある。高架橋の高さが記載されていない。近隣の教育施設として大安寺西小を囲って挙げてあるが、この距離で言えば北から大宮小、奈良女子高、三笠中、大安寺小、奈良病院、大安寺。評価書では所定の距離(20m)では騒音は問題ないとしているが、恋の窪東町では住宅地と近接し、基準を超過するのでは?さらに北には近鉄新大宮駅があり、踏切の事を考えると、どういう動線を期待しているのか理解に苦しむ。また、横浜市で建造中のトンネル道路に関するQ&Aを見ると、深さ40mなら、道路の中心から80〜100mの幅にそって地盤沈下の可能性があることになる。これはすぐ隣を通るJRや、地上道路の周辺にとっても心配になる。活断層も近くにあるとされ、建造時は問題なくても、地震には「想定外もありうる」事を考えると、地下水位の事も考えても、ユネスコが非常に憂えるのは理解できる。
4.おわりに
投稿について主として歴史的な町並み地区においてまちづくり活動を行っている人たちにチラシの配布や呼びかけ等を行ったが、こういった電子上での議論がなれないか、または、苦手なのか、比較的、直接まちづくり活動を行っている方や若者の参加が少なかったことは、残念なことである。こういった人の参加をさらに増やして行くには、気軽に投稿できる場の設定など工夫も必要である。また、あまり議論を制約したくなかったため、投稿に際し分類項目等を設けずにスタートしたため、かえって投稿しようとする方達に更に投稿を気軽にし難い状況になってしまったのではないかと思われ、今後の課題として検討をお願いする。 もともと「まちづくり」というのは、環境、景観、コミュニティ、福祉、地域の活性化、都市計画など広範な課題や展望を包含したものであり、議論が拡散しがちであり、自由に広がらざるを得なかったとものと思われる。しかし、人によって「まちづくり」そのものものとらえ方も多様であることを確認し、さらに議論の基礎となる「自分たちでできるまちづくり」そのものの内容も多種多様であることを改めて考え直す機会の場となったのではないかと思う。
III−2。テーマ2
「みんなで教育について語ろう」
−地域ぐるみで学校をつくる−
コーディネーター:三宅基之
1.はじめに
「学校へいこう!」と誘われたら、あなたは・・・
この会議室では「おらがまちの学校」として自慢できる「元気な学校」づくりの方法や子どもたちが健やかに育つための学び舎の姿などを中心に議論し、その中で大人が学ぶことを通して、少しでも県内各地域の取組が活発になり、豊かな子どもたちの育ちの場として、多様な「おらがまちの学校」が生まれることを目的とした。
大分類は【理念】−【現状把握】−【求める姿】−【方法論】とする。
(1)「学校」ってなんだろう−(「学校教育」の目的?あなたの主張は?)
(2)「学校」あるある大辞典−(今時の「学校」話や昔の思い出話など)
(3)こんな「学校」がいい?−(どんな「学校」なら行きたくなるかな?)
(4)地域で子どもを育てる実践(オラがまち自慢、学校自慢で披露して!)
会議室のおおまかなスケジュールとして、(1)→(4)の順で進めたが、その都度考えたことや実践の情報は分類ごとに自由に投稿でき、参加者が考える材料になるように、また情報やデータの提供をして、できるだけ考える材料が多くなるように工夫した。
2.提案
(1)学校支援地域本部を積極的に設置する。
学校地域支援本部について、平成20年度予算への概算要求が発表されたこともあり、話題が集中した。教育コミュニティの地域の拠点として整備していく方向で、具体的に学校と協働する時のポイントや、人材養成のシステム、教育行政としての学校マネジメント制度が議論された。
(1)8月24日毎日新聞夕刊1面
文科省は4年間で中学校1万校区に、仮称「学校支援地域本部」設置方針を固めた。
概算要求の段階だが、初年度は2500校区に設置する方針で予算に盛り込む。
(2)学校の教員も、学校外には目が向きにくく、学校に地域の教育力を活用するのが苦手だと思う。そうした現状を変えるのは「ひとはだ脱ごうという人」の存在であり、役所・学校・地域などでこうした気持ちの人のネットワークができればいいなと思う。
(3)仕掛けや仕組みを作るには人材の養成や認証の仕組みなどの手間がかかる。大阪府は地域コーディネーターを新たに養成して、地域に配置している。合わせて学校の校務分掌にコーディネーターを位置づけて、学校の内と外に、責任者をつくる制度を「公」としている。このような制度は民間には作れないし、単独の学校でもできない。
(4)「教育コミュニティ」「協働」というキーワードについて、大阪府下での「地域に根ざした学校づくり」のバックボーンとなった池田寛氏の引用があった。<教育協議会制度>
(2)PTAや学校に向けた学校支援地域本部の設置研修会を行う。
学校支援地域本部を設置していくための具体案として、PTAを軸にした指導者養成講座や研修のような仕組みを行政が提供する必要性が議論された。地域間格差、学校間格差を生み出さないようにするためにも、PTAや学校への取組のサポートや活動の担保を行政が担うべきである。
(1)実際、校区によって随分格差がでそう。いい先行事例があれば、それを参考に自分の校区で実践できる形を見つけていける。こうなると、和田中学校でもそうだったように、既に学校と信頼関係があるPTAやPTAのOB,OGの繋がりが、学校支援本部のスタートに大きく関わるような気がする。PTAでも「学校支援本部」について勉強し始めなければ・・・
(2)学校や先生がある程度の裁量が与えられているのであれば、そのやる気のある先生を見つけて協働するファシリテーターの役割が重要になる。それを公的に担保することが必要でしょう。
(3)ネットワーク型授業(よのなか科の授業)をカリキュラムに導入する。
学校が地域と協働するために学校に変化をもたらす最良の方法が、よのなか科の授業実践であるという議論の中で、地域に開かれた学校を作るために、また地域と学校が教育活動において協働する具体的な方法として、よのなか科の授業カリキュラムの導入が求められた。
(1)和田中学校の「よのなか」科をみて、すばらしいと思った。藤原さんは、民間会社OBの人であり、学校サイドの理解や協力が必要。奈良県でこのような取り組みをする場合、何かネックになるものはあるのだろうか。学校や校長先生の考え方で可能になるのだろうか。奈良県に300数十校ある公立学校のなかから、「よのなか」科のような取組がでてきてもよいと思う。
(2)〔よのなか]科のネタは、本当に今の社会の中にあるものを取り上げて、身近であり生活観がある。大人でも目から鱗のこともあってとても勉強になる。これは、社会人として生きるためのキャリア教育という種類のものかもしれない。こんな授業が必要なのだと思う。正解が1つでない問題について、いろんな情報を基に、共に考え、深め、伝え合い、学びあう。学校と社会を繋ぐ、そんなコーディネーターがいたらいい。
(3)実際に先生とうまく連携ができれば、いろいろ話に出ている[よのなか]科の授業実践などが可能になると思う。実際に奈良市で、小学校の先生とNPOの連携で、[よのなか]科授業が行われた。
(4)地域のリソースを学校教育に注入するための検討会「産業教育研究会」を設置する。
よのなか科の授業実践を促進したり、学校支援地域本部のマネジメント機能を構築するためにも、教育行政担当と産業界の関係者が産官学連携のような形態で、地域のリソースを生かした教育の充実の方法を検討する必要があるのではないかという議論がされ研究会設置が提案された。
(1)長年、同じ世界(業界)で育ってきた人は、他の世界の理解が乏しいのはごく自然なこと。しかし、多様化した現代では、教育現場で他の世界が分らないでは、教育にはならないのではないだろうか。1人の教師では、限界があるわけで、そこを補う人材を見つけて教育現場と調整し、それを企画立案して推進することではないでだろうか。
(2)教育と産業界との関係について、非常に興味を持った。この関係をうまくコーディネートするために、教育関係者と意見交換する場として「産業教育研究会」のようなものを作る。
(5)学校経営に関する管理職向け研修会(人事交流も含めて)を積極的に行う。
学校支援地域本部の設置も視野に、管理職のマネジメント力を養成する仕組みを強化しなければならないという議論の中で、実は管理職だけの問題に留まらず学校の中でPDCAマネジメントサイクルを機能させることによって、効果のある学校運営が可能になると提言された。
(1)90年代に若手時代を過ごした、現在中堅の先生方が、そうした当時の風潮のために、指導技術が弱いという話を聞いたことがある。この時代から、インフォーマルな教師の学びの場が減少していったという事情もあるらしいが。どのようにして教育の質を維持・向上していくのか。すでに様々な試みも始められているが(教委による教師塾など)、市川先生が提唱されるような、裏付けのある確かなアプローチはたいへん重要だと思う。
(2)教員の年齢構成がいびつで、教育技術を伝達すべき若手の教員が少ない。伝達対象の若手が、個性尊重教育を受けているため助言を聞く耳をもたない。伝達者側が団塊の世代の個人主義で、他人に干渉しようとしない。(自分がよければいい?)もしくは権利主張が強く、協調性が低い。実践と検証のサイクルを学校の仕事の中に生み出さないと、やりっぱなし教育のままとなる。
3.発言の概略<経過と論点>
2007年4月〜2007年9月の論点
「地域ぐるみで学校をつくる」というテーマで、大まかに下記のように議論を進めた。
(1)学校ってなんだろう
みなさんが持っている学校のイメージや、そもそもの学校の役割みたいなものを考え合って、前提になる学校の【理念】や目的のようなものを確認仕合った。
(1)学校は学習の場である
・「学校」は「学習をする場」である。学習、正確には習学、即ち、習ってしかるのちに学ぶ。学習とは詰め込み教育でも、がり勉作りでも、まして塾のようなHow
toの学習でもない。塾は不要で、How toでなくWhat isである。何が本質なのかをまず習い、しかるのちに自ら学ぶこと。
(2)学校の目的<経営目標>
・和田中学には「社是」でなく、具体的実行計画がある。子供たちも納得して実行できる。
(3)公立学校は大切な地域資源
・「学習する場」。義務教育の小・中学校は特にそう思う。「学習」っていろんなことが含まれている。子どもたちが大人になるための幅広い「学び」が「学習」なんじゃないだろうか。
(2)学校あるある大辞典
学校の現実や自分たちの学校の思い出などを出し合って、具体的な話合いが出来る材料を出し合い、学校の【現状把握】をするのが目的である。
(1)スクールサポーターの役割
・僕が派遣されている学校の教頭先生は、よく僕たちの感想や意見を聞いてくれるが、僕自身の性格もあり、教室におられる先生方と直接意見交換をする機会は、なかなかもてていない。
(2)クレーマーの存在
・最近?は、学校には言わずに直接教育委員会や教育長にクレームを直言するケースが増えているようにも聞きますが・・・何だかなあって気がする。
(3)地域のリソースを活用した教育の推進
・産業教育フェア」は、毎秋に県教育委員会主催で開催されている。昨年は田原本の奈良県教育研究所内でした。これを小学生が見学するのも良いと思う。
(4)学校支援地域本部のような新たな取組
・和田中の取り組みを読んでつい「うちもやれるかも!!」と打ち込んでから、「はやるな、はやるな…」と自分を抑えた。私の今取り組みかけたことが始まったばかりなのだから。よのなか科の取り組みを始めていけば道がついてくるなら、何とかなるかもしれない・・・誰が大事って、やはり校長先生ですか?
(3)こんな学校ならいいなぁ
現状から見えてくる理想の学校や、各々の持つ学校のイメージや経験から学校に【求める姿】を出し合い、どんな学校を地域で創っていくのがいいのかの参考にするのが目的である。
(1)体験で学ぶことを大切にする
・情報だけでなく、現場で体に感じるものを大事にする。生徒は感受性の高い年頃で、工夫する習性、体験する環境が大事。こういうことを重視する学校があればいいなあ!と思う。
(2)学習を大切にする
・学校の学習が一番大切。これをまず議論する必要がある。家庭教育、地域教育はその次でよい。
(3)地域と共に取組む
・教育界という殻のなかにいると、外部との協働作業がなかなか難しい。そこに人事交流が必要ではないだろうか。
(4)地域で子どもを育てる実践
【現状把握】で出された数々の実践や、【求める姿】で紹介される先進的な取組や実践のアイデアなどを出し合い、地域で子どもを育てる時に、学校を軸に出来る仕組みや方法を検討する。
(1)学校評価で情報公開することで創る地域との連携の仕組
・教育関係のリーダーの方には,ぜひ,そのような学校評価,学校教育に関わるアセスメントの必要性を認識して欲しい。
(2)総合的な学習を通した学校への支援と「産業教育研究会」の設置
・「産業教育研究会」なんてあたり前かも知れませんね。子供たちが生活しているのは産業に囲まれている訳で、教育材料は山とある。ブロフェッショナルである先生方がこの山とある産業材料をどう料理してゆくかだと思う。そういう結びつけの意識が大切だと。
(3)連携を推進する仕組としてのコーディネーターやファシリテーター制度
・皆の力を合わせて新しい取組を進め、良い実践に導くにあたっては、コーディネーターというか、やはりきちんとその役割を果たせるスキルをもった人材が必要だなあと、つくづく思う。
(4)教員の意識改革と質的向上の仕組
| 【学校の仕掛け】 | |||
| ☆校務分掌で正式に位置づける ☆学校経営計画に具体策を表明 ☆ネットワーク型授業の導入 |
|
(5)学校支援地域本部の設置
・実際に奈良市でその活動をしているNPO、http://www.nara-e.net/heart/index.html
(5)成果
(1)学校は学びの場であり、全ての営みが学習につながるものであるという前提が確認できた。
(2)学校と地域が協働するためには、コーディネートする仕組が必要である。
(3)総合的な学習やキャリア教育の分野で特に地域のリソースを活用する仕掛けが必要になる。
(6)課題
(1)会議室への全体の参加者数を増加させる必要がある。
(2)学校現場からの意見を紹介できるようにする方法を検討する。
(3)県内の学校での教育活動の的確な情報を発信出来るようにする方法を検討する。
4.おわりに
平成19年度上期のテーマとして選ばれた「教育」分野についての、特に学校教育に話題を絞り込んだ「地域ぐるみで学校をつくる」という設定は、学校教育改革の中でも地域住民や保護者が参加できる公立学校改革の大きなトレンドになっている。学校評議員制がほぼ全校で導入され、地域に開かれた学校づくりという考え方や学校評価の推進についても既定路線となっているが、その本格的な実践はこれからの取組による。県内では、例えば南部と北部に特区申請で生まれた小中一貫校の取組もあり、北部の事例では成果を上げている理由の一つに、地域ぐるみで学校を支援する仕組があることが指摘されている。(奈良市立田原小中一貫校)そのような状況で当該会議室での議論が、県民への学校教育活動への関心を喚起し、地域をあげて公教育を後押ししていくための啓発の一環として位置付けることは意義のあるものだと思われる。
コーディネーターとしての配慮は、議論が錯綜しないよう整理をすることであった。そのための手法としてRVPDCAマネジメントサイクルを会議の進行に導入した。教育の「理念」を確認することを起点に、現状を把握するR(リサーチ)、現状の把握から生まれる求める姿をV(ビジョン)、実施計画P(プラン)、計画の実施D(ドゥー)、実施を検証するC(チェック)、検証から生まれる次の取組A(アクション)というサイクルを議論の基軸にすることを心掛け、また扱う話題を常に実践を基にした。「この意見はどの分野の意見か」という全体の中での位置付けを、閲覧者が常に把握できるように仕分けを行なった。これは途中からの参加でも、議論の全体が見通すことが出来どの議論に参加するかを選択しやすくする意図もあった。しかし全体として電子会議室への書込み参加者の広がりは見えず、不特定多数の県民を対象にした電子会議室の会議運営の難しさが際立った。内容については、学校の教育活動の実践がほとんど知らないために書き込むことが出来ない、もしくは意見を出せないといったことが影響していると思われる。
基本方針として「実践をもとにした会議をする」という拘りが影響した可能性も高く、今後の課題となった。しかしながら議論で出された意見は具体的であり、より深いものとなっている。地域で子どもを育てるというのはどういうことか、そのために果たす学校の役割とは何か、学校と地域の協働のあり方はどうあるべきか、それを実践するための課題は何か、紹介された実践例から何を学ぶのか、公立学校をよりよくしていくためには何が必要とされるのか、といったことが焦点化された。この電子会議室の仕組みがより発展的に活用されることにより、時代に合った地域における子育ての共同性を回復する道筋が見え、子どもを地域で育てるために大人が力を合わせる教育コミュニティづくりによる地域の再生に一歩でも近づいていくことを願っている。
III−3。テーマ3
奈良県の観光戦略について考えよう
〜観光振興は県最大の課題。皆さんの知恵をお貸し下さい!〜
コーディネーター:鉄田憲男
1.はじめに
前期会議室のテーマであった「奈良の魅力の大発見」の一部を引き継ぐ形で、観光振興に的を絞って意見を募った。このテーマで、6か月間の会議室参加者は33名、会議室での発言数は 398件)、期限(9/30)間際の時刻まで、活発な意見交換ができた。概要は以下の通り。
2.提案
(1)地場産の農畜産物を購入しやすい仕組み作り
旅館・ホテルが、地元食材を使った料理(大和高原野菜会席など)を提供しようとしても、仕入れ(安定供給の確保)が難しい。大和野菜や大和肉鶏を(共同)購入できるような仕組み作りを支援・助言してほしい。
(2)この会議室で出てきた各意見についての県の評価
県民と行政が力を合わせて、新しい観光振興策を作り上げていくべき。出てきたそれぞれの意見については、きちんと県でも評価し回答を示してほしい。
(3)海外論調の把握、外国語ページの充実
海外で奈良がどう報道されているか把握すべき。少なくとも行政側が情報提供したものは、(県の)ホームページ等で開示してほしい。また外国語で発信する(観光情報の)ホームページをもっと充実させてほしい。
(4)道路標識や案内板が不親切、充実した地図やパンフレットも必要
(一見の)観光客や外国人旅行者にとって、奈良の道路標識や案内板は分かりにくいので、改善を望む。商店などが、観光客に周辺の地図やパンフレットを提供できるような支援も必要だ。
(5)奈良観光のモデルコースの設定
県は、今頃になって「観光ルートの提案に乗り出す」というが、感覚がちょっと違う(=新聞に県のコメントが掲載されていた)。(「入込客数」という言葉も変えてほしい。観光客をモノ扱いしているニュアンスがある。)観光モデルコースは、1〜3日コースなどを設定して、奈良について不案内な方でも分かりやすく選択できるようにすべき。
(6)観光3団体の連携が必要
観光情報を一元化して強力に発信するため、3団体の一層の連携(または一体化)が必要。
(6/23の奈良交通・坂本相談役の講演でも「同趣旨の団体が3つあるのは不効率」と指摘。)
(7)知事公舎の迎賓館化
荒井知事は「元首級が泊まれるホテルがない」と指摘していた。それなら、優れた立地の知事公舎を迎賓館に改装し、利用しては。
(8)奈良「ランドオペレーター」構想
ランドオペレーターとは、他府県や海外の旅行社などに対し、地元の観光素材を提供したり、ツアーや観光コースを企画・提案する人(または団体)で、奈良にはいない。少なくとも観光情報を受発信する結節点が必要(ネット上の旅行代理店にならい、インターネットを使って情報を発受信するのも良い)。大学やNPOなどの中立的な立場の所が中心になって、この構想進めてほしい。
(9)バーチャル・リアリティによる平城宮跡の復原(幻視)
手軽なバーチャル・リアリティ装置を用いて、過去の平城宮を体験できるような仕掛けを。これだと遺構を壊さず、巨費も投じなくて済む。
(10)県庁の移転と跡地のホテルへの転用
大和郡山(JRと近鉄線の交差点付近)や八木に県庁を移転し、現在地には世界的な高級ホテルの誘致を(奈良市が誘致したマリオットホテルは、高級ホテルではない)。
(11)正倉院展宝物のレプリカ(模造品)展
混雑がひどい正倉院展を補うものとして、レプリカ展の開催を(常設または巡回)。県下の小学校などで巡回開催すれば、地域おこしにもなる。
なおレプリカ展は、過去に朝日新聞社主催で開かれた例がある。
(正倉院展そのものの改善については、前期の電子会議室や、6/23の坂本相談役の講演でも指摘されていた=年2回開催など。しかし宮内庁の許認可が必要なため、実現は極めて困難。)
(12)奈良美観都市宣言
これ以上の景観悪化を食い止めなければならない。県庁に「空間景観プロジェクトチーム」等を設けて検討を。和風建築の促進、電線地中化、郷土・奈良を愛する心も教育してほしい。壁面緑化などに取り組めば、CO2の府県間排出権取引にも使える(県南部にとっても朗報)。
(13)投稿方法の改善
「事前登録」はできたが、意見の書き込みがうまくできなかったという人がいた(手順が分かりにくい、2重のチェック体制が煩わしい)。登録時に電話番号は必須でなくても良いのでは。
コーディネータなしで反映される(待たされない)ような、練習用テーマも設定してほしい。
IDやパスワードは、ブラウザ側の機能で保持してくれれば、以後の投稿が容易になる。
携帯電話からも簡単にアクセスできるようにしてほしい(現状では画像が邪魔する)。
(14)奈良観光振興への提言
奈良に足りないのは大衆性。京都は格調の高いところと大衆的なところの棲み分けが上手い。今井町などは立派だが、「触るな」「入るな」が多すぎて開放感がなく、敷居が高い。
(県のうまいものづくりとも関連するが)古代食とか茶粥など、健康的で素朴な郷土料理が手軽に楽しめるようなPRも重要だ。
奈良にはコンセプトのしっかりした都市計画が必要。奈良は京都と並ぶ日本の宝なのだから、県民・市民の意見だけでなく、もっと広く意見を求めるべき。
女性の視点に立ち「雰囲気で癒されること」、「グルメ」(高野山の精進料理がモデル)、「甘いもの」、「宿坊」(県の助成を受けながら充実)、「体験型プログラム」、「買い物のしやすさ」「観光客満足度のチェックと専門家による分析」、「トイレ問題の解決」、「全面禁煙」などに留意を。
かつて「サイトウ・キネン・フェスティバルを奈良が断った」という愚を繰り返してはいけない。奈良で開催していれば、国際的な知名度はずいぶん違っていた。
(15)B&B(Bed and Breakfast 宿泊と朝食のみの施設)による誘客
若者や海外旅行者(バックパッカー)の来県促進のため、安くて安心して泊まれる宿泊施設(駅の近くが好ましい)が必要。若い時にこのような施設を利用し史跡めぐりをすれば、中高年になった時には再訪し、高級ホテルを利用してくれるようになる(リピーターが獲得できる)。
奈良には民宿も宿坊も少ない。宿泊可能なお寺に依頼して、もっと宿坊を増やそう。
小さい宿ならではの、観光ガイドなどのサービスを提供することも大切。
3.発言の概略(「2.提案」の各番号とは、リンクしていません)
(1)泊まらなければ見られない魅力の発信
・少人数でゆっくり滞在できるプランの提案を(かぎろひ、朝の社寺、ライトアップ、蛍など)
・早朝に奈良公園を散策して、モーニングコーヒーも楽しめるように
・「あそこに泊まりたいから奈良に行く」と思わせる宿泊施設が必要(奈良には民宿も少ない)
・奈良の観光業者には自助努力が欠けている(集客できない責任を、他に転嫁している)
・奈良の菓子屋の話「奈良の土産物には滋賀や三重産が多い。自分は奈良産にこだわる」
・シルク博は、その年だけ観光客が増え、後で大幅に落ち込んだ。これは「役所の仕事」の典型で、「観光分野の公共工事」になり下がっているから。特定の企画会社だけが利益を得ている
・例えば奈良市内の宿泊業者が、大和野菜や大和肉鶏を共同購入し、地場食材の料理の提供を
・(上記については)「大和高原野菜会席」などが考えられるが、なかなか業界が一丸とならないし、キャンセルなどの不確定要因も大きい。農家もリスクを取りたがらないだろう
・外国人には、B&B(Bed and Breakfast
宿泊と朝食のみ)が一番。知人の米国人女性は、能登半島の民宿に行き、「今まで日本で泊まったうちで最高。毎日、日本人と同じ生活体験ができた」
・奈良のホテルは中途半端だし勉強不足、情報が生駒の山を越えていない。観光立県が実現できるかどうかは、「見世物」になれるかどうか。東国原知事の例が参考になる。
・郊外の駅近くに、B&Bの宿泊施設を増やす(近鉄ファミリー公園前、JR長柄、JR柳本、近鉄壷坂山、天理など)。また、割り切って既存ホテルの人手を減らし、簡素化して安くする
・JR東海が東京で大々的に奈良をPRしてくれているが、県も市は協賛金すら出していない
・この会議室に出てきた県民の意見に対し、行政の方たちも一緒に考えていただき、県民・行政が力を合わせて、新しい奈良の観光振興策を作り上げていくべきだと考える
・電子会議室の説明では「県民の身近な関心やニーズを掌握、会議室で生まれた意見や提案を県政の推進に活用」となっていたが、これまでの会議室の各テーマについての県での評価は?
(2)奈良の夜をどうするか
・京都では定期観光バスにも夜のコースがある。夜に開いている施設も多い。奈良でできないか
・奈良の観光では、夜の静けさを売り物にしてほしい。「夜は平城京の昔に戻る」くらいで
・修二会のポスターにしても、「お松明」を出すのは反対。二月堂の雰囲気が伝わり、声明が耳に聞こえてくるようなものを
(3)海外交流のすすめ
・外国人観光客に神社仏閣を見てもらうだけでなく、地域の人との交流の場を作ることで、良い印象を与え、宿泊の機会も増えるのでは
・海外のメディアが奈良に関してどんな報道をしているか、県民が知らなければならない。そのため、少なくとも行政が情報提供したものはホームページで公開するなど情報開示し、また外国語のHPを充実させ、気軽に問い合わせができるシステムを作らねばならない
・「奈良独自の海外文化交流の場」が必要。新たな団体を立ち上げるのは大変なので、既存の団体や機関を有機的に活性化すれば実現できる
・(上記について)良いと思うが、団体には性格(クセ)があり、また役人が出向している団体は、得てして今までの職分以上の仕事をしない傾向がある
(4)地元以外の人をもてなす
・標識や案内表示は、もっとキメ細かく。地元民は気がつかないが、来県者には不親切
・外国人から奈良公園内の標識の苦情を聞いた。地元商店などで簡単な地図が提供できれば重宝
・モノより、一般住民が観光客に接する態度が大切。「もてなしの心」で接しているのか、疑問
・アメリカでは、その土地に全く不案内な人の意見を聞きながら標識を付けていくそうだ
・残念ながら奈良の観光客への対応は、海外や日本の集客できている地域に比べ、かなり遅れて
いる。その基本が、充実した地図及びパンフレットだと思う。
・新聞記事で「観光ルートは観光客が勝手に選べばよい、という姿勢は、今後は通用しない」という県観光課の反省コメントを読んで、いまだに行政ではこの感覚なのかと驚いた
・もてなしのマニュアルはできたが、行政は観光客数を「入込客数」とまるで物扱いしている
・JR奈良駅の観光客の受け入れ姿勢は、国際観光都市の玄関とは思われない。どれだけの観光客が重い荷物を持ってあのホームの階段を昇り降りしたか、リピーターが増えるはずもない
(5)ターゲットは団塊世代
・ (財)社会経済生産性本部『レジャー白書2006』で「団塊の世代が今後10年でしてみたい旅行」
のベストは、名所旧跡・世界遺産の訪問、郷土料理などの食べ歩き、季節の花を訪ねる など
・ヨーロッパ人の日本旅行のターゲットも「奈良・京都」。大阪・神戸ではない
・5日間〜1週間程度、地元の大学や奈良国立博物館、文化財研究所などとタイアップして、学習と観光を兼ねた『奈良学』講座を開講してはどうか。ボランティアガイドとの連携も良い
・昨年の東大寺での谷村新司コンサートには、宿泊して聞きに来た団塊世代がたくさんいた
(6)修学旅行のサポートプラン
・奈良では古代史を受講し、そのあと現場へ。宿泊して古代史の余韻に浸り、翌日はUSJへ
・旅館業者でも、雅楽を聞き和楽器を吹く、奈良の民話を聞く、薬師寺の僧の法話を聞く、など
のプランを作った。やりたくで、どうしてもできなかったのが遺跡発掘
・「奈良の夜は真っ暗」を逆に利用し、歴史を感じる夜間遊歩コースの設定、常設展、夜間コンサートなど、奈良らしい「夜のおもてなし」を積極的に行う
・天理の企業には「奈良の文化と先端技術を同時に体験できる」と多くの修学旅行生が来ている
・数年前の事例では、修学旅行にボランティアガイドを要請すると「事前学習」が始まる。テーマを設定し、その内容と疑問点を、奈良に来る前から学校側とキャッチボールをする。これができる学校とそうでない学校(修学旅行を消化試合ととらえている)で、差が出る
・奈良の旅館は学校に対し、例えば「大仏建立に際し、聖武天皇はこんなことを考えました」「大仏に込められている意味は…」「春日大社が、神と対峙する際にこんな所作をします」というようなご当地ネタをプレゼンテーションし「奈良へ来て下さい、面白いですよ」とPRしている
・薬師寺はよく頑張っている。伽藍担当として4人程度の僧がいる。彼らが現場で、修学旅行生に対して面白く説明し、生徒も聞き入る。夜には旅館・ホテルへ出向いて話もしてくれる。
(7)奈良観光のモデルコース
・1日目:東京から奈良町へ、猿沢池周辺の旅館・ホテルで宿泊。2日目:奈良町から帯解寺を経て柳本・纏向・三輪から長谷寺へ、長谷寺門前泊。3日目:長谷寺・室生寺を見学し帰京
・1日目:近鉄特急で吉野山へ、泊まりは「さこや」か「竹林院」。秋の紅葉時期がねらい目。
2日目:朝から飛鳥、泊まりは橿原神宮。3日目:長谷寺・室生寺から近鉄名古屋経由で帰京
・1日目:西大寺下車で秋篠寺、平城宮跡、法華寺。2日目:JRとバスで柳生の里へ。帰りは徒歩で奈良へ。3日目:浄瑠璃寺、岩船寺。バスでJR加茂駅まで戻り、京都から新幹線。
・仏像の旅
1日目:東寺下車、徒歩で東寺。奈良で東大寺、興福寺を回り市内泊。2日目:法隆寺、岡寺、壺阪寺、橿原神宮泊。3日目:長谷寺・室生寺へ。近鉄特急を乗り継いで名古屋へ
・歩いて巡る天平文化見聞コース:近鉄平城駅から御陵めぐり(神功皇后陵、成務天皇陵、日葉酢媛命陵、称徳天皇陵)、平城宮跡巡り。時間があり健康に自信のある人は古墳巡り(磐之媛命陵、小奈辺陵墓、宇和奈辺陵墓)も。時間的に余裕がない人は、レンタサイクルで
(8)観光戦略(イベント誘致 等)について
・東大寺や平城宮跡や薬師寺など、社寺でのコンサートは幻想的。野外や会館なども併用して
・コンサートは音響設備に大変な経費がかかる大企業の協賛か、1500人程度のお客が必要
・小出力のFM放送局を構えて手持ちのラジオで聞く、携帯電話(ワンセグ)で聞く、ユビキタス端末を使う、など、経費のかからない方法もある。要は工夫次第
・県内の観光案内所は見つけにくい。JR、近鉄奈良駅も駅の中だが、なかなか目につかない
(9)奈良の観光活性化
(※6/23の第6回運営委員会での奈良交通相談役の講演を契機とする意見=講演内容は注記)
・バス停周辺にトイレがないのは、奈良交通の問題であり、奈良の問題ではない
・旧三井ガーデンホテルは奈良交通もメンバー。大型コンベンション誘致をしようと建てたホテ
ルが「小さい」というのなら、開発当初のマーケティングが間違っていたことになる
・奈良観光の振興のためには、観光3団体の連携が必要だし、天下った人の努力も必要
・奈良に関する観光情報はいろんな所からバラバラに出ている。どこかで一元化してほしい
・荒井知事は「元首級が泊まれるホテルがない」と話していたそうだが、(近くに名園もあり)
かつては天皇を迎えたという知事公舎を迎賓館として改装し、宿泊してもらえば良い
・京都市は94年に「平安建都1200年記念
京都国際映画祭」を開催した(東京国際映画祭の第7回目を京都で開催)。河瀬監督のカンヌ映画祭グランプリを記念し、ぜひ奈良で国際映画祭を
(10)平城宮跡の復原
・国営公園化を機に、復原された朱雀門から現在復原建設中の大極殿のラインを、早急に建物などの復原をし、古の奈良の宮の姿を見せていただきたい
・これ以上の建物の復原はやめてほしい。いまの朱雀門も大極殿も、復原というのには疑問が残る。ポータブル型のバーチャル・リアリティ装置を用いて幻視できるようにするのが良い
・復原でできないところをバーチャルで補えば良い。原っぱに大極殿だけぽつんと建つのは寂し
い。門を持ち回廊に囲まれた大極殿院として復原されることで、催しなどに活用できるものだ
・平城京を一望できる建物を建設し、ここから一望する際にバーチャル・リアリティを重ね合わせれば良い。実際の平城京を自分の目で見ながら、当時の構成をIT技術で再現する
・「地下トンネルを通すと地下水位が変化し、木簡に影響を与え破壊する」という説明には、納得がいかない。地下水位云々と木簡の保存は無関係だ
・(奈良市埋蔵文化財センター勤務の方から)平城宮跡にトンネルを掘れば、地下水脈には必ず大きな変化が起きる。変化は必ず悪い変化を含む、予想できず、取り返しのつかないものになる
・県庁の移転は検討の価値あり。現在の位置に県庁を置く必要性は少ない。跡地には、世界的な高級ホテルの誘致などが良い。県庁の移転先は、JR大和路線と近鉄橿原線が交叉する所(大和郡山市)がよい(他の人から提案のあった八木駅近辺では、南過ぎる)
(11)ランドオペレーター構想
・ランドオペレーターとは、地元と旅行社の間に立ち、他府県や海外に対し、地元の観光素材を
提供したり、ツアーや観光コースを企画・提案する人のこと(旅行社に旅行素材を卸売りする人)であり、これは今の奈良に欠けているものを埋める素晴らしい発想だ
・奈良には確かにランドオペレーターが必要。中心にプロのランドオペレーターがいて、観光業者が支援するとともに、行政や大学、NPOなどの民間組織が観光産業と連携しネットワークをつくっていく必要がある。ネットワークの結節点は大学やNPOなどが担う
・現行、観光情報の発受信はバラバラなので、誰も全貌を把握していない。情報の発受信を束ねることが先決。観光情報の「結節点」を作ることがランドオペレーター構想の第一歩となる
・欧米では、ランドオペレーターが海外旅行業界ではトップのカテゴリーだが、日本の場合は大手旅行会社の下請けのように見られがち。その殻を破る可能性を持っているのが、インターネットサイトによる集客である。大手に頼らず、地元を知り尽くしたランドオペレーターの志ある人が集まりITを活用すれば、世界中に情報を発信し、予約を受けることができる。
(12)奈良市によるホテル誘致(=コートヤード バイ マリオット)
・(同ホテルの東京店に泊まったというレポートを受け)これは奈良市長が提言した「高品位・高価格」のホテルではない。個人ならいざ知らず、VIPや来賓・国賓に自信を持って奨める施設ではない。噂で、他所が全部辞退したのでここに決まった、とも聞いた
・高さ40mは、市が再開発促進のために定めた規制緩和の産物だが、古都奈良の玄関口として相応しい選択か、疑問。世界に誇る古都として、もっと景観や美観を大事にしていくべき。
(13)正倉院宝物のレプリカ(復刻・模造品)展
・正倉院展は人気が出すぎてゆっくり見られなくなった。布製品などは傷みも激しい。宝物にはそれ自体芸術品と言えるレプリカ(復刻・模造品)も多いので、これらを集めた「模造品展」(常設または巡回)を開いてほしい。(過去に、朝日新聞社主催で「甦(よみがえ)る正倉院宝物」展が開かれた例あり。)
・県下市町村持ち回りで巡回するのも良い。公民館や地元の小学校などを夏休みの間などに間借りして。地域おこしにもなることだから、小学生も理解して協力してくれる
(14)アジアの人に来てもらおう
・姉妹都市、友好都市とタイアップして、「奈良県デー」フェスティバルを開催し、奈良観光を売
り込む。これら姉妹都市とは、相互に観光誘致イベントを計画する(姉妹都市も増やす)。
・東南アジアの各国では、マスメディアの宣伝費用は日本ほど高くないと思われるので、テレビや新聞を介して奈良観光の宣伝をかける
・奈良単独での誘客活動に加え、関西の各県・都市・地域と共同で、観光客誘致をする。関西周遊プログラムを組み、優待サービスも加える
(15)奈良美観都市宣言
・「奈良美観都市宣言」で、強いコミットメントを内外に示すべき。百年の計で、奈良の空間景観をどうすれば日本一にできるか、県庁に「空間景観プロジェクト」を立ち上げて検討を
・近鉄奈良駅前の再開発(近鉄ビルは景観上のネック)、JR奈良駅周辺の混沌とした景観の見直し、住宅街での和風建築(外観)の促進、街路樹整備・電線地下化の促進、奈良を愛する教育を
・地域間CO2取引(排出権取引)を提案したい。壁面緑化などに積極的に取り組み、この分を
大阪などに公債のような形で買い取ってもらい、そのお金を自転車道整備、バスの利用促進(100円均一など)・鉄道立体化に回す。森林資源に恵まれる県南部にとっては良い取引になる。
(16)観光産業(ホテル、商業施設 等)の誘致
・中南和の中心である橿原ロイヤルホテルでも客室数は200室程度。JR奈良駅、近鉄奈良駅、近鉄西大寺駅、近鉄八木駅、JR法隆寺駅周辺等にホテルや商業施設の誘致を図り、観光振興を。
・JR奈良駅前にはJR西日本、近鉄奈良駅前には近鉄がホテルの建設を表明、このままでは奈良が「コンクリートジャングル化」するおそれがある。これ以上の誘致・建設はやめるべき。
・奈良観光=奈良市だけではない。中南和も含め、奈良県全体の観光PRに注力する必要がある
(17)投稿方法の改善
・(登録確認のメールが届けば良いのだから)電話番号は必須でなくても良い。
・事前登録は済んだが、投稿がうまくできなかったという人がいた。
・コーディネータなしですぐに反映されるような、練習用のテーマもあったほうが良い。
・IDやパスワードは、ブラウザ側の機能で保持してくれれば、以後の投稿が容易になる。
・携帯電話からも簡単にアクセスできるようにしてほしい。
(18)奈良観光振興への提言
・基本的なビジョンが見えず、何かにつけて後手に回るという奈良の通弊を感じる。
・酷暑の今夏、奈良・飛鳥には閑古鳥が鳴いていたが、京都は大勢の人々で賑わっていた。奈良に足りないのは大衆性。京都は格調の高いところ、大衆的でいいところの棲み分けが上手く出来ている。奈良は一般の人々には大衆的な魅力の薄い退屈な街になっている。
・京都では建築や広告看板を制約するため、何十か所かポイントを明確にした。
・今井町は立派だが、「触るな」「入るな」が多すぎて開放感がなく、敷居を高く感じる。
・古代食とか茶粥などの健康的で素朴な郷土料理が手軽に楽しめるようなPRも重要。
・奈良にはコンセプトのしっかりした都市計画が必要。奈良は京都と並ぶ日本の宝なのだから、県民・市民の意見だけでなく、もっと広く意見を求めることも大切。
・女性の視点に立って、どれだけ魅力的であるかが重要。ポイントは「雰囲気で癒されること」、「グルメ」(高野山の精進料理がモデル)、「甘いもの」、「宿坊」(県の助成を受けながら充実)、「体験型プログラム」、「買い物のしやすさ」「観光客満足度のチェックと専門家による分析」、「トイレ問題の解決」、「全面禁煙」。毎年必ずLOHASな奈良に癒されに行きたい、と女性達に思わせ、男性を引っ張ってきてくれる位の独自競争力がないと、奈良の観光は衰退する。
・かつて「サイトウ・キネン・フェスティバル」を奈良が断ったのはとても残念。受け入れていれば、国際的な知名度はずい分上がっていただろう。
(19)B&B(Bed and Breakfast 宿泊と朝食のみの施設)で誘客
・若者や海外旅行者(バックパッカー)の来県促進のため、安くて安心して泊まれる宿泊施設(駅の近く)が必要。大阪西成区(2,600円)や京都駅近く(2,500円)にはある。若い時にこのような施設を利用し史跡めぐりをすれば、中高年になった時には再訪し、高級ホテルを利用してくれるようになる(リピーターが獲得できる)。
・日吉館は廃業したし、もともと奈良には民宿も宿坊も少ない。宿泊可能なお寺に依頼して、もっと宿坊を増やそう。
・かつてはYH(ユースホステル)を使った旅行が盛んだったが、最近はペアレント(マネージャー)の高齢化などで廃業するYHも多い(しかし、ニーズはある)。小さい宿ならではの観光案内などのサービスを提供することは大切。
※注:第6回運営委員会における講演要旨
(6/23開催 演題:奈良の観光活性化 講師:奈良交通(株)取締役相談役 坂本成彦氏)
[宿泊施設]
・県下のホテルは、最大のホテル日航奈良でも330室、橿原ロイヤルホテルが205室と規模が
小さく、コンベンションが誘致できない
・日本では1泊2食の固定価格がほとんどなので、割高感がある。欧米のシティホテルやコンド
ミニアムのように、外食と同様の価格帯で食事が提供できるようになれば、宿泊客は増える
[交通体系]
・市民病院に行こうとしても、渋滞で動けない。ターミナルの整備やマイカー規制などの対策が
必要。かつてロンドンでは5ポンド(当時で千円)払わないと市内に入れなかった
[官民の観光事業への取り組み]
・私は常々「正倉院展を年2回開け」と提唱している
・金沢には芸妓さんがたくさんいる。花代は自治体が負担している。奈良も学ぶべきだ
・奈良には観光振興の団体が3つもあり(県観光連盟、市観光協会、コンベンションビューロー)、不効率
[美しい街並みづくり]
・欧米の町には市民広場がある。きれいに整備され花が咲いていて、誰でも写真を撮りたくなる
・奈良には公衆トイレが少ない。通りの名称が分かりにくく標識もない。電柱も目障り
[旅行商品の企画]
・オリジナリティのある旅行商品が必要。奈良交通では、修学旅行の再現ツアーを企画している。
4.おわりに
抽象的、イメージ的な意見でなく、具体的な提案・提言を求めるように努めた。
投稿者の中には、文化財保護に携わる人(奈良市埋蔵文化財センター勤務)や旅館経営者がおられ、また県外の有識者からも意見をいただいたことで議論が深まり、地に足の着いた意見交換ができたと自負している。
県にとっては耳の痛い意見も多いと思うが、背後には投稿者の愛郷心・奈良を愛する心が感じられるものばかりである。これら提案を決して無駄にすることなく、十分検討し、県の施策に反映していただきたいと願う(「きちんと県で評価を示してほしい」との意見があった)。
なお事務的なことであるが、6か月通しての「まとめ」というのは負担が大きいので、3か月目で一旦区切りを設けた方が(テーマは共通だが、前半と後半で話題を一旦切り離す)、まとめやすいし、読んでいただきやすいと思う。ネット上でも何らかの区分ができれば有り難い。
「事前登録」「コーディネーターによるチェック」という2重チェック体制の見直しも、下期の検討事項であると思われる。
今後の課題としては、引き続きこの会議室の県民への周知に努めるとともに、会議室の運営委員、県の担当部署職員、観光や文化に実際に携わっておられる外部の専門家にも閲覧・投稿をお薦めし、実りある議論ができるような素地を作り上げることが重要であると思う。
IV.登録・投稿・アクセス集計
(1)電子会議室アクセス数(2006/11/1〜2007/9/30)
| ホームページ | 19/テーマ1 | 19/テーマ2 | 19/テーマ3 | |
| 2007/04後半 | 4141 | 860 | 691 | 1392 |
| 2007/05前半 | 2816 | 671 | 444 | 1022 | 2007/05後半 | 2466 | 774 | 443 | 991 |
| 2007/06前半 | 1948 | 577 | 316 | 854 |
| 2007/06後半 | 1498 | 507 | 479 | 735 |
| 2007/07前半 | 1397 | 503 | 368 | 721 |
| 2007/07後半 | 1900 | 770 | 646 | 961 |
| 2007/08前半 | 1883 | 498 | 564 | 877 |
| 2007/08後半 | 1388 | 400 | 338 | 605 |
| 2007/09前半 | 1500 | 522 | 368 | 698 |
| 2007/09後半 | 1755 | 585 | 519 | 1123 |
| 合計 | 22672 | 6667 | 5176 | 9979 |
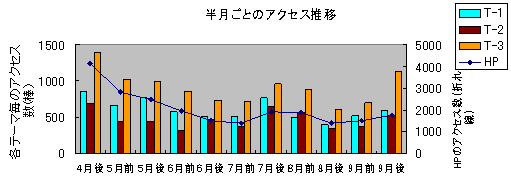
(2)月別登録者数(4/13-9/30)
|
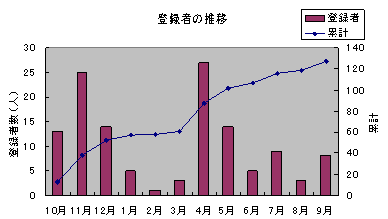 |
(3)半月別投稿数
| 年月 | 19上/T1 | 19上/T2 | 19上/T3 | 合計 |
| 2007/04後半 | 18 | 47 | 94 | 159 |
| 2007/05前半 | 14 | 24 | 36 | 74 |
| 2007/05後半 | 13 | 2 | 21 | 36 |
| 2007/06前半 | 12 | 10 | 31 | 53 |
| 2007/06後半 | 3 | 30 | 18 | 51 |
| 2007/07前半 | 10 | 20 | 36 | 66 |
| 2007/07後半 | 18 | 62 | 45 | 125 |
| 2007/08前半 | 8 | 69 | 24 | 101 |
| 2007/08後半 | 7 | 20 | 15 | 42 |
| 2007/09前半 | 12 | 27 | 25 | 64 |
| 2007/09後半 | 9 | 49 | 53 | 111 |
| 合計 | 124 | 360 | 398 | 882 |
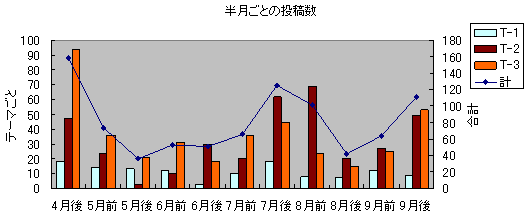
V.まとめ
今期の投稿には、内容の濃い充実した内容で、専門知識や情報を持った実務に明るい議論が多かった。団塊の世代の定年後の話題も増えて、電子会議室においてもシニアー世代の投稿者が多かったものと思われる。インターネット上のやりとりが進むにつれて、バーチャルな出会いや交流から、いままで、疎遠だった地域活動にどのように参加したらよいかとまどいも見受けられる。教育支援など地域活動への期待は強くなってきている。これらの動機を引き付ける吸引力が必要になる。それは、県民の目線にあった施策にある。
6ヶ月間における電子会議室のアクセス・投稿状況は、アクセス数(トップ頁)が22,672件、登録者数が127名(累計)、投稿者数が53名、投稿件数が882件(平均147件/月)であった。内容の濃い議論ができ、評価のできる内容であったと思われる。内容としては、真面目な投稿ばかりで、テーマ1では、5項目、テーマ2では、5項目、テーマ3では、15項目にまとめて提案することができた。しかし、広報活動や、運営の方法はどうであったか等を総括して、更に、よりより電子会議室にするためには、いくつかの課題を解決する施策が必要である。特に、アクセス数を増やす施策、登録・投稿者を増やす施策が必要である。
1.課題
(1)アクセス数を増やす施策、登録者数、投稿数を増やす施策、運営方法。
(2)広報活動の強化:電子媒体/紙媒体、口コミ
(3)運営方法の研究:投稿しやすい仕組み、ルール
2.県への要望
(1)県職員の参加について
議論していることについて、制約のある範囲内で議論に参加することが望まれる。
(2)広報活動について
「なら県民電子会議室」は、まだまだ、県民に知られていない。電子媒体/紙媒体を利用して、広報に努めているが認知度は低い。関係部門の広報支援をお願いしたい。
(3)県の政策への反映
投稿者からは、提案に対する県の取り組みについて、強い関心を持っている。その期待があるからこそ、投稿を続けている。電子会議室を継続させるには、提案に対する県の前向きな取り組み姿勢が望まれる。
■ 19年度上期「電子会議室」キックオフ大会(第5回運営会議)(平成19年4月13日)
■ 会場:中小企業会館 中会議室

委員長ご挨拶

出席者

