
�ޗnj��������m�������L��E�L���ہ@�l
�P�X�N�x�����u�Ȃ猧���d�q��c���v�̕�
�`�����ɂ��Č������m�ł̈ӌ������`
�Q�O�O�W�N�x�S���X��
NPO�@�l�d�q�����̃A�h�o�C�U�[�N���u
�������@���ƍF�F
�y�ځ@���z
I�D �͂��߂�
II�D ��
III�D�d�q��c���̕�
�@�@III-1 (�e�[�}�P) �F�X�g�b�v���g�����l����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�ƒ�E�n�悩�牷�g���h�~�̎��g�݂��L���悤�`
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�[�f�B�l�[�^�[�F�V���`
�@�@III-2 (�e�[�}�Q) �F���E�ɊJ���ꂽ�ޗǂÂ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�C�O�ւ̓ޗǂ̏�M��O���l�ό��q�̗U�v�Ȃǁ`
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�[�f�B�l�[�^�[�F�吼�@�O
�@�@III-3�i�e�[�}�R�j�F�݂�Ȃŋ���ɂ��Č�낤
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�q�ǂ�����Ă邽�߂̉ƒ�E�w�Z�E�n��̋����`
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�[�f�B�l�[�^�[�F�O���V
IV�D�L���A�o�^�E���e�E�A�N�Z�X�W�v
V�D �܂Ƃ�
�y�Y�t�����z
I�D�͂��߂�
�i�P�j�ړI
�@���̓d�q��c���́A�C���^�[�l�b�g�����p���Č������m�������ɂ��ĕ��L���c�_�ł�������邱�Ƃɂ��A�����̌����Ɋւ��闝���ƊS�����߂邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B
�i�Q�j�d�q��c���Ɋ��҂������
�C���^�[�l�b�g������Z�p�ƃT�[�r�X�̐i���������Ă���B�l�b�g��̍s��������ʒu����g�ݍ��킹���L���z�M�͌��ʓI�ȃ}�[�P�e�B���O��@�Ƃ��ċr���𗁂тĂ���B06�N�ɍ����̃l�b�g�L����́A3630���~�ƌ����Ă���B�e���r�A�V���A�G���ɕ��ׂ��4�̔}�̂ɐ��������B�L���������܂߂��3�{���x�ɂȂ�A�G�������ɒ������Ƃ����̂��ƊE�̏펯�ƂȂ��Ă���B�߂������A�V���Ɠ������̈꒛�~�K�͂ɒB����B��U���~�Ƃ��������L���s��̓l�b�g�̑䓪�Ō��������D��̑ΏۂɂȂ��Ă���r�W�l�X���琭���܂ŎЉ�̉c�݁A����ɂ́A�����I�Ȃ��̂܂ŁA���̖{���I�ȕ����Łu����v���Ă���B�u���̃f�W�^�����v�ɂ���āA�L�^�E�`���E�~�ς��e�Ղɂł���悤�ɂȂ�A���͗��Ȃ��Ȃ����B���̗͂��A�ߔN��IT�i���ʐM�Z�p�j�̐i���̎��A�ω��ޗ̖͂{���ł���B�����āA���̗͂́A����̎Љ�̉c�݂̂��܂��܂Ȍ`���E�K���E�@���Ȃǂ̕����I����A�g�͉����A�s���͂��������ɑς��Ă������߂ɁA�V�������݂����߂��Ă���B21���I�ɂȂ茰���ɂȂ��Ă���B
���l�ȏ��{�I�ɂ͋��L�́u�f�[�^�x�[�X�v�Ƃ��Ĉ�����悤�ɂȂ�A���̌��ʂ͏���̋ɒ[�ȃR�X�g�_�E���ɂȂ�B���̏��̎�ނɔ���ꂸ�ɒN�ł���������̂��A�R���s���[�^�[�ł���A�v���O�����Ƃ��������̎菇���������A�u���E�U�[�i�C���^�[�l�b�g�{���\�t�g�j�ł���B�u���E�U�[�́A�Z���̑��l�������ӌ����ꗗ�ł���ƂƂ��ɁA�Θb���邱�Ƃ��ł���L���Ȏ�i�ł���B�s���́A���̎�i��L�����p���ׂ��A�V�����g�����߂Ă��܂���Ă���A�V�����K�i�̐،����K�v�ɂȂ�B�ޗnj��ł́A�p�\�R���̕��y���͑S��3�ʁi����07�N�Łj�A�C���^�[�l�b�g�l�����y���͑S��1�ʁA�g�ѓd�b�_�l����͑S��17�ʁi������04�N�Łj�ł���A��ɂ�����ޗnj����̊S�͍����ƌ�����B�n��SNS��u���O���̊g��ɂ��A�C���^�[�l�b�g�𗘗p���Đ����̋��X�܂ōL����V�����T�[�r�X�A���l�̑n�����n�܂��Ă���B
�d�q��c���́A�C���^�[�l�b�g�̃z�[���y�[�W��ɐݒu�����d�q�f�����g���āA�Q���҂����R�Ɉӌ����q�ׁA�c�_�ɎQ���ł��邽�߁A�Q���ғ��m���邢�͎Q���҂ƌ��E�����n��̉ۑ�ɂ��Ĉꏏ�ɍl���Ă����V���Ȍ����Q��̏�Ƃ��āA�L�������̈ӌ����W��L���Ȏ�i�ɂȂ��Ă���B�d�q��c���̓����́A�u���l���v��F�ߍ������Ƃł���B������o���̈قȂ�l���A���R�ɑΘb���邱�Ƃɂ��C�t�����Ƃ�����B�d�q��c���ւ̃A�N�Z�X�E���e�𑝂₷�{�K�v�ł���A���l�����x����s�f�̊v�V�������̌��ƌ�����B
19�N�x�����́A3�̃e�[�}�ɂ��āA6�����ɘj���āA�c�_��i�߂Ă����B�e�d�q��c���ŁA�c�_���ꂽ���e����܂Ƃ߂������L����B�ޗǂ��悭�������A�����̏Z��ł���n���ǂ��������A�Ǝv�����l�������W�܂��ċc�_�������e�ł���A������n�抈���ɐ������Ă���������K���ł���B
II�D��
�e�d�q��c���ł܂Ƃ߂��u��āv�̍��ڂ�Ƃ��č��ڂ̂݉��L����B�ڂ����́A��L����e�d�q��c���̕����Q�Ƃ������������B
�P�D�e�[�}�P�F�u�X�g�b�v���g�����l����v
�@�@�@�`�ƒ�E�n�悩�牷�g���h�~�̎��g�݂��L���悤�`
�@�@1)�u���]�Ԃ̒��A�G�R�ޗǣ�̎���
�@�@2)�@�܂邲�ƈ���}�C�J�[���g��Ȃ���
�@�@3)�@����͊X�Â��肩��
�@�@4)�@�ȃG�l���C�g�A�b�v�Ǝ��R�G�l���M�[���̓���
�@�@5)�@�r�o�ʎ���̓ޗǃX�^���_�[�h���I
�@�@6)�@�ޗnj��͒n�����g���ւ̋������b�Z�[�W��
�Q�D�e�[�}�Q�F�u���E�ɊJ���ꂽ�ޗǂÂ���v
�@�@�@�`�C�O�ւ̓ޗǂ̏�M��O���l�ό��q�̗U�v�Ȃǁ`
�i�P�j�C�O�ւ̓ޗǂ̏�M
�@�@1)�@���ۑ����ޗNJw�����Z���^�[�v�̐ݒu��
�@�@2)�@�O���̃��f�B�A�̏��҂���
�@�@3)�@�ޗnj����̃z�[���y�[�W�O����ł̉��P���
�i�Q�j���ی𗬂̐ϋɓI���i
�@�@1)�@�ޗǂɐV�������ی𗬂̕���
�@�@2)�@�z�[���X�e�C�̊���
�@�@3)�@����҂̍��ی�
�i�R�j�O���l�ό��q�̗U�v
�@�@1)�@�ߍx�s�s�Ƃ̘A�g�ɂ��V���Ȋό��J��
�@�@2)�@���l�Ȋό��v���O�����̊J����
�@�@3)�@�_�Ɗό��i�A�O���c�[���X���j�̒��
�@�@4)�@�L�\�ȊO����K�C�h�̗{��
�R�D�e�[�}�R�F�݂�Ȃŋ���ɂ��Č�낤
�@�@�@�`�q�ǂ�����Ă邽�߂̉ƒ�E�w�Z�E�n��̋����`
�@�@1)�@�w�Z�x���n��{���ݒu�̎��g�ݏ���ϋɓI�Ɍ��J����B
�@�@2)�@PTA��w�Z�Ɍ������w�Z�x���n��{���̐ݒu���C����s���B
�@�@3)�@�n�抈��������v���O�����ɂ���
�@�@4)�@���F����ޗǂ̋������邽�߂̐��E�I�ȃl�b�g���[�N�����
III�D�d�q��c���̕�
III�|�e�[�}�P
�u�X�g�b�v���g�����l����v
�`�ƒ�E�n�悩�牷�g���h�~�̎�g���L���悤�`
�R�[�f�B�l�[�^�[�F�V���`
�P�D �͂��߂�
�@���܂��ɐg�߂Ő[���Ȗ��ƂȂ��Ă��Ă���n�����g���ɂ��āA�ޗǂ̌���c�����珫���̂���ׂ��p�A�����Ď������͂ǂ����ׂ����A�ǂ����������A���ɂ��āA�܂��͋C�y�ȋC�����ŃX�^�[�g���A�ƒ��n��ł̗l�X�Ȏ��g�݁A�����đ����̈ӌ����Ă����B6�����Ԃɂ�����{�e�[�}��c���ւ̎Q���҂�25���A��������177���ł������B
�Q�D ���
�@��c���ł̑��l�Ȕ����̒��ŁA������ʓI�����͒��ۓI�Ȉӌ���v�]�͏����A�͂����薾�L���ꂽ��āA�y�ы�̐��������ĂƂȂ肤��ӌ��𒊏o���A�ȉ��ɂ܂Ƃ߂��B
�P�j �u���]�Ԃ̒��A�G�R�ޗǣ�̎���
�@���ΔR�����g��Ȃ��ړ���i�ōł��D�G�Ȃ��͎̂��]�Ԃł��B�u�T�C�N�����O�V�e�B�@�G�R�ޗǁv�䂽��̂�т�ό����L���b�`�R�s�[�Ƃ��āA�ȉ���̒�Ă��܂��B
(1)���]�ԓ��̐����A�y�ь�����ʋ@�ցi�d�ԁE�o�X�j�Ɏ��]�Ԑ�p�ԗ������A���]�Ԃ����̂܂ܐςݍ���ŏ���悤�ɂ���B�i�T�C�N���g���[�����o�X�j
(2)�ޗnj����Ɂu�T�C�N�����O���[�h�P�O�O�v�I�肵�Ď��]�ԓ��H�⒓�֏�����ăA�s�[���B
(3)��������̉w�܂ł̒ʋ�H��Ζ����\�Ȑl�͌��N���i�����˂ăT�C�N�����O�ʋɂ���B
(4)���ꂳ����X�[�p�[�ւ̔������͎��]�Ԃł���B
(5)�����{�݁A�H��A�w�̒��ԏ�X�y�[�X�𒓗֏�X�y�[�X�ɕύX����B
(6)�ޗǂɂ͔����������X�g���������Ȃ��ƌ����Ă��邪�A�x�O�̃��X�g�������Ȃ����ɂ��_������̓ޗNJό����Ăł���B
(7)���s�`�ޗǁ`�g��`�F��܂ł̃T�C�N�����O�c�A�[���[�X���@��悷��B
(8)�܂����]�ԓ��ɂ͑��z�d�r����ׂāA���̓d�C����ʉƒ�ɋ����B���E�ň�ԑ��z�d�r�Y���Ă���ޗnj��́A���]�ԂƑ��z�d�r�̒��Ŕ���o���܂��傤�B
�@����ɂ��ό��q�����ɂ��Ȃ���A���⌒�N�ʂ���́A�����K�\�������g�킸��CO2�팸�ɑ傫���v�����A���H�̏a���啝�Ɋɘa����B�܂��l�I�ɂ͌��N���i�ɂ��Ȃ���܂��B
�Q�j �u�܂邲�ƈ���}�C�J�[���g��Ȃ����v
���S�̂ł͖����ł��A�s�������x���ŁA�y���j�ȂǂɁu�܂邲�ƈ���}�C�J�[���g��Ȃ����v�����߂Ď��s���{����B�n�����X�X�̊������ɂ��Ȃ��āA��ΓB�@�Ȃ������Ɍ�����ʋ@�ւ̗��p���i��}�邽�߁A�ȉ��̃V�X�e���⊄��������B
(1)��������̓p�X���iSIICA��PITAPA���j�̒��Ȃ���A��Ƃ͒ʋΔ���x�����Ă͂����Ȃ��ƌ�����ᓙ�����A�ʋΎ҂͑S���A��ʗA����i�̓d�Ԃ�o�X���͎��]�Ԃ𗘗p����B
(2)�܂����]�ԒʋΎ҂ɂ͏�����������B
(3)��ʎ��Ǝ҂́AIC�J�[�h�����p�҂ɂ͊�������������œK�p����B�Ⴆ��A�j�אڂ����w�ǂ����̏�芷���̕X�Ƃ��āA�R�O���ȓ��ł���Βʂ������ŗ��p�ł���悤�ɂ���(����藿�������d�ɉۋ��p�~�j�B���R��Ԃ����p���������A�R��Ԗڂ̘H���̉^�����������铙�B
�R�j����͊X�Â��肩��
��&�i�Ϗd���̓ޗǂƂ��ēޗǃu�����h���l�����グ��ׂ��ŁA�X�Â���ł����Ɋ��t�����h���[�Ȏd�g�݂��\�z���Ă���������ł��B
(1) �p�[�N&���C�h���i�̂��߁A�ߑO�X�F�R�O�`�[���T���܂ł́A�o��H�̍��������وȓ��̓���
���s�ғV���ɁA���̓o�X��w��ԈȊO�͏�����֎~�ɂ���B��{�I�ɂ͓ޗnj������ӂ́A���s�҂ƌ�����ʂ�D�悵����g�����W�b�g���[����Ƃ��A�܂����]�ԓ������A�T�C�N�����g���C���y�уo�X����������B
(2)JR���ȓ��ւ̎Ԃ̏�����𐧌����邽�߁A���ԏ��Ɂu���������͋��v����悹����B
(3)�r�M����(����)�Ŕ��ɖ��̂��鍂�w���z�ɑ��Ă͋K���������Ă����B
(4)�ޗǒ��ɑ�\�����̂Ȃ���̋�C���C�d���̖ؑ����{�Ɖ��́A�G�R�Œ������B�����̐X�є��̂��T�C�N���Ƃ��čs���A�����e��}��A�؍ޗ��p�̌������ɂ��Ă͌�����⏕���s���A��X�̃T�C�N���Ƃ̋�����}��Ȃ���G�R�I�ȊX�Â���A�ƂÂ���œޗǂ炵���i�ςɌ����������{����u���Ă����ׂ��B
�S�j�ȃG�l���C�g�A�b�v�Ǝ��R�G�l���M�[���̓���
�@�����������ł�����ł����C�g�A�b�v���߂��ł���B�܂��͑Ό��ʂ��\���������A���Ԍ����G�ߌ���̃��C�g�A�b�v�������A�ߏ�ȃ��C�g�A�b�v�͋֎~�Ƃ���B�܂����{����ꍇ�͈ȉ����`���Â����i�ł���Ύ��R�G�l���M�[�̗p�������ȏ�ȂNjK��j���𐧒肷��B
(1)�ȃG�l�u������LED�����̏ȃG�l���ϋɓI�Ɏ����ꂽ���C�g�A�b�v�̎��{�B
(2)���z�����d�����R�G�l���M�[�̓����A�����̓O���[���d�͂̍w����J�[�{���I�t�Z�b�g�̊��p�B�@�ޗǂ̃��C�g�A�b�v�́A���R�̃G�l���M�[�Řd���Ă��܂��ƃA�s�[�����鎖�ɂ��A�ό��q�����ɂ��Ȃ���ƍl����B
�T�j�r�o�ʎ���̓ޗǃX�^���_�[�h���I
�@���͂␢�E�̒����́A���Ԃ̖��Ŕr�o�ʎ���̓��������i�ނƎv����B���̌����ł��A�g�s���{���̊Ԃł̔r�o������͌��݂̂Ƃ��댟������Ă��Ȃ��A�܂������̊Ԃł̔r�o��������x�����{���Ă��鍑�͖����Ǝv����g�Ƃ���Ă��邪�A���łɢ�V�h�E�ɓ߃��f��������o�����Ă���A�ނ���ޗnj������[�_�[�V�b�v���Ƃ��āA���ʓI�ȃX�^���_�[�h�������Ă��܂����Ƃ��d�v�œ���ł��B�@�܂��͑��}�ɑ��l�ȃ����o�[�ɂ�錟���ψ���𗧂��グ�A�����ɐ�삯�����`���{���邱�Ƃ��Ă��܂��B
�U�j�ޗnj��͒n�����g���ւ̋������b�Z�[�W�������Ăق���
�@�X�g�b�v���g���ł����ޗnj��Ȃ�ł͂̋������b�Z�[�W���o���ׂ��ŁA�ȉ��̂R�_���Z�b�g�ɂ���Ȃǃ��j�[�N�Ȋ��{����l����ׂ��ł���B
(1)����J�s�P�R�O�O�N�ƒn�����g���h�~�����т���B
(2)�ޗnj��̐X�т��~�����ߒn�����g���h�~�ƌ��т����A�ޗnj��I�����[�����̎{����l����B
(3)��҂ɓޗnj��ɂ��Ă��炤�ׂɐ_�Е��t�͏������ɂ����āA�T�C�N�����O�A�O���[���c�[���Y���A�X�ї��A��V�сA�G�R�̕��@�Ȃǎ�҂����g�߂�n�����g���h�~�������l����B
�R�D �����̊T��
�@�ꉞ���m�点���ɢ�b�̐i�ߕ�����ȒP�Ɏ����X�^�[�g�������A����ɂ͑S���W�Ȃ��c�_�͓W�J�B�J�n�����͓���10�����x������������A���ꂵ���ߖ��グ�������ɓ��ɏ��Ȃ��Ȃ�A�Q���o�^�҂̑��������Ȃ��A�K�X�R�[�f�B�l�[�^�[������̔����i�U���j���s�����͕s���ŁA���ɏI�Ղ͋c�_���o�s��������������ɂ߂Ēᒲ�ƂȂ����B����܂ł̔����̊T�v���ȉ��ɂ܂Ƃ߂�B
�i�P�j�n�����g���̉e��
�E�O���[�o���ɂ́A�k�ɂ��ɋy�уO���[�������h�̕X���n���Ă��܂��B�X�̗Z����C�����x�̏㏸���ɂ��C�ʏ㏸�A���剻����n���P�[����䕗�॥��B�X�͂▜�N�Ⴊ�Ȃ��Ȃ�ƁA���z���̔��˗����ቺ���āA���g�����������܂��B�G�x���X�g�̕X�͂������ĎR�ԕ��Ɍ����X�ƒa���i�X�͌j�A���đ�^�����N�����댯�������債�Ă���A�ȂǁB
�E�g�߂ȓޗnj��ł́A�̂ɔ�ׂĒg�����Ȃ����B�R�O�������x�Ⴊ�ς�������A�P�����̕X������悤�ȓ~�̓��͂܂��͂Ȃ��Ȃ����B�Ԃ̍炭�̂������Ȃ�A�p���W�[�⒩��͂��܂ł����Ă��炢�Ă���B�ƒ�؉��̃S�[���͂P�O���ɂȂ��Ă��̂��B�ŋ߂̑䕗�͂V���A�W���A�X���̌o�H���̂ɔ�ׂĂ�����ƈႤ�悤�Ɋ�����B11���������ł����߂��̐_�Ђ̍��̖ɁA���̉Ԃ�5�قǍ炢�Ă���B�����_�{�ߕӂł��������͂܂������~��Ă��Ȃ��B�ޗnj����̍g�t���N�X�x���Ȃ��Ă��āA���ɍ��N�̍g�t�͉Ă̖ҏ��̂����ő啝�ɒx��܂����B�܂����N�̂P���ɂ́A�g�~�̂����ŕ���{�Ջ߂��̒r�ŏ��u�i����ʔ����B���������������ُ�ɑ����ĖؒÐ�̐������������Ă���B��̂䂫���̉Ԃ��炫�n�߂܂����B���ɁA���~�A�Ă�����̉Ԃ��炫�n�߂܂����B���������͌�˂̒r�ɕX�������āA�X�ʂ�����������ł����A�ŋ߂͓��邱�Ƃ͂܂�����܂���B���X�@����ȂƂ��ɂ��C��ϓ��̉e�����o�Ă��n�߂Ă���悤�ł��B���ꂩ�炷��ƔM��or���M�ђn���́h�����ǁh�Ȃ�Ă̂���茻������ттĂ��܂��B
�i�Q�j�X�g�b�v���g���ւ̓ޗnj����ӎ�
�E��ISO�iISO14001�j�̔F�؎擾�Ō���A�S�����ς�肩�Ȃ�Ⴍ�x��Ă���Ƃ����܂��B�����ڕW�ݒ肵���̂��x���ł����A�債���{����o�Ă��܂���B
�E���܂�ؔ������Ȃ��̂��A�ޗǂł͊��ۑS�̉^��������オ�炸�A�ƂĂ��c�O�ł��B
�E�����ōs���Ղ�₻�̑��s���ł̃S�~�̂āA�����̋z���k�����������ɗ����Ă܂��B�H��ł̃S�~������A�����e�łٓ̕��̋�S�~�̎R�ȂǁA�ޗnj��l�Ƃ��āA�ƂĂ��p���������v���B
�E�̌��Q�̒��A�k��B�s����s�͍������i�s�s�ɕϖe�B���R�͈ꌾ�A���Q�ŋꂵ�o���B�ΖL���Œɂ݂��o�����Ă��Ȃ��ޗǂł́A���̂悤�Ȕ��z�͏o�Ă��Ȃ��̂ł��傤������B
�E��^�V���b�s���O�Z���^�[���������ԏ�Œ����ԃN�[���[�������ăA�C�h�����O���Ă���Ԃ��悭�������܂��B�g�߂ŏo���鉷�g���h�~�̌[���������܂��܂��s�\���B
�E�ω��������邻�̈ӎ����Ȃ���Ή��������Ȃ��A�C�Â����Ƃ��͎�x�ꂾ��������B����鎞�_����߂���Ɩ߂�Ȃ��|�C���g��I�u��m�[���^�[���́A��C���^�[�Q�b�g���Q���Ƃ���Σ����10�N�ȓ��ł���B�{���ɂ��̎l�G�܁X�������ޗǂ̎��R����X�͂��܂Ō����̂ł��傤���B
�i�R�j�X�g�b�v���g���Ɋ֘A���ޗnj��������Ɍւ�����
�E���R�ł����ƁA�X�тƋ�C�Ɛ������ł��傤���B�X�����o���V�N�ȋ�C�Ƃ��ꂢ�Ȑ��́A�����ɂ��ウ��f���炵�����̂ł��B�܂��l�H���ł����܂��ƁA�䏊�s�̑��z�����d��A�씗�쑺�̕��͔��d������ɊY������ł��傤�B
�E�ޗǂƌ����Η��j�I��Y�̎��@���t�Ƃ��V����B�����̏@���Ɓi���V�����_�傳��j���W�܂��āA�u�ޗǃG�R�錾�v�̂悤�Ȓ�����A�傫�ȃC���p�N�g������܂��B
�i�S�j�d�_����Ƒ�ɂ���
�P�j�S�~
�E�S�~�̕��ʂ�������ƍs���ƁA���ʂɏċp���Ȃ��čς݁A���ʂƂ��ĕK�v�Œ���̏ċp�����ꂾ���ōςނ悤�ɂȂ�A�S�~��R�₷���߂̐ŋ����ߖ�ł���i���l�s�̗�j�B�������A�ċp�ɔ����Y�_�K�X���������łȂ��A��C�����ɂ��Z���ւ̌��N��Q���������A��Ô�̏o�������Ƃ����ǂ��z�ɂȂ��Ă���B���̕ӂ͎q���̂������狳���Ă����K�v������܂��B
�E������⎩����̋��͂ɉ����A�����Ō�������̂�NPO�̊��p�ł��B
�E���ݏ����͂ǂ̎s�����ł���Ȃ菬�Ȃ�K���������Ă�����ŁA�R�q����������Ȃ��̐��_�ɂ��ʂ����l�ЂƂ�̃��C�t�X�^�C���ϊv�̊�{�B
�E���݂̃��T�C�N������1�ʂł������_�ސ쌧���q�s�́A�y�b�g�{�g���A�A���~�ʁA�g�p�ςݐH�p���A�A�̙��蓙�S�~��20��ނɕ��ʎ��W���Ă���B���ߍׂ������ʂɂ͌o������邪���T�C�N���͎s�Ɏ����������炵�A���T�C�N������50�����A06�N�x��8900���~�̔��オ�������B
�Q�j�N���}
�y�}�C�J�[�ЂƂ₷�݁z
�E�ޗnj����Ƃ��ẮA����ꂽ�w�͂����Ɏg������悢���B���̃L�[���[�h�͎����Ԃł��B�����Ԃ͕֗��ł����A���̎Љ�R�X�g�͕֗����������Ă���B�}�C�J�[�𗘗p������Ȃ��s�s�\�����̂��Ă��邱�Ǝ��̂��A�n�����ւ̍U���Ȃ̂ł��B�����炱���A�}�C�J�[�����}������A��_���Y�f�r�o�팸�̖ڕW���l�͂炭�炭�B���ł������ł��B���H�Ԃ̉^�p�����P���āA�}�C�J�[�����ŕ�点��X�ɂ��Ă������Ƃ��A��������ʓI�Ȓn�����g���h�~�Ǝv���܂��B
�E�}�C�J�[�����l���Ă��炤���߂́u�傫�Ȏ��v�Ƃ��āA�x�O�̑�^�V���b�s���O�X��ł��~�߂���S�ӋC���~�������̂ł��B�i����̓R���p�N�g�E�V�e�B�ւȂ���j
�E�K�\�������i�̍����Ŗ��ԉ�Ћy�ьl�ł̓K�\��������̏��Ȃ��y�����Ԃ̗��p�������Ă���B��Ԑl���A�ו��ʁA�������ɂ��o�C�N�A�y�����Ԃ̗��p���������ׂ��ł���B
�E�E�B�[���̃O���[�x���ʂ��t�B�����c�G�̃x�b�L�I���A�x�l�`�B�A�̃T���}���R�L��ɊY������悤�Ȕr�C�K�X�����̋�Ԃ��ό��헪�Ɛ��������������ޗǂ͔�����ׂ��ł��B
�y�A�C�h�����O�X�g�b�v��p�[�N�����C�h�z
�E�ޗǎs�ł̓A�C�h�����O�X�g�b�v��Ⴊ����10���~�̔����ł��B�ޗǎs�̏��ł́A������Y���s�����w�肷�����ꂽ�n�悾���ŁA�s�\���ȋC�����܂��B�i���𐧒肵�Ă��邾���ł��܂��ł͂��邪�j�ނ��댧�ŏ��𐧒肵�A�L���Ԃ������ċK�����ׂ����Ǝv���܂��B
�E���p�Ԃ�Зp�Ԃ̕s�K�ȉ^�p���Ď�����Ƃ�����A�h���C�u���R�[�_�[�Ƀ^�R�O���t��������������悢��������܂���ˁB
�E�ߓS�A���/���{��Ŏ��������́u�p�[�N�����C�h�v�����́A�ޗǂł��傢�ɎQ�l�ɂ��ׂ��B�ޗnj������ӂ̎{�݂ƃX�[�p�[���A�g���͂��营��ޗǂł��������B
�E�ޗǂ̕\���֍�ޓ��H���痬���ԗ��̃p�[�N�A���h���C�h���n�ɁA500m �����J�ʂ��Ă��Ȃ���a�������H�̊��p���B�܂������ɓ��s���͌����ԗ���p�Ԑ���1�{���݂����ʓI�B
�y���]�Ԃ̊��p�z
�E���ΔR�����g��Ȃ��ړ���i�ōł��D�G�Ȃ��͎̂��]�Ԃł��B���[���b�p�ł͉��ΔR����������炷���߂Ɏ����Ԃ��玩�]�ԁ�������ʋ@�ււ̓]�����i��ł��܂��B���{�ł͂܂��{�i�I�Ɏ��g�ޒ��͏o�Ă��܂��ޗǂ͏����I�ɂ����]�ԂɗL���Ȓn�`�����Ă��āu���]�Ԃő����Ċό��ł���C�����������v�Ƃ��đS���ɐ�삯�Ď��g�ނׂ����Ǝv���܂��B
�E�x���M�[�̃n�b�Z���g�s�́A�X�̊O���Ɍ��݂���\�肾�����O�Ԗڂ̊H�̌v�������߁A����ɂ��ܓ����H�̂����������A�����ɖ�A���A�����Ǝ��]�ԓ����g�����A�o�X�̉^�]�ƃT�[�r�X�����コ���A�₪�Č�����ʂ��ɂ����B�P�N��A������ʂ̗��p�҂��W�O�O�����������B���X�傽���͔��オ�������Ċ�сA��ʎ��̂ƁA���̂̔�Q�҂������������߁A�X�����������ꂽ�B�o�X�������ɂȂ����̂Ɠ������ɒn���ł����z���ꂽ�B���s�̏Z�����x�����Ă���ŋ��́A�P�O�N�O�������Ȃ��Ȃ����B�Z�����������ĐŎ����������̂ŁA�ł����z���邱�Ƃ��ł����̂ł���B�����o�X�́A���H���݂�����������Ăł��萬�������B
�R�j�G�l���M�[�i�n�G�l�ƏȃG�l�j
�y���q�͔��d�z
�E �n�����g���̓G�l���M�[�̘Q��ɂ���ċN�����Ă��܂��B���̍ł��T�^�I�ȗ�͌��q�͔��d�Ŏ��ۂɎg�p����G�l���M�[�̔����ȏ���̂ċ�C�␅�����߂Ă��܂��B�����͒n�����g�����l�����ꍇ�A�ň��̔��d���@�ł��B1)���Y������ꏊ���牽�S�L��������Ă���i���d���X�j
2)��ʂ̉��r����r�o���C�����x�������グ�A���ӊC��̐��Ԍn��ω������Ă���3)���M��S�N�ȏ���o����������ː��p�����B4)�����̃S�~�̓v�[���ŗ�p���K�v�ȂقǍ��M���o�������܂��B�����͉����N�̖����ɂ��Q���y�ڂ�������̐ݔ��Œn�����g���̌����ł��B
�E�����̋��唭�d�ݔ������A��������S�L�����^��ŕ��z���鋌����̔��z���̂āA�e�ƒ�ɔR���d�r�⑾�z�����d��ݒu���n���n�Y�^�Љ��z���ׂ��ł��B��͑�a�i�����j�Ȃǂ�߁A�[����i�R���d�r�A���z�����d�A�}�C�N�����́j�̊J���ɑS�͂𒍂��ׂ��ł��B���{��d�͉�Ђ́u������CO2���Ȃ��n�����g���ɗL���v�Ƃ�����`�͕��ː��p��������̔��M��n���������L�������E�����R���̗A�����H�Ȃǂ̘Q������Ă��܂��B
�E�n�Ղ����肵�Ȃ��ޗǂɂ͕s�����ł��傤�B����ɑ�ʂ̐����v�����܂��B�����Ĕp�F����͑��ʂ̕��ː��p�������������A���̏�����T���A�������H�A�Ɩ����֊����������t���邱�Ƃ�F�����Ă��������B�܂�LCA�iײ̻��ٱ����āj�]�����d�v�ł��B
�E���{�ł͌����̌��ݏꏊ�ɋ�J���Ă��邪�A���������̎ז��ɂȂ�Ȃ��ꏊ�ō�����d�͂��g�킹�Ă�����āu�������v�ƌ�����̂��H�S�~�ċp��̒n��G�S�Ɠ��l�̊��o�ł́B�n�����g���̓G�R���[�h�ʼn�������̂��H
�y���R�G�l���M�[�z
�E���z�����d�ł�������ɐݒu���Ă��܂��B�ŋ߂��V�������@���J������A���d���������サ�A�l�i�������Ȃ��Ă��Ă��܂����A���Îs����o���Ă��܂��B
�E���d�ɂ��Ă̑I�����́A�E���͔��d�E�n�M���d�E���͔��d�A�����낢�날��܂��B���Ƃ͓d�͉�Ђ̕ςȐ���������Ηǂ��̂����ǁB���͔��d���݂ɓd�͉�Ђ��u���[�L�������Ă��܂��B���R�́A�s���ɑ�փG�l���M�[���g����ƁA�����̓d�C�����̕�����Ȃ��Ȃ邩�祥��B
�E���z�d�r���l�ނ̃G�l���M�[�����������Ă����Ǝv���܂����A���݂̕ϊ�������R�X�g�ł͂܂��܂��{���Ƃ͌����܂���B���`���́A���́A�g�͂Ȃǂ̃��[�J���G�l���M�[���p�̋Z�p�J�����i��ł��܂����A�K���n�̖���R�X�g�Ȃǂ��l����ƂƂĂ��{���Ƃ͍l���ɂ����B����A�����Ԃ͉����炸�R���d�r���~�d�r�ő���Ǝv���܂����A�����̃G�l���M�[���͓d�C�ł��B
�E�Ԕ��ޓ��̔p�ނ���o�C�I���d��o�C�I�R�����́A�ޗǂ炵���n�G�l��i�ł���B
�E�@�������o���Ă��Ȃ����߁A���Ƃ��Δ��d���Ă������d�͂̔��d���o���Ȃ��B���߂ăh�C�c���݂̖@�I�������K�v�ł���B
�y�ȃG�l�z
�E�n�����g���h�~�Ɋւ��A�����◝�_����ł����A�ȃG�l���M�[�̎��H��������ł͂Ȃ��ł��傤���H�����Ă܂��́A�N�ł��o���鉷�g����P�O���ځiJCCCA�Q�Ɓj�̎��H����B
�E���ʓI�Œn���ȏȃG�l�̎��H�i�u�����d���A������ہA�Ȃǁj�͉ƌv�̐ߖ�ɂ��Ȃ���B
�E�Ƃ̒f�M���ɕ⏕�����o���V�z�̉Ƃ͍��f�M���`������Ȃǁu�����Ɓi�ȃG�l�Z��j�v�ɂ������g���ׂ��ł��B����A�������̉J�˂̗����ɋC�A�V�[�g��\��t���Ēf�M���ʂ�������B�����x�̍����f�M�Ƃ����A�i�{�[���\���̓����v���X�`�b�N������y�ł��B
�E08�N1���A�u���o�������j�^�[�v�ɂ��C���^�[�l�b�g�����ɂ��ƁA�u���H���Đߖ���ʂ������ł���v��\��Ƃ��āA���C�̎c�萅���ė��p����A�����Ō���������A�g�[�̃X�C�b�`�͂��܂߂ɐ�A�R���Z���g���ҋ@�d�͂��J�b�g�A�Ȃǂ������B
�E���C�g�A�b�v�͊m���Ɍ��z�I�Ȗ�i������A�ό��q�U�v�Ȃǂɂ͌��ʂ�����Ƃ͎v���܂����A���ł�����ł����C�g�A�b�v���߂��̊������܂��B���{����ꍇ�́A���Ȃ��Ƃ����ꂩ��̃��C�g�A�b�v�܂ߌ����{�݂��^�X�܂̌��ݎ��́A���R�G�l���M�[���������R�O���`�T�O���ȏ�ɂ���ȂNjK�肷�ׂ��ł��B�܂����C�g�A�b�v�ł����ƁA�M���@�Ɠ������k�d�c�������ʓI�ł��B
�S�j�X��
�E���E�I�ɂ͐X�ь����i���́A�Ĕ��A�X�щЂȂǂŁj�������Ă��āA�ŋ߂̓o�C�I�R���p�̑哤��T�g�E�L�r�����ւ̐X�є��̂�������@�I��ԁB�����ɔ����Ĕr�o�����CO2�́A���E�ɂ����鉻�ΔR���̔R�ē��ɂ��CO2�r�o�ʁi�N��230�����j�̖�S���̂P���Ă��܂��B�X�є��̂͒Z���Ԃł����A�X�т̍Đ��͐�10�`��100�N���̒����N����������܂��B���̂܂܂ł͐A�т͒ǂ����܂���B���g����ƐX�ь����̖h�~�̓Z�b�g�ōl���˂Ȃ�܂���I
�E�ޗnj��̐X�тɂ��P�N�Ԃ�CO2�z���ʂ�1000��tCO2�ŁA���CO2�r�o�ʂ�560��tCO2�ƁA����͋z�������Ȃ�����Ă��邪�A���������{�S�̂̌���́A�z���Ɣr�o�͂قړ����x�̐��l�Ƃ̂��Ɓi���������u�����j�B���ꂩ�炵�Ă��ޗnj��⍂�m���ȂǁA�X�ї��̍������ɂ͍���Ƃ��Ă����ƐX�ѕی�琬�̎x��������ׂ��ł��B
�E�ޗnj��̎R�́A�����R���ɓ���ƍׂ����肪������A�����˂����܂Ȃ��̎R���قƂ�ǂł��B�ޗnj��͐X�т������ƌ����܂����A���̂܂܂ő��v����B���������x�����Ă���X�ъ��ł͐����Ă���̂ł��傤���H
�T�j���̑�
�E�n�����g���͂b�n�Q�̖�肾���łȂ��A�l�ނ̃G�S�ւ̌x���ł���A�o�ύ������̎Љ�玩�R���������̎Љ�ւ̓]���ł���Ǝv���B
�E���a�̐����ɖ߂�̂ͤ�����s�\�Ȃ̂��낤���H�v���{��͋}�����A�摗�肹������{�B
�E�H���̐H�ނ��A�A���R�X�g�̊ϓ_����n�Y�n���̊��������\�B��^�������̋֎~�B
�E�Q�S���ԉc�Ƃ̒i�K�I���~�B���d���̌o�c���O��]���B
�E���{�̐̂Ȃ���̋�C���C�d���̖ؑ����{�Ɖ����ޗǂɂ͈�ԓK�����܂��B
�E���s���ɂ��āA�ߖ�͎������͔��g�Ɋ����Ă��܂��B�����Ȓ�����܂����A���X�����ƌ����v���ł��B���s�c�菑�́A�����s�݂̒��ŋc������A�����A�č��͖����ɔ�y���Ă��܂���B�킪���́A���̓w�͂�������ōX�ɍ����ڕW��ݒ肵���̂ł��B�킪���̌l���Ή��ł�����E�������Ă��܂��B���A���y�юs�����̊��ۑS�s�����ǂ͉���ڕW�ɁA�����ɉ������߂Ă���̂ł��傤���A���m�Ȏw�j��������邱�Ƃ����߂܂��B
�E���N�ޗnj�����o����Ă���u�������v�̒n�����ۑS�ւ̎�g���e�̔c���ƁA���s�̏���B�܂���ʁE�����Ԣ��ʑ̌n�̏ȃG�l������̐��i�́A���O�Ɍ����֏\���Ȃ�������B
�E�x�O�̃V���b�s���O�Z���^�[�ȂǂŌ�ʗʂ̑啝�ȑ����������炷���Ǝ҂ɑ��A�������ʃK�X�̔r�o�}��������߂�����ŁA�n�����g�������i�@�̉������̎�����}��ׂ��B
�E�ޗǂł͉ƒ�ƃN���}����������̂͊m���ł��B�������[��������10���팸���\�ł��傤���H�@������̑O�̒|������p�̂悤�ŁA���͂�v�������{�K�v�ł��B
�EETC��p���������㓹�̃X�}�[�g�ȋ@�\����ɂ���(ETC�ݒu�ꏊ�H�v�ⷬ����ޯ�����)
�E�g�C�I�����g���h�~�錾�g��]���B���Ђ�����Ǐ]���ė~�������̂ł��B����ɂ́A��X�s���̃o�b�N�A�b�v����ԏd�v�ł��B
�E����300�N�̕��a���x�������������̉��`���w�ԓ��A���{�̊�������̒m�b�Ŏ��B
�E����T�~�b�g��傢�ɐ���グ�A�ޗnj����̊S���ĂуX�g�b�v���g���ӎ����グ�悤�
�E�J�[�{���I�t�Z�b�g�̍l�����Ɠ����B��}�C�J�[�I�t�Z�b�g��₢���ȃI�t�Z�b�g���p������
�E�h�o�b�b��S��������b�n�o�P�R�ɂ��Ă̊T�v����ȂǁB
����s���{���Ԕr�o��������ޗnj����甭�M���F�ޗnj��Ƃ��Ă͑��͖{��ł͂Ȃ��A�s���{���Ԃł̔r�o���������ϋɓI�ɍL���铙�����鐭��Ɏ��ł��A�A�L���Ȏ��R���ɊÂāA�قƂ�ǒn�����g����ւ̓��������Ă��Ȃ�������C�Â��������Ȃ���A���Ԃ��̂��Ȃ����ԂɂȂ�܂��B�����s�A�_�ސ쌧�A���m���A���{�Ȃǂɔ�r���āA�ޗnj��͗������A�Y�Ƃ����Ȃ��̂ŁA�������ʃK�X�̔r�o�ʂ͏��Ȃ��Ǝv���܂��B�����s�ɓޗnj��̔r�o�g���Ă��炦�A���̍����������͗ǂ��Ȃ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�@����������ۂ̌�����
�P�j�s���{���̊Ԃł̔r�o������͌��݂̂Ƃ��댟������Ă��Ȃ��B�����̊Ԃł̔r�o��������x�����{���Ă��鍑�͖����Ǝv����B�n����Y�ƍ\���̈قȂ鎩���̖��Ɍ����ɔr�o�ʂ����蓖�Ă邱�Ƃ�����ł��邱�Ƃ�A������̔r�o�̒��ړI�ȗ}����i�Ɍ��E�̂��鎩���̂ɔr�o�g�����蓖�Ă邱�Ƃ̍������A�����̂��ŋ��ő��̎����̂���r�o�����w�����邱�Ƃ̑Ó����ȂǁA�������ׂ��ۑ�͑����B
�Q�j�X�т��L�x�Ȏ����̂��r�o������ŗL���ɂȂ�Ƃ͌���Ȃ��B�s���{���̔r�o�g���߂�ɓ�����A�Ⴆ�A�s���{���ɂ����鑍�r�o�ʂ���X�т̋z���������炩���ߍ��������Ĕr�o�g�����蓖�Ă���Ƃ����ꍇ�ɂ́A���̓s���{���ɔ��p�ł���ʂ͏��Ȃ��Ȃ�\�������邽�߁A�X�т𑽂��������̂��r�o������ŗL���ɂȂ鐧�x�ƂȂ�Ƃ͌���Ȃ��ƍl���܂��B�r�o��������x�͕ʂƂ��Ă��A���܂��܂Ȗ����������Ă���X�т���邱�Ƃ͑�ł��邱�Ƃ���A���ł́A�X�ъ��ł����ĐX�т̊���ۑS�����g�𐄐i���Ă��܂��B
�E�������ʃK�X�r�o�ʎ���̎����̔ł�����܂����B�����s�V�h��ƒ��쌧�ɓߎs�Ţ�V�h�E�ɓ߃��f����ƌĂ�Ă��܂��B�V�h�悪�ɓߎs�̊Ԕ����x�����A�X�ѐ�����i�߂邱�Ƃɂ���ē�_���Y�f���팸���A���̑����̓�_���Y�f�r�o�ʂ̑��������I�t�Z�b�g��������ł��B���̂悤�ɐX�т̑����n���̎����̂Ɠs�S�̎����̂��A�g������g�݂�S���Ɋg���悤�Ƃ��Ă��܂��B
�܂�������@�ɓs��ƒn���̐l�̌𗬂�ϋɓI�ɐ[�߂鎖�����荞�ނƂ̂��ƁB
�i�T�j���H�̌���
�E�X�g�b�v���g�������H����ɂ������āA�ł��d�v�Ȃ̂́u�����Ȏ�����R�c�R�c�Ɓv�ł͂Ȃ��A�u�傫�Ȏ�����o�b�T���Ɓv�Ƃ������j���Ǝv���܂��B���ׂ̈ɕK�v�Ȃ͖̂��m�Ȍ���c���A���m�ȃr�W�����A���m�Ȑ헪�ł��B�Ȃ����̃L�[�͎����Ԃł��B
�E�͐[���Ƃ͌������̂̒��ڂ̎��Q�͏��Ȃ��A��ʎs���̑命���͉�����������ׂ����������Ă��Ȃ��B�����͢�܂��͐g�߂Ȏ�����R�c�R�c�ƣ���܂����H���A���ɢ�傫�Ȏ���������ƣ�ł͂Ȃ��ł��傤���B������l�ЂƂ�͂�����ς�����ӎ����v�̑����ŁA���_�͂Ȃ���������{�ł��B�ޗnj��̃X�g�b�v���g���̃L�[�̓N���}�Ɠd�C�̏ȃG�l�ɂ���Ǝv���܂��B
�E�n�����g���h�~�ւ̎�g�݂����܂�ߊϓI�ɂƂ炦���ɁA�o�ϓI�Ȑߖ��ւ̕��ƒ���A�X���[���C�t�ւ̖������A�q�������ւ̋���H�A�Ȃǎ����̐S�L���ȐV���������X�^�C����グ��Ƃ����ʂ��炠�ꂱ��l�������Ă���̂͂������ł��傩�B���܂ł̌o�ύ�����`�̐����X�^�C������l�Ԃ炵�������ɖ߂��Ƃ����O�����ȍl�����Ŏ��g�ނ̂��ǂ��Ǝv���܂��B
�E���g�݂̐��ʂ���̓I�ɉ���A����ɍH�v�����w�͂���������ł��傤�B�ƒ��n��ł̓w�͂��ǂꂾ������t���Ă���̂��A���Ȃ��̂���̓I�Ȑ��l�Ŏ������������̂ł��B
�E�u�ł�����̂���n�߂Ă݂܂��傤�v���u���ʂ̑傫�����̂���n�߂܂��傤�v�Ƃ��ׂ��ł��B
�E�ߖ�͌��E������܂��B������g������Ɋ댯�ȕ����A�Ⴆ�A�X�x�X�g���Ɠ��l�Ɉʒu�Â��A�Ζ��i���g���������N�����̂Ŋ댯�j���g��Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ���ł��B
�E�ޗǂɂ��˂�����������@�t���́A�u�}�C�J�[���~���A����������v���͎��]�Ԃɂ���B
�E���ʂŁu�ޗǂɂ��˂���������v�ɂ́A�܂��́u�}�C�J�[�̎��l�v�ł��傤�B
�S�D������
6�����Ԃ�ʂ��ĉۑ�́A�P�ɂ��Q�ɂ��Q���o�^�҂������Ƒ��₵�A��葽�l�ȋc�_��W�J���邱�Ƃł��������A�㔼�������Ƃ����Ԃɉ߂��Ă��܂����B�܂������w��Ⴂ�w�̎Q�������܂芴����ꂸ�A�������班�����I�ȓ��e������A�܂��ׂ������������͌������e���������Ղɓ���h�������e��������������Ȃ����A���{�I�ɂ͂킴�킴���e�Q������K�v���^�����b�g���A��͂荡������Ȃ��ƍl������Ȃ��B�����������̊��҂�菭���c�_�̊͏������������A�S�ʂɓ��e�͍L�͈͂ŁA�ƒ납��n��ł̂����镪��Ɍ��y�ł��A�܂��͂��߂̋c�_�Ƃ��Ă͓ޗnj��̎����������x�I�m�ɑ��܂����c�_�A�y�ђ�Ă��ł����̂ł͂Ǝv���Ă���B�܂����\���e�͂��Ă��Ȃ����A��c���͌��Ă�����͔��ɑ����A�@���ɓ��e�s���Ɍ��т��邩�̍X�Ȃ�H�v�ƁA�������@�t�����K�v�ł���B
�X�g�b�v���g�����͂��ߑ����̖�肪�R�ς��錻��ɂ����āA���l�Ȉӌ����t�����N�ɓ��������c�_����āi�����ցj�ł����͋M�d�ł���B������m���ւ̊Ԑڂł͂��邪�A�m���ȃ��b�Z�[�W�̓`�B�m�ɃA�s�[�����A��葽���́A����葽�l�Ȍ����ւ̗����ƊS�����߁A�����ł������̉�c���Q���҂̌Ăт��������������p�����A��������L���c�_�ł��颂Ȃ猧���d�q��c����̔��W�����҂�����̂ł���B
III�|�e�[�}�Q
�u���E�ɊJ���ꂽ�ޗǂÂ���v
�`�C�O�ւ̓ޗǂ̏�M��O���l�ό��q�̗U�v�Ȃǁ`
�R�[�f�B�l�[�^�[�F�吼�@�O
�T�D�n�߂�
�@�@���e�Ґ��Q�V���A���e�����Q�P�Q���B�����Ȃ�ׂ����L���w����̓��e�����҂��Ă������A���ʓI�ɂ͑S�̂̂V�S���ɓ�����P�T�V�����P�P���i�����X���j�̓��e�҂ɂ����̂ł������B���������Ӗ��ŁA���̉�c�ɉ����锭�����e���ǂꂾ�������̈ӌ��f���Ă�����̂ł��邩�A�^��_�͎c�邪�A����͂���Ƃ��āA�ނ��듊�e�̓��e�ɂ���ĕ]�����Ē�����A�K�r�ł���B
�������e�����l�ō��ڕʂɂ܂Ƃ߂鎖�͎���ł��������A�ꉞ�u��āv�Ɓu���̑������v�̂Q���ڂɕ��ނ����B��Ăƌ����Ă��K��������̓I�ȓ��e�ɂ܂Ŏϋl�܂��Ă��Ȃ����ڂ����Ȃ肠�邪�A����X�Ɍp�����Č������鉿�l������Ǝv������̂͊����Ē�Ă̍��ڂ̒��ɓ��ꂽ�B����A��Ăƌ������A����N�ɗ��܂��Ă��锭����A�ӌ���������Ē�ĂƂ��Ă܂Ƃߓ���̂́u���̑������v�Ƃ����B�Ȃ��A�������e��ԗ����邱�Ƃ͓���̂ŁA��|�݂̂������ʂɂ܂Ƃ߂�`����点�Ē������������������������B
�U�D���
�@�P�D�C�O�ւ̓ޗǂ̏�M
�@�@�P�|�P�D�C�O�֓ޗǂ̖��͂�@���ɔ��M���ׂ���
�i�P�j �u���ۑ����ޗNJw�����Z���^�[�v�̐ݒu��
���ݓޗnj����ɂ́A��������������l�Êw�������E���t�Ñ㕶���������E���厛�j�������Ȃǂ������e�n�ɑ��݂��Ă��邪�A�������Ȃ����킹��w�ۓI�Ȏ{�݂��Ȃ��B���s�́u���ۓ��{���������Z���^�[�v�̂悤�ɁA���E���猤���҂��W���A�����Đ��E�ɔ��M���Ă䂭�����I�Ȍ����{�݂́A�ޗǂɂ��K�v���Ǝv���B�����ɁA�ޗNJw�������ΏۂƂ��Ă��鐢�E�̑�w������A�����ҁA���邢�́A�m����_�E�E�|�p�Ƃ̐l�������o����ł���{�݂ł����Ă��A�����Ǝv���B���ɁA���t���E�܂Ȃ���̂��n�݂���A���E�̖��t�����҂�\�����鐧�x���n�܂��Ă��邪�A������X�Ɋg�傳���S�ޗNJw�W�������̌����҂�ΏۂƂ����A�u�܂ق�ΐ��E�܁v��n�݂��鎖���Ă������B
�i�Q�j�O���̃��f�B�A�̏��҂���
�ޗǂ͂Q�N��ɕ���J�s�P�R�O�O�N�L�O���Ƃ��T���Ă���A��̍D�ޗ���o����傫�ȃ`�����X�ł��B���f�B�A�̐l�B�̐S�𑨂���ɂ́A���ʂ̏��җ��s�Ƃ͈قȂ��������I�ٕ����̌������Ă��炤���ł��B�����ŁA�P�R�O�O�N�L�O���Ƃ̈�Ƃ��āA���L��Ă�v���܂��B�傫�Ȕ������Ăԉ\��������Ǝv���܂��B
�P�D���҂̃^�C�~���O�͋L�O�s���̂����P�N�O�̂Q�O�O�X�N�S�����{���̋G�߁B�x���Ƃ��P�P���B�i�L�O���Ƃ̔N�ɊC�O���瑽���̊ό��q�ɗ��Ē����ׂ̌Ăѐ����ʂ�_���j
�Q�D�Ώۍ��͔�p�Ό��ʂ��l�����A�����E�؍��E��p�ɍi�荞�ނ��A���Ẵ��f�B�A���܂߁A�l���z�����l������B���A�ݓ��O���l���f�B�A�������鎖�������������B
�R�D���҂���l���͂T�`�U�l�A�����Ă��P�O�l�ȓ����]�܂����B�i���l����ؖڍׂ����A�e���h����������ʓI�B���߂���Ƃǂ����Ă��Ή����G�ɂȂ菟���ɂȂ�j
�S�D�h���͗��فi�ٍ���j�ƃz�[���X�e�C�i���{�l�̓��퐶���ɒ��ɐG��Ă��炤�j�̃~�b�N�X���������낤�B
�T�D������_�Ђ��ē����鎞�́A�̂����V����ɒ��X�Ɉē������Ē����B�i�����C���p�N�g��^����j
�U�D�F�Ɏs�Ƃ����撬���̓��{�̌����i��z�N�����鏊�Ɉē����A�y�n�̐l�B�Ƃ̐G�ꍇ���̏��ݒ肷��B�i�ʏ�̊ό��Ƃ͈ꖡ�Ⴄ�̌��j
�V�D�ʖ�K�C�h�͈ꗬ�����O�ɑI�сA�؍݊��Ԓ��O��I�ɖ����A�e���h������B�i�ʖ�K�C�h�ƒ��ǂ��Ȃ�A��胊���b�N�X���A���S�o����̂ŁA�L�ѐL�тƎ�ނ��o���A�����L���������Ă��炦��傫�ȃ`�����X�ݏo���j
�i�R�j�ޗnj����̃z�[���y�[�W�O����ł̉��P���
�@�@�ޗnj����̃z�[���y�[�W�ɂ��ċC�t�����_�ɂ��āA�������̉��P��Ă������Ē��������Ǝv���܂��B
�P�D�X�V���ɂ���
�p��ł̍X�VDate�͂Q�O�O�U�N�P�Q���P���ƂȂ��Ă��܂��B�܂�Tourism�̃g�b�v�y�[�W�̃f�[�^���Q�O�O�R�N�Q�����݂Ə�����Ă���͔̂@���ɂ��M�����˂܂��B���}�ɃA�b�v�f�[�g����鎖�������߂��܂��B
�Q�D�uInformation before coming�v�̍��ڂ�lj�����鎖���Ă��܂��B�C�O����̊ό��q�̓C���^�[�l�b�g�Ŏ��O�ɏ��鎖�������Ǝv���܂��B���������l�B�ɋ����[��������鎖�ɂ���āA�ό��q�̗U�v���ʂ������Ղ��Ȃ�ł��傤�B���s�̃z�[���y�[�W�͎Q�l�ɂȂ�܂��B
�R�DTansportation-Access�̍��ڂɊ�y�шɒO����̃����W���o�X�T�[�r�X���L�ڂ���Ă��܂���B���ۂɂ͑����̕��B�����p����Ă���֗��ȃT�[�r�X�ł�����A�L�ڂ����̂��Ó��ł͂Ȃ��ł��傤���v
�S�DAccommodation �̍��ڂɃz�e���y�ї��ق̏Z���A�d�b�^�t�@�b�N�X�ԍ����̏��̓��������X�g���ڂ��鎖���Ă��܂��B�p��̃z�[���y�[�W�������Ă���Ƃ���̓����N���Ă����ΐe�ł��B�n�}�ŏh����̏��ݒn���m�F�o����l�ɂ���A���e���Ǝv���܂��B
�P�|�Q�D���ی𗬂̐ϋɓI���i
�i�P�j �ޗǂɐV�������ی𗬂̕���
���{�̕����ɖ�������A�[���ւ���Ă���C�O�̐l�B�͔��ɑ����Ǝv���B�����ԁA�����A���|�A�ڔ��A�~�́A�͌铙�X�̓��{�̓`��������Ώۂɂ��������𗬂̗ւ��L����w�͂����Ă͂ǂ����B�`�������Ɍ��炸�A����≹�y�Ȃǂ̐��E���ʂ̕���ɉ����镶���𗬂̗ւ��L���鎖���V���ȓޗǃt�@�����ɍv������Ǝv���B
���̗l�Ȓn���ȕ����𗬊����͐l�Ɛl�̂Ȃ��肪��{�ƂȂ�̂ŁA��l���m�̃z�[���X�e�C�Ƒg���������o����A��w���ʂ����҂ł��邪�A�c�_���傫�����W���Ȃ������̂ŁA����̌����ۑ�Ƃ��Ďc���Ă��������B
�i�Q�j�z�[���X�e�C�̊���
�O���l�ό��q���P�Ɋό��n�����ĉ�邱�Ƃ����łȂ��A�l�Ƃ̌𗬂╶���𗬂������邱�Ƃɂ��A��ۂ��[�܂�A���s�[�^�[�ɂȂ���̂��낤�Ǝv���܂��B���E�ɊJ���ꂽ�ޗǂÂ���Ƃ��āA�����ƍ��ۓI�Ȋ����������ɂ��ׂ����Ǝv���܂��B�ޗǂ͓������Ós�ł���Ȃ���A���s�ɔ�ׂĔ��ɑ����̓_�Ŗ��͂Ɍ����Ă���ׁA�ό������ł͂ǂ����Ă������؍݂��Ă��炤��������̂�����ł��B���̓_�A�z�[���X�e�C�̏ꍇ�A�ό������łȂ������B�̓��퐶���ɒ��ɐG��Ē������ɂ��A�P�Ȃ�ό��ł͌����ē����Ȃ��l�ԓI�G�ꍇ���₻�̓y�n�̐l�Ԃ���Ȃ���Γ��鎖�̏o���Ȃ��M�d�Ȍo�������Ă��炦�܂��B���̌��ʁA�ޗǂł̑؍݂����Ɉ�ې[���Ȃ�A�F����[�܂�A�ޗǃt�@���𐢊E�ɍL���邫�������ɂȂ�܂��B��l�̓ޗǃt�@�����P�O�l�̐V�����ޗǃt�@���̎�������ĉ�����`�����X������܂��B����e�s�����̍s���̃g�b�v�����������n���ȑ��̍��̍��ی𗬊�����ϋɓI�ɕ]�����A���シ�鎖�����҂������B���荑�̒m����s���̐e�����g���ė���悤�Ȋ����O���[�v�ɑ��ẮA�\�h�K�����Ȃǂ̑Ή���ϋɓI�ɂ��鎖���Ă������B
�i�R�j����҂̍��ی�
�w�Z�̐搶���m�̃z�[���X�e�C�������ی𗬂��������鎖���o���Ȃ����B������͍�����{�����ł͂Ȃ��S���E�I�ȃe�[�}�ł�����A���ʍ��̑������삾�Ǝv���܂��B���R�̎��Ȃ���A���݂��̔Y�݂Ƃ��o���ȂǑo���ɂƂ��ċ����[���b��͌���Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ɛ��@���܂��B�����������ẮA�ޗǂ̓����������������E��Y�w�K�ƍ��ۗ���������e�[�}�ɂ��āA�ޗnj����ɂ���w�Z�̐搶���Ɛ��E�e���̐搶���Ƃ̌𗬂��Ă��܂��B���ꂪ��������A���E�ɊJ���ꂽ�ޗǍ��̈�̑傫�Ȑ���ƂȂ�\��������A�Ӌ`�[�������Ǝv���̂ł��B�z�[���X�e�C�͐l�ԓ��m�̐G�ꍇ���Ɋ����鎖�̏o����L���Ȏ�i�ł��B�S���E�ɃN���u��L����z�[���X�e�C�g�D�Ƃ̘A�g���o����A�v���W�F�N�g���i�̑傫�ȗ͂ɂ��Ȃ�ł��傤�B
�Q�D �O���l�ό��q�̗U�v
�@�@�\�@���͂���ޗǍ��ׂ̈Ɂ@�\
�i�P�j�ߍx�s�s�Ƃ̘A�g�ɂ��V���Ȋό��J��
USJ��ɉ؊X�̊y���݂���������{�ƁA���E��Y��Î₪���蕨�̓ޗnj�������g���A�P�̊ό��v�����̒��ő��ݕ⊮���ł���悤�Ȏ藧�Ă��l���Ă͂ǂ����B�����l�ό��q����Ώۂɂ����V���b�s���O�Ɗό����~�b�N�X�����v���������ʂ����҂ł���\��������B�Ⴆ�A���厛�E�ޗǒ��E�C�I�����̌��Ƃ��A���������E���䒬�E�A�����i�_�C�������h�V�e�B�j�Ƃ����g�ݍ��킹����āB
�i�Q�j ���l�Ȋό��v���O�����̊J����
�Ós�ޗǂ̓������������Џ���ɉ����A�n��̃C�x���g��`���Y�ƁA�l�X�̕�炵�Ԃ�Ȃǂ�g�ݍ��킹���ٍ����������薡�킦��悤�Ȋό��v���O�����̊J�����l���Ă݂Ă͂ǂ����B�ޗǗ��j�E�H�[�N�Ȃǂ�g�ݍ���ł��ʔ��������m��Ȃ��B
�t�E�H�̊ό��V�[�Y�������łȂ��A���厛�̂������Ƃ����撬�̐��l�`������C�x���g�Ȃǂ̃��j�[�N�ȃv���O������g�ݍ��킹��A�~�̋G�߂ł��V���Ȋό��J�����\�ł͂Ȃ����낤���B����A�W�A�̐l�B�ɂƂ��ẮA��i�F���������ׁA�킴�킴���̋G�߂ɓ��{��K���ό��q�����������ł�����APR�̎d������ł͊ό��U�v�ɂȂ�\�����l�����܂��B
�i�R�j�_�Ɗό��i�A�O���c�[���X���j�̒��
�@�@�ޗnj����œƎ��̔_�ƌo�c�Ő������Ă���_�ƂȂǂƃ^�C�A�b�v���Ď��ӂ̗��j�I�Ȍ����Ƃ��`���s������Y�����𑍍��I�ɃR�[�f�B�l�[�g���āA�V���Ȍ`�̊ό��Ƃ��ĊJ�����Ă͂ǂ����낤���B��a�S�R�̋����̗{�B�Ȃǂ���̉\���Ƃ��Ėʔ������Ǝv����B
�i�S�j�L�\�ȊO����K�C�h�̗{��
�@�@�ޗǂ̊ό��Ɋւ��Ă݂̂Ȃ炸�A������_�Е��t�A���z�A�X�ɂ͓��{�����S�ʂɂ��ē��{��ŃK�C�h�o����l�͂��Ȃ肨����悤�ł����A�O����ŃK�C�h�o����l�̐��͋ɂ߂Č����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����A������������Ղ����y�����O����Řb����K�C�h����R����y�n�Ƃ��čL���m����悤�ɂȂ�A�ޗǂɖ�������O���l�̐��͑傫���L�т�\��������ł��傤�B���Ń{�����e�B�A�K�C�h�{�����C��s��ꂽ��A�Љ�l��ΏۂɃK�C�h�{���u�������{����Ă����w������悤�ł����A�܊p���C���u�����I������Ă��A���ۂɊ���ꂪ�Ȃ��ƌ���������Ă��܂��B���̂܂܉����Ȃ���Ȃ���A�P�R�O�O�N�L�O���Ƃ̔N�ɂ������ƌP�����ꂽ�K�C�h�̐����啝�ɕs������ƌ������Ԃ��N����̂ł͂Ȃ����ƌ��O����܂��B�L�\�ȊO����K�C�h�̗{�����}���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�����ŁA���ׂ̈̑�Ƃ��āA���̂悤�Ȓ�Ă�v���܂��B
�P) ���܂��͂P�R�O�O�N�L�O���Ƌ���K���Ȑ��i��̂ɈϏ����āA�O����{�����e�B�A�K�C�h�{���ׂ̈̓��ʌ��C�v���O���������A����ő�����o����K�C�h�̗{����}��B����ɂ͌���o���̖L�x�ȍu�t���w���ɓ�����B
�Q) �����u�ʖ�K�C�h���Ǝ����v�̓ޗǔłɑ������錟�莑�i���x���m�����A�K�C�h���u���l�B�����Ȍ��r����ڕW�����B����ɂ��A�K�C�h�v���̐�����L����Ƌ��ɁA���x���A�b�v��}��B�L���i�҂ɂ͗L���ŃK�C�h�o���铹���J���B
�R) �K�C�h�̗L���i�҂�{�����e�B�A�K�C�h�̃��X�g���쐬���A�O�l�ό��q�����p�ł���d�g�݂����B�i�Q�l�܂łɋ��s�ł̓��X�g���z�[���y�[�W�Ō��J���Ă���j
�����̒�Ă��������ɂ́A�������̃N���A�[���ׂ����_������Ƃ͎v���܂����A�������厖�Ȏ��́A�܂������{�����e�B�A���_�����l�B�Ɋ���̏����邱�Ƃ̏d�v����F�����A�ϋɓI�ɉ����ׂ̈̎��g�ݎp�����������ł͂Ȃ��ł��傤���B
�U�D���̑�����
�@�P�D���͂���i�ς��c����
�i�P�j �Ós�Ƃ��Ă̓ޗǂ�ڎw����
�ޗǂ̌i�ς͏X�������Ă���B���ɋߓS�ޗljw�A�����A�i�q�ޗljw��{�ʂ�Ȃnj������Ђǂ��B�R���N���[�g�̃r���͌Ós�ޗǂɂ͑��������Ȃ��B�Â����j�ƕ����������A�����̐��E��Y���ւ�ޗǂɑ��������Â��ȘȂ܂�������������i�ϐ�����������Ăق����B�ޗǂɂ������{�Ōւ��s�s�i�ς��c���Ă����ׂ��ł���B
�i�Q�j���������{�̎c���ɂ���
�@���m���������ƃA���b�N�X�E�J�[���̒����u���������{�̎c���v�����������{�̌i�ς�����čs���ׂ̋M�d�Ȏ����𑽂��܂�ł���Ƃ��ďЉ�ꂽ�B����Ɋ֘A���āA�i�q�ޗljw���ӂɌ��ݗ\��̐V�����O���n�z�e�������������̎ʐ^�Ƃɓޗǂ��\�����̗D�ꂽ�i�σX�|�b�g�Ƃ��Đe���܂�Ă����i�ς������˂�댯���̂��鎖���w�E���ꂽ�B����A�ޗǂ���{�̓`���������\�����̒��Ƃ��āA����ȏ�i�ς��j��Ȃ��悤�ɁA�ޗnj��O�ɏZ�ފO���̐l�B�̋q�ϓI�Ȉӌ����@������ׂ��ł͂Ȃ����B
�i�R�j�ޗǂ͖��͖���
�`�j�Љ�ׂ����m���R�g���A�ޗǂ͂�����ł������Ă��܂��B�͂����肢���āA�ό������̕�ɂł��B�u����Ȃ��v�͎̂����ł����A����́A���͂��܂������Ă��Ȃ������ł��B�V�������͓̂��ɓ��ɉ��l�������܂����A�Â����͓̂��ɓ��ɉ��l�������Ă����܂��B�g����x��̃g�b�v�����i�[�h����ޗǂɖ��͂����o���҂Ƃ��ẮA��K�͂ȓs�s�J���͒f�ŋ��ۂ��܂��B�ޗǂ̖��͂̃A�s�[���́A���̉��番�̈�̃R�X�g�Ŏ����\�ł��B
�a�j�����ޗǂ̖��͂͋��s�̂悤�ȑ�ό��s�s�ł͊������Ȃ��A����Ȃ��f�p���Ɠ��{�̗��j��`�������̗̌������������鉽�����}���̂悤�Ȃ��̂��c���Ă���Ƃ���ɂ���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă����l�ł��B�]���āA���s�Ɠ����悤�Ȗ��͂�Nj����鎖�ɂ͎^���o���܂��A�t�ɋɂ߂Ēn���ȓޗǂ̖��͂��ǂ̗l�ɑi�����ׂ����ƌ������ɂ��Ă͖��m�ȓ������܂������Ă͂��܂���B
�i�S�j�ޗǂ𖣗͂��钬�ɕϖe�����悤
�@�@�ޗǂ𖣗͂���}�`�ɕϖe���邽�߂ɁA��̓I�ȉ��L�̒�Ă������Ē����܂��B
�@�@(1)�i�q��a�H���{�i�q�a�̎R���{�i�q������������A�ޗNJ������������B
�@�@(2)�ޗNJ���̓������s�X�n�Ƃ��āA�V�����w�܂��Â���x�𐄐i����B
�@�@(3)�ޗNJ���̊O���Ɋw���s�s�E�H�ƒn�сE�ߍx�^�_�Ƃ�ߍx�^�ыƂ�z������B
�@�@(4)���ې�E��E��a��̐앝�g���Ɛ��ʑ����̌v������{����B
�@�@(5)����������j���Y���A�������ʂ̖������͎̂��{���Ȃ��i��C�ɗ��߂�j�B
�@�@(6)�e�s�����̍������\���v���X�ɕϊ�����i���s�s��7��8�S���~�̍����ł���j�B
�@�@(7)�����ޗǏ��q���j�����w�ɂ��āA������w�ɕϖe����B
�@�@(8)�ޗnj����̕\�D���w�ޗnj��L�x�ɉ��߂�B�i�����̈ӌ������̈Ӗ������ł��j
�@�@(9)�ޗnj���60�Έȏ�̐l�ނ������̂ŁA�����l�ޏЉ��Ђ����i�V���o�[�Z���^�[�͂��߁j�B
�@�@(10)�w�O�̊�������}��B���{������̐V�K�Q�����Ǝ҂́A10�N�ԁ@���łƂ���i�n���ł̂ݖ��Łj�B���ȂǁA��̍����������ΐ肪����܂���B���L�e�ʂ̂������ƌ����̈ӎ����v��ؖ]���܂��B
�@�Q�D�ό��q�ɑ���e�ȑΉ��̑��
�i�P�j�ޗǂ̏h���q�����̂��߂�
�@�@��r�I�R�X�g�������u�T�[�r�X�ʁv�̌����}�鎖����͂��߂Ă͂ǂ����B�ƊE�����C�⎋�@���J��Ԃ��A�]�ƈ�����Ɠ����ɃI�[�i�[�̈ӎ����v��}���Ė{���́u�����ĂȂ��̐S�v��\������p���w�ԓw�͂����Ăق����B�^�ʖڂȓw�͂����Ă��铯�Ǝ҂��������ŁA�ꕔ�̋ɂ߂Ď��̈����T�[�r�X�ƑΉ������o���Ȃ����ق��ޗǂ̃C���[�W�_�E���������Ă��錻��͎c�O�ł���B��̈ĂƂ��āA�ό��R�c�̂���{�����A�ƊE���W�ׂ̈ɁA��ۂƂȂ��Ă������̂����{���ł��o�����͏o���Ȃ����̂��B
�i�Q�j�B�e�̋K���͂����Ɗɂ߂�ׂ�
�@�@�ޗǂ̐_�Е��t�┎���ق͑��̌��⏔�O���ɔ�ׁA�ʐ^�֎~�̗��ĎD�����߂���B�ޗǂ�K���ό��q���v���o�Ƃ��Ď����A�肽���C���������Ƒ��d���āA�K�����ɂ₩�ɂ��ׂ��ł͂Ȃ����B�O���l�ό��q�����E���v���ɂ��Ȃ��Ă���͎̂c�O�ł���B�ꍇ�ɂ���ẮA�ʐ^�B�e��L��������Ȃǂ̍H�v���Â炷�Ȃǂ��Ăł��A�ێq��K�ɋ֎~�ƌ������͂������낤�B
�i�R�j�ό��Z���^�[�Ȃǂɉ�����e�Ȃ��ĂȂ�
�O�l�ό��q���p�ɂɖK���ޗǎs�ό��Z���^�[�̂悤�ȂƂ���ł̐e�Ȃ��ĂȂ��̃T�[�r�X���D��ۂ�^���A�ޗǃt�@�����ɂȂ���̂ł͂Ȃ����B�ό��q�̏��X�̎���ɑ��āA�p��ł�����Ɠ�������{�����e�B�A�K�C�h�풓���A�����̃T�[�r�X������Ȃǂ��āA������Ƃ����ό���������I�A�V�X�̂悤�ȏꏊ��o����Αf���炵���Ǝv���B
�@�R�D���j�I�������Y�̌��ʓI�i��
�@�@�P�D����{�Ղ̍��c�������ɂ���
�@�@���^���ӌ����@�`�j�ޗǂ̏����ɂƂ��Ă͉���I�ȏo�������Ǝv���܂��B
�a�j���{�̗��j�̒��ŋɂ߂ďd�v�Ȉʒu���߂�ޗǎ���̍ł��ے��I�Ȉ�Ղł��镽��{�����鎖�ɂ͍��ƓI�ɂ��傫�ȈӋ`������B�ޗnj��ɂƂ��Ă��ό��J���̐�D�̃`�����X�ɂȂ�ł��傤�B���@��Ƃ����s���Đi�߂�ׂ����Ƃ͎v�����A������������A�����I�ɂ͂��̍L��ȕ~�n�̒��ɓޗǎ���̖�l�̓@���X���݂����A���̈ꕔ���݂₰���X��ޗǂ̓��Y����X��W���ꓙ�ɗ��p����A�ޗNJό��̖ڋʂ̈�ɂ��Ȃ蓾��̂ł͂Ȃ����B
�@�@�����Έӌ����@�`�j��ɓa��鐝��̕����o����ċ����܂����B�����܂ŋ��������Ȃ��Ă������̂ł͂Ȃ����B
�a�j�������邾���̎���������Ȃ甭�@��Ƃ�D�悷�ׂ����Ǝv���B����{��ɓa�ɂ��Ă���ꎟ�Ƒ�Ƃ�����܂��B��ꎟ��ɓa�Ə̂��錚���݂̂̌������J�ɂ���āA���ʓI�ɗ��j�̗��ꂪ�}�X�N����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����B������������{�̌����́A�J�s�ƂȂ�Ƃ��ׂĕ����E�^�����čĎg�p�����̂������̗��j�ł��B�P�v�I�Ȍ������Ƃ��āA�\�����ו�������ɂ����Ȃ����̂��A����𓊂��Č��ĂĂ��܂����Ƃɂ͋�����a����������B�����Ə̂��āA�s�{�ӂɎ���ꂽ�킯�ł��Ȃ������́A�z����̃C���[�W�ɉ߂��Ȃ��A�����������ȓ`���H�@�ł����Ȃ��͌^�����ĂĂ��܂��̂́A���j�ɑ��闝���Ɠ��@��W����̂ł͂Ȃ����Ɗ뜜���܂��B������A�����������N�Ԉێ��������Ȃ̂ł��傤�B���Ă�Ȃ�A�������̔�p�̐ςݗ��Ă����Ă����Ȃ��Ɩ��ӔC���Ǝv���܂��B
�V�D������
�@�@�U�����Ԃɘj��A�M�S�ɐF��Ȋp�x����c�_���s���ė������͈Ӌ`�[�������Ǝv���B
�܂��܂��������s�\���ȍ��ڂ�@�艺���̑���Ȃ����ڂ��������͔ۂ߂Ȃ����A���ɂ͍���̌����ۑ�Ƃ��āA����ׂ̈̓w�͂𑱂���ɒl���鍀�ڂ����Ȃ��Ȃ��Ǝv���B
�����̍��ی𗬑g�D�ɂ����̋��L���⋦���̐����Ƃ��n��Z���ɂ�閣�͂���X�Â���ƍs���̎x���̐��Ƃ������e�[�}�ɂ��Ă̋c�_���Ȃ���Ȃ������̂͏����S�c��Ɏv���B
�U�����ƌ����A����ꂽ���Ԃŋɂ߂ĕ��L���e�[�}��v�̂悭���[�h���Ȃ���A�ӌ����W�čs�����͗\�z�ȏ�ɓ���A���ʓI�ɓ��e�҂̐������҂����قǑ����Ȃ��������ɑ��ăR�[�f�B�l�[�^�[�Ƃ��Ď���̗͕s����Ɋ������B
����ŁA���̉�c�������̈Ϗ����Đ��i����Ă��鎖�Ƃł���ƌ����Ȃ���A���ۂɌ��̃g�b�v�̕��X���S�������Ă�����̂��ǂ����S���������Ȃ��������ɂ͈ꖕ�̎₵�����ւ����Ȃ������B��̒�Ăł����A�R�����Ɉ�x���炢�͒m������̃��b�Z�[�W����ʐ^�Ƌ��ɉ�c���̃g�b�v�y�[�W�ɍڂ��Ē������͏o���Ȃ����̂ł��傤���B���̎��ɂ���āA���̃g�b�v�������̐���ϋɓI�ɕ����p�������鎖�����ړ`���A���e�҂̐����傫���L���鎖�ɂ��Ȃ���̂ł͂Ȃ����Ǝv������ł��B�R�[�f�B�l�[�^�[�ɂƂ��Ă��傫�ȗ�݂ɂȂ�ł��傤�B
�Ō�ɁA�c�_��i�߂čs���r���ŁA���グ��ꂽ�e�[�}�Ɋւ���ӌ���������������A���͂����肢�����ۂɁA���������ĉ�����A���ӂ���Ή������Ē������W�̕��X�ɐS���犴�Ӑ\���グ�܂��B
III�|�e�[�}�R
�u�݂�Ȃŋ���ɂ��Č�낤�v
�`�q�ǂ�����Ă邽�߂̉ƒ�E�w�Z�E�n��̋����`
�R�[�f�B�l�[�^�[�F�O���V
�P�D�͂��߂�
���̉�c���ł͑O������̌p�������e�[�}�ŁA�n��̎q�ǂ���n��ň�Ă�Ƃ������Ƃ�ʂ��A�u����R�~���j�e�B�Â���v���g���Ă������Ƃɂ��ċc�_�����Ă��܂����B�O���ł͊�{�I�Ȋw�Z�⋳��ɑ���l�������A���H���Љ�Ă��������Ȃ���b�������܂����B
�啪�ނ́y���O�z�|�y����c���z�|�y���߂�p�z�|�y���@�_�z�Ƃ��ĉ��L�̂S��ݒ肵���B
�i�P�j�u�w�Z�v���ĂȂ낤�|�i�u�w�Z����v�̖ړI�H���Ȃ��̎咣�́H�j
�i�Q�j�u�w�Z�v���邠��厫�T�|�i�����́u�w�Z�v�b��̂̎v���o�b�Ȃǁj
�i�R�j����ȁu�w�Z�v�������H�|�i�ǂ�ȁu�w�Z�v�Ȃ�s�������Ȃ邩�ȁH�j
�i�S�j�n��Ŏq�ǂ�����Ă���H�i�I�����܂������A�w�Z�����Ŕ�I���āI�j
�㔼�ɕ��@�_�Ƃ��āu�w�Z�x���n��{���̐ݒu�����v�Ƃ�����Ϗd�v�ȏ�����炳��A���Ɍ���́A�����̎��H�𒆐S�ɁA�c�_���邱�ƂƂ��܂����B
 ���H���Љ�Ȃ���c�_��i�߁A���ɁA�u�w�Z�x���n��{���v�i���́j�̂��������̓I�ȃe�[�}�̈�Ɍf���܂����B
���H���Љ�Ȃ���c�_��i�߁A���ɁA�u�w�Z�x���n��{���v�i���́j�̂��������̓I�ȃe�[�}�̈�Ɍf���܂����B
�啪�ނ́A�y�n��z�y�w�Z�z�yPTA�z�y�����z�y�t���[�z�y���W�z
�i�P�j�n��̎��g�ݏЉ�@�@�@�������� �@�U�R��
�i�Q�j�w�Z�̎��g�ݏЉ�@�@�@�������� �@�Q�P��
�i�R�jPTA �̎��g�ݏЉ�@�@�@�������� �@�@�O��
�i�S�j�w�Z�ƒn��̋����@�@�@�@�������� �@�T�P��
�i�T�j�V���ȃA�C�f�A�@�@�@�@�@�������� �P�O�Q��
�y���W�z�w�Z�֍s�����I�@�@�@�@�������� �@�S�T��
���ɑO���̔��Ȃ���A���ۂɊw�Z�֑����^��ł���������c���̋c�_���A���H�Ɍ��т��悤�ȋ@��ɂȂ�悤�y���W�z�w�Z�֍s�����I��ݒ肵�܂����B�܂��A���H����������Ǝ��R�Ȉӌ��\�������ɂ����Ȃ邱�Ƃ��ɘa���邽�߂ɁA�y�t���[�z�V���ȃA�C�f�A�A���������߂�ݒ�ɂ��܂����B�c�_�^�c��A�S�̎�g�̃J�e�S���[�����ƁA���R�ɋ���ɂ��Č���X�y�[�X�A�c�_�����H�Ɍ��т���@��A������Ƃ�����c���ł̋c�_�̐ݒ�ɂ����̂�����̓����ł��B�܂��A�O�����́u2-�i1�j�w�Z�x���n��{����ϋɓI�ɐݒu����v��Ă��{��Ƃ��Đ��荞�܂ꂽ���ƂŁA����̓I�ȋc�_���o����悤�ӎ��I�Ɏ��グ�܂����B
�Q�D���
�i�P�j�w�Z�x���n��{���ݒu�̎��g�ݏ���ϋɓI�Ɍ��J����B
�@����20�N�x�\�Z�Ŕ��\���ꂽ�w�Z�x���n��{���֘A�\�Z�͎s�������s�ψ���ɂ́A500,000�~�A�e�X�̒��w�Z��̊w�Z�x���n��{���ɂ́A2,257,000�~�A����62�ӏ��ɐݒu����v��ŁA���Ŏs�A����s�A�ޗǎs���S�Z��ݒu�ƂȂ��Ă���B���̐�s�����g�̏����J���邱�ƂŁA�����S��ł̐�������Ă�����̂ł͂Ȃ����B�w�Z���A����R�~���j�e�B�̒n��̋��_�Ƃ��Đ������Ă��������ŁA��̓I�Ɋw�Z�Ƌ������鎞�̃|�C���g��A�l�ޗ{���̃V�X�e���A����s���Ƃ��Ă̊w�Z�}�l�W�����g���@�_���c�_���ꂽ�B�u�w�Z�]���v��I�m�ɍs�����Ƃ��K�v���Ƃ����c�_�����킹�āA�w�Z�̎�g���̌��J�����߂���B
�y265�z�w�Z�x���n��{���ݒu�^�c�̊�{�v��
�w�Z�x���{���^�c�ɂ́A�w�Z�̏��J������{�ł��ˁB�܂��M�������ł��B���ɑS�̉^�c�̒n�拳��R�[�f�B�l�[�^�[�A�e�v���W�F�N�g�̃R�[�f�B�l�[�^�[�A���H�{�����e�B�A�Ƃ����\���B�����̕����S���Ƌ��ςɂ��K�v���B���̋K�͂����ɂ́A������ƕ��݂̌o�c�͂�����܂���B
�i�Q�jPTA��w�Z�Ɍ������w�Z�x���n��{���̐ݒu���C����s���B
�@�w�Z�x���n��{����ݒu���Ă������߂̋�̈ĂƂ��āAPTA�����ɂ����w���җ{���u���⌤�C�̂悤�Ȏd�g�݂��s��������K�v�����c�_���ꂽ�B����̓d�q��c���ɂ��قƂ��PTA���̏������݂��Ȃ��A�����Ă�����\�z�ł���B�n��Ԋi���A�w�Z�Ԋi���ݏo���Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɂ��APTA��w�Z�ւ̎�g�̃T�|�[�g�⊈���̒S�ۂ��s�����H�v���S���ׂ��ł���B
�y199�z���̓��e�������Ă���ƁA�ޗǎs���̊w�Z�̎�����ł��ˁI
�����̊w�Z���ɐ�߂�ޗǎs���̊w�Z���͏��Ȃ��̂ł���B���̑�������炸�A�b�܂ꂽ�n�悾�������̎��́A�ޗnj��̈����Ƃ���ł��B���Ȃ��Ă��������B�����グ�Ȃ����āA����V�X�e���̌���Ȃǂ���܂���B
�i�R�j�n�抈��������v���O�����ɂ���B�i�h�Жh�Ƃ̊������A�q�ǂ��̒n�拳��̈�ɂȂ�j
�@����h�Ђ�h�Ɗ����ƁA�X�N�[���K�[�h�̃{�����e�B�A�������P�̂̂��̂ŏI���̂ł͂Ȃ��A�w�Z�����_�ɂ��čs���邱�ƂŁA�q�ǂ���n��ň�Ă�̌��v���O�����ɂł���Ƃ�����āB���̂��߂ɂ�NPO�@�l�ޗǒn��̊w�ѐ��i�@�\�̂悤�Ȓc�̂��K�v�ɂȂ�B
�y221�z2���͎���h�ЌP�����e�n�ōs����悤�ł����A�����n�悳��̂悤�Ȏ�g������Ă���Ƃ���͑��ɂ�����̂ł��傤���H���ЁA����h�Ђ̌����s���킩��܂��A��Ŏ�g�̔��\�����Ă��������Ă͂ǂ��ł��傤�H�q�ǂ������̈��S����ƒn��v���̗��������Ȃ��b�ł��ˁB�����Ɗw�Z�����͂����悤�Ɏv���܂����������̈�ł����̂ˁB
�i�S�j���F����ޗǂ̋������邽�߂̐��E�I�ȃl�b�g���[�N�����B
�@���E��Y�������ɗL����ޗnj��́A���̃��\�[�X�����p�������F���鋳��J���L�����������邱�Ƃ��o����B���̂��߂ɂ͓ޗnj����̋�����q�ǂ��������A���E�̐��E��Y��L����s�s�̋�����q�ǂ������ƌ��Ԃ��Ƃ��A�n��w�K�𐄐i���铮�@�t���ƂȂ�B
�y200�z�����E�Ƃ��̕���ɉ�����l�B��S���E�I�Ɍ��т���ƌ����v���W�F�N�g������܂��B���܂��܍��N�̎�v�e�[�}�����番��ɂȂ��Ă���܂��B�E�E�E�o���̊�{�I���ӂ�������A�����̉\���͂���Ƌ߂Â��Ǝv���܂���B
�R�D�����̊T�����o�߂Ƙ_�_��
2007�N10���`2008�N3���̘_�_
�u�q�ǂ�����Ă邽�߂́A�ƒ�A�w�Z�A�n��̋����v�Ƃ����e�[�}�ŋ��������c���ł����A��܂��ɉ��L�̂悤�ȋc�_�����킳�ꂽ�B
�i�P�j�n��̎�g
�n��̎�g�̃��|�[�g�����ƂɁA�n��Ŏq�ǂ�����Ă�Ƃ͋�̓I�ɂǂ��������Ƃ����l�������B
1)�h�Жh�ƒn�抈�����w�Z���犈���ɂ���������
�y221�z2���͎���h�ЌP�����e�n�ōs����悤�ł����A�����n�悳��̂悤�Ȏ�g������Ă���Ƃ���͑��ɂ�����̂ł��傤���H���ЁA����h�Ђ̌����s���킩��܂��A��Ŏ�g�̔��\�����Ă��������Ă͂ǂ��ł��傤�H�q�ǂ������̈��S����ƒn��v���̗��������Ȃ��b�ł��ˁB�����Ɗw�Z�����͂����悤�Ɏv���܂����������̈�ł����̂ˁB
�y234�z�~�o�P���ł̓X�g�[���[���l���A�|�ꂽ�؍ނ̉��~���ɂȂ����l�`�������o���^���J�[�ɏ悹�ċ~�}�Ԃ܂ʼn^�Ԃ܂ł��s���܂������A�~�}�Ԃɂ͏悹�Ȃ��ʼn��ɒu�������ŏI���܂����B
�l�`�̎���ɂ�1�N���̎q�����S�z�����Ɋ��`�����肵�Ă����̂ŁA�ǂ������̂��Ɛ����|�����Ƃ���A���̐l�`���������ƌ����܂����̂ŁA���N���g�����炠�����Ȃ��Ɛ��������A��ċA���Ăǂ�����̂��Ɛq�˂�ƁA���ꂢ�ɐ���ĉ�������������Ƃ̎��ŁA�ł͐l�`�Ǝʐ^���B���ē͂��Ă����邩�炻��ʼn䖝���Ă���܂����Ɛq�˂��Ƃ����������̂ŁA���O���F�B�������ĎB�e�����܂����B��������Ȏq���̐S�͉���Ȃ��ꍇ�������ł��B
�i�Q�j�w�Z�̎�g
�w�Z�̎�g�̃��|�[�g�����ƂɁA�n��Ƌ��͂ł����̓I�ȕ������@�͂Ȃɂ����l�������B
1)�w�Z�x���n��{���̐�s����
�y243�z�����Z���搶�������[�����|�[�g�����J����Ă��܂��B
���w�Z�x���{���̌��ʁi�y�j�����q���j
���J���L�������Ґ��i���Ƃ̍H�v�j
���e���r�����̐����i�ƒ���^�j
��̓I�ȓ��e�ŋ������䂩��܂��B
�����������H�̏�A�������̎�g�̎Q�l�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤�����
http://www.wadachu.info/data/fujihara_report_070714.pdf
�y188�z�搶�����ƒ���⋳���s����Q���Ă�����̂́A�ǂ��łł������܂����A�u�ł͂ǂ����邩�H�v�ƂȂ�ƁA�藧�Ă��Ȃ��Ȃ�܂���ˁB
���̈Ӗ��ŁA�ƒ�Ƌ��Ɋw�K�K���Ǝ��Ɖ��P�s���Ď��g�݂���Ă���H���s���w�Z����̒���_�ƁA���̓w�͓͂��M���ׂ����̂�����̂��킩��܂����B
�i�R�jPTA�̎�g
PTA�̎�g�̃��|�[�g�����ƂɁA�w�Z���T�|�[�g�ł����̓I�ȕ������@�͂Ȃɂ����l�������B
�b�������܂���ł����B
�i�S�j�w�Z�ƒn��̋���
�w�Z�ƒn��̋������H�����ƂɁA�n��Ƌ��͂ł����̓I�ȕ������@�͂Ȃɂ����l�������B
1)�n��̊����Ɗw�Z�ł̋����ڑ�������IT�̊��p
�y86�z�ޗnj��Ɠ����悤�ɎR�ԑ����������Q�N�O����IT�l�b�g���g���Č��Ǝ��̋��ʃe�X�g���e�w�Z�ɔz�M���Ď��{���Ă��������ł��B
IT���p�������g�b�v�̌��ʂłȂ��ł��傤���A�x��Ă���u����̏�v�i�ޗnj��͓��oBP�БS�������Ńr������O�Ԗځj���x���A�b�v�̂��ߋ���ψ��IT���p����𗧂��グ�Ă͂ǂ��ł��傤���B
�y87�z�����A���̃j���[�X�����܂����B����ψ�����S�ɂȂ��āA����IT���p�Ɏ��g�݁A�搶���̕��S���y�������邱�Ƃɂ��Ȃ����Ă���Ƃ̂��Ƃł����B�uIT���p����v�����З����グ�������̂ł��ˁB����́A�S���I�ɍs�����ƂɌ��ʂ�������̂Ǝv���܂��̂ŁA���̋���ψ����A���猤�����Ȃǂł̎��g�݂ɂȂ�̂ł��傤���B
2)�w�Z�n��x���{���̉^�c�ɂ���
�y178�z������ׂĂł͂Ȃ��Ǝv���܂����A�w�Z�x���{�������̂悤�Ȍ`�œ����Ă��邱�ƂɎ��]�������܂��B���������ɂ��Ă��A������v�͌������w�Z�ɏm�̍u�t���L���ňꕔ�̐��k�ɓ��ʂȎ��Ƃ����邱�Ƃ���h������e���́A����̌�����̂��肩���ɗǂ��e����^����̂��ǂ����ɂ������Ă���Ǝv���Ă��܂��B
3)�����𐄐i����d�g�Ƃ��ẴR�[�f�B�l�[�^�[��t�@�V���e�[�^�[���x
�y118�z���
�^�c�`�ԁF
�E�g�D�F�s���~�b�g�^����l�b�g���[�N�^�ցE���ƁF�搶�̕����^���烏�[�N�V���b�v�^��
�}�l�W�����g�F
���t�̂��C�A���̒������ނɂ���A���k�̂��C�A�n�����������
���̂悤�Ȏ��g�݂́A���L���o�����K�v�ł���A����E�����ł͓���̂ł͂Ȃ����Ɗ����܂����B����I����A���̒n���Z��̏����w�Z�̍Z���搶�ɉ���Ă݂܂����B���낢��Ɖۑ肪���邪�A�o����Ƃ��납���g��ł݂����Ƃ̂��Ƃł����B�搶���̂��C�A���z�̓]���Ɋ��҂��A�S����n��Z���̐ϋɓI�Ȏx���ɎQ���������Ǝv���܂����B
�y2�z���̂Ȃ��������Ă��������̂ŁA�@��邲�Ƃɋ��͂��Ă������������ȕ��ɂ͂��b�����āA�ǂ��l�̗ւ�����悤�y����̂���Œn���ɂ������Ă���܂��B
�ǂ̕����ŏ��́u���ꉽ�H�v�Ƃ��������ł����A���ɂ͑O�����Ȕ��������Ă��������������܂����A�l���Љ�Ă���������������܂��B
�y109�z������l�b�g�f�B���x����4�l�̃L�[�p�[�\��
�i�P�j�w�Z�R�[�f�B�l�[�^�[
�@�w�Z���̑����Ƃ��ē��O�̒����̗v��S���A���E���̍��ӌ`�����s�����[�_�[�V�b�v���Ƃ��āA�\���ɋ���I���ʂ��ł���悤���E���Ă��s�����B
�i�Q�j�n��R�[�f�B�l�[�^�[
�@�ی�҂�n��Z���ɑ��鑋���ƂȂ��āA�����̒n��c�̂Ƃ̘A�g�𑣂��A���s�ψ���ɂ����Ď哱�I�Ȗ������ʂ����Ċ���A�g�̂Ƃ�܂Ƃߖ��B
�i�R�j�Z�p�R�[�f�B�l�[�^�[
�@�v�����Ԃ�H���{�����e�B�A���痊���Ȃ���A�����������瓖���܂ł̍H���̎w���E�ďC���s����
�i�S�j�����R�[�f�B�l�[�^�[
�@�L�x�Ȍo���Ƌ�����Ƃ𑣂��_��Ȕ��z�ƍs���͂������A�S�̒�����O�������̋�����
�i�T�j�V���ȃA�C�f�A
�ƒ�E�w�Z�E�n��Ƌ��͂ł����̓I�ȕ������@�͂Ȃɂ��A����ɂ��ܕK�v�Ȃ��Ƃ��l�������B
1)�n��������������鋳��̃A�C�f�A
�y168�z�@�ޗǏ��q��̍ݍZ���⑲�Ɛ��ɔ��Έӌ�������̂ł�����A�ޗǏ��q��w����n�݂��Ă��Ηǂ��Ǝv���܂��B�ޗǏ��q��̉��v�Ȃ����ēޗnj��̔��W�͂���܂���B�ޗnj��ɂ́A�����̑�����w���Ȃ��̂ł���I�ޗnj��̋����i����ŊJ���܂��傤�I�ޗnj��̑�w����ɂ��Đ^���ɍl���܂��傤�B
�y37�z��Ƃɂ��q�ǂ�����
����������쏊�F�u�ƒ닳��v���c������Ă���B���ŁF�u�Ȋw����v���ʼnȊw�قŎ��{�B
�����d��F�u��������v�~���[�W�A�����Ŏ��{�B�V���[�v�F�u������v�o�O�������{�B
�J�V�I�@�u�R���s���[�^����v
�����͂��Ԃ�A�e��ƓƎ��̔��f�ōs���Ă��邱�ƂƎv���܂��B�ޗnj��̊e��Ƃ��ǂ̂悤�炳��Ă���̂��́A���͂���܂���B
�t�ɍl����Ɗw�Z���瑤�ŃJ���L���������Ă��Č�����Ƃ̋��͂�ƌ����l�������邩���m��܂���ˁB
�y240�z�ޗǒn��̊w�ѐ��i�@�\�̃z�[���y�[�W��q�����܂����B
http://www.nara-e.net/chiiki-manabi/
�|�C���g�߂Ă������Ƃ́A�q�ǂ��ɂƂ��Č��\�͂��݂ɂȂ�悤�ł��B���������ꂾ��������Ƃ��������ɂ��Ȃ�܂����A���Ղ�H���d�g�݂�����̂́A�ƂĂ������Ǝv���܂��B
���낢��Ȓc�̂������Ă���v���O�����������ɎQ������A�q�ǂ��������o���o���ɎQ�����Ă���v���O�������A�|�C���g�v���O�����Ƃ��ēo�^�������Ă��Ƃł���ˁB�q�ǂ������̑̌��̏��@��|�C���g�Ōq����A�|�C���g�����܂��Ă����Ƃ������@�t������A�����Ƃ����Ȏ����������Ƃ������@�����܂�Ă���悤�Ȋ��Ҋ�������܂��B
�S�D����
1)�w�Z�x���n��{���ݒu���ǂ̂悤�ɐi�s���Ă���Ƃ������A���^�C���ȏ���ł����B
2)�w�Z�ƒn�悪�������邽�߂̏�L�̎d�g���L���ł��邱�Ƃ��킩�����B
3)�n��̃��\�[�X�����p���邽�߂̎d�|���Ƃ���NPO�@�l�ޗǒn��̊w�ѐ��i�@�\���a�������B
�T�D�ۑ�
1)��c���ւ̑S�̂̎Q���Ґ��������邽�ߎ��H�Z�Ƀ��|�[�g�Q����v������K�v������B
2)�ȒP�Ɋw�Z�����PTA����̈ӌ����Љ�ł���悤�ɂ�����@����������K�v������B
3)�w�Z�]���⌧���̊w�Z�ł̋��犈���̓I�m�ȏ��M�o����悤�Ɍ�������K�v������B
�U�D������
�����P�X�N�x��ʂ����e�[�}�Ƃ��đI�ꂽ�u����v�ɂ��āA���Ɍ����w�Z�̋���ɘb����i�荞�ݒ�́A�w�Z������v�̒��ł��n��Z���̊w�Z�Q�����傫�ȃg�����h�ɂȂ��Ă���B�w�Z�]�c�������قڑS�Z�œ�������A�n��ɊJ���ꂽ�w�Z�Â���Ƃ����l������w�Z�]���̐��i�ɂ��Ă�����H���ƂȂ��Ă��邪�A���̖{�i�I�Ȏ��H�͂��ꂩ��̎�g�ɂ��B�u�w�Z�v�̂������ɂ��ē��c�p�T�͂��̒����u������v�v-��������̊w�Z�Â���-�i��g�V���j�ɂ����āA���̂悤�Ɏw�E���Ă���B�u�܂�A�w�Z�͒n��̐l�X�ɂƂ��ċ������̊�ՂƂ��đ��݂��Ă���Ƃ������Ƃł���B���܂��܂Ȋ��������ɂ��A�v���◘�Q���Ԃ������A���ʂ̌o����~�ς��A���ʂ̎v���o�ƈ�������ފ�ՁA�����I�������̊j�Ƃ��đ��݂��Ă���B��P4���v�Ƃ����̂ł���B����20�N�x����́A�w�Z�x���n��{����ݒu����Ƃ����{�ł��o����A�����ł�62�ӏ��ł̉^�c��ڎw���Ă��邱�̐ߖڂ̎����ɁA���Y��c���ł̋c�_���A�����ւ̌����w�Z�̋��犈���Q���ւ̊S�����N���A�n��������Č�������㉟�����Ă������߂̋�̓I�Ȋ������l�������Ƃ����[���̈�Ƃ��Ĉʒu�t����ꂽ���Ƃ͈Ӌ`�̂�����̂Ǝv����B
�@�R�[�f�B�l�[�^�[�Ƃ��Ă̔z���́A�c�_���������Ȃ��悤���������邱�Ƃł������B���̂��߂̎�@�Ƃ���RVPDCA�}�l�W�����g�T�C�N������c�̐i�s�ɓ��������B����́u���O�v���m�F���邱�Ƃ��N�_�ɁA�����c������R�i���T�[�`�j�A����̔c�����琶�܂�鋁�߂�p��V�i�r�W�����j�A���{���邽�߂̌v��P�i�v�����j�A�v��̎��{D�i�h�D�[�j���{��������C�i�`�F�b�N�j�A�����琶�܂�鎟�̎�gA�i�A�N�V�����j�Ƃ����T�C�N�����c�_�̊�ɂ��邱�Ƃ�S�|���A�܂������b�����Ɏ��H����ɂ������̂ɂ����B����ɂ����ẮA���g�݂��w�Z�APTA�A�n��A�����A�ƕ��ނ��Ȃ���u���̈ӌ��͂ǂ̕���̈ӌ����v�Ƃ����S�̂̒��ł̈ʒu�t�����A�{���҂���ɔc���ł���悤�Ɏd�������s�Ȃ����B����͓r������̋c�_�ւ̎Q���ł��A�S�̂����ʂ����Ƃ��o���āA�ǂ̋c�_�ɎQ�����邩��I�����₷������Ƃ����Ӑ}���������B�O���̔��ȂŁA�S�̂Ƃ��ēd�q��c���ւ̏������ݎQ���҂��L����Ȃ��������߁A�s���葽���̌�����Ώۂɂ����d�q��c���̉�c�^�c�̓����Ɋ������B���e�ɂ��ẮA�w�Z�̋��犈���̎��H���قƂ�ǒm���Ă��Ȃ����߂ɏ������ނ��Ƃ��o���Ȃ��A�������͏������܂ꂽ���ƂɁA�ӌ����o���Ȃ��Ƃ��������Ƃ��e�����Ă���悤�ɍl�������߁A�t���[�Ɉӌ��\�����ł���u�V���ȃA�C�f�A�v�̕��ނ�݂����B�܂��R�[�f�B�l�[�^�[�̊�{���j�Ƃ��āu�c�_�����H�ɂȂ���v���Ƃ�ڕW�Ƃ������߁A���n���|�[�g����u�y���W�z�w�Z�ւ������I�v��ݒ肵�A�c�_�ւ̎Q���҂��w�Z�֑����^�ԋ@��ɂȂ�悤�ɍH�v�������B�����������̑����݂͂��Ȃ��������A�c�_�ŏo���ꂽ�ӌ��͋�̓I�ł���A���[�����̂ƂȂ��Ă���悤�Ɏv����B���Ɋw�Z�x���n��{���ɕK�v�Ƃ����v����ۑ�A�n��̊������ǂ̂悤�Ɏq�ǂ�����Ă�Ƃ������ƂɌq�����Ă��邩�A���̂��߂ɉʂ����w�Z�̖����Ƃ͉����A�w�Z�ƒn��̋����̂�����͂ǂ�����ׂ����A�Љ�ꂽ���H�Ⴉ��ǂ̂悤�Ɋw�Ԃ̂��A�����w�Z�����悭���Ă������߂ɂ͉����K�v�Ƃ���Ă���̂��A�Ƃ��������Ƃ��œ_�����ꂽ�B���悢��w�Z�x���n��{���ݒu�̎�g�������e�n�Ŏn�܂�B���̓d�q��c���̎d�g�݂���蔭�W�I�Ɋ��p����邱�ƂŁA����ɍ������n��ɂ�����q��Ă̋����������铹�������A��l���͂����킹�鋳��R�~���j�e�B�Â���̊����̃m�E�n�E�����L�ł��A�w�Z�����_�ɂ����n��̍Đ��Ɉ���ł��߂Â��Ă������Ƃ�����Ă���B
IV�D�L���A�o�^�E���e�E�A�N�Z�X�W�v
�P�D �d�q��c�̍L���i���{�����L��}�́j
�i�P�j�V�����\�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2��
�i�Q�j�z�[���y�[�W�����N�i�c�́A�@�ցj�@�@�@�@�@�@�@ 10��
�i�R�j���[���}�K�W���i�c�́A�@�ցj�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@6��
�i�S�j�@�֎��^�n���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@10��
�i�T�j�����@�ց@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@4��
�i�U�j�|�X�^�[�i�����{�݁A��ƁA��ʋ@�ցj�@�@�@�@�@144��
�i�V�j�`���V�@�i�����{�݁A��ƁA��ʋ@�ցj�@�@�@�@14602��
�Q�D�d�q��c���@�A�N�Z�X�E���e��
�i�P�j �d�q��c���A�N�Z�X���i2006/11/1�`2008/3/31�j
| �g�b�v�� | 18�� T-�P |
18�� T-�Q |
19�� T-�P |
19�� T-�Q |
19�� T-�R |
19�� T-1 |
19�� T-2 |
19�� T-3 |
|
| 2006/11 | 2991 | 1540 | 982 | ||||||
| 2006/12 | 2556 | 932 | 618 | ||||||
| 2007/01 | 1696 | 786 | 543 | ||||||
| 2007/02 | 1840 | 495 | 288 | ||||||
| 2007/03 | 1995 | 666 | 254 | ||||||
| 18�N�x�� | 11078 | 4419 | 2685 | ||||||
| 2007/04 | 4141 | 290* | 138* | 860 | 691 | 1392 | |||
| 2007/05 | 5282 | 228 | 119 | 1445 | 887 | 2013 | |||
| 2007/06 | 3446 | 135 | 80 | 1084 | 795 | 1589 | |||
| 2007/07 | 3297 | 83 | 56 | 1273 | 1014 | 1682 | |||
| 2007/08 | 3271 | 93 | 53 | 898 | 902 | 1482 | |||
| 2007/09 | 3255 | 84 | 54 | 1107 | 887 | 1821 | |||
| 19�N�x��/ �v |
22702 33780 |
913 5332 |
495 3184 |
6667 | 5176 | 9979 | |||
| 2007/10 | 6834 | 219 | 100 | 220 | 226 | 566 | 2081 | 2073 | 1328 |
| 2007/11 | 3940 | 100 | 70 | 81 | 90 | 415 | 1403 | 1456 | 988 |
| 2007/12 | 2784 | 91 | 65 | 75 | 68 | 398 | 983 | 1093 | 703 |
| 2008/1 | 2995 | 91 | 62 | 72 | 60 | 261 | 1141 | 1221 | 772 |
| 2008/2 | 3013 | 99 | 67 | 63 | 78 | 276 | 1011 | 1151 | 741 |
| 2008/3 | 2790 | 160 | 113 | 112 | 128 | 252 | 867 | 1123 | 800 |
| 19�N���v/ �����v |
22356 56136 |
760 6092 |
477 3661 |
623 7290 |
650 5660 |
2168 11774 |
7486 | 8117 | 5332 |
���@���P�ʂ̃A�N�Z�X���̐���
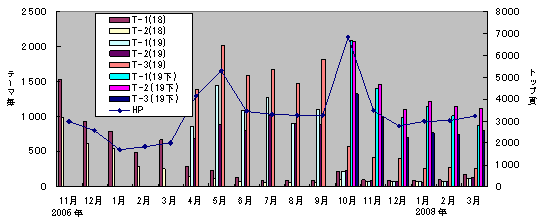
�i�Q�j���ʓo�^�Ґ��i2006/10/1-2008/3/31�j
| 18���� | 19��� | 07/10 | 07/11 | 07/12 | 08/01 | 08/02 | 08/03 | 19���� | �v |
|
| �o�^�� | 60 | 65 | 15 | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 | 37 | 162 |
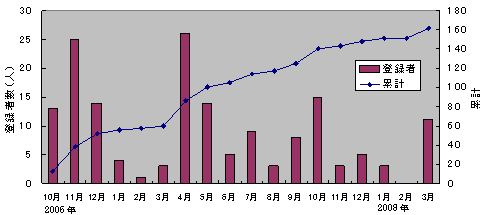
�i�R�j���ʓ��e���i2006/11/1-2008/3/31�j
| �N�� | 18�� /T1 |
18�� /T2 |
19�� /T1 |
19�� /T2 |
19�� /T3 |
19�� /T1 |
19�� /T2 |
19�� /T3 |
���v |
| 2006/11 | 24 | 15 | 39 |
||||||
| 2006/12 | 29 | 19 | 48 |
||||||
| 2007/01 | 31 | 14 | 45 |
||||||
| 2007/02 | 9 | 9 | 18 |
||||||
| 2007/03 | 31 | 4 | 35 |
||||||
| 18�N�x�� | 124 | 61 | 185 |
||||||
| 2007/04 | 18 | 47 | 94 | 159 |
|||||
| 2007/05 | 27 | 26 | 57 | 110 |
|||||
| 2007/06 | 15 | 40 | 49 | 104 |
|||||
| 2007/07 | 28 | 82 | 81 | 191 |
|||||
| 2007/08 | 15 | 89 | 39 | 143 |
|||||
| 2007/09 | 21 | 76 | 78 | 175 |
|||||
| 19�N�x�� | 124 | 360 | 398 | 882/1067 |
|||||
| 2007/10 | 54 | 52 | 58 | 164 |
|||||
| 2007/11 | 38 | 35 | 68 | 141 |
|||||
| 2007/12 | 22 | 27 | 25 | 74 |
|||||
| 2008/01 | 26 | 42 | 36 | 104 |
|||||
| 2008/02 | 20 | 29 | 51 | 100 |
|||||
| 2008/03 | 14 | 27 | 59 | 100 |
|||||
| 19�N�x�� | 174 | 212 | 297 | 683/1750 |
���@���P�ʂ̓��e���̐���
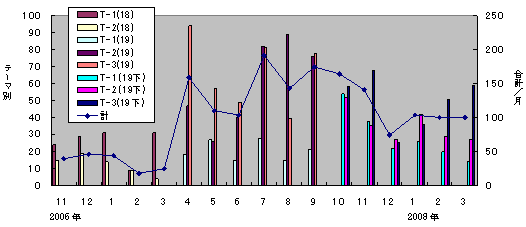
�i�S�j���e�҂̓��e��
���@�o�^�Ґ��F37���i�v�F162���A����18�N11��1���`20�N3��31���j
���@���e�Ґ��F84���i51.8���j
���@���e���F683���i�v�F1750���A����18�N11��1���`20�N3��31���j
���@�A�N�Z�X���F22356���i�v�F56136���A����18�N11��1���`20�N3��31���j
���@�������5�l�̓��e���F332���i48.6���j�@���@�������10�l�̓��e���F468���i68.5���j
�y�l�@�z�@�E�o�^�Ґ��̐L�т��݉����Ă����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�o�^�҂œ��e���Ă��������Ă���l�A84�l�i51.8���j�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E���e�����10�l�ŁA2�^3�̓��e�����߂�B
�R�D�d�q��c���̉^�c�ɂ��Ẳ��P
�ۑ�F�@���@�o�^�Ґ��������Ȃ�
�@�@�@�@�@���@���e�҂��Œ艻���Ă���
�@�@���N�x���A���L�̌��ɂ��āA���P���邱�ƂɂȂ����B
�i�P�j�g�b�v�ł̌�����
�@�g�b�v�y�[�W���R��ɂ��A���BOX���E���Ɉړ�����B
�@�@�@�E���ꂼ��̉�c���g�b�v�ŏ��BOX���E���ɕ\��
�@�@�@�E�c���[�\���ŁA�I������Ă���^�C�g����ڗ��悤�ɂ���
�i�Q�j�o�^�Ȃǂ��������A�C�y�ɓ��e�ł���悤�ɂ���B
�@�@�l���ɂ��āA�K�{���ڂ����炷���Ƃɂ��A�o�^���₷������B�����A�����A�Z���A�d�b�ԍ��͕K�{����͂Â��B�n���h�����̏d���`�F�b�N�Ɠo�^�m�F�̃��[���A�h���X�����͍Œ���K�v�ł���B�n���h�����A�p�X���[�h�A���[���A�h���X�̕K�{�o�^�͎c���B
�i�R�j���e����A���[���܂ł̎��Ԃ̒Z�k
�@�@�@�E���s2���@���@1��
�i�S�j����e�[�}�i1���j��݂���
V�D�܂Ƃ�
�P�D�S��
�U�����Ԃɘj��A�L�͈͂ŁA�ƒ납��n��ł̂����镪��Ɍ��y�ł��A�M�S�ɐF��Ȋp�x����c�_���s���A�ޗnj��̎����������x�I�m�ɑ��܂����c�_�A�y�ђ�Ă��ł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�e�[�}�P�ł́A6���A�e�[�}�Q�ł�10���A�e�[�}�R�ł�4���A���v20���̒�ĂƂ��Ă܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł����B�܂��A�g�b�v�ł̃A�N�Z�X����22356���ɂȂ�A�����̕��X���{�����Ă��������Ă���B����̌����ۑ�Ƃ��āA�����▯�Ԃɂ����Ēn��̊������ׂ̈Ɏ�g�ނɒl���鍀�ڂł���Ǝv���B���ۂɁA���̓d�q��c���̐��ʂƂ��āA��̓I�e�[�}�Œn�抈����i�߂�NPO��O���[�v���a�����Ă���A�X�ɁA�������A���̂悤�ȋ@�^���������A������܂Ƃ߂郊�[�_�[�����߂���B���̓d�q��c���́A�Θb�ɂ�莖�Ƃ̉肪�o�n�߂ĕY�����n�߂��n��Љ�ŁA��Ăɂ܂Ƃ߂邾���łȂ��A��������H����s���ɂȂ����Ă���B
��Љ�ɂ����āA�����̖�肪�R�ς��钆�ŁA���l�Ȉӌ����t�����N�ɓ��������c�_����Ăł����Ƃ��āA�d�q��c���͍L�������Ƀ��b�Z�[�W��`�B���A�c�_���Č����̈ӌ����W��L���Ȏ�i�ł���B��葽���̌����ւ̗����ƊS�����߁A�����ł������̉�c���Q���҂̌Ăт��������������p�����A��������L���c�_�ł��颂Ȃ猧���d�q��c����ɂ��Ă��������B
�Q�D�ۑ�
�@�@1)�@�S�ʂƂ��āA�Q���o�^�ҁA���e�҂������Ƒ��₵�A���ɁA�����w��Ⴂ�w�̎Q���𑝂₵�A��葽�l�ȋc�_��W�J���邱�Ƃł���B���e�ɎQ������K�v���^�����b�g����������{�K�v�łȂ�B
�@�@2)�@���e�҂́A�o�^�҂̖��ł���B�c��̕��X�ɂ����e���Ă��������铮�@�t�����K�v�ł���B�܂��A��c�����{�����Ă���������ɑ����A�@���ɓ��e�s���Ɍ��т��邩�̍X�Ȃ�H�v���K�v�ł���B
�@�@3)�@���猻�ꂩ��̎Q�������Ȃ������͎̂₵���B�w�Z�����PTA����̈ӌ����C�y�ɕ�����悤�ȕ��@�⋳�猻��Ƃ̏��������ł�����Â��肪�K�v�ł���B
�@�@4)�@�����̒c�̂�g�D�ɂ����̋��L���⋦���̐����Ƃ��n��Z���ɂ�閣�͂���X�Â���ƍs���̋����̐��Ƃ������e�[�}�ɂ��Ă̋c�_���Ȃ���Ȃ������̂͐S�c��Ɏv���B
�@�@5)�@���̉�c���͌��̎��Ƃł���Ȃ���A��ʂɂ͌��̍l����������Ȃ��Ƃ����s��������B���̕��j�Ȃ�l���������ċc�_���邱�Ƃ������Ă��悢�B���ۂɌ��̃g�b�v�̕��X���S�������Ă�����̂��ǂ����S���������Ȃ������B
�R�D���ւ̗v�]
�i�P�j���E���̎Q���ɂ���
�@�@1)�@�W�����̋Ɩ��ɊW���铊�e���������ꍇ�A���Ɏ��{���̎��Ƃɂ��āA���e�҂������m��Ȃ��ꍇ�A�S���ۂ���A����I�ɓ��e�̏Љ�����ė~�����B
�@�@2)�@�S���Ɩ��ƊW�̂Ȃ��E�����A���l�Ƃ��āA�ϋɓI�ɋc�_�ɎQ�������肢�������B
�@�@�@�@�����Ȃǂ̌l���͓o�^�s�p�ƂȂ�A�Ɩ��Ɏx������������Ƃ͂Ȃ��B
�@�@3)�@�������m���c�_���Ă��邱�Ƃɂ��āA�S�����Ƃ̓��e���Ԉ���ē`�����Ă���ꍇ�A���́A����𐳂��Ă��炢�����B
�@�@4)�@�R�����Ɉ�x���炢�͒m������̃��b�Z�[�W����ʐ^�Ƌ��ɉ�c���̃g�b�v�y�[�W�ɍڂ��Ē������͏o���Ȃ����̂��B���̎��ɂ���āA���̃g�b�v�������̐���ϋɓI�ɕ����p�������鎖�����ړ`���A���e�҂̐����傫���L���鎖�ɂ��Ȃ���B�R�[�f�B�l�[�^�[�ɂƂ��Ă��傫�ȗ�݂ɂȂ�B
�i�Q�j�L���ɂ���
�@�@�@�u�Ȃ猧���d�q��c���v�́A�܂��܂��A�����ɒm���Ă��Ȃ��B�`���V�A�|�X�^�[�A���[���}�K�W���A�T�C�g�Ȃǂ𗘗p���āA�L��ɓw�߂Ă��邪�A�F�m�x�͒Ⴂ�B�e�[�}�ɊW���镔�傩��̍L��x�������肢�������B
�i�R�j���̐���ւ̔��f
�@�@���e�҂���́A��Ăɑ��錧�̎��g�݂ɂ��āA�����S�������Ă���B���̊��҂����邩�炱���A���e�𑱂��Ă���B�d�q��c�����p��������ɂ́A��Ăɑ��錧�̑O�����Ȏ��g�ݎp�����K�v�ł���B
�S�D�⑫
�@���@�^�c�ψ���̊J�Ó��F2�������ƂɊJ��
�@�@�@�E��8��^�c�ψ���07�N10��6���@�E��9��^�c�ψ���07�N12��15��
�@�@�@�E��10��^�c�ψ���08�N2��24��
�@���@�R�[�f�B�l�[�^�[��c�F�^�c�ψ���̂Ȃ��u���ɊJ��
�@�@�@�E07�N11��10���@�@�@�E08�N2��2���@�@�@�E08�N3��22��
�Ō�ɁA���̓d�q��c����グ�Ă����������^�c�ψ���̊F�l��A�L���ɂ����͂�����������ƁA�c�́A�l�̕��X�ɐS���犴�Ӑ\���グ�܂��B

