
18年度「なら県民電子会議室」報告書の概要
〜県政について県民同士での意見交換〜
2007年度 4月 13日
NPO法人電子自治体アドバイザークラブ
I.目的
この会議室は、インターネットを活用して県民同士が県政について幅広く議論できる場を提供することにより、県民の県政に関する理解と関心を高めることを目的とする。
II.はじめに
電子会議室は、インターネットのホームページ上に設置した電子掲示板などを使って、参加者が自由に意見を述べ、議論に参加できるため、参加者同士あるいは参加者と県職員が地域の課題について一緒に考えていく新たな県民参画の場として期待されている。
日本の経済・社会は既にサービス中心社会へ移行し、インターネットがそのインフラになって、社会構造の根底が変ってきている。ネットワーク社会が進展するに伴い、一般家庭、企業、地方行政において、もはや、携帯電話、パソコンおよびインターネット、特にネットワークサービスにおける、ブロブ、SNS、電子掲示板等の普及により、個人として、或いは、組織として情報社会に関わるツールとなり、社会発展のために、なくてはならない存在になってきた。「なら県民電子会議室」は、まさに、時代の背景に合った県民の意見交換の場として注目されている。
「なら県民電子会議室」を昨年11月に開設し、2つのテーマについて、5ヶ月に亘って議論を進めてきた。テーマ1(奈良の魅了の大発見)、テーマ2(みんなで取り組む防災対策)について、電子会議室で、議論された概要を報告します。
III.電子会議室の報告
III−1 (テーマ1) 奈良の魅力の大発見
私は奈良県の”これ”をPRしたい!〜奈良の売り、奈良の魅力を情報発信!〜
1.はじめに
奈良のいろんな魅力を、また更なる魅力アップを、奈良の売りをどうPRしますか?について述べていただくことによって、県や各市町村の観光振興策を理解して頂く。また、会議室の成果は今後の施策に反映していただこうと、出来るだけ沢山の人に、いろんな意見や提案を、述べていただこうとの主旨でスタートしました。5ヶ月間の会議室参加者数は23名、会議室での発言数は124件(うち9件が非承認)でした。サブテーマ数は28件でそのうち13件については複数の参加者によって意見や提案が交換されました。
2.提案
1) 正倉院展のありかた; 観光客のリピータを増やすために春と秋の2回の展示,1日の開館時間の延長(朝8時から21時まで)、あるいは常設にして休館日を設けるようにする事。
2) 奈良文房三宝展;どう認知されたのかを調査するために、県内の書道関係者、県内の関連企業、県職員、観光協会会員にアンケートをとり、来年度の展示会に向けた企画作成。
3) 平城の魅力は?; のんびりと,じっくりと、癒しの古都、古寺めぐりや大自然にもふれることの出来るのがならの魅力、環境や自然を破壊せずに、じっくり奈良を味わってもらえる仕組みつくりが必要。宿泊客と日帰り客は1対10ですので、2万円の宿泊客を、2倍にする戦略もありますが、今の日帰り客に2、3千円余分につかってもらう戦略もあり現実的。奈良在住の人と県外の人などのボランティアによる情報提供と情報共有などの仕組みが不可欠。現在も公のホームページで、一方的な情報は提供されていますが、よさが出ていないように思うので改善が必要。
4) 奈良をPR;地域の観光推進に必要なのは観光地のマーケティングであり,人材の育成である。県内各地域の文化遺産や自然を守り、支えている人を見出し、リーダーとして養成する仕組みが必要、各市町村で活躍されているグループをバックアップする仕組み作りが必要。また行政サイドまたは観光協会にて、県内観光スポットの変化情報をリアルに且つ一覧的に紹介して欲しい。
5) 国際交流; 各都市との交流を活発にするために各市町村や旅行会社にも協力していただいて、民の力も発揮できるような検討委員会を作ることを提案します。市民参加型にするためには、担当部門の努力以上に、住民が積極的に行動する必要があります。奈良の自然を壊さず、今の生活を変えず、知的な情報を活用して心のゆとりを広げるイベントが重要と考えます。
6) 平城宮跡事業(平城遷都1300年記念事業);終われば撤去する建物には金をかけない。建物で参加者を囲うのではなく、最近のIT技術を利用し、お金を払った参加者だけ有効な多くの情報を提供することによりバーチャルに囲う方法を考えてほしい。
7) 奈良にいてできる海外文化交流;海外からのホームステイを受け入れる研修会を企画してほしい。
8) 奈良の歴史と現代の融合について;奈良の貴重な遺産を現代と結びつけて紹介をしてゆくべきだ。長い歴史の経緯でどのようになって現代があるのかをパネル、冊子、或いはIT技術を使っての表現とかで、現代とを明確に繋いでいってほしい。
9) 平城宮跡の発掘;県民の総意の下、1300年記念事業協会が中心となって発掘促進の活動をして頂くことを提案します。
3.発言の概略
(1)うまいもの
-
1) 奈良のうまいものや特産品
2) ならのおいしいもの発見
(2) イベント
-
1) 正倉院展のありかた
2) 19年1月7日若草山やまやきです。
3) 奈良検定の受験者!全員集合
4) 第2回奈良文房三宝展に参加しよう
5) 奈良文房三宝展を終えて
6) 訪日外国人受入待遇研修会のご案内
(3) もてなし
-
1) 外国人観光客の対応
2) 外国人でも分かる観光地表示
(4) お気に入りの観光ルート・スポット
-
1) 学研北生駒駅周辺には
2) 山辺の道
3) 二上山の雄岳は、なぜ有料なのですか?
(5) 奈良の魅力
-
1) 奈良の魅力の尺度(平成17年奈良県観光客動態調査結果を含む)
2) 平城の魅力は?
(6) ならをPR
-
1) 観光カリスマ
2) 奈良をPR
3) 奈良県を全国レベルで認知してもらおう
(7) 国際交流と住民参加
-
1) 世界のなかのの奈良
2) 奈良でいてできる海外文化交流
(8) 新たな奈良の魅力の創造
-
1) 奈良の歴史と現代の融合について
2) 奈良の新たなる魅力の創造
3) 平城宮跡の発掘を急げ
4) 奈良の観光資源
4.所感
古寺や旧跡,文化遺産や伝統工芸、美しい自然に恵まれた環境,おいしい物や特産品など、その魅力の情報は多く、結果的に改めて語られることは少なかった。しかし観光産業に尽力し、伝統を守り,ボランティアや国際・広域交流をやっている沢山の人々のお陰で、奈良の観光が維持発展、更に奈良を訪れた人に,もう一度来たいと思っていただいているのは素晴らしいことだと再認識しました。課題は、会議室の参加者の皆様から指摘されていますように、豊かな資源に安住することなく、日本中いや世界中の人々とこの資源を子孫にわたって共有する新しいことに挑戦しているか、あわせて、奈良県の産業・経済・教育・文化・社会全般について活性化されているか、ということだったと思います。この課題を克服していくことが新たな魅力アップに繋がっていくのだと思います。
またこのテーマ設定でもありますが,県民のもっと多くの人が観光大使になりきって、“自信をもってPR”できているか、観光客数は奈良の魅力の尺度ではなく、“自信をもってPR”出来たかの尺度だと考えると、残念ながらPR力がまだまだ弱いと思いました。
最後まで観光産業に従事している方々や若い人や女性の参加が少なかったのは残念ですが、奈良の魅力や、魅力アップについて新しい取り組み提案や仕組み作りについての、貴重なご意見、ご提案を広範囲にいただきました。これらが『21世紀観光戦略』の今後の各施策の具体化を図る段階で是非とも生かされることを望みます。
反省点として、県や各市町村の施策や方針発表が各HPで紹介されているにもかかわらず外れた議論が一部有ったり、疑問点が残ったものもあり、予め紹介内容を把握するとか、適宜その内容と同期を図るとかの工夫があればもっと会議室を活性化できたのではないかと思っています。4月以降も観光に関連するテーマが設定されるのであれば、今回提起された問題点がより一層深耕され、広がっていくことを期待します。
III−2.みんなで取り組む防災対策
〜自分たちでできる防災対策について話し合う〜
1.会議室の趣旨
身近にできる住宅・建築物の耐震対策や家庭における防災対策(防災グッズなど)の紹介と地域防災力の向上について、自主防災組織、防災イベント、施設(近所の避難所、消火栓等など)などの紹介をする。またこれからの良い方法、企画などを提案する。さらに震災時の連絡方法や帰宅困難者支援対策について意見を交換する。
2.投稿タイトル(大項目) 24項目
・知って得する講座「防災に活かす知恵と心構え」
・第2回目 自主防災・防犯訓練
・災害時の安全確認用掲示板
・県の防災訓練
・各種訓練の広報用テープの吹込みを小学校にお願いしました
・奈良の災害は?
・近隣の災害情報提供について
・自治会で『迷惑駐車をなくそう運動』を実施しています
・自分でできる災害対策
・災害後の被災者達に配られる物資の不公平を無くすには
・安全・安心について
・防災カレッジ
・「炊き出し訓練」実施します〜
・奈良は暗い道が多いです
・ライフラインの災害安全性について
・地震発生から約2分後に震度速報、約3分後には津波予報が発表されます
・地震観測では、地震計と震度計が使われています
・地震・津波と安全・安心 「地震観測と地震情報・津波予報」 の概要
・奈良県の昭和・平成年代における主な災害(奈良県地域防災計画より抜粋)
・地区自主防災会議について
・防災訓練
・平成18年度奈良県防災気象講演会に参加しました
・備えあれば憂いなし!
項目数の多いスレッド
(1) 災害時の安全確認用掲示板
自治体によっては、既に、ブロブを立ち上げて活動しているところもあるようです。
(2) 奈良の災害は?
奈良には、私たちが震え上がる災害は非常に少ないと思います。これが、県民の本音ではないでしょうか?奈良県は、決して災害の少ない地域ではありません。4年程前に、奈良県を南北に縦走した台風がありました。
3.投稿の内容
「防災対策」というテーマそのものが非常に大きく、従がって投稿も多岐にわたっている。しかし、それぞれの項目について深く議論するには至っていない。もうすこし議論する期間が必要ではないかと思われる。
いくつかの投稿例
・やっぱ、確実なのが、回覧板です。内容をどこまで読んでもらっているかわかりませんが。
・防災ブログの活用理由としては、対外的な情報発信力です!
・物資を送ることが被災地の人たちに役に立つのかどうか、テレビでも報道されていますが、
送るほうが必要と思っても役に立つとは限らないと伝えられています。
・これから、局地的な集中豪雨被害が多くなる可能性があるので、住民にリアルタイムに
情報提供が必要と思います。
・大きな災害情報も必要ですが、生活に支障が起きる身近な災害情報提供の仕組みつくりを
提案します。
・この掲示板(ある地域の)は出会い系の書き込みに妨害される為削除いたしました。
・ここで感じたことは、一般的に災害に対する認識が希薄であるので、何か利害に結び付けた
活動がよいのではないかと思います。
4.提案
(1) 「みんなで取り組む防災対策」というテーマからは、「行政の取り組みはともかく、住民の目線で防災対策を話し会ってほしい」との意図が感じられる。そうだとしても、防災については行政を抜きには語ることができず、せめて防災について行政は何ができ、地域、個人にはなにを期待するのかを明らかにしてから電子会議室での会議を開始する必要があると思える。
(2) 特定の人(例えば地区防災に関係している人)の関心は高い。また、行政職員のこの分野の人の意識も相当高い。しかしながら、これらが有機的に結合するまでには至っていない。一つの方策として今後これらの地域の防災への取り組みを連携させ、シナージー効果を発揮できるようにインターネットを活用するのがよいと思われる。
すなわち、インターネットの防災ネットをいきなり住民レベルまで拡大せず、自治会などの地域の中間段階のネットをまず構築し、その後住民レベルまで拡大するのがよいと思われる。
IV.登録・投稿・アクセス集計
(1) アクセス件数
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| アクセス数(トップ頁) | 2991 | 2556 | 1696 | 1840 | 1995 | 11058 |
| テーマ1 | 1540 | 932 | 786 | 495 | 666 | 4419 |
| テーマ2 | 982 | 618 | 543 | 288 | 254 | 2684 |
| 登録者数 | 39 | 14 | 5 | 3 | 5 | 66 |
| 投稿件数 | 39 | 48 | 44 | 18 | 25 | 185 |
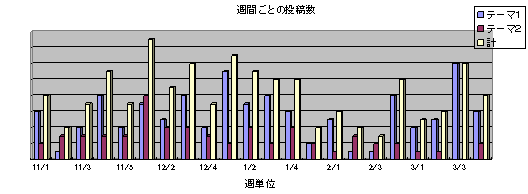
V.まとめ
5ヶ月間における電子会議室のアクセス・投稿状況は、アクセス数(トップページ)が11058件、登録者数が66名、投稿者数が36名、投稿件数が185件 (平均 約5件/1人、 約37件/月)であった。初めての試みとしては、評価のできる内容であったと思われる。内容としては、真面目な投稿ばかりで、テーマ1では、9項目、テーマ2では、2項目にまとめて提案することができた。しかし、テーマの選定はどうであったか、広報活動は十分であったか、運営の方法はどうであったか等を総括して、更に、よりより電子会議室にするためには、いくつかの課題を解決する施策が必要である。
特に、アクセス数を増やす施策、登録・投稿者を増やす施策が必要である。運営委員会のメンバーとして、テーマに関係する業界や地域で活動されている方の参加や、コーディネーターとして、テーマに経験のある方にお願いして、盛り上がりのある電子会議室にいたします。

