
奈良県総務部知事公室広報・広聴課 様
20年度上期「なら県民電子会議室」の報告書
〜県政について県民同士での意見交換〜
2008年度10月4日
NPO法人電子自治体アドバイザークラブ
理事長 奥家孝彦

【目 次】
I. はじめに
II. 提言
III.電子会議室の報告
III-1 (テーマ1) :まほろばからストップ温暖化を考える
〜これなら奈良、奈良ならこれだ、ストップ温暖化〜
コーディネーター:坪内信行
III-2 (テーマ2) :世界に開かれた奈良づくり
〜平城遷都1300年祭を契機に国内外から誘客できるまちづくり〜
コーディネーター:遠藤英樹
III-3(テーマ3):うまいものがある食の風土づくり
〜身近なうまいもの情報から奈良の食文化まで幅広く語り合おう〜
コーディネーター:木村隆志
IV−4(テーマ4):奈良に泊まってもらうには
〜こんなにある奈良の隠れ観光スポット、お祭り、みやげもの〜
コーディネーター:金田充史
IV.広報活動、登録・投稿・アクセス集計
V. まとめ
【添付資料】
1.20年度上期運営委員会委員
2.な20年度上期「ら県民電子会議室」ポスター
I.はじめに
(1)目的
この電子会議室は、インターネットを活用して県民同士が県政について幅広く議論できる場を提供することにより、県民の県政に関する理解と関心を高めることを目的とする。
(2)電子会議室に期待するもの
奈良県の実態を統計に立脚した指標を見ると、
・県内就業者比率は約71%、全国最下位
・県内消費率は約82%、同45位
・県民一人当たりの個人県民税額は、全国6位なのに、法人二税額が、43位
かって製造業は、賃金の安い東南アジアや中国に流れた。その結果、それらの国は確実に豊になる。資本が世界的規模のデジタルネットワークで流れ、仕事が流れて国の間の豊かさも、格差は減っている。減った分の格差は国内に向かう。奈良県はどうであろうか。デジタル化の流れの中で、場所に拘束できるメリットが無い限り、企業や工場は県外に逃げ、県の財政は潤わない。地域の活性化のために、奈良にどんな産業を育成すればよいか、まだ見えていない。
人は物理的なだけでなく、文化的な場所としての地域に縛り付けられている。場所のもつ本来的な強みとして、奈良の強みを真剣に考えなければならない。
奈良県の中小企業の他に、いまや、NPO法人も約280団体になり、地域活性化の大きな担い手になってきている。それで、どうすればいいの? 県民の目にみえるメリットの追求や、情報化の時代に相応しいシステムづくりや情報の共有化などに努力することが重要である。
情報化社会において、多くの問題が山積する中で、多様な意見をフランクに投げかけ議論し提案できる場として、電子会議室は広く県民にメッセージを伝達し、議論して県民の意見を集約する有効な手段である。より多くの県民への理解と関心を高め、少しでも多くの会議室参加者の呼びかけを引き続き継続し、今後も幅広く議論できる「なら県民電子会議室」にしていきたい。
II.提言
各電子会議室でまとめた「提案」の項目を提言として項目のみ下記する。詳しくは、後記する各電子会議室の報告をご参照いただきたい。
1.T−1:まほろばからストップ温暖化を考える
〜これなら奈良、奈良ならこれだ、ストップ温暖化〜
前期に引き続き地球気候変動、一般には地球温暖化防止に関する議論を行った。前期の流れを受けて、その延長線から会議を進め、「奈良県ストップ温暖化防止条例」を念頭に置き、奈良県民の声で作られる、他県にない条例(案)を提案としてまとめた。以下に条例案を記載する。
条例の題目:奈良県悠久の歴史と環境を未来につなぐためのストップ温暖化条例
・他に提案された題目:「なら低炭素社会条例」
「みんなでストップ温暖化条例」
「あなたも参加ストップ温暖化条例」
「何ができますか?ストップ温暖化条例」
序 文
奈良県民は、奈良悠久の歴史と地球環境を過去から未来につなぐため、人類共通の問題である地球温暖化の防止に向けて、われわれ多くの市民の知恵と熱い情熱と強い意志をもって、ここに条例を作成した。
第1条 奈良の森林保護・育成と木材(バイオマス)資源の積極的な活用をはかる。
第2条 奈良に潜在する自然エネルギーを自然と調和した形で利用する。
第3条 都市部での温暖化防止対策の対応を強化する。
第4条 マイカーに関して適正な利用を促進する。
第5条 自転車利用への優遇措置を図り、利用の拡大に努める。
第6条 公共交通機関とその交通システムを充実、利用者の利便と費用の負担を軽減する。
第7条 温暖化防止の啓蒙と教育の充実をはかり、定期的に教育を受ける機会を設ける。
第8条 企業、行政、学校その他の団体は地球温暖化にかかわる全ての情報が機を逸しない範囲で定期的に公表、公開しなければならない。
第9条 温暖化防止のための推進体制を確立し、運用する。
第10条 奈良の生活、文化に根付いた温暖化防止活動の推奨をはかる。
第11条 適正な環境税の導入とその有効的な利用をはかる。
第付録条 遷都1300年イベントへの地球温暖化防止対策の強化実施を行う。
2.T−2 :世界に開かれた奈良づくり
〜平城遷都1300年祭を契機に国内外から誘客できるまちづくり〜
(1)平城遷都キャラクター:せんとくん、まんとくん、なーむくんを有効活用できる制度整備。
(2)奈良のもてなしの心を醸成させる
①お茶とトイレは、旅行者には必須の要件。そのサービスで観光もてなしの心を育む。
②世界交流の場をつくる。奈良県文化会館の2階、地下に多くの部屋が空いている。
(3)奈良の交通問題渋滞の解消策の提案
①アイデア提案
a)遊びに来るのは電車を利用、b)バスを増発・路線系統の見直し、
c)パーク&バスライド・サイクルライドを充実、d)近郊住民は車で出ない。
③大仏前から近鉄奈良・JR奈良・大安寺・薬師寺(西ノ京)を路面電車で結ぶ。
④観光用の電動路上ミニ列車を走らせる。
⑤案内表示板の改善:駅や電車の表示、市中の道路標示。国土交通省の道路標示など。
⑥近鉄電車への要望:運行者の都合の情報でなく、利用客への情報公開を最優先にする。
⑦奈良県内のJR線と私鉄の在来線を環状線にする?奈良環状線の予定路線。
(4)ウェブを用いた奈良の地域づくり
(5)平城遷都1300年を迎えるまでの、奈良におけるその他の問題点
①安全問題:不審者の排除と安全の徹底という基本を世界に発信できる奈良の価値。
②子どもの遊び場:奈良公園の一角に有料の公園区域を作る。
③「遷都1300年」をPRできる図柄入りの年賀状、かもめーる、一般用ハガキ
④大型ホテル建設のドキュメンタリービデオを残す
⑤奈良のお気に入り風景の選定
⑥なら本選定:奈良の豊かな自然や歴史、文化等について書かれた「なら本」を選定する。
3.T−3 :うまいものがある食の風土づくり
〜身近なうまいもの情報から奈良の食文化まで幅広く語り合おう〜
(1)「素朴で地味ではあるが、誇れる奈良の味はたくさんある。」
(2)「奈良にうまいものあり!」を具体的な食育実践で認知させるべき。
(3)三輪素麺文化は観光資源としても有効で、もっと生かすべきである。
(4)平城京遷都1300年祭のイベントは、一過性ではなく継続できる集客装置として考えるべき、また奈良県全県下も舞台にすべき。
(5)奈良県ブランドのロイヤリティ向上と育成を積極的に行う必要がある
(6)「奈良のうまいもの」の選定は消費者が決めるべき
(7)吉野の割り箸は胸を張って全国に普及するキャンペーンを実施して欲しい。
(8)「奈良にうまいものなし」といわれている現実はPR不足とマーケティング力不足。
(9)県南部に奈良の食文化館を創設して、農業や観光での活性化ができないか。
(10)奈良の土産物は「鹿せんべい」で活性化を。
4.T−4 :奈良に泊まってもらうには
〜こんなにある奈良の隠れ観光スポット、お祭り、みやげもの〜
(1)奈良を楽しい街にすべし
(2)旅行会社に頼らない宿泊政策の実現すべし
(3)宿泊施設は多様な宿泊プランを呈示すべし
・早朝に集まって東大寺の朝の勤行を見る
・春日大社で特別に舞を舞ってもらう
・国立博物館や興福寺国宝舘を繰り上げて開館静かな雰囲気で展示物を見る
・薪で炊いた「茶がゆ」をいただく
・早朝に霊山寺のバラ園を訪ねる 等々
(4)宿泊施設は、泊まって良かった場所の研究をすべし
(5)自分が欲しいと思える名産品を開発すべし
(6)行事・催事を徹底的に広報宣伝すべし
(7)奈良県に真に相応しい宿泊施設は大型ホテルでは無い事を自覚すべし
(8)奈良の販売方法を研究すべし
①テーマ別に分かれた研究意欲の湧く地図の開発
②鹿男をはじめとするロケ場所の広報
③放送ライブラリーの設置・映像資料や写真の一元管理をする場所。
奈良文化会館内に有った、旧奈良県立図書館跡の有効利用を考える
④奈良県観光連盟主催の文化講座にもっと参加して頂く事を考える
⑤奈良にランドオペレーターの必要性を観光関係団体と関連業種に認識すべし
⑥体験メニューを開発すべし
文学・落語・音楽・お能・春日奥山原始林の自然等々
(9)夏休みなどの旅行プランを参考に奈良の楽しみ方を再考すべし
奈良県民が奈良県内で宿泊する様な政策を考える
(10)奈良の観光関連業種は、マーケティングを重要視すべし
III.電子会議室の報告
Ⅲ−1(T−1):まほろばからストップ温暖化を考える
〜これなら奈良、奈良ならこれだ、ストップ温暖化〜
コーディネーター:坪内信行
1.はじめに
前期に引き続き地球気候変動、一般には地球温暖化防止に関する議論を行った。議論は前期においてほとんど煮詰まった状態であり、むしろこの会議室では、前期の流れを受けて、その延長線から会議を進め、「奈良県ストップ温暖化防止条例」を念頭に置き、奈良県民の声で作られる、他県にない条例をアウトプットできることを期待した。
その結果、ストップ温暖化をキーワードに環境に関する種々の意見が展開され、これから奈良県、あるいは奈良の市町村において、議論・制定されるべき地球温暖化防止条例のさきがけとなる議題と議論が展開できたと考える。
2.提案、発言の概要
前述したように「奈良県ストップ温暖化防止条例」を念頭に置いて議論された。そのため、提案として条文形式でまとめアウトプットとした。当然、条文番号を付す以前の議論も踏まえて、それらの意見それぞれを各条項に該当する場所に振り分けた。そのため、この報告書では条例の体裁を整えるため、会議室の議論の条例配列(条文番号)を変更し、多数の同じ主旨を持つ議論(投稿)を主条文のもとにまとめた。さらに、個々の意見として出された議論内容を「・」にて示し、主文の補強ならびに具体的な方法として記載した。このために議論の内容を逸脱しないように、リライトしたことを了解していただきたい。また、実際の条例では文書化にもそれなりのルールがあると考えるが、それらは本会議室の目的、目標とは異なるので細部に触れないことを了解願いたい。
各条文の最後にはコーディネーターとしての意見を述べた。マイノリティーな意見かもしれないが何らかの参考にしていただければ幸いである。
なお、投稿の一つに県職員からの情報提供希望があった。これには投稿の場以外でも対応したが、その後この投稿者からの発言がなかったのは残念である。会議室でも述べたように「この会議室で、良いアイデアをたくさん出して、公知の事実にしておきましょう。」将来、奈良県に条例ができたとき、「あの時の私の意見と同じ内容だね。」と、少し斜に構えて言うのも良いかもしれないと考えている。時代のさきがけを行くには、「燕雀いずくんぞ鴻鵠の志を知らんや」であろう。
以下に条例案を記載する。
条例の題目
奈良県悠久の歴史と環境を未来につなぐためのストップ温暖化条例
・他に提案された題目:「なら低炭素社会条例」
「みんなでストップ温暖化条例」
「あなたも参加ストップ温暖化条例」
「何ができますか?ストップ温暖化条例」
序 文
奈良県民は、奈良悠久の歴史と地球環境を過去から未来につなぐため、人類共通の問題である地球温暖化の防止に向けて、われわれ多くの市民の知恵と熱い情熱と強い意志をもって、ここに条例を作成した。
第1条 奈良の森林保護・育成と木材(バイオマス)資源の積極的な活用をはかる。
・森林の適切な保全と整備の推進及び支援と森林吸収量の実態、森林整備計画の公表
・森林整備をかねた植林技術の継承、海外移転などグローバルな教育
・奈良の物産店でレジ袋不要客への割り箸プレゼントなど、間伐材、端材の利用
・間伐材含む廃木材の燃料利用支援、木材チップの生産とストーブ、ボイラーへの利用
・春日原始林などの自然環境保全
・県産吉野杉等木材利用のエコ木造住宅購入者への支援
・特に中北部の耕作放棄された農地の活用
<コーディネーターコメント>
なんといっても奈良県は森林資源の宝庫である。また、この資源を利用した伝統的工業もあり、これらの利用は、もはや過去のものとなったかも知れない、心の文化を取り戻す「なら資源」になるかもしれない。
森林保全、整備のノウハウはまだ奈良県には十分あると思われる。この技術、技能を海外に向け、県のトップから強い意志と、熱い情熱を持って、世界の人々の琴線を揺り動かすがごとく発信をする。目立たず、即効性は期待できないかもしれないがないが、これらの積み重ねはきわめて有益な運動展開になるはずである。
県内各地、特に山間地域に温泉施設がある。これらは温泉とはいえ加熱して利用している。この加熱に廃木材チップが利用できないであろうか。経済的には議論にもあったように、青森県の状況、そして奈良県の廃棄物税の利用などを合わせると経済的採算が計算できる。もし採算があうなら是非取り入れてみたい。
奈良に来た観光客はレジ袋の代わりに吉野杉の割り箸を受け取る。レジ袋のコストでかなりの部分をまかなえ、全国的な、いや世界的な話題になりそうな予感がする。遷都のイベントで是非取り入れてみたい提案である。
奈良の気候風土から生み出される、たとえば奈良野菜、休耕田こそ、これらいわば現代のビジネスにならない野菜類の栽培に適しているのではないだろうか。市民や学校に委託し、県外国外から個人(家庭)を尋ねてくる訪問客への心のこもったもてなしとして見直されても良いのではないだろうか。
第2条 奈良に潜在する自然エネルギーを自然と調和した形で利用する。
・太陽光発電、風力発電など、自然のエネルギーを利用した発電システムの導入を自然環境に配慮して積極的に進める
・公園の照明や街路灯、公的な施設は太陽光発電システムを採用、或いは併用する
・民間において自然エネルギーの採用を促進するために、また、民家に対して先進例として助成処置を講じる
・ライトアップは自然エネルギーの利用と、休止時間が少なくとも投光時間を上回るようにした間歇照明として見学客を照明時間に誘導し、見学客の感動を促す努力をする
<コーディネーターコメント>
奈良県にもバイオマスエネルギー以外太陽光、風力、水力などの自然エネルギーは多く存在する。潜在的なエネルギー量は知見の範囲にないが、これらを有効的に利用すればかなりのエネルギーは県内でも確保できるようにも考える。
特に県内にはソーラー工場があり、県はこれらの企業とタイアップし県内に多くのソーラー設備を備えた屋根を見かけるようにしたいものである。県としてはこれらの企業に対して税制面で優遇を図ることができるかもしれない。また、余剰電力は電力会社に購入してもらうことになるが、ドイツのように高額で引き取るには国レベルの交渉あるいは法律に頼らなければならない。しかし、奈良県の河川での水力発電と抱き合わせて、電力会社と交渉し、電力引き取り価格のアップが可能ならば今以上に普及するのではないだろうか。
それは、たとえ自然エネルギーであっても大切に利用したいものである。社寺などのライトアップは連続的に照射しているよりも間歇的に行うほうがより感動をもたらすと考えられる。
私たちの文化はその瞬間をめでる感性を持っていた、しかし物質的な豊かさは「惰性的連続」となり、結果、感動をなくし地球温暖化をもたらした。
第3条 都市部での温暖化防止対策の対応を強化する。
・都市部でのビル屋上の緑化をはかると共に、これらに用いる散水は雨水を利用する
・駐車場への緑化をはかる
・自動販売機(主として、加熱、冷却装置を備えた)の設置は、その電力を自然エネルギー起源としたもの、あるいはカーボンオフセットしたエネルギーを用いるもの以外は設置できない
・一定以上の規模の建造物(オフィスビルやマンション等)には、規模に応じて太陽光発電・マイクロ風力発電設備の設置を義務づける
・過度な建築を控え、適正な都市計画を行う
<コーディネーターコメント>
都市部は農村・山間部と違い、地球温暖化への負荷が多いことを理解しなければならない。そのためにも、都市部に住む人々は利便性に比例して、地球温暖化に大きく影響していることを自覚し、きめ細かな防止活動が要求される。建築物にそれらの対策を講じると相当のコストがかかるが、それができない施設、建物は都市に建築できないようにすべきであろう。
そもそも都市の機能とは何であろうか、都市部が農村山間部の資源を搾取する構造になっていないだろうか。かつて大和朝廷が全国から貢物を運ばせたように、現状、奈良の道路はその形であり、さらにこれが東京に続く。地球温暖化を考えるに際して都市とは何であるのか、奈良の南部(山林)と北部をつなぐ道路・交通(車)など、もう少し議論を重ねなければならないと考えられる。
第4条 マイカーに関して適正な利用を促進する。
・奈良県にある事業所はマイカー通勤の実態を把握し、その総距離を年ごとに目標を定めて縮小し、奈良県は目標達成した企業を表彰する
・まるごと1日マイカーを使わない日の設定し、県民に周知する
・アイドリング、駐車時のエンジン停止を義務付ける
・地域の住民以外は通行できないよう通過自動車進入禁止箇所を拡大する
<コーディネーターコメント>
マイカー利用の規制はできないものの、将来炭酸ガスを排出しない車の普及までは何らかの規制を行いたいものである。しかし、現状は運転者の自覚に任せた、自動車利用の抑制をどのように展開すべきかの議論でしかならないのはいたし方がない。
その中で、マイカー通勤の抑制は企業(事業者)がその気になればかなり進むのではないかと考える。たとえば、マイカーの駐車場のコストを考えれば、マイカー通勤者に駐車場の費用を負担させる。あるいは、非マイカー通勤者には相当の手当てを支給する。
奈良県の大多数の企業はマイカー通勤における駐車場の労働協定などはないはずで、地球温暖化が言われる今、このような労働協定を作るべきではないだろうか。それが大企業、あるいは一流企業であればあるほど企業の社会的責任(CSR)としてその重みを増すに違いない。
第5条 自転車利用への優遇措置を図り、利用の拡大に努める。
・自動車優先の社会構造からの脱却のための、自転車などにおける優遇制度の導入
・人と自転車優先の社会的資本の拡充
・公共交通機関に自転車をそのままの形で乗られる交通システムの確立
<コーディネーターコメント>
前条とあいまって、おおいに活用展開を図りたいのは自転車の利用である意見が多く出た。そのために、新たな条項を設けた。コーディネーターも通勤に自転車をよく利用しているが自転車に対する道路のインフラはお粗末な限りである。
新道路交通法によれば自転車は特別な表示がない限り車道の走行が義務付けられている。これは、自転車に乗るものにとっては被害者になり、一方自動車を運転する側に立つと加害者となる恐れがある。言い換えれば、地球温暖化という世界的レベルの問題に、日本の道路交通法と道路整備が全く合致していない、きわめて未熟な状態に今ある。洞爺湖サミットの宣言を本当に実行するなら、道路特定財源を用いて、人・自転車・公共交通(バス、救急車など)を優先した道路の抜本的改修(補修レベルではなく作り変えるぐらい)が必要ではないだろうか。
今、不況に喘ぐ県内土木業者も息をつけると思う。
第6条 公共交通機関とその交通システムを充実、利用者の利便と費用の負担を軽減する。
・地球温暖化防止を念頭に置いた輸送機関と人の移動を考えた新交通システムの開発
・カーボンオフセットバスの導入、税制での優遇措置を図る
・LRTの導入、バストレーン
・人や自転車に優しい道路整備の遅れ(道路交通法と道路実態の矛盾)
・シュア・スペースによる人、自転車、車の共存
・電車、バスなど窓が開けられる構造にする
<コーディネーターコメント>
県内の公共交通機関の主なものはJR西日本、近鉄、奈良交通である。しかし、公共交通機関でありながら、当然経営は民間であり公共性の維持は企業経営の健全性の維持に他ならない。企業は集客の努力をすることは当然だが、どのようにしてこの公共性を維持できるか、難しいが重要な課題である。
特に県内交通の要である奈良交通には、利用の機会を多くもって応援したいものである。
第7条 温暖化防止の啓蒙と教育の充実をはかり、定期的に教育を受ける機会を設ける。
・温暖化防止の学校教育への導入義務化をおこない、小学校で、ゴミ問題や地域の環境を学び・中学生で温暖化や地球の資源について考えるなどの適正なカリキュラムが作成、教育される
・奈良県では高校入試試験に必ず地球温暖化に関する問題が出題される
・企業での温暖化防止教育の義務化を図る
・奈良県、市町村その他関連する職員の採用試験は、高度な地球温暖化に関する試験が行われなければならない
・運転免許更新時、地球温暖化の講習を受けなければ免許は更新されない
・自動車販売者は、販売時に自動車を使用することによる、地球温暖化影響を明確に伝えなければならない
・これらの教育ツール、情報は日本国内にとどまらず。広く各国からも取り寄せ、常に新しいものでなくてはならない
・ドイツなど環境先進国にその事例を学ぶ
<コーディネーターコメント>
地球温暖化の啓蒙は徐々に浸透しつつある。しかし、これらを系統的、組織的に行い、それが習慣つけられること、さらに機会ごとに復習すること、これらの社会的システムが作動してこそ地球温暖化防止活動の効果が目に見えて出てくるものと考えられる。
小学校、中学校の教育に組み込み、それが高校受験で試される。また、公務員は指導的立場を要求され、採用試験にはより高度な温暖化防止の知識と行動が要求される。一般市民には機会があるごとに教育が行われるべきである。
かつて、日本は公害防止立国であった、それが何時しか環境立国ではドイツなどに追い越された?しかし、今でもそのポテンシャルは高い。奈良県でも力のある環境NPOが多数あり、これらとの協働による環境教育の社会的システムを奈良県から濫觴させてはどうだろう。
第8条 企業、行政、学校その他の団体は地球温暖化にかかわる全ての情報が機を逸しない範囲で定期的に公表、公開しなければならない。
・一定規模以上の事業所に、CO2など温室効果ガス排出量の毎年報告・公表、義務化
・電気・ガス事業者に、自治体単位の電力・ガス等の使用量情報公表、義務化。
<コーディネーターコメント>
成果の見える形はいかなる運動でも必要に違いない。計画を作り、実行し、チェックする、そしてステップアップして次の計画、行動に移す。PDCAのCは見落とされやすい。しかし、必要なデーターの積み重ねは継続的な活動に欠かせない。
第9条 温暖化防止のための推進体制を確立し、運用する。
・各市町村での地球温暖化推進計画(自治体区域内の排出実態把握と報告、自治体削減目標、削減達成の為の対策、施策、等の明記)の策定と実践及びフォローを義務化
・行政サイドの推進体制構築
目標の見直し及び目標達成のための措置等の提言を行う、市民の意見を反映できる「ストップ温暖化委員会(仮称)」の設置
それらの実施を含め県行政を横断的に把握し施策及び対策を実施する、独立した「地球温暖化対策局or部(仮称)」の設置
・市民サイドの推進体制構築
温対法に定められた奈良県地球温暖化防止活動推進センターの地球温暖化対策を担う中核的支援組織としての積極支援
県知事委嘱のストップ温暖化推進員への、地球温暖化対策実践をリードする地域の要としての、県、センター及び市町村と連携した支援
地球温暖化対策地域協議会が、地域における地球温暖化対策を担う実践組織として、積極的な取組を推進する役割を果たすことができるよう市町村と連携した支援
<コーディネーターコメント>
県を上げての推進体制つくりはきわめて重要な課題である。しかし、予算面でかなり懸念される。奈良県の地球温暖化に向けての取り組みは、奈良県のおかれた経済レベルと同じ程度ではないであろう。県内の生産レベルが少ないから炭酸ガス排出量も少ない、そのため温暖化防止への取り組みも少ない。このままでは落ち込むばかりである。
思い切って逆をしてみよう。現在の温暖化防止への県の予算は、都道府県中きっと一人当たりの県内総生産と同じ順位(最下位クラス)ぐらいではないだろうか。これを、全国のトップクラスまで予算を上げる。環境立県を宣言し、奈良に住むこと、奈良で働くこと、企業が奈良に工場を作ることがステータスになる。予算面での裏づけのある推進体制がほしいものである。
第10条 奈良の生活、文化に根付いた温暖化防止活動の推奨をはかる。
・太陽の動きに従った自然な生活活動への理解
・奈良は早起きの県「早起きは三文の徳」生活を推奨
・氷室、雪室の標準設置に向けた自然冷房への研究開発
・温暖化が進む中での快適化検討、ウオームビズ、クールビズ
・自転車ライフで自分の町を見直す活動
・地産地消、県内産の野菜や果物を食べ、家庭菜園
・夜型都会人が考えた、世界から失笑を買いそうなイベントへの不参加
・スローライフの推奨
・江戸時代の生活、もったいないなどを踏まえた3R(4R)の実践
<コーディネーターコメント>
奈良県は早起きの県だといわれている。一説には、玄関先で鹿が死んでいると処罰を受けるので早起きをしてそれを確認するとか、このようなネガティブな発想はやめよう。「早起きは三文の徳」徳=得とも書くこともあるらしいが、「徳」にしたい。朝早くお坊さんが托鉢に回る。そのとき三文の徳を施させていただくのが奈良らしい。
暑いときに冷たいものを食す、先人たちはいろいろな物の保存に知恵を出した。氷室など、今一度エネルギー保存の観点から奈良の研究機関で研究をしてみるのも面白いかもしれない。
私たちはつい最近まで太陽の動きと共に寝食を共にしてきた。それがいつの間にか、夜と昼の観念がなくなり、食べ物に季節がなくなり、場所までなくなってきた。
最近は温暖化防止の啓蒙活動に不思議なことがまことしやかに行われる。自然の営みを知らない、自然に逆らった、都会人の傲慢から無理強い、北風と太陽の話を思い出す。
おかしいことに気づかない、変なことが変でなくなる、大変なことになる前ぶれであろう。
第11条 適正な環境税の導入とその有効的な利用をはかる。
・独自に環境税を導入し、クリーンエネルギーの積極的な導入
・排出権取引
・非カーボンオフセット形自動販売機への課税
<コーディネーターコメント>
排出権取引と環境税は地球温暖化防止にさいして必ず議論をしておかなければならないテーマであろう。
奈良県の森林は是非排出権の権利として都市部に売り、その収入を世界の緑化に役立て奈良の太っ腹を見せよう。また、環境税も最初は自動販売機といった特定のものを対象に他府県に先駆けて行うのはいかがであろうか。環境先進県に名乗りを上げようとすればそれなりのリスクは伴う。しかし、その見返りは日本、世界から注目の的になり、結果的に潤うはずである。奈良の名産、大和郡山は金魚で有名だが、金魚の糞にはなりたくない。
失敗を恐れては何も進まない、まさに決断のときである。
第付録条 遷都1300年イベントへの地球温暖化防止対策の強化実施を行う。
・すべてのイベントにおいても環境と共生は最重点課題であり、平城遷都1300年祭においても脱クルマや省エネ・創エネ(自然エネルギー導入)対策を中心に、多くの対策を考慮する
・世界的失笑を買うような、温暖化を助長すべき活動は行わない
・古都奈良の人々の生活と共に、次の遷都1400年、1500年へと繋がり、永遠に
子孫につながるイベントのモデルにする
・地球温暖化防止専門員を含め、早起き奈良県民のイベントとして知恵を出す
<コーディネーターコメント>
議論の調所に遷都1300年イベントの話題が出てきた。そのため、この条項を付録として設けた。議論はこのイベントが環境に配慮されたものか問うものであった。
かつての奈良は日本として国の骨格ができた場所でもあり、世界に開かれたところでもあった。このイベントは奈良が1300年綿々と続いたそのお祝いであり、世界の舞台に奈良を今一度押し上げたいものであろう。
しかし、環境に配慮しないイベントは世界の笑いものになりかねない。私とて、このイベントが、言い換えれば、奈良の人々が世界の笑いものになってほしくない。先の愛知万博でもあったように、環境に配慮したイベントはそれだけでも集客ができる。
このことは奈良の賢人を集めた会議で議論されたであろうが、今からでも遅くはない、今一度地球温暖化防止、環境配慮への点検・確認をし、県民にその内容をよりわかりやすく、多くの機会を捉えて情報を流してほしい。先のキャラクター問題のような奈良県民との乖離に十分な配慮が必要である。
遷都1300年イベントは過去の奈良の歴史に胡坐をかいたイベントではなく、真に歴史の先達に奈良が再びよみがえるイベントであってほしい。
3.まとめ
前回の会議に引き続き、ほぼ同一のテーマでの会議室であった。ただ、前コーディネーターの力量にはるかに及ばず、結果的に低調な会議室となったことは残念であり、コーディネーターとしてお詫びしておきたい。
さて、本会議室のテーマ・議論は、あえて言うなら前回ではほぼ出尽くされた感があった。しかし、それらをまとめる意味もこめて、市民の作る奈良県温暖化防止条例を念頭において議論を重ねた。その結果、条例案にまとめてみると奈良らしい、しかもかなり重量感を持ったものができたと考えている。議論の中には直接温暖化防止と異なるものもあった。大きな目で見るとかかわりはあるので、議論はそのままとしてすすめた。
条例案では「これなら奈良、奈良ならこれだ、ストップ温暖化」のサブテーマに掲げたように、奈良を特徴とした案も多数提案されている、しかも温暖化防止にかかわる内容ながら奈良の産業に貢献しそうな提案もあった。一般に、環境と経済は対立軸で見られがちだが議論の中には共存、補完しあう内容が含まれていた。くしくも、この会議室開催期間に原油の高騰、ガソリンの値上がりをみた。この状況は、奈良県のみにかかわらず、国家的にも問題視されるが、経済基盤の弱い地域ほど影響が大きいと思われる。奈良県の経済状況は全国平均に遠く及ばず、今のような状況が続く限り、大胆な発想の転換がなければ、何時までたっても奈良県は下位に甘んじなければならない。何か行動を起こすとき、予算がないことを告げられる。それが、何時しか予算のないことが隠れ蓑、言い訳になっていることに気づかない。金がなければ知恵を出せ、知恵を出したら決断せよ。
本会議室のコーディネーターをして強く感じたことは、奈良県が環境立県として強く、国内外に宣言(たとえば、遷都1300年イベントは良いチャンスと捉えることもできる、過去に胡坐をかいたイベントはいらない)をし、広く知恵を出し合い、世界から人々を奈良に集めることが必要であると強く感じた。そのためにも、この地球温暖化防止への条例は必要最小限のものに違いない。 今回の会議室で、先進の他府県の条例に比べ全く引けをとらないレベルで、奈良県の市民の知恵で考えられた条例として、インパクトのあるものが作られたと確信をしている。本会議室の成果が将来作られる条例の骨格になってほしいものである。
今回の会議室で、先進の他府県の条例に比べ全く引けをとらないレベルで、奈良県の市民の知恵で考えられた条例として、インパクトのあるものが作られたと確信をしている。本会議室の成果が将来作られる条例の骨格になってほしいものである。
最後に、本会議に参加、意見・議論をしていただいた方々、また関係された各位にこの場を借りて心から謝意を述べて終わりたい。
< 人々曰く >
奈良は歴史と環境の調和の取れた、くらしよい、くらしてよかった「国のまほろば」といえる麗しい県ですね。
Ⅲ−2(T−2):世界に開かれた奈良づくり
〜平城遷都1300年祭を契機に国内外から誘客できるまちづくり〜
コーディネーター:遠藤英樹
1.はじめに
この会議室では、「世界に開かれた奈良づくり――平城遷都1300年祭を契機に国内外から誘客できるまちづくり」をテーマに議論してきた。
まずは自由に楽しく議論してもらいながら、次第にサブテーマを設定し、そのサブテーマに沿って投稿してもらうようにした。コーディネーターがサブテーマをうまく仕掛けることができず、最後の2ヶ月は議論が少々停滞した。これは大きな反省点であるが、しかし投稿者の方々の活発な議論のおかげで、積極的で建設的な議論が飛び交う掲示板となったものと自負している。
なお発言内容のすべてをそのまま掲載するわけにもいかないので、部分的にコーディネーターが編集しているが、その点、ご了承頂きたいと思う。
2.提案
以下では発言内容から比較的、具体性を帯びた提案を掲載する。
(1)平城遷都キャラクター
せんとくん、まんとくん、なーむくんというマスコットキャラクターを最大限に有効活用できるような制度整備をする。
(2)奈良のもてなしの心を醸成させる
①先週、県の観光センターに立ち寄ったら、お茶のサービスがあることを知りました。観光シーズンの土曜、日曜日になると、1日4000人ほどの観光客が訪れる。奈良公園を歩いて一休みできる場所として、お茶のサービスは非常にありがたいものである。また、この辺で観光センター以外にトイレのできるところが無く、トイレの利用も多い。お茶とトイレは、旅行者には必須の要件であり、観光もてなしの心を育みたいものである。
②奈良には、世界交流の場になるところが無いようですね。世界に開かれた奈良を目指すには、恥ずかしいかぎり、大阪や、京都には、世界交流センターがある。そこで、外国の留学生や、滞在者が自由に意見交換をしたり、調査する資料などが集まっている。そこで、県に提案するのであるが、奈良県文化会館の2階、地下に多くの部屋が空いている。ここを世界交流の場に利用しては如何であろうか。
(3)奈良の交通問題
①観光で訪れた街でいちばん困ることの一つは「時間の浪費」だと思う。道に迷ってウロウロ、という体験は楽しく勉強になることもあるが、施設や食堂の待ち行列や、交通渋滞にはまって身動きがとれなくなるのは、愉快なものではない。休日になると、奈良市の旧市街の道はクルマでいっぱいで、特に大宮通りは、マイカーとバスとタクシーでぎっしり。交通手段として、まともに機能しているように見えない。この渋滞はすぐにでもどうにかすべきだと思うが、みなさま、何かアイディアはありませんか?
②アイデア提案
a)遊びに来るのは電車を利用
車は便利ですが、逆に車の中で一日過ごす事は不快であり、「奈良市内は電車しかダメ」位の政策を取るべきかと感じる。また、近鉄の乗車料も同業他社と比較して安い料金設定をして頂く。
b)バスを増発・路線系統の見直し
複雑怪奇な路線系統を見直し、乗って貰いやすい様にアピールする事が必要である。
c)パーク&バスライド・サイクルライドを充実
道路情報を充実させ、郊外駐車場へ誘導。
d)近郊住民は車で出ない
問題が有るが、ほとんどの車輌は奈良・京都・なにわナンバーで近郊日帰りである。これは電車・バスが割高か不便だからという理由で車を利用して居る。aとbを解決させれば、このdは自然と解決する。
無論一方通行も解決策の一つであるが、もう車を流入させない抜本的方策を考えないと解決しない、と感じる。
③奈良の場合、観光資源を考えると大仏前から近鉄奈良・JR奈良・大安寺・薬師寺(西ノ京)を結ぶ路面電車が一番有望と思う。
④以前観光旅行でヌーメア(ニューカレドニア)という都市で、観光用の電動路上ミニ列車が走っていた。輸送力に問題がありそうであるが、この電動ミニ列車の改良型のような輸送手段を、奈良に応用できないものか。
⑤仕事で久しぶりに近鉄奈良駅から西大寺経由で八木へ行きました。本当に久しぶりなのでどのホームから乗ればよいのか案内表示板をにらめっこでしばし立ち止まる必要があった。日頃日常的に利用している人には迷うことなく動けるのでしょうが、久しぶりの人や、他府県の人、観光客の人はきっと迷って、立ち止まるでしょう。西大寺駅では到着する電車の表示をしっかり見ておかないととんでもない方向へ行ってしまう。奈良へ行きたいのに、乗り間違えると橿原神宮へ行ってしまう。京都へ行くつもりが慌てると難波へ行ってしまう。平城遷都祭には多くの観光客が来られる。車でなく、電車で移動される。近鉄電車の利用が大半である。初めて利用される人々が迷う事無く、スムーズに移動できる方法を提供する必要があると感じる。これは近鉄電車の駅に限らず、市中の道路標示にも言える。国土交通省の道路標示も突然ことなる表示があったりする。平城遷都祭を期に奈良県内の案内表示の方法、判りやすい手法を考えて見たらどうか。
⑥近鉄電車への要望は「運行者の都合の情報でなく、利用するお客様への情報公開を最優先にして下さい」ということか。電光板は近鉄他駅より多くの情報が出ているが、一つの電光版に集約されているので、どこが3番線なのか、4番線なのか判らないのに、自分が居るところが何番ホームか判らないのに今の電光板では判断しにくい。今立っているホームにどのような電車が入ってくるのか、どのような順番でどこ行きが入ってくるのか時系列で判ればよくなるように思う。ホーム番号表示のところに電光表示板を併設してこのホームに入線する電車情報を最低3つ先くらいは表示する。何故一つではいけないのか?それほど色々な電車が次々入線するからである。また平城宮跡地(平城遷都祭メイン会場)の周りには、近鉄西大寺駅、近鉄平城駅、JR平城山駅(これをナラヤマと読める人はいるだろうか)、と地図上に見える。「平城メイン会場」へ行くにはどの駅で降りようと感じるだろうか。この当りの情報公開も急務かと思う。「そんな事ちゃんと調べて勉強して来い!」では世界に開かれた奈良づくりは実現不可能だと思う。
⑦奈良県内のJR線と私鉄の在来線を環状線にしてはどうであろうか?奈良環状線の予定路線は下記の通りである。近鉄生駒駅〜JR王子駅(近鉄生駒線)〜JR高田駅(JR和歌山線)〜JR桜井駅・天理駅〜JR奈良駅〜近鉄西大寺〜近鉄生駒駅、が提案する環状線ルートである。
(4)ウェブを用いた奈良の地域づくり
グーグルストリートビューでまち案内
(5)平城遷都1300年を迎えるまでの、奈良におけるその他の問題点
■安全問題
不審者の排除とセキュリティの徹底という基本を行ってこそ、はじめて世界に発信できる奈良の価値かと思う。
■子どもの遊び場
子どもの遊び場がすくなっている。外国には、有料の公園があって、公園の管理を行っているところもある。日本でも、そういうものが必要な時代になってきたのではないであろうか。
奈良公園の一角に、そのような区域を作っては如何なものか。
■「遷都1300年」をPRできる図柄入りの年賀状、かもめーる、一般用ハガキ
奈良県として「遷都1300年」をPRできる図柄入りの年賀状、かもめーる、一般用ハガキなどを郵便会社に作成依頼することは出来ないだろうか。
■大型ホテル建設のドキュメンタリービデオを残す
県は、ここの立地条件が幹線道路に面し近鉄やJRの駅から便も良く、観光資源へのアクセスにも優れているとして、宿泊力の強化及び経済発展に資するためホテル誘致の具体化に動き出した。このホテル建設の計画から完成までをドキュメンタリー風に記録し、進捗状況を内外メディアにも情報公開しながらホテル完成を見届けることを、1300年記念事業のイベントの一環に加えていただきたい。この敷地は平城京の条坊では長屋王邸をも含む左京三条ニ坊の区画(16坪)内にあって、南には三条通を挟んで藤原仲麻呂邸(田村第)の遺跡が確認され、その一部の発掘現場説明会が昨年秋に行われたことは記憶に新しい。おそらく今回の計画を実現完成するまでには、遺跡の保存と都市開発、景観問題など様々な問題点を提供してくれると思う。観光都市奈良の現実の姿を内外にさらけ出すことによって、私たち県民にとっても古都奈良を知る絶好の生きた教材になると思う。
■奈良のお気に入り風景の選定
■なら本選定
平城遷都1300祭に向けて、奈良の豊かな自然や歴史、風景、文化等について書かれた「なら本」ライブラリーを選定し、広報する。
3.発言の概略
次に、上記以外の発言内容について、その概略を示す。
(1)平城遷都キャラクター
①「せんとくん」のデザインを公募せずに意見を求めず役人だけで密室で決めたことに問題があるのでは?
②「せんとくん」は、県のイベントに芸術家個人の思想をそのまま持ち込んでしまったのである。芸術家の思想や作品を非難するつもりもなく、それはそれで結構良い作品を発表されている。しかし、その思想そのままのキャラクターを使ったイベントなんて、見たことも聞いたこともない。
③個人的には平城遷都1300年記念事業にキャラクターが必要なのかともっと根本的なところで「?」を感じてしまう。地域づくりで、なんでもキャラクターをつくることがはやっているが、そうしたキャラクターをつくるべきものとそうではないものを分別するべきではないのかなと思う。キャラクターに頼りすぎているような気がする。キャラクター化された地域社会をもうちょっとじっくりと再考すべきだと思う。平城遷都1300年記念事業で言えば、この事業は奈良という地域で育まれている文化、社会、自然などなどを後の世代、諸外国(他の文化)などにしっかりと伝え、後の世代や、他文化へもつないでいける奈良を再発見、再発掘し、発信することにこそ意義があるのではないだろうか?その場合、キャラクターに頼ったりしないで、自らの文化力そのものを高め、その力で情報発信できる社会づくりをしていくべきような気がしている。イメージキャラクターそのものが問題というよりも、そのもっと、もっと奥にある、深い文化観、歴史観、自然観こそを私たちは今一度作り直し、育てていくべきときが来ていると思う。
④イメージキャラクターの話題に接っすると、色々と在職中のことを思い出す。デザインは誰にも解りやすいので万と意見が出てくることが多かった。論理ではなく、あくまでもイメージである。大多数の方が批判するものでなければ、代表者が選んだものを尊重する。それで進んではどうだろうか。むしろ、このキャラクターを県民が育て上げてイベントを成功させることに努力すればいいのではないだろうか。
(2)奈良のもてなしの心を醸成させる
①街を歩いていて観光客かなと思われる人・外国の方を見かける。きょろきょろ何かを探しているようすであったり、どちらへ行くべきか迷っているような様子であったり、でも声掛けは勇気がいる。「英語で話さなければ」と躊躇する。考えればここは日本だからまず日本語で声掛けすれば良いのではと思う。「ここにはこんな場所があるよ」とか「ここはこういう意味のある場所だ」とか身近なことを自分の住む国、場所を「誇り」を持って「自己紹介」することが出来ればよいのではと思う。自分の生活する国・地域の歴史を知っておかなければならないのでは。
②昨年の3月、「もてなしの心推進県民会議」が発行した、「奈良のおもてなしハンドブック」(まちづくり編)と(ビジネス編)がある。多分事務局は奈良県庁にあると思う。「おもてなし」の気持ちを醸成することの必要性が、これまでも繰り返し議論されて県民会議まで立ち上げられた
のだと思う。立派なハンドブックも作って、その成果もあげられていると思うが、実感としてはまだまだこの会議室でも議論が必要だと思う。
③「世界に開かれた奈良つくり」として、文化交流は欠かせないと思う。ホストファミリーは、その担い手として、大きな役割を果たしていると思う。
(3)奈良の交通問題
「奈良交通」には県外から来る観光客に対して「もてなしの気持ち」が足りないのではないかと感じる。もちろん地元民に対しても。それより行政との関係をうまく保つことの方を重視しているように感じる。以前、本社を訪れて観光都市にふさわしい気配りをしてほしい旨をお願いした時に、「お話は解りますが、わが社は輸送を目的にする業務で観光業が目的ではない・・・」と言われた。
(4)奈良県の南部と北部の問題
①奈良県は県庁のある地域だけではない。平城遷都にくるまではむしろ南部の御所五条明日香橿原吉野がメインだった。今も何でもかんでも奈良市県庁周辺、東大寺周辺、奈良駅周辺を中心に考えられている。そこが奈良の問題点ではないだろうか。十津川村から北上して奈良市に至る風景を、遷都1300年祭りを契機に広報したいものである。
②私は、北部に住んでいる者ですが、確かに、南の方に行く機会が少ないですね。従って、南のことについて知る機会が少ない。逆に、南の方に住んでおられる人は、北部に来られる機会は多いのであろう。大阪に出る方が多いのかもしれない。南部の自然を生かした特徴を発信する、しかも、関西のリゾートといえるくらいの取組ができないものか。大きな企画を考える事業者を募集してみては如何であろうか。
③この事は昨日今日に始まった訳ではないが、原因の一端は判る気がする。私の個人的考えではありますが・・・。
a)交通が不便。道路が24号線と奈良桜井線でしかも大混雑です。20キロ程度に1時間以上かかるのはざら。これでは交流は生まれにくい。我々の感覚は、「橿原って大阪と同じ位の距離」と云う感覚である。また近鉄も今でこそキチンとした車輌を走らせているが、昭和50年位まではボロボロの木造車が走っていた。また駅舎も板張りの露天の駅が多く、大阪・京都線とは2ランク以上の差が有った。
b)行く用事が無い。奈良市に住んでいると、市内で間に合うか大阪で段取りという訳で、中南和へ行く機会が無い。で奈良市内の人はさほど中南和へ足を伸ばさない。中南和の方々も、いまでは元大阪府民の方も多く、こちらよりもむしろ大阪へ出られるだろう。
このように双方向の人の動きが見られない訳である。これでは温度差も出るであろうし、意志の疎通も生まれないであろう。
④中和の交通網が東西に発達し、南北は昔ながらってところが交流を生まない原因のひとつではあるかと思うが、もうひとつの原因は、確か県外勤務者が8割ということもあるかと思う。つまり多くの人は定期券を持っており、休日に遊びに行くにしても大阪まで電車料金が不要である。おそらく大学生の方でも似たりよったりでは?
(5)美しい自然環境を守るためのまちづくり
①日本で一番汚い川(環境省調査)で『ワーストワン』に選出されたのが奈良県の菩提川である。菩提川(率川)は、『葉根蘰(はねかづら) 今為(す)る妹を うら若み. いざ率川(いざかわ)の 音の清(さや)けさ』と万葉集に読まれた由緒ある川である。猿沢池周辺からJR奈良駅を横切って、恋の窪付近まで流れる総延長3.85kmの1級河川である。『ワーストワン』を脱出してから、国内外から誘客できるまちづくりを進めようではないか。
②大和川の上流に初瀬川があって、桜井市金屋・海石榴市(かなや・つばいち)と言う地名がある。552年に、百済から初めて仏教が公式に伝えられた地であり、「仏教伝来の地」の石標が今も建っている。当時は大和の物流の中心地として繁栄を極めていたそうである。629年には、小野妹子や南淵晴安等の遣隋使が、海石榴市の港を出発し難波津を経由して、隋の都・大興城(長安)に旅立ったと言われている。また、当時の遣隋使の総勢は500人〜600人ぐらいの船団で、数十隻の船が一同に初瀬川や大和川を下って行ったようである。昔の川の風情を、現在の奈良県民に見せてあげて下さい。
(6)ウェブを用いた奈良の地域づくり
1300年協会のHPがリニューアルされ、「職員ブログ」ができたが、ブログとは名ばかりの一方的な情報発信にとどまっている。
(7)平城遷都1300年を迎えるまでの、奈良におけるその他の問題点
■周囲の景観との整合性
①高さ抑制、8階建てに−橿原・丸山古墳付近 高層マンション建設(2008.6.12 奈良新聞)
局地的なスポットの高さ制限だけでなく、周囲の景観との整合性をどう規制していくべきか、奈良では他府県とは異なった配慮が必要だと痛感した。
②高さ規制は大事であるが、奈良の「導線」となる筋道の外観改善、浄化をしっかりやっていかないと皆が共倒れになるのでは?
■コマーシャリズムに乗ったイベントだけに終わらない
遷都以前の「奈良時代」「古代」が奈良を紹介するにふさわしいテーマだと思う。それがひいては日本民族を知るに必要なこと。世界に日本人を知ってもらうのに必要が時代である。奈良だからできることなのに、遷都祭りでコマーシャリズムに乗ったイベントだけに終わらないこと!
■公益性
①行政主導で税金を使って観光のイベントや宣伝をする事は良く思っていない。特に奈良県は、1300年事業のみならず、行政主導のイベントが多いように感じる。そもそも観光客誘致は、行政の仕事なのか?という疑問は常々思っていた。税金を使って何かをするという場合、「公益性」が必要であるが、観光客を誘致して、観光事業者を儲けさせることに「公益性」があるのか?という疑問である。
②観光振興には公益性がある。だから自治体だけでなく政府までが、国策として「ビジット・ジャパン・キャンペーン」をやるわけである。もうすぐ観光庁も誕生する。観光客が車で来県すれば、ガソリンスタンドの売上げも上がるであろう。奈良の良さが広く認知されれば、他府県から人が移ってこられ、子供の数が増えて学習塾も潤うかも知れない。官と民がお互いに補い合うことで、観光振興が実りあるものになると思う。県も市も町も村も、もっと本気になって観光振興に取り組めば、本当に必要なものが見えてくると思う。
③ハワイが素晴らしいのは、全島あげて、観光客をお迎えする体制ができていることである。関連業者だけでなく、地域住民全てが観光客を歓迎してくれる。それは、全住民のきちんとしたコンセンサスができているのである。遷都1300年を控え、奈良県民がそういう気持ちで来県者をお迎えすることができるのかどうか、ここで県民の意識レベルが問われるのだと思う。
■平城京の復元
①急がれるのは、大極殿をはじめとして、平城京の復元である。平城京とその町並みの復元によって、妻籠のように、疑似体験できるようになると目玉になる。もしも、これが間に合わなかったら、全く味の無い、夢の無い、刹那的行事で終わってしまう。
②平城京の復元といっても、実態がわからないものを無理に造れば、それは捏造というもので、後世に恥を遺すことにほかならない。
③時々散見する復元案であるが、安易な、物理的な復元には賛成できない。復元しなくても遺跡としての価値を充分に示している例として、NHKが調査した「日本人に人気が高く、一番行きたい世界遺産」の「マチュピチュ(ペルー)」を挙げておく。
■外国人旅行者のリピーターの確保
①外国人旅行者のリピーターは温泉や食に関心が高まっているという。日本観光への意識を調べ、奈良へのインバウンド(奈良への誘客)強化策が必要だと思う。奈良における、温泉や食文化で、外国人を意識した対策はなされているだろうか。
②日本に行くとしたら訪ねてみたい観光地(3つまで選択)の追加情報である。東アジア・豪州の6都市(ソウル、香港、台北、上海、北京、シドニー)での消費者調査:奈良は20位でした。20位までの順位:1.北海道、2.東京、3.富士山、4.東京ディズニーランド、5.大阪、6.京都、7.沖縄、8.USJ、9.別府温泉、9.広島、11.草津温泉、12.神戸、13.横浜、14.伊豆、14.蔵王温泉、16.仙台、17.道後温泉、18.黒部、19.箱根、20.ハウステンボス、20.奈良。奈良には、3つの世界遺産や、多くの観光地があるので、もっと上位にランクされてもよいと思うのだが、これらに対する関心が低いのか、情報の発信力が弱いのか、どちらかであろう。
■1300年記念事業は要らない?
この機会に世界へ宣伝する事は可能であるし、やるべきである。「世界に誇れる遺産が奈良に有る」って事を世界中の人々に理解して頂く事により、世界の奈良になれる訳である。しかし、それは、一つの一里塚に過ぎない。既存の催事・行事に1300年記念の冠をかぶせるだけではダメではないだろうか。1300年祭のコンテンツが大切だと思う。
■メディア「鹿男あをによし」の効果
今日の新聞折込みの広告で、「鹿男あをによし」撮影エピソード、というチラシを見つけた。私はこのチラシを見て楽しくなった。たわいの無いこと。私はあのテレビドラマが果たした役割は大きかったと思う。世間に奈良を、しかも3世紀にまで遡って意識させたその効果は、ドラマ放映が終った今も続いているように思う。昨日の奈良新聞では、奈良公園での「鹿せんべい」の売れゆきが好調で製造業者が嬉しい悲鳴を上げていると報じていた。「鹿愛護会」にとっても嬉しい話だと思う。私たち人間と鹿たちの正しい共生のしかたをPRするよい機会でもあると思う。
■奈良の知名度
①やはり行ってみたいと思わせる「奈良の知名度」と「奈良への憧れ」がもっと表現される必要があると思う。平城遷都1300年以前から連綿と続くこの地域を、日本の原点であるこの地域を、古代史愛好家だけの世界にせずにもっと露出させる。1300年祭りを「契機」にでなく、今からもっと「露出」させることに尽きると思う。キャラクター問題でニュースになり、話題になり、全国的に露出できた。もっと議論してぶつかって話題になればよい。
②平城遷都自体は「祝」かも知れないが、平城京って奈良最後の繁栄時代である。平城京がなくなった時点で歴史が止まっているって感じでる。それならば、平城京までの長い歴史をもっとうまくアピールするべきである。
4.おわりに
平城遷都1300年祭は、世界に開かれた奈良づくりの最終ゴールでは決してない。もちろん、それは、重要な祭典にするべきものだが、それ自体が目標であってはならない。平城遷都1300年祭を大きな契機としながら、そこを一通過点として、より良い奈良のまちづくりを展開していくことが重要である。そのためには、奈良に息づく深く豊かな歴史・文化・自然等を掘り起こし、それらの意味を再考するとともに、それらを活かすための方策を模索し実行に移していくことが重要である。この掲示板は、こうした議論が市民の間で充分に可能であるし、非常に重視されるべきものであることを証立ててくれるものとなった。
Ⅲ−3(T−3):うまいものがある食の風土づくり
〜身近なうまいもの情報から奈良の食文化まで幅広く語り合おう〜
コーディネーター:木村隆志
1.はじめに
美しい山々に囲まれた自然豊かな奈良県。歴史と文化の発祥地でもある奈良県は、各地にこれまで多くの食文化を届けてきた。都があった昔より四季の変化に富んだ環境が、たくさんのおいしいものを育んできた。しかし、いつのころからか、奈良にうまいものなしとの風評が、奈良の食文化の魅力を薄れさせている。本テーマの電子会議室では、こんな奈良を元気にしなければと、ジレンマを感じている方々からの投稿が寄せられた。
誇れる奈良の味はたくさんある。磨けば宝の資産が奈良県にはある。との共通した思いの投稿内容が多数であった。「奈良はおいしい」奈良の人と風土がつくる食文化が脈々と育っている。しかし残念ながら、これまで発掘されず、磨かれず、眠っているのも多くあるのが現実のようである。奈良を元気にすることは、食文化を育てること。そんな熱い発言者の思いから、このテーマに寄せられた貴重な意見を集約し提案をするものである。
2.提案
会議室の中での多彩な発言の中で、ごく一般的な或いは抽象的な意見や要望は除き、はっきり明記された提案、及び具体性があり提案となりうる意見を抽出し、以下にまとめた。
1)「奈良の食文化を育てよう」県民キャンペーンの実施。
(1)素朴で地味ではあるが、誇れる奈良の味はたくさんある。
長屋王グルメの掘り起こしや伝統食文化の育成(三輪そうめん、大和茶、奈良漬など)
郷土のおやつや祭事のお菓子の発掘(いもぼた、しきしき、半夏生餅、でんがらなど)
伝統野菜、地域ブランド産品の育成(大和牛、大和ポーク、大和肉鶏、飛鳥ルビー、大阿太梨、吉野富有柿などその他にも多彩にあり)
(2)「奈良にうまいものあり!」を学校給食などの食育実践で認知させる。
大和のおかいさんを朝食キャンペーンに。また地場農産物の五感体験教室の実施。宇治市では学校で宇治茶を自由に飲める環境をつくっている。大和茶も同様に対応すべきではないか。地域特産品や郷土食を学校給食やスーパーの店頭などでもっと認知普及すべきである。県農林部マーケティング課にぜひ期待したいものである。
2)観光支援策は食文化の活性化で。
(1)三輪素麺文化は観光資源としても育成強化をはかる。
秋田稲庭うどんや但馬出石そばに比較しても観光面では随分劣る。
1300年来の三輪素麺の伝統産業を守るためも、新連携事業や新規商品開発の積極支援や旧態組織からの脱皮を図るための県の支援策が必要である。三輪の里づくり、観光街道づくり。
(2)平城京遷都1300年祭のイベントは、一過性ではなく継続できる集客装置として考えるべき、また奈良県全県下も舞台にすべき。
姫路菓子博は奈良県で実施して欲しかった。また遷都1300年祭は、中南和地域では疎外感がある。奈良県を歴史街道のエリアに分けて、奈良市以外でもそれぞれを舞台にしたイベントを行うべきではないか。高知県では全県下くまなく実施する「であい博」というイベントを1年通して実施していた、見習うべきである。
(3)県南部に奈良の食文化館を創設して、農業や観光での活性化を図る。
奈良のうまいものが出来ても食べる場所や環境が乏しい。うまいものや食文化は五感で味わうもの。うまいもの商品をお土産的な店で売るだけでは今の観光客の満足はない。ふれあい回廊夢しるべ風しるべのオープンは食べる所がなかったので便利になった、がしかし、一部観光客からも「なるほど奈良や!と思えるものがない」と不満の声も。
道の駅「小淵沢」などのような農業を主体とした、観光拠点づくりが奈良県南部にも必要である。また、旧JR奈良駅舎が何に使われるかわからないが、「奈良うまいものセンター」にしたらどうか。
(4)奈良の土産物は「鹿せんべい」で活性化を。
奈良の土産物の活性化に鹿せんべいを開発してはどうか。全国的に認知度の高い鹿せんべいを人が食べられる商品に仕立て直して販売する。
商品の開発はメーカーやNPOや有識者などでのプロジェクトで立ち上げてみてはどうか。
3)奈良県ブランド、食文化の育成強化。
(1)奈良県ブランドのロイヤリティ向上と育成を積極的に行う必要がある。
奈良県産ブランド牛は宇陀牛、榛原肉、大和牛などのブランド多彩だが消費者にはわかりにくい。その他の農産物の奈良県ブランドもわかりやすく広報して欲しい。
また奈良県ブランドは基準を明確にして認証の一元管理をする必要がある。
「ぜんとくん」はもっと商品に露出させるべき。
(2)「奈良のうまいもの」を切れ目なく開発される仕組みづくり。
現状は選定基準が不透明のように感じる「奈良のうまいもの」はうまくないという風評もある。売れてなんぼの「奈良のうまいもの」。全国の消費者が決める仕組みの導入を。選考委員は県外のプロの目も必要である。また、「うまいものの」商品はもっと品揃えが必要で、毎年、切れ目なく開発される仕組みづくりが必要。主婦や大学、高校生部門の参加も望まれる。
4)奈良県ブランド、奈良発の食文化の販売運営や販売の支援強化。
(1) うまいもののある風土作りを担う新連携事業体への県独自の支援策強化。
奈良の食や農に対する新連携の枠組み(生産農家、NPO、大学、企業などそれぞれの強みを持ち寄った連携事業体)に対する件独自の支援策が必要。それらの新連携をサポートする専門家育成も重要な施策。
(2)販売力、マーケティング力の強化で奈良のうまいものを押し出そう。
奈良にはうまいものがたくさんある。そして今、時代が求める健康、郷愁、癒しの味は「奈良のうまいもの」ニーズと合致している。しかし、多くの消費者に受け入れられるには、味を含むデザインなど現代の時代に仕立て直す必要がある。消費者ニーズを生産者へつなぐ農業マーケティングの支援が求められる。具体的には、奈良県農畜産物の販売底上げ県内外消費アップへの販売促進、農産加工品など新規商品開発、パッケージデザイン、販売ルート開発などのコンサルティング支援など。
5)その他
(1)吉野の割り箸は、県が率先して全国普及するキャンペーンの実施。
吉野の割り箸は、森を守る、森を育てるという意義のある商品であるが、しかし生産者は零細家内工業で販売力は非常に乏しいところから、県としても普及するキャンペーン支援が必要である。
割り箸のリサイクルと割り箸活性化の事業を計画するNPOの参加は心強く、頼もしい。これらの事業計画には県の積極支援が求められる。
3.発言の概略
うまいもののある風土づくりという広いテーマであったが、何故、奈良にうまいものなし、と言われているのか、ではどうすればいいのか、というストーリーで展開したいと考えていたが、
電子会議という難しい面もあり、論点がぼやけてしまった反省点が残る。コーディネーターの力不足の感もあるが発言の概略を下記にまとめる。
・ 奈良のまほろばといったら吉野のおかいさん。
おかいさんを県民の健康朝食キャンペーンに普及啓発したらどうか。
・ 奈良のフルーツというと奈良いちごの飛鳥ルビー、吉野の柿、大宇陀のブルーベリー、大阿太の梨、平群のメロン
・ 奈良県の畜産品ブランド基準がわかりにくい。
宇陀牛と榛原肉と大和牛ブランドの違いは?
また品質の基準がよくわからない牛肉のブランド
大和牛は鎌倉時代より国牛の十牛に指定されていたとされる伝統ある和牛。
・ 大和牛100%を使ったコロッケや榛原肉とホウレン草のうまかまんは好評。
・ 健康志向の牛肉開発を。牧草中心の飼料と低温熟成技術で旨味醸成向上もある
・ 大和肉鶏のこだわり。テレビの番組で紹介された大和肉鶏のたたきは全国に誇れる味。
・ 給食食材のコスト意識と安全性のギャップ。
安心、安全を優先すべきであるが、コスト優先の現実。
・ 森を守る、吉野割り箸の育成支援が必要ではないか。
中国製割り箸の安全性の不安、また森林保護の観点から吉野割り箸の育成支援が必要
間伐材や端材の活用での森林保護、CO2削減に寄与。
割り箸を広告媒体として、または地球環境啓発媒体として普及活動すべき。
また、この会議で使用後の割り箸などを、家庭に還元を実感できるリサイクルシステムの創造(木質ペレット燃料として)と、食文化伝承との意義と目的を持った新しい割り箸の商品と販売の開発の研究がNPOで始められることは大変興味深い。
・ 郷土のおやつ、お菓子の掘り起こし。
東吉野のでんがら(朴の葉でくるんだ餅)御所のいもぼた(餅米を里芋で代用したおはぎ)東吉野では芋もち、や亥の子餅と呼ぶ 橿原の半夏生餅(小麦餅)當麻のよもぎ餡つけ餅、しきしき(昔のホットケーキ)など探せば各地に多数ある。
・ 遷都1300年祭は奈良県北部(奈良市)のみの行事で中南部には関係ないという声も。
中南和、東部では全く盛り上がりに欠ける。
・ 歴史ロマン、歴史街道などをいくつかのルート設定し全県下で盛り上げる企画が必要ではないか。国民休暇県の宣言をしている高知県では「であい博」というイベントを1年通して開催されていて、県内くまなくイベントを実施されている先例もある。
平城宮が到達地になるのが遷都。葛城から大神から明日香・藤原と来て平城京。奈良市だけでないと思うし奈良県はそれを忘れられている気がする。
・ 県外で知る奈良のうまいもん情報
観光資源の情報発信の一元化を図るべき(各観光団体の連携)
・ エコバックと土産物ショッピングバッグの開発のアイデア
観光情報発信型の何度も使える買い物(エコバック)の商品開発はどうか。
・ 三輪素麺と出石そばの観光比較。
出石そばの観光客の誘客に学べ、三輪素麺文化と街道まちなみの復活を急げ。
三輪明神や山之辺の道など見所も歴史や文化も出石にも負ける要素はないはずである。
・ 三輪素麺の製造日の改ざん問題発覚。
業界あげて根本的な出直しのイメージ回復とブランドロイヤリティの向上が必要。
生き残りをかけた三輪素麺再生プログラムと新しい組織の枠組みが必要ではないか。
・ 健康祈願、三輪素麺の食べ方
旬の鰹と五色の野菜のトッピングで「厄落としそうめん」の提案
カレー素麺、豆乳そうめんなどもどうか。奥村彪夫先生のお話によると正倉院の文献から麦縄や小豆、はちみつなどを使った記載があるところから、素麺をしるこで食べたのではないかと。「しるこそうめん」ということも考えられると聞いた。
・ 食べる楽しさの創造、器や箸の創造
平城京出土品やその時代の文献など箸や器の研究と復元し奈良ブランドとして販売も。長屋王のグルメを発掘して奈良の食文化としてアピールしてはどうか。
・ 食料自給率と食料廃棄率の問題
食料自給率40%を切る状況のなか、食料廃棄が25%という現実。
地域や学校、家庭での食育の必要性と食育情報発信の積極的取組み
・洞爺湖サミットでのPR
間伐材で作った割り箸やボールペンがCO2削減グッズとして販売されていたが、それは奈良県産のものであったのかどうかは不明ですが、奈良県産をアピールすべきだったのでは。
・ 姫路菓子博のような食文化イベントは奈良県で実施して欲しかった。
24日間の開催期間の入場者は当初目標の50万人を大きく上回り、92万人の入場者あり。
・ 県がすすめている「奈良のうまいもの」商品認定の決め方は公平と透明性の確保を。
売れて何んぼの「奈良のうまいもん」。行政主導ではなく、全国の消費者が決める仕組みの導入を、の声も。
・ JR奈良駅舎を食文化館として使うことはできないか。
旧JR駅舎が何に使われるか知りませんが、「奈良うまいものセンター」にしたらどうか。
・ 奈良のお土産はこれといったものがない
ぶと饅頭、葛、糊こぼし(お水取りの椿)最中では郡山の菊屋の最中、
三輪の御室の最中、東吉野のいつべ最中、団子では橿原のだんご庄などが喜ばれる。
・ 高知市の食文化の取組みでは、1キロにおよぶ「日曜市」を恒例化している。生産農家の方々のイキイキとした顔が印象的。訪れる観光客も増えているという。
・ 高知の「ひろめ市場」では土佐の食文化カツオを顔にして、たいそう賑わっていた。奈良県にもこんなところがあったらいいなとの意見。
・ おもてなしとは感動のストーリーをつくること。
奈良ロイヤルホテルの八坂豊社長のお話。これまでの売上利益の予算数値優先の経営から顧客満足度の度合いを数値化し経営の柱に据えて、徐々に経営も回復傾向。
・ 鹿せんべいを奈良の土産物にしてはどうか。
鹿せんべいは、誰しも一度食べて見たいと思ったはず、知名度もあり人間用の土産ものに開発してはどうか。開発については県がしっかり指導することが必要である。
また開発は民間の新連携の枠組みが必要で、それを県が助成支援することも必要ではないか。
4.おわりに
「果たして奈良にうまいものはあるか」という論点から食文化育成支援、販売拠点の開発など幅広くご意見を頂戴しましたが、奈良県には歴史文化はもちろんのこと、食の観光資源も多彩にあり、ひとつひとつを見てみると誇れるものが多くある。「奈良はうまいものばかり」と実感する。しかしそれらのほとんどは、小さな点と点の存在であり、まだまだ世に認められていないのも事実である。その大きな要因はマーケティングを実践する人材不足と県の支援策不足であったと思う。創作の奈良のうまいものも、伝統食文化の三輪素麺も、県内ブランド産品も県の育成支援がおろそかになっていたのは否めない。今後は生産者任せの点と点を線へ、そして大きな面へのマーケティング展開の必要にせまられている。商品の開発はもちろんのこと、新たな観光をも視野に入れた販売拠点づくりも早急の課題である。奈良の食文化や奈良県産品の全体の底上げには、それらを担う中心的な人材育成も必要である。また大学やNPOや関連企業、生産者などとの連携や、新しい事業体の枠組みも求められる。それらをめざす事業体には国の支援策にプラスするきめ細かな積極的な県の支援制度が必要である。
今、電子会議では6ヶ月間という短期間で、しかも、必ずしも多くない投稿者であったにもかかわらず、大変意義ある論議が出来たことは投稿者の皆さんのお力添えによるものであり感謝申し上げたい。
吉野の割り箸論議では、この割り箸を使うことが森を守り、育てる理解につながった。それに呼応して、食との融合で割り箸を普及活動を実践されるNPOの計画が出てきたことはうれしい限りである。
食文化を活性化させることが奈良を元気にすると言っても過言ではなく、この電子会議室で論議された意見や提案は、公式なテーブルで検討され、プライオリティ高く実現していただくように希望するものである。
Ⅲ−4(T−4) :奈良に泊まってもらうには
〜こんなにある奈良の隠れ観光スポット、お祭り、みやげもの〜
コーディネーター:金田充史
1.はじめに
世界遺産が県内に3カ所も有って、尚かつ名所・旧跡などに事欠かない奈良県ではありますが、他府県の日帰りに観光に甘んじている点が多々有る様にも見受けられる。
「この会議室では、奈良の魅力を再発見していく事により、奈良に泊まってもらう為にはどうすれば良いかと、更にそれを実行していく為の政策までを考えたいと思います。
観光は誰しもが楽しむ事が出来きます。それ故に皆様一人一人が「こんな奈良なら楽しい」というアイデアをお持ちだと思います。是非ともこの会議室で議論して、奈良で宿泊して頂く意義は何かを考えたいと思いますので、ちっちゃなアイデア大歓迎で。難しく考えずに井戸端会議気分で発言して頂ければ幸いです。」
と、冒頭での説明をし、趣旨を伝えさせて頂き、「宿泊して頂くには、どうやれば」の議論に終始させる様に心がけた。宿泊する事は、通常一般的に、何方もされている事乍ら、それでいて年間何日も無い為に、また、奈良で泊まった事が無いか、若しくはほとんど無い方々での意見交換の為、奈良のイメージで捉えられる傾向が有った事も否めない。しかし、他府県や外国での宿泊体験を下にした、宿泊させる目的を探して、議論展開をはかっていった。
2.提言
(1)奈良を楽しい街にすべし
(2)旅行会社に頼らない宿泊政策の実現すべし
(3)宿泊施設は多様な宿泊プランを呈示すべし
・早朝に集まって東大寺の朝の勤行を見る
・春日大社で特別に舞を舞ってもらう
・国立博物館や興福寺国宝舘を繰り上げて開館静かな雰囲気で展示物を見る
・薪で炊いた「茶がゆ」をいただく
・早朝に霊山寺のバラ園を訪ねる 等々
(4)宿泊施設は、泊まって良かった場所の研究をすべし
(5)自分が欲しいと思える名産品を開発すべし
(6)行事・催事を徹底的に広報宣伝すべし
(7)奈良県に真に相応しい宿泊施設は大型ホテルでは無い事を自覚すべし
(8)奈良の販売方法を研究すべし
①テーマ別に分かれた研究意欲の湧く地図の開発
②鹿男をはじめとするロケ場所の広報
③放送ライブラリーの設置・映像資料や写真の一元管理をする場所。
奈良文化会館内に有った、旧奈良県立図書館跡の有効利用を考える
④奈良県観光連盟主催の文化講座にもっと参加して頂く事を考える
⑤奈良にランドオペレーターの必要性を観光関係団体と関連業種に認識すべし
⑥体験メニューを開発すべし
文学・落語・音楽・お能・春日奥山原始林の自然等々
(9)夏休みなどの旅行プランを参考に奈良の楽しみ方を再考すべし
奈良県民が奈良県内で宿泊する様な政策を考える
(10)奈良の観光関連業種は、マーケティングを重要視すべし
3.電子会議室の報告 ① 街角スポット
① 街角スポット
② 奈良の宿泊プラン
③ 泊まって良かった都道府県
④ 奈良でダメだった宿泊施設の例
⑤ 奈良の人が使う土産物
⑥ 奈良の行事・催事
⑦ 奈良県に相応しい宿泊施設
⑧ JR奈良駅西側のホテル問題
⑨ 世界遺産を廻る方法
⑩ 奈良の販売方法
⑪ 夏休みの旅行プラン
⑫ 泊まって貰う為に不足している条件
⑬ 奈良にもっと来てもらう
⑭ 観光客誘致とは
(1)街角スポット
時代かご・鯉のぼり・にぎり墨・バンビーバス・まちかど正倉院、等々
奈良市内の物ばかりではあるが、最近、新規事業や新型バスなどが目に付く様になり、新しい風物詩が出てきた。楽しい町に成りつつあるのでは。
(2)奈良の宿泊プランと旅行会社の奈良に対する対応
大手旅行会社の営業マンは、「奈良は泊まらずに京都・大阪で泊まって、奈良は日帰り」と勧めている。もっと本質的な問題がここにあるのでは無いか、との事だが、旅行会社には、自社で一番儲かる物しか売らない。しかし「奈良で泊まりたい」と云う人々が居れば旅行会社は紹介をしている。それと、最大手氏は、北海道・東京・京都・沖縄だけで利益の70%近くを稼ぎ出して、この辺では一番京都が大切な地区で、京都に横を向かれれば利益は吹っ飛ぶ。だから京都への送客は社命に近い。しかし、奈良でも売れる時期は旅行会社も部屋を放さない。また大手も販売人員はネットエージェントに追い抜かれ、利益確保に走っている。奈良は、見せていく事で、旅行会社都合では無い御客様に来て頂く事の方が大切で、この様な御客様は沢山居られる。
また、菩提川の石仏や、元林院の元遊郭の名残など、未発掘の見所が沢山有ったり、旅館組合が、今年になって発表した、修学旅行生向けの「金魚すくい選手権」「バサラを踊ろう」「平城京カルタ」や「薬師寺の法話」なども有る。また、「早朝に集まって東大寺の朝の勤行見学」「春日大社で特別に舞を舞って貰う」「国立博物館や興福寺国宝舘を繰り上げ開館し、静かな雰囲気で展示物を見る」「薪で炊いた茶がゆをいただく」「早朝に霊山寺のバラ園を訪ねる」等々の早朝のプランを考える。また、奈良公園内でモーニングコーヒーが飲めたり、ホットドックが食べられる様な事も研究すべきである。
(3)泊まって良かった都道府県・宿泊施設等
*「エクシブ京都 八瀬離宮」
施設も部屋も食事も素晴らしく、景観にも十分配慮。6階建てだが、わざわざ地下3階として高さを抑え、無粋な駐車場も地下に収めている。ここの社長の理想のホテルが「奈良ホテル」というのには、ちょっと驚き
*淡路島の「ウェスティン淡路」
宿泊を目的とした“旅行”と言うより、休憩。
ふだん、バタバタと暮らしているので、ホテルの部屋でダラ〜として過ごし、公園を散歩したり、植物館をのぞいたりで過ごす。お食事が美味しいこと、お気に入りのマッサージ師さんが抜群に上手いこと、そしてキレイな花が見られること、それとベッドが良いこと。それからウェスティンにしてはリーズナブルな宿泊費。ホテルはいつも気持ちよく、でも来る度に過ごしやすくするための工夫が加えられていることに密かに驚きを感じる。
以下・例
* カードキーが、次に行った時には2枚渡されるようになり便利だなと思っていたら、今回2枚の絵柄が違うものになっていた。花の写真だったけれど、綺麗で花の栽培が盛んな土地らしいと感じた。
* 宿泊した初期は、バス用に圧縮スポンジが用意されていた。体をこするのに少し頼りない感じがしていたのだが、気がつくと入浴用のタオルに代わっており、少し薄手で使いやすいものになっていた。
* 1泊朝食付きというプランでは、朝食バイキングになるが、時として人を気にせず娘と二人で、部屋でゆっくりと取りたい時がある。以前はセットされたプランは変更を断られたと思うのだが、ルームサービスに変更できるようになっていた。
* バイキングのコーヒーは、カフェオレで頂くのが好みなのだけれど、ホットミルクが出ていないので自分で工夫して暖めたりしてコーヒーに入れていた。先日行ったら、湯煎にしたミルクがコーヒーの横に置かれていて大感激、など些細なことばかりだが、誰かが頼んだりしたのかどうかは解らないが、自分が感じていたことが、宿泊の度に改善されていくので、常に客のニーズに答えようとしてくれているのだな、と考える。リピーターが多いホテルだと関係者が言っておられたが、とてもうなづける話である。
*軽井沢の「星のや」。 非日常を堪能。チェックインから宿泊棟までわくわくする演出が見事。思わず、わぁ!とゲストの心を鷲掴み。風、音、光、水辺どれをとっても、寛ぐ、癒すことに徹した演出のホスピタリティ。
*松本市の「扉温泉明神館」
一軒宿だが、若い女性や熟年夫婦の客が多い。やはり、ここも非日常の演出がいい。
*高校ラグビーの選手たちの宿泊受け入れのことを聞いた。花園で行われるラグビーは甲子園の高校野球ほどに一般には知られていない。選手たちの受け入れには、食事をはじめ試合に勝ってもらうために言のほか気を使われる。しかし、選手たちには忘れられない思い出の宿になるであろう。将来家族を連れて来て、青春の思い出を語るかもしれない。私たちも、もっと関心を持って選手たちを歓迎し、全国から応援に来る人たちにも奈良に泊まってもらい、いい思い出を作ってもらいたい。
(4)奈良でダメだった宿泊施設の例
議論不十分につき省略
(5)奈良の人が使う土産物
地元の人が御土産店で手みやげを調達する事は、まず無い。通り一遍の手みやげで持って行くならいざ知らず、普通は「嬉しい」と思って頂ける様にお持ちする訳で、今、梅ぞの・さつま焼き・なかにしの和菓子・各社の柿の葉寿司・遊中川の袋物・玉うさぎの団子・わらび餅、おかずでは、天ぷら、コロッケ等々
(6)奈良の行事・催事
・「お水取り」:二月堂へ通えば通うほど不思議な魅力にとりつかれ、深夜、あるいは未明に戻れる部屋がほしい。
・「采女まつり」:月夜の奈良の風景を観たい。東塔の水煙の上に昇る月、中秋の名月には、唐招提寺や、甘樫の岡での観月会など。
・「修正会」:唐招提寺の餅談議。正月1日〜3日毎夜6時から営まれる。3日目の法要の中でユーモラスな抑揚で全国の餅を賞賛する。聴聞者は有難い「牛玉札」を貰った。
・「かぎろひを観る会」:旧暦の11月17日未明。大宇陀の「かぎろひの丘公園」で日の出前に集う会
・「源氏ボタル」:大仏殿と大湯屋の間。時間は日暮れ間もない7時40分頃、はじめ一つ、二つがここにも、あそこにもと増えて来る。自然の豊かな所に住んでおられる人にはめずらしいものではないかも知れない。しかし、市内の河川の汚染が問題になっている時、身近にホタルがいてくれることが嬉しい。8時には「奈良太郎」が頭上でズシリ・ズシリと時を告げ、宿に泊まってくれているお客さんに、そっと教えてあげたい
(7)奈良県に相応しい宿泊施設
パブリックスペースには、ご当地の歴史やいわれといった書物や写真集を読みながら、見ながら、アフタヌーンティ−をゆっくりと、時間を気にせず人の節介を気にせず過ごせる空間の有る様な宿泊施設が望ましい。奈良県には歴史があるので、その地域の歴史が分る解説書や展示品があって、1〜2時間程度で、ある程度インプットでき、近くを散策できる環境が有ると良い。日本の文化である「旅館」とコンビニエンスな「ホテル」の最善に融合された宿泊施設が望まれる。また、「一人でも泊まりやすい」宿泊施設が欲しい。今も旅館は一人を受けたがらない。しかし、一人で旅をしたい人は多数居られる。また、一人で泊まったらヒマなので、ロビーやラウンジで研究できる資料室が欲しい。「図書館」でなく「ライブラリー」という表現か。その土地の歴史や風習、風景をゆったり予習あるいは復習できる空間であってほしい。でもそこは旅館でありホテルという飲食業、昼は、「ライブラリー」でのアフタヌーンティー、夜にはお酒を頂きながらのホテルタイム。
(8)JR奈良駅西側のホテル問題
仮にゼファーがダメでも、奈良地区に高級ホテルの需要が有れば、別の不動産管理会社で出てくる事が予想されうる。しかし現状は止まったまま。県の言い出した県営プール跡も未解決。これで官のホテルは、見込み薄のモノばかりになっている。官側は、サミットや国際会議ばかり強調するが、こんなのは年間通じてそうそう無い。民間は、需要が見込めれば進出する。その証拠にビジネスホテルは何軒か出来た。残念ながら、奈良のポテンシャルはこのレベルなのか。これには、旧来の高度規制・建坪率・容積率の問題が有り、ホテル単独での解決は難しい。
(9)世界遺産を廻る方法
3つの世界遺産めぐりを効率よく行うコースを開発する。時間的制約の中で訪れる人が大部分だから、地形学的に効率の良いコースを考える。宿泊は、都会では味わえない雰囲気のある旅館、民宿でも良い。山と川と空気、ついでに温泉とゴルフ場も加えて交通手段のアクセスのよいところが条件になる。
(10)奈良の販売方法
奈良全県下のわかりやすい、一点集中地図が望ましい。例えば県内の神社仏閣の由来入り地図。踏破してやろうという気の起こる地図 神社地図 仏閣地図 古墳地図 名所地図、等々。また、エリアを一目で俯瞰できる広域地図は、位置関係が良くわかり「ここならこうしたら行ける」を思わせてくれたが、対象物を中心にした最寄駅からの地図だけだと奈良県のどの位置にあるのか判りづらいのは「地図を楽しむ」気をそいでしまう。位置関係が判っている人は、意外に少ないのでは。
法隆寺夏季大学が、今年も7月26日〜29日の4日間開催された。参加者名簿によると、北海道から九州までおよそ全国35都道府県から約600人が受講されている。その内訳、地元奈良300人、東京圏100人、関西圏100人、その他道県100人。遠隔地から参加の方は宿を取り、一流講師の講義を楽しみながら奈良への旅も満喫されている。昭和25年頃から続いている様だが、10回以上参加されている方もたくさんおられる様に見受けられる。これこそ「売り物」だと考える。斯様なノウハウをお持ちの、社団法人「奈良県観光連盟」にランドオペレーター役をお願いしたい。50年前の、「奈良県観光課」主催の文化講座に参加して以来奈良ファンだが、私みたいな人が他にもおられると考える。「観光連盟」がその講座を引き継いで、今年57回目を開催しているので、57年間の文化講座開催の実績とノウハウを持っているので、このノウハウを生かして販売する事でランドオペレーターとしての役割を果たす事が出来る筈だ。
燈花会、元興寺まんぷく祭り、バサラ祭りと 趣向は違うが、老若男女楽しめるお祭りが増えて、奈良も楽しくなった。この様な手法はどんどんすべき。
「鹿おとこ」のロケ地マップというものを、県庁のホールに置いてあるのを見つけた。中身も充実していた。このマップを見ていて、地元人では有るが、行ってみたい・・・と 感じた。もっと大々的にいろんな所に配布する必要が有る。また「鹿おとこ」を一過性のものに終わらせないために、「なら文学と映像の館」を作って、映像を紹介したりしては如何か。「鹿男」人気を保つためにはやはり 拠点となるスペースが必要で有る。そこに行けば「鹿男」に関するいろんな情報、たとえば原作本、ドラマのストーリー、ロケ地、キャスト、ロボット鹿などの情報が手に入れられるというスペースが望ましい。シアタールームを兼ね備えて実際に映像が見られれば尚良い。あと河瀬監督の映画も有料で上映する。英語の字幕をつければ、海外のお客も楽しい。この映像館は、立ち寄る人は多いと思われる。奈良文化会館内の、旧県立図書館のあったスペースを、この場所にあてられないだろうか。県庁や県警本部、NHKに近いので、通信回線を敷きやすいメリットも有る。他の映像資料は、ライブラリーに隣接する形で展示すれば、効果的。どれだけ集まるかわからない映像資料を期待するよりも、関西・西日本の映像視聴拠点に仕立てることで、奈良を販売するツールが一つ増えると考える。
奈良に来て、いろんな楽しいことを体験できれば、忘れられない思い出が出来るしリピーターも増える。文学・落語・音楽・お能・春日奥山原始林の自然観察など、ちょっと考えただけでも沢山出す事ができる。新聞社が歌人の俵万智さんや俳人の黛まどかさんを招いて名所をめぐり、歌や句をつくるイベントを企画されているが、素晴らしい企画ではないか、と感じる。例えば「みうらじゅんさん」「いとうせいこうさん」と”見仏会”するイベントなどは、参加したい。色々な企画は、電車の吊広告は結構よく目に付くので、鉄道会社と連携してアピールすると良い。
鹿をとこをガイドする際に役だったのは、「鹿男と歩く〜あをによし奈良〜」を見つけたからだ。今日の高評価は、このマップのおかげと考える。鹿男のドラマに限らず、奈良県民が、観光客の目線と思考にシンクロさせる事が一番大事だ。朱雀門で目撃したが、「遷都1300年祭」の腕章をした女性2人が、観光客に、まるで尋問でもするかのように「食事はうまかったか」「もてなしはどうだったか」「小遣いはいくら使ったか」「拝観料は高いと思うか」など相変わらずのアンケート調査をしており、部外の観光関係者を、まるで邪魔者扱いするような横柄な態度で有った。
(11)夏休みの旅行プラン
3日間、宇陀市室生区の「民宿むろう」に泊めていただいた。1泊2食付で7350円という安さと豪華な食事に惹かれて行ったのだが、最も感銘を受けたのが女将さんの温かいおもてなし。こういう宿があまり知られていないのが残念で有る。「奈良に泊まってもらう」には、このように小さくて良心的な宿が、もっと県内に増えれば、宿泊者が増えると考える。
奈良県民に、あえて苦言を呈する。奈良県に宿泊した人の数は117万人で全国ワーストだが、問題は内訳。奈良県民が奈良県内に泊まっていない。だから全体の宿泊者数が伸びない。宿泊者数の構成比は、奈良県では「県内」が13%(ワースト4位)、「県外」が83%(ベスト3位)、残りは外国人。「遠方の客が大阪や京都に泊まるから、奈良に泊まる人が少ない」との論評が有るが、「過去5年間で県内に泊まったことがあるのですか」の問いには、「ない」という答えがほとんどで、「いまだかつてない」という人も居る。泊まったことがないから良さを知らないし、県外の人に良さをPRできない。飲食店でも同じで、地元民が利用しない店を、県外の人が利用したくなるかは、甚だ疑問で有る。「奈良に泊まってもらう」には、「隗より始めよ」で、「なぜ泊まってくれないのか」と嘆く人が率先して県内に泊まることから、すべては始まると考える
しかしこれは、「泊まってくれない」と嘆く事よりもむしろ、奈良県民にも泊まって貰う仕掛けをしていない宿泊施設側にも問題がありそうだ。例えば、日頃修学旅行生が泊まっているのを目の当たりにして、ここへ泊まりたいと感じるだろうか?団体のバスが大挙している旅館へ泊まりたいと思うだろうか?無論、修学旅行をしているからと云って、年中では無いのだが、仮に修学旅行生が居なくても、修学旅行の施設と云う事で敬遠される。他府県では目に付かない事でも、地元ではそうはいかない。ただ、奈良県民が泊まりたいと云う宿泊施設の知られていないのも問題で、宿泊施設側がもっと県内への宣伝をする必要性が有る。以前、奈良県制度融資で、宿泊施設にバストイレ付きにする際に低利融資する制度が有ったが、全く利用実績が無かった。何故なら、ほとんどの施設は既に設備されていて、無い所は郡部の一部にすぎなかった。修学旅行が泊まっているからバストイレが無く外国人対応が出来ない、との想定は全く外れた。これも、修学旅行旅館は、広間みたいな部屋で泊めている、と云う想定から出た事で、修学旅行の泊まる旅館は斯様な設備が無い、と云う所から始まっている。これも県内消費が行われていないから起こった事で、金融機関も役所も知らなかった。観光産業は、県内にもっと情報発信が必要だが、まず、ここにこんな宿泊施設が有って、どんな所か、から知って貰う手段に打って出る必要性が有る。
奈良も、女性客をターゲットに、美容・健康・おしゃべり・体験 というフレーズを聴かせれば、興味を持たれる。それ故、宿泊施設の皆様は、ここの所にご注目頂き、例えば「飛鳥美人になれるコラーゲンたっぷりの牛乳鍋」とか「奈良時代のエステ」とかを開発・アピールしていただくと 寄っていきたくなる。また、アロマテラピーも流行っていて、「大和茶を使った茶香炉」のサービスというものも心惹かれる。お茶を炒る香りの良さは抜群。また県内在住者を5%引きにするとか グループで宿泊したら土産物10%引きのクーポンを渡せは、女性グループが泊まるのではないかと考える。また、女性グループといっても、様々な年代が有って、子育てからすこし解放されるのは、40代後半以降の女性たちだ。この年代の人は、好奇心いっぱい、やりたいこといっぱい、お喋り大好きなひとが多い。ゆっくり休みたいというより、いろいろ新しいものや、ことに出会いたいと 旅に出るほうが多い。このような新しさに出会えるなら、県内・外問わずに行きたくなる。だから、燈花会などは抜群のイベントで素晴らしい。是非ともいろんな新しいこと、トレンドなことを仕掛けて欲しい。近鉄が発行している女性向きパンフ「タビーク」を参考に。また、広報はとても重要。JRと近鉄線が至近の駅、例えば、王寺、桜井、吉野口などに県の南部、北部の観光イベントのパンフを意識的に置くと各鉄道オンリーの人が、違う路線の旅をしたくなるのではないかとも考える。
(12)泊まって貰う為に不足している条件
まず、観光産業が、橿原考古学研究所友史会の会合や例会に参加する事だと考える。考古学ファンの興味やニーズを知る事からはじめよ。男女や年代によって、そのニーズやウォンツは異なる。全てのニーズに合わせようとせず、自分にあった顧客を絞り込む。次に考古学に興味を持つ事。縄文文化、弥生文化の発祥地、律令国家の成立、飛鳥・白鳳・天平・奈良文化の経緯など等、勉強する事は多い。また、奈良観光は、東大寺・春日大社・興福寺だけが名所では無く、自分だけの名所を発見したいと思って居る。例えば、飛鳥の棚田、三輪山周辺や山之辺の道、葛城の社寺仏閣、竹之内周辺と飛鳥、田原本や笠縫の社寺仏閣と環濠集落、馬見丘陵の古墳群と社寺仏閣、吉野の歴史と景観、曽爾村の景勝などアピールするポイントは沢山。キーポイントは、やはり『参加型の観光』が重要。これからは、観光業にも『思考力』『企画力』『実行力』が必要と考える。
(13)奈良にもっと来てもらう
外国人の場合は、中国人が増えるので、東京・大阪に有る、都会型のホテルではだめ。奈良は緑豊かな閑静なホテルにし、温泉があればなお良い。中国人は、「日本にきて第一印象は何?」と言う問いに対して「緑豊かで空気がおいしいし、気が休まる。」という返事がほとんど。信貴山はホテルも充実して、また温泉もあり時間的にも便利。良い旅館もあり紅葉も見事だが、宣伝不足で損をしている。川上や十津川も、道路が整備されてそれほど不便では無い。しかし、まだまだ不便との意見も有った。奈良県の宿泊観光の誘致には、吉野と宇陀にもっと頑張ってもらわないといけない。
奈良市を代表する「奈良ホテル」も婚礼宴会で稼いで、中途半端。せっかくの「あの正面玄関」を持ちながら横に都会のホテルに憧れた最悪の宴会場を見せ付ける。「緑豊かな閑静なホテル」を自ら破壊している。しかし、ホテルを営業すれば、奈良ホテル・日航奈良の客室・最大収容人員は、132室/249人・330室/600人。これを仮に1名15.000平均で売れたとしても、奈良ホテルは3.735.000円、日航は900万円。しかし宴会場収容は、奈良ホテル最大1000名、日航奈良は460名、これが一日最大5回転。婚礼なら一人約5万円、一般宴会でも2〜3万円程度の売上げが有る。婚礼なら一回で最低300万、これが2回転、多いときでは4回転、日航ではそれ以上。宴会収益と云うのは、これだけ稼げるので、これが奈良だけでは無く、日本のホテル産業の収益を支えている。また、今の時代は、木造建築をするより建造費も安く、また、メンテナンスも楽で、保安性も高い鉄筋になるのは至極自然だ。また消防の火災予防の観点からも、木造は推奨されていない。だから、現代に生きている木造の旅館・ホテルは、斯様な意味でも貴重。総論賛成・各論反対とならないような政策が必要。
稲渕は、棚田が有名で日本一美しい里山の風景を見ることが出来るが、先週から稲渕名物の『かかしコンテスト』が開催。この風景こそが日本の景色で、東京都庁のある新宿高層ビルは日本の風景とは言えない。奈良県廰通りの建物や鳥居や仏像と言った無機物を観光資源としているのでは無く、棚田と言う有機物や村民の知恵が詰まった『かかしコンテスト』は、観光客の興味をそそる。知恵をしぼることは、素晴らしい。
また、奈良市内の観光関係者と話をしていると、途中で「おかしいな」と気づく。彼らの「奈良」は「奈良市」であり「古都奈良」だ。他府県出身の私から見た奈良とは、まず吉野であり御所・葛城であり宇陀・桜井・飛鳥であり、最後に奈良市。1300年記念事業協会は、全県挙げたお祭りにしようとしているが、それは間違っていない。葛城王朝があり、大和朝廷があり、吉野離宮、飛鳥の宮、藤原京があって平城京があるのだから。このタイトルも「奈良県にもっと来てもらう」ととらえれば、有益な話ができるし、「奈良に来てくれた人」には、次はリピーターとなって「奈良に泊まろう」という気にさせる魅力を私たちが創らなければならない。さらに、口コミで多くの人に伝播してもらえるように。
(14)観光客誘致とは
栢森は、10年前から村おこしの運動が始まり、飛鳥川源流の遊歩道の整備や村の清掃をボランティアの人たちが中心となって、活動を続けてこられた。ここでの一つとして、和風レストラン『さらら』が有る。廃墟になった人家を『神奈備の郷活性化推進委員会』が買い取り、自己資本で経営する田舎料理のレストランだ。安くは無いが、人里はなれた『神奈備の郷』で食べるランチは素晴らしい。このように、観光とは、『人様に後押しされて』村人の『やる気とアイディア』で、顧客が口コミでやってくるものだと考える。ホテル業や旅館業の方は、是非頑張ってほしい。
4.まとめ
「奈良で泊まってもらうには」の議論をするに当たり、「宿泊」の定義をまずどこへもっていくか、と云う事を最初に考えた。「宿泊」とは、高級ホテル・旅館へ泊まる事から、オートキャンプまでが定義される、非常に広範囲の物である。しかし、この会議室では、料金の発生しない、無論オートキャンプでもキャンプ場使用料などは発生するが、基本的に宿泊料が発生する宿泊施設のみを定義した。宿泊して貰うには、宿泊施設が存在する事が大前提であるが、宿泊施設だけでは宿泊客は発生しない。周辺の環境や食事、時期によっては催事・行事、コンサートやコンベンションまで、宿泊しようとする為の動機付けが絶対に必要である。それで、その上で、この会議室は「旅を楽しむのは、一般的な普通に生活して居られる国民でその目線」と云う視点を前提として、旅行者自身が奈良県で宿泊したくなる様になるにはどうすれば良いかを、議論していった。また、他府県に宿泊するよりは、奈良県で宿泊して頂く為の手段も同時に議論していったつもりである。宿泊には、旅行会社を抜きにしては考えにくいが、ここでは敢えて旅行会社を抜きで考え、「人々が来たい・泊まりたい、と思って頂ければ、おのずと宿泊者は有る」との考え方で、奈良のポテンシャルを上げる為の手段や他府県との比較、独自の宿泊プランなどを考えた。また、旅行会社の本音の部分も、会議室参加者の意見より、片鱗が伺えた事も成果かと考える。また、全国の旅館再生事業に拘わっているファンドなどの動向を見ると、旅行会社が独自の送客増で再生した例は無く、今の時代、旅行会社頼りの集客は曲がり角に来ている事も示されている。また、それと同時に旅館・ホテルをはじめ、地域の広報手法と云うのも問題である事が伺えた。どんな素晴らしい地域素材や施設も、正確に消費者に伝わらないと意味を為さない。奈良の行事・催事が上手く全国に発信出来ていない現状は、逆に言えば発信次第で誘客に結びつく事ができ、ここでも各団体や市町村の広報担当の腕が試される事である。半年間の意見を踏まえて、奈良県内には素材が多数有るが、この素材を如何にしてブラッシュアップして来て頂ける素材として魅力付けをし、適切な広報をしていくと云う正攻法で、十二分に宿泊者は増えるのでは無いか、と考える。しかし、一部では、真摯に議論をしていくにつれ、考える事が難しくなれば、投稿が止まる例も見受けられたのは残念である。
IV.広報活動、登録・投稿・アクセス集計
1. 電子会議の広報活動(実施した広報媒体)
(1)新聞発表 (奈良新聞) 1件
(2)ホームページリンク(団体、機関) 10件
(3)メールマガジン(団体、機関) 6件
(4)機関紙/地域情報誌 1誌
(5)ポスター(公共施設、企業、交通機関) 122枚
(6)チラシ (公共施設、企業、交通機関) 5740枚
2.電子会議室 アクセス・投稿状況
(1) 電子会議室アクセス数(2006/11/1〜2008/9/30)
| HP |
TP |
18下 T-1 |
18下 T-2 |
19上 T-1 |
19上 T-2 |
19上 T-3 |
19下 T-1 |
19下 T-2 |
19下 T-3 |
|
| 06/11 |
2991 |
2523 |
1540 |
982 |
||||||
| 06/12 |
2556 |
1551 |
932 |
618 |
||||||
| 07/01 |
1696 |
1331 |
786 |
543 |
||||||
| 07/02 |
1840 |
783 |
495 |
288 |
||||||
| 07/03 |
1995 |
920 |
666 |
254 |
||||||
| 18年度 下期計 |
11078 |
7108 |
4419 |
2685 |
||||||
| 07/04 |
4141 |
3376 |
290* |
138* |
860 |
691 |
1392 |
|||
| 07/05 |
5282 |
4696 |
228* |
119* |
1445 |
887 |
2013 |
|||
| 07/06 |
3446 |
3685 |
135 |
80 |
1084 |
795 |
1589 |
|||
| 07/07 |
3297 |
4108 |
83 |
56 |
1273 |
1014 |
1682 |
|||
| 07/08 |
3271 |
3428 |
93 |
53 |
898 |
902 |
1482 |
|||
| 07/09 |
3255 |
3993 |
84 |
54 |
1107 |
887 |
1821 |
|||
| 19年度上 累計 |
22702 33780 |
23286 30394 |
913 5332 |
495 3184 |
6667 |
5176 |
9979 |
|||
| 07/10 |
6834 |
6822 |
219 |
100 |
220 |
226 |
566 |
2081 |
2073 |
1328 |
| 07/11 |
3940 |
4609 |
100 |
70 |
81 |
90 |
415 |
1403 |
1456 |
988 |
| 07/12 |
2784 |
3489 |
91 |
65 |
75 |
68 |
398 |
983 |
1093 |
703 |
| 08/1 |
2995 |
3690 |
91 |
62 |
72 |
60 |
261 |
1141 |
1221 |
772 |
| 08/2 |
3013 |
3490 |
99 |
67 |
63 |
78 |
276 |
1011 |
1151 |
741 |
| 08/3 |
2790 |
3572 |
160 |
113 |
112 |
128 |
252 |
867 |
1123 |
800 |
| 19年度下 累計 |
22356 56136 |
25672 56066 |
760 6092 |
477 3661 |
623 7290 |
650 5660 |
2168 11774 |
7486 |
8117 |
5332 |
| HP |
TP/計 |
T-1(20上) |
T-2(20上) |
T-3(20上) |
T-4(20上) |
|
| 08/04 |
4913 |
6286 |
793 |
1323 |
1333 |
1393 |
| 08/05 |
3455 |
4786 |
775 |
1205 |
929 |
1003 |
| 08/06 |
3515 |
5181 |
1071 |
1352 |
959 |
905 |
| 08/07 |
3250 |
4927 |
1091 |
1236 |
851 |
793 |
| 08/08 |
3064 |
4471 |
838 |
789 |
779 |
1087 |
| 08/09 |
3348 |
4308 |
760 |
859 |
799 |
1002 |
| 20年上計 累計 |
21545 77681 |
29948 86014 |
4328 |
6758 |
5650 |
6183 |
● トップページ・アクセス状況
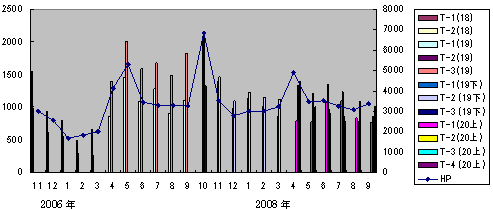
(2)登録者状況(2006/10/1-2008/9/30)
| 18下期 |
19上期 |
19下期 |
08/4 |
08/5 |
08/6 |
08/7 |
08/8 |
08/9 |
累計 |
|
| 登録数 |
60 |
65 |
35 |
5 |
8 |
5 |
5 |
1 |
8 |
192 |
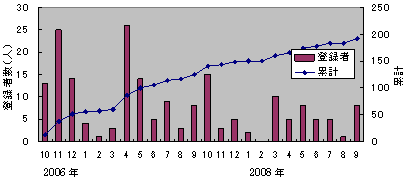
(3)月別投稿数(2006/11/1-2008/9/30)
| 年月 |
18下 /T1 |
18下 /T2 |
19上 /T1 |
19上 /T2 |
19上 /T3 |
19下 /T1 |
19下 /T2 |
19下 /T3 |
合計 |
| 2006/11 |
24 |
15 |
39 |
||||||
| 2006/12 |
29 |
19 |
48 |
||||||
| 2007/01 |
31 |
14 |
45 |
||||||
| 2007/02 |
9 |
9 |
18 |
||||||
| 2007/03 |
31 |
4 |
35 |
||||||
| 小計 |
124 |
61 |
185 |
||||||
| 2007/04 |
18 |
47 |
94 |
159 |
|||||
| 2007/05 |
27 |
26 |
57 |
110 |
|||||
| 2007/06 |
15 |
40 |
49 |
104 |
|||||
| 2007/07 |
28 |
82 |
81 |
191 |
|||||
| 2007/08 |
15 |
89 |
39 |
143 |
|||||
| 2007/09 |
21 |
76 |
78 |
175 |
|||||
| 小計 |
124 |
360 |
398 |
882/1067 |
|||||
| 2007/10 |
54 |
52 |
58 |
164 |
|||||
| 2007/11 |
38 |
35 |
68 |
141 |
|||||
| 2007/12 |
22 |
27 |
25 |
74 |
|||||
| 2008/01 |
26 |
42 |
36 |
104 |
|||||
| 2008/02 |
20 |
29 |
51 |
63 |
|||||
| 2008/03 |
14 |
27 |
59 |
100 |
|||||
| 下期計 |
174 |
212 |
297 |
683/1750 |
| T-1(20上) |
T-2(20上) |
T-3(20上) |
T-4(20上) |
合計 |
|
| 08/04 |
17 |
43 |
59 |
52 |
171 |
| 08/05 |
15 |
30 |
13 |
25 |
83 |
| 08/06 |
40 |
48 |
48 |
17 |
153 |
| 08/07 |
35 |
41 |
65 |
19 |
160 |
| 08/08 |
24 |
5 |
17 |
43 |
89 |
| 08/09 |
10 |
17 |
31 |
34 |
92 |
| 計 |
141 |
184 |
233 |
190 |
748/2498 |
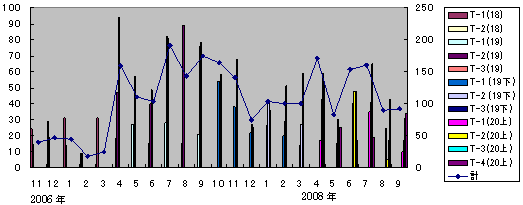
V.まとめ
1.全般
電子会議では6ヶ月間という短期間で、大変意義ある論議が出来たことを投稿者の皆さんに感謝申し上げたい。広範囲で、家庭から地域でのあらゆる分野に言及でき、熱心に色んな角度から議論が行われ、奈良県の実状をある程度的確に捉まえた議論、及び提案ができたのではないかと思う。投稿件数は、今期は748件になり、累計で2498件に達した。この中で、テーマ1では、11件、テーマ2では5件、テーマ3では10件、テーマ4では10件、合計36件の提案としてまとめることができた。また、トップ頁のアクセス数が21,545件になり、累計で77,681件、多くの方々が閲覧していただいている。今後の検討課題として、広く県民に広げるための広報のあり方と、県政や民間において地域の活性化の為に取組むに値する項目を実行することであると思う。
情報化社会において、多くの問題が山積する中で、多様な意見をフランクに投げかけ議論し提案できる場として、電子会議室は広く県民にメッセージを伝達し、議論して県民の意見を集約する有効な手段である。より多くの県民への理解と関心を高め、少しでも多くの会議室参加者の呼びかけを引き続き継続し、今後も幅広く議論できる「なら県民電子会議室」にしていきたい。
2.課題
① 投稿者が固定化してきている。登録者、投稿者をもっと増やし、特に、女性層や若い層の参加を増やし、より多様な議論を展開することである。投稿に参加する必要性/メリットを感じられる施策が必要でなる。
② 投稿者は、登録者の約半数である。残りの方々にも投稿していただける動機付けが必要である。また、会議室を閲覧している方も非常に多く、如何に投稿行動に結びつけるかの更なる工夫が必要である。
③ 既存の団体や組織による情報の共有化や協調体制作りとか地域住民による魅力ある街づく
りと行政の協働体制といったテーマについての議論がなされなかったのは心残りに思う。
④ この会議室は県の事業でありながら、一般には県の考え方が分らないという不満がある。県の方針なり考え方を明示して議論することがあってもよい。実際に県のトップの方々が関心を持っておられるのかどうか全く感じられなかった。
3.県への要望
(1)県職員の参加について
① 関係部署の業務に関係する投稿があった場合、既に実施中の事業について、投稿者がそれを知らない場合、担当課から、自主的に内容の紹介をして欲しい。
② 全く業務と関係のない職員が、私人として、積極的に議論に参加をお願いしたい。
氏名などの個人情報は登録不用となり、業務に支障をきたすことはない。
③ 県民同士が議論していることについて、担当事業の内容が間違って伝えられている場合、県は、それを正してもらいたい。
④ 知事自らのメッセージを顔写真と共に会議室のトップページに載せて頂く事は出来ないものか。その事によって、県のトップが県民の声を積極的に聞く姿勢がある事が直接伝わり、投稿者の裾野を大きく広げる事にもつながる。コーディネーターにとっても大きな励みになる。
(2)広報活動について
「なら県民電子会議室」は、まだまだ、県民に知られていない。チラシ、ポスター、メールマガジン、サイトなどを利用して、広報に努めているが、認知度は低い。テーマに関係する部門からの広報支援をお願いしたい。
(3)県の政策への反映
投稿者からは、提案に対する県の取り組みについて、強い関心を持っている。その期待があるからこそ、投稿を続けている。電子会議室を継続させるには、提案に対する県の前向きな取り組み姿勢が必要である。
4.補足
■ 運営委員会の開催日:2ヶ月ごとに開催
■ コーディネーター会議:運営委員会のない隔月に開催
最後に、この電子会議室を盛り上げていただいた運営委員会の皆様や、広報活動にご協力いただいた企業、団体、個人の方々に心から感謝申し上げます。
【添付資料】
1.20年度上期 「なら県民電子会議室」運営委員
2.20年度上期 「なら県民電子会議室」ポスター

