| 【104】北緯34度32分は、太陽の道です。 | |
| 気くばりくん(投稿日時:2008/06/16 00:41:33) | |
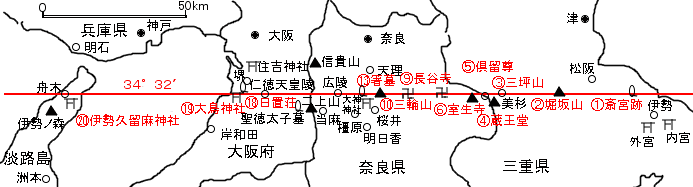 暦や時計を持たなかった古代の人々は、太陽や月、星、雲、風といった自然の変化は、神の業と映ったのでしょう。その声に耳を傾け祈りを捧げて、実りの時を迎えることが出来たのでしょう。豊作を願う切ないまでの思いが、神々の物語を生み、ここ大和の地に語り継がれているのです。 暦や時計を持たなかった古代の人々は、太陽や月、星、雲、風といった自然の変化は、神の業と映ったのでしょう。その声に耳を傾け祈りを捧げて、実りの時を迎えることが出来たのでしょう。豊作を願う切ないまでの思いが、神々の物語を生み、ここ大和の地に語り継がれているのです。日の出の三輪山と落日の二上山は、飛鳥時代の中心であった大和盆地南部の人々に特別の感慨を抱かせます。 日本の稲作は、ほぼ春の彼岸から耕作が始まる。太陽が真東から昇り、真西に沈む日を定めて、この日から50日〜60日目に種を蒔く。地球上で稲作北限の日本では、種を蒔く時期が収穫を左右する。早すぎると霜に遭うし、遅すぎると結実しない。春秋の彼岸の日、三輪山の山頂から出た太陽は二上山の二つの山の間に沈む。まるで神のはかりごとような風景を古代の人々は、どんな思いで見つめたのでしょうか。太陽の運行を知り、人々を指導したのが『日知り』即ち『聖』である。太陽や月、星、雲、風といった森羅万象に神を見て、その神託を伝える人こそが『大王』であると言う。従って、魏志倭人伝の卑弥呼もこの大役を担ったのでしょうね この三輪山と二上山を結ぶ北緯34度32分に注目して欲しい。西の延長上には伊勢斎宮、東に行けば淡路島の伊勢の森を結ぶ。この線上に点在するのは、三輪山、二上山はもとより、箸墓、多神社(田原本町多字宮ノ内)など古代史の重要ポイントである。この由緒ある地を結ぶ聖なる線は、北緯34度32分である。ここを歩けば、神話に込められた古代の人々の声が聞こえるかも知れません。古代人のおおらかな心に近づけることでしょう。少なくとも1年に1秒の狂いも無い時計を持つ現代人より、確かな感性を持って生きていた古代人の息づかいが聞こえてきます。 奈良県民の皆様、是非、この北緯34度32分『太陽の道』を歩きましょう。 また、世界の人々に『日本の稲作文化』の極意を、奈良の地から伝えましょう。 |
|